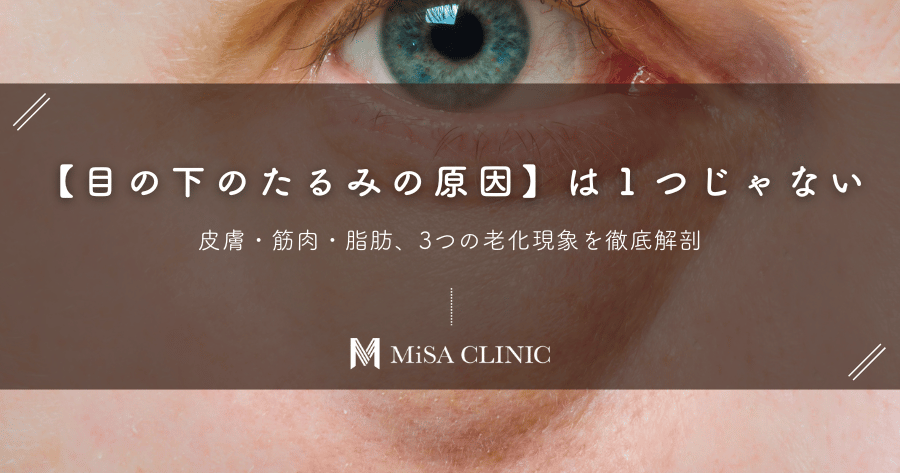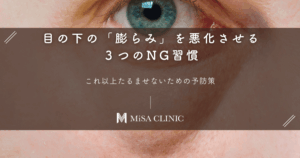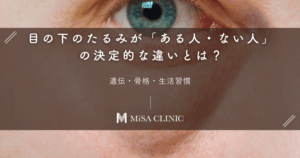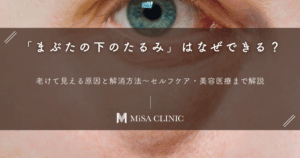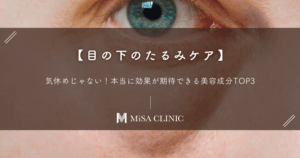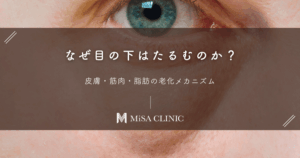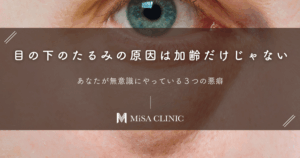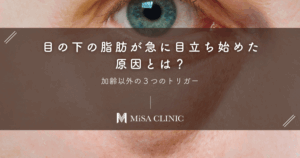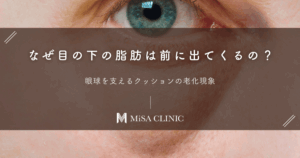鏡を見るたびに気になる、目の下のふくらみや影。「疲れているように見える」「実年齢より上に見られる」など、目の下のたるみは多くの女性が抱える深刻な悩みです。
様々なセルフケアを試しても、なぜか改善しないと感じていませんか。その理由は、目の下のたるみの原因が一つではないからです。
実は、皮膚の「ゆるみ」、筋肉の「衰え」、そして脂肪の「突出」という、3つの異なる老化現象が複雑に絡み合って生じています。
この記事では、あなたの目の下のたるみがなぜ起きているのか、その根本原因を一つひとつ丁寧に解剖し、悩みの本質に迫ります。
目の下のたるみとは? なぜ老けた印象を与えるのか
目の下のたるみは、単に皮膚が伸びることだけを指すのではありません。目元の構造的な変化が、見た目の印象に大きく影響します。
まずは、たるみがどのような状態なのか、そしてなぜ疲れた印象や老けた印象につながるのかを理解しましょう。
たるみが「影」を作り出す
目の下にたるみができると、皮膚がふくらんだり、逆にへこんだりして凹凸が生まれます。この凹凸に上からの光が当たると、影ができます。この影が、一般的に「クマ」と呼ばれるものの一つです。
特に、たるみによってできる「影クマ(黒クマ)」は、コンシーラーなどのメイクで隠すのが難しく、常に疲れたような印象を与えてしまいます。
顔の印象を左右する「目の下」という部位
目は顔の中でも特に視線が集まりやすいパーツです。そのため、目の周りの些細な変化も、顔全体の印象を大きく変えてしまいます。
ハリのあるすっきりとした目元は若々しく健康的な印象を与える一方、たるんだ目元は実年齢以上に老けた印象や、不健康なイメージをもたらす原因になります。
たるみの主な種類
| たるみの種類 | 主な原因 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| 皮膚のゆるみ(皮膚型) | コラーゲン・エラスチンの減少 | 目の下に細かく浅いしわ(ちりめんじわ)が目立つ |
| 筋肉の衰え(筋肉型) | 眼輪筋のゆるみ | 涙袋がぼやけ、目の下のふくらみが平坦に見える |
| 脂肪の突出(脂肪型) | 眼窩脂肪が前に出てくる | 目の下がぷっくりとふくらみ、影ができやすい |
加齢だけではない たるみを加速させる要因
目の下のたるみの最も大きな原因は加齢ですが、それだけではありません。
紫外線によるダメージ、乾燥、目をこするなどの物理的な刺激、さらには睡眠不足や栄養バランスの乱れといった生活習慣も、たるみの進行を早める要因となります。
これらの要因が複合的に作用することで、たるみはより深刻化していきます。
原因① 皮膚のゆるみ ハリを失う皮膚の構造変化
目の下の皮膚は、顔の中でも特に薄くデリケートな部分です。厚さはティッシュペーパー1枚分ともいわれ、外部からの刺激や内部からの変化の影響を非常に受けやすい特徴があります。
この薄い皮膚がハリを失い、ゆるんでしまうのが、たるみの第一の原因です。
皮膚の弾力を支えるコラーゲンとエラスチン
皮膚の真皮層には、コラーゲンとエラスチンという2つの重要な線維状のタンパク質が存在します。
コラーゲンは皮膚の構造をしっかりと支える柱のような役割を、エラスチンはコラーゲン同士を繋ぎ止め、弾力性を与えるゴムのような役割を担っています。
これらが豊富にあることで、肌はハリと弾力を保つことができます。
皮膚の弾力を保つ主な成分
| 成分名 | 主な役割 | 加齢による変化 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 肌の構造を支え、ハリを保つ | 量・質ともに低下し、硬くなる |
| エラスチン | 肌に弾力を与える | 変性し、弾力を失う |
| ヒアルロン酸 | 水分を保持し、うるおいを保つ | 産生量が減少し、肌が乾燥しやすくなる |
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少と変性
年齢を重ねるとともに、肌内部でコラーゲンやエラスチンを産生する「線維芽細胞」の働きが衰えていきます。これにより、コラーゲンやエラスチンの量が減少するだけでなく、質も低下します。
古くなったコラーゲンは硬くなり、エラスチンは変性して弾力を失います。その結果、皮膚はハリを失い、重力に逆らえずに垂れ下がり、たるみとして現れます。
紫外線ダメージが皮膚の老化を加速させる
紫外線、特にUVA(紫外線A波)は、皮膚の深い部分である真皮層にまで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊する酵素を活性化させます。
これにより、肌の弾力が失われる「光老化」が引き起こされます。日常的に紫外線を浴び続けることは、目の下のたるみを深刻化させる大きな原因の一つです。
日焼け止めやサングラスなどによる対策が重要です。
原因② 筋肉の衰え 目元を支える「眼輪筋」の機能低下
目の周りには、「眼輪筋(がんりんきん)」というドーナツ状の筋肉があります。この眼輪筋は、まぶたを開け閉めしたり、涙を目の表面に行き渡らせたりと、重要な役割を担っています。
そして、目の下の脂肪(眼窩脂肪)が前に出てこないように、ハンモックのように支える役割も果たしています。
目の下の構造を支える「眼輪筋」の役割
眼輪筋は目の下の皮膚や脂肪を内側から支える土台のような存在です。この筋肉がしっかりとしていることで、目元は引き締まり、ハリのある状態を保つことができます。
若々しい印象を与える「涙袋」も、この眼輪筋のふくらみによって形成されています。眼輪筋の力が保たれていることは、すっきりとした目元にとって必要です。
眼輪筋はなぜ衰えるのか
他の体の筋肉と同じように、眼輪筋も加齢によって徐々に衰えていきます。
また、筋肉は使わないと衰えるため、表情をあまり動かさない生活を送っていると、眼輪筋が使われずに衰えやすくなります。
特に現代人は、PCやスマートフォンを長時間見続けることで、まばたきの回数が減少しがちです。これも眼輪筋の運動不足につながり、衰えを加速させる一因と考えられます。
眼輪筋を衰えさせる生活習慣
| 習慣 | 眼輪筋への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| PC・スマホの長時間利用 | まばたきの回数が減り、筋肉が凝り固まる | 意識的にまばたきをする、適度に休憩を取る |
| 無表情でいることが多い | 筋肉を使う機会が減少し、衰えやすくなる | 意識して表情を豊かにする、笑顔を心がける |
| 目をこする癖 | 筋肉や皮膚に物理的なダメージを与える | 目のかゆみは点眼薬で対処し、こすらない |
筋肉の衰えが脂肪の突出を招く
眼輪筋が衰えてゆるむと、その内側にある眼窩脂肪を支えきれなくなります。
土台である筋肉がゆるむことで、今まで抑えられていた脂肪が重力に負けて前方へと押し出され、目の下のふくらみ、つまりたるみとなって現れます。
これは、皮膚のゆるみとは別に、たるみを形成する非常に大きな要因です。
原因③ 脂肪の突出 前に出てくる「眼窩脂肪」
目の下のたるみの原因として、最も直接的にふくらみを作り出すのが「眼窩脂肪(がんかしぼう)」の突出です。
眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションのような役割を持つ、元々目の奥にある脂肪です。これがなぜ前に出てきてしまうのでしょうか。
眼球を保護するクッション「眼窩脂肪」
眼窩脂肪は、誰の目にも存在する正常な組織です。病的なものではなく、眼球を外部の衝撃から守るために必要なものです。
この脂肪は、通常、眼輪筋や、そのさらに奥にある「ロックウッド靭帯」といった組織によって、適切な位置に保持されています。
脂肪を支える組織のゆるみ
加齢によって、先述の眼輪筋が衰えることに加え、ロックウッド靭帯などの支持組織もゆるんできます。
脂肪を包んでいる袋(眼窩隔膜)がゆるみ、さらにそれを外側から支えている筋肉の力が弱まることで、風船がしぼむように脂肪が前に押し出されてしまいます。
これが、目の下の特徴的なふくらみの正体です。
加齢による骨の変化「骨萎縮」の影響
あまり知られていませんが、顔の骨も加齢によって変化します。特に、眼球が収まっている骨のくぼみ(眼窩)は、加齢とともに拡大する傾向があります。
眼窩が広がると、相対的に内部のスペースが大きくなり、眼球がわずかに奥へ移動します。その結果、余ったスペースを埋めるように眼窩脂肪が前方へ押し出されやすくなり、たるみが目立つ原因となります。
加齢による目元の構造変化
| 組織 | 若年期 | 加齢による変化 |
|---|---|---|
| 皮膚 | ハリと弾力がある | コラーゲンが減少し、薄くゆるむ |
| 眼輪筋 | 脂肪をしっかり支える | 筋力が低下し、ゆるむ |
| 眼窩脂肪 | 奥の位置に収まっている | 筋肉や靭帯のゆるみで前方へ突出する |
| 骨(眼窩) | 適切な大きさ | 拡大し、脂肪が突出しやすい環境になる |
セルフケアでできることとその限界
目の下のたるみの原因が分かると、何か対策をしたいと考えるのは自然なことです。セルフケアでできることもありますが、その効果には限界があることも理解しておく必要があります。
ここでは、日々の生活で取り入れられるケアと、その注意点について解説します。
保湿と紫外線対策は基本中の基本
皮膚の乾燥は小じわの原因となり、たるんだ印象を強めます。また、紫外線は皮膚の弾力を奪う最大の外的要因です。
これらに対するケアは、たるみの進行を遅らせる上で非常に重要です。
- セラミド
- ヒアルロン酸
- コラーゲン
これらの保湿成分を含むアイクリームや美容液を使い、優しくケアしましょう。また、紫外線対策は季節を問わず一年中行うことが大切です。
日焼け止め、UVカット機能のあるメガネやサングラス、帽子などを活用してください。
紫外線対策のポイント
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| 日焼け止め | SPF/PA値の高いものを選び、こまめに塗り直す |
| サングラス・メガネ | UVカット率の高いレンズを選ぶ |
| 帽子・日傘 | 物理的に紫外線を遮断する |
マッサージやエクササイズの注意点
眼輪筋を鍛えるエクササイズや、血行を促進するマッサージは、一部で推奨されています。しかし、やり方を間違えると逆効果になる可能性があります。
目の周りの皮膚は非常に薄いため、強い力でこすったり引っ張ったりすると、皮膚のゆるみや色素沈着を招く危険性があります。行う場合は、専門家の指導のもと、極めて優しい力で行う必要があります。
生活習慣の見直しで内側からケア
たるみの進行には、生活習慣も大きく関わっています。質の良い睡眠を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけることは、肌の健康を保つ上で基本です。
特に、タンパク質やビタミンC、ビタミンA、ビタミンEなどは、肌のハリを保つために必要な栄養素です。また、スマートフォンを長時間見続ける際は、定期的に休憩を取り、目を休ませることも意識しましょう。
- うつぶせ寝
- 目を強くこする
- 喫煙
上記のような習慣は、たるみを悪化させる可能性があるため、避けるように心がけることが大切です。
美容医療という選択肢について
セルフケアにはたるみの進行を緩やかにする効果が期待できますが、一度進んでしまった構造的な変化(筋肉の衰えや脂肪の突出)を元に戻すことは困難です。
根本的な改善を望む場合、美容医療が選択肢となります。
原因に応じたアプローチ
美容医療では、たるみの原因に合わせて様々な治療法を提案します。例えば、皮膚のゆるみが主な原因であれば、レーザーや高周波治療で肌の引き締めを図ります。
脂肪の突出が原因であれば、余分な脂肪を取り除いたり、適切な位置に移動させたりする外科的な手術が検討されます。
自分のたるみの原因が何であるかを正確に診断してもらうことが、適切な治療への第一歩です。
セルフケアと美容医療の比較
| 項目 | セルフケア | 美容医療 |
|---|---|---|
| 目的 | 予防・進行を遅らせる | 現状の改善・根本治療 |
| 効果 | 穏やか・限定的 | 高い効果が期待できる |
| 費用 | 比較的安価 | 高額になる場合がある |
まずは専門医に相談を
目の下の状態は一人ひとり異なり、原因も複雑に絡み合っています。自己判断でケアを続けるよりも、まずは専門の知識を持つ医師に相談し、自分のたるみの原因を正確に知ることが重要です。
カウンセリングでは、どのような治療法があるのか、それぞれのメリットやデメリット、費用などについて詳しく説明を受けられます。信頼できるクリニックを見つけ、相談することから始めてみましょう。
治療を受ける前に知っておくべきこと
美容医療を受けると決めた場合でも、すぐに治療に進むわけではありません。治療法によってはダウンタイム(回復期間)が必要なものもあります。
また、期待できる効果や潜在的なリスクについて、十分に理解し納得した上で治療を選択することが大切です。医師からの説明をよく聞き、疑問点はすべて解消しておくようにしましょう。
【目の下のたるみ】に関するよくある質問
最後に、目の下のたるみに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
- 目の下のたるみは何歳から始まりますか?
-
個人差が非常に大きいですが、一般的には30代後半から気になり始める方が多いです。しかし、肌質や骨格、生活習慣によっては20代からたるみの兆候が現れることもあります。
特にPCやスマートフォンを多用する現代のライフスタイルは、若年層のたるみの一因となる可能性が指摘されています。
- 男性でも目の下はたるみますか?
-
はい、たるみます。目の下のたるみの基本的な原因である加齢による皮膚・筋肉・脂肪の変化は、性別に関係なく起こります。
男性は女性に比べてスキンケアや紫外線対策を怠りがちな傾向があるため、気づいた時にはたるみが大きく進行しているケースも少なくありません。
- 急にたるみがひどくなった気がします。なぜですか?
-
急激な体重の減少、睡眠不足や過労の蓄積、ホルモンバランスの変化などが原因で、一時的にたるみが目立つことがあります。
また、花粉症などで目をこする機会が増えた後なども、たるみが悪化したように感じることがあります。
ただし、多くの場合、それ以前から進行していたたるみが、何らかのきっかけで顕在化したと考えるのが自然です。
- 一度できてしまったたるみは自力で治せますか?
-
残念ながら、一度構造的に変化してしまったたるみ、特に脂肪の突出が原因のものをセルフケアだけで完全に元に戻すことは極めて困難です。
保湿や紫外線対策、生活習慣の改善は、これ以上悪化させないための「予防」や「進行抑制」として非常に重要ですが、できてしまったたるみを解消するには、美容医療によるアプローチが必要になる場合が多いのが実情です。
参考文献
SAMIZADEH, Souphiyeh. Anatomy and Pathophysiology of Facial Ageing. In: Thread Lifting Techniques for Facial Rejuvenation and Recontouring. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 61-89.
COBAN, Istemihan, et al. Anatomical basis for the lower eyelid rejuvenation. Aesthetic Plastic Surgery, 2023, 47.3: 1059-1066.
MUPAS-UY, Jacqueline, et al. Age-related eyelid changes. J Cosmet Med, 2017, 1.1: 16-24.
DAMASCENO, Renato Wendell, et al. Eyelid aging: pathophysiology and clinical management. Arquivos brasileiros de oftalmologia, 2015, 78: 328-331.
GEORGESCU, Dan; BLEYS, Ronald LAW. Eyelid and Facial Anatomy. In: Oculoplastic, Lacrimal and Orbital Surgery: The ESOPRS Textbook: Volume 1. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. p. 17-30.
POTTIER, Françoise; EL-SHAZLY, Nihal Z.; EL-SHAZLY, Amr E. Aging of orbicularis oculi: anatomophysiologic consideration in upper blepharoplasty. Archives of Facial Plastic Surgery, 2008, 10.5: 346-349.
GUO, Lei; SONG, Baoqiang. Enhancing aesthetic outcomes: The role of biomechanics in periorbital and eyelid cosmetic surgery. Indian Journal of Ophthalmology, 2024, 72.10: 1424-1432.