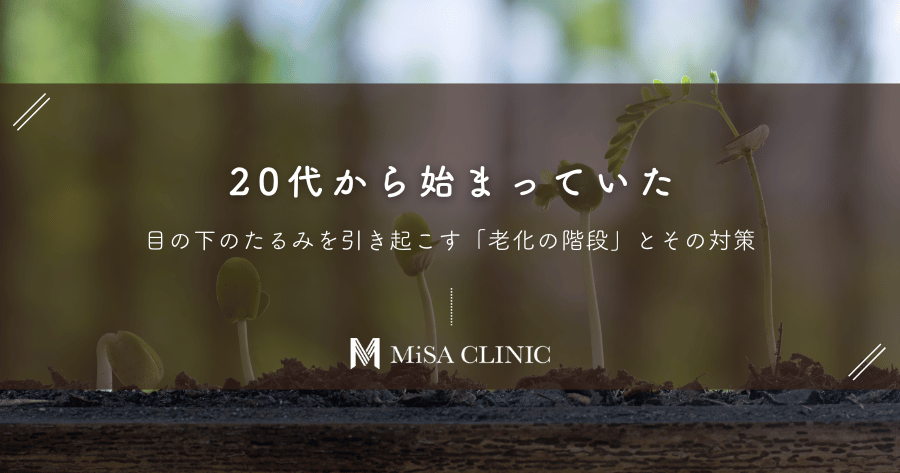ふと鏡を見たときに感じる、目の下のたるみ。「疲れているのかな?」と感じるそのサインは、実は20代という早い段階から静かに始まっているかもしれません。
なぜ年齢とともに目の下はたるんでしまうのでしょうか。
この記事では、目の下のたるみを引き起こす「老化の階段」を年代別に紐解き、その根本的な原因を詳しく解説します。
さらに、今日から始められる具体的なセルフケア方法から、進んだ悩みに対応する美容医療の選択肢まで、あなたの疑問と不安に寄り添いながら、若々しい目元を取り戻すための情報を網羅的にお届けします。
なぜ?多くの女性を悩ませる「目の下のたるみ」の正体
多くの人が「老けて見える」「疲れて見える」原因として挙げる、目の下のたるみ。
まずは、その正体が何なのかを正しく理解することが、効果的な対策への第一歩です。見た目の印象を大きく左右するこの現象について、基本的な構造から見ていきましょう。
目の下のたるみとは?(影クマとの違い)
目の下のたるみとは、下まぶたの皮膚がゆるみ、その下にある脂肪(眼窩脂肪)が前方へ膨らみ出て、段差やふくらみが生じている状態を指します。
このふくらみの下には影ができ、これが「影クマ」と呼ばれるものです。影クマは、寝不足や血行不良による「青クマ」や「茶クマ」とは異なり、メイクでは隠しにくいという特徴があります。
照明の当たり方、特に上からの光で影が濃くなる場合は、たるみが原因の影クマである可能性が高いでしょう。
たるみの主な原因は「眼窩脂肪」の突出
私たちの眼球は、クッションの役割を果たす「眼窩脂肪(がんかしぼう)」によって守られています。
この眼窩脂肪は、通常、「ロックウッド靭帯」という組織や「眼輪筋(がんりんきん)」という目の周りの筋肉によって、所定の位置に保持されています。
しかし、加齢などの要因でこれらの支持組織がゆるむと、眼窩脂肪を支えきれなくなり、重力に従って前方へと押し出されてしまいます。
これが、目の下のふくらみ、すなわちたるみの直接的な原因となるのです。
皮膚の構造から見る目の下の脆弱性
なぜ、顔の他の部分に比べて目の下はたるみやすいのでしょうか。その答えは、皮膚の構造的な特徴にあります。目の周りの皮膚は非常に薄く、デリケートです。
目の周りの皮膚の特徴
| 部位 | 皮膚の厚さ | 皮脂腺の量 |
|---|---|---|
| 目の下 | 約0.5mm~0.6mm | 少ない |
| 頬 | 約2mm | 多い |
| 手のひら | 約1.5mm | ない |
上の表が示すように、目の下の皮膚は頬の約3分の1から4分の1程度の厚さしかありません。また、皮脂腺が少ないため、皮脂膜による保護機能が弱く、乾燥しやすい傾向にあります。
乾燥は肌のハリや弾力を失わせる大きな要因であり、薄さと相まって、目の下を特にたるみやすい部位にしているのです。
セルフチェックで見つけるたるみのサイン
自分の目の下の状態が、単なるむくみなのか、それともたるみの始まりなのか、気になる方も多いでしょう。簡単なセルフチェックで、たるみのサインを確認できます。
手鏡を持ち、顔を正面に向けた状態から、ゆっくりと真上を向いてみてください。
このとき、目の下のふくらみが目立たなくなったり、平坦に近くなったりする場合は、たるみが始まっているサインと考えられます。
これは、上を向くことで眼窩脂肪が重力で奥に戻り、一時的にふくらみが解消されるためです。
20代から始まる「老化の階段」目の下のたるみ原因を年代別に解説
目の下のたるみは、ある日突然現れるわけではありません。20代から始まる「老化の階段」を一歩ずつ上るように、少しずつ進行していきます。
年代ごとの主な原因と体の変化を知ることで、より効果的な予防と対策が可能になります。
【20代】忍び寄る初期サイン「スマホ老化」と生活習慣
20代では、本格的なたるみが表面化することは少ないものの、その原因は着実に蓄積され始めます。特に現代のライフスタイルが、目元の老化を早める一因となっています。
長時間のスマートフォンやPCの使用は、まばたきの回数を減少させ、眼輪筋の働きを低下させます。また、画面を長時間見続けることで目の周りの血行が悪くなり、むくみやクマが定着しやすくなります。
これが、将来的なたるみへとつながる第一歩です。
【30代】コラーゲン減少が加速 見た目に変化が現れる時期
30代に入ると、肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンの生成量が本格的に減少し始めます。肌の弾力が失われ、乾燥による小じわが目立つようになります。
この時期から、目の下のふくらみがうっすらと現れ始め、「何となく疲れて見える」と感じることが増えるかもしれません。
20代で蓄積されたダメージが、肌の衰えと相まって表面化し始めるのがこの年代の特徴です。
年代別たるみの主な原因と特徴
| 年代 | 主な原因 | 現れやすいサイン |
|---|---|---|
| 20代 | 生活習慣の乱れ、眼精疲労、紫外線ダメージの蓄積 | むくみ、乾燥小じわ、一時的なクマ |
| 30代 | コラーゲン・エラスチンの減少、皮膚の弾力低下 | 影クマの始まり、ハリ不足 |
| 40代以降 | 眼輪筋の衰え、骨格の変化(骨萎縮) | 明確なたるみ、深い溝(ゴルゴライン) |
【40代以降】眼輪筋の衰えと骨格の変化が追い打ちに
40代以降になると、皮膚のたるみに加え、それを支える土台部分の変化が顕著になります。眼窩脂肪を支えている眼輪筋が年齢とともに衰え、脂肪を支える力が弱まります。
さらに、顔の骨格、特に目の下の骨(眼窩)が加齢によりわずかに萎縮し、後退します。これにより眼窩の容積が広がり、結果として眼窩脂肪が前方にますます突出しやすくなるのです。
皮膚、筋肉、骨という複数の層での変化が重なり、たるみが深刻化します。
年齢だけではない!たるみを悪化させる生活習慣
加齢は誰にでも訪れるものですが、ライフスタイルによっては、たるみの進行を早めてしまうことがあります。以下のような習慣は、目元の老化を加速させる可能性があるため注意が必要です。
- 睡眠不足
- 塩分の多い食事
- 目をこする癖
- 喫煙習慣
あなたはどのタイプ?目の下のたるみの種類と特徴
一口に「目の下のたるみ」と言っても、その原因や見た目の特徴によっていくつかのタイプに分類できます。自分のタイプを知ることで、より適切なケア方法を見つけやすくなります。
脂肪の突出が目立つ「脂肪型」
主に眼窩脂肪が前方へ突出しているタイプです。生まれつき眼窩脂肪が多い方や、比較的若い年代にも見られます。
目の下にぷっくりとしたふくらみがあり、その下の影が目立つのが特徴です。皮膚自体のハリはまだ保たれていることが多いです。
皮膚のハリ不足による「皮膚たるみ型」
加齢や紫外線ダメージにより、皮膚のコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚そのものが伸びてしまっているタイプです。
ちりめん状の細かいしわが多く見られ、目の下の皮膚をつまむと、薄く伸びやすいのが特徴です。脂肪の突出はそれほど目立たない場合もあります。
筋肉の衰えが原因の「筋肉ゆるみ型」
眼輪筋の衰えが主な原因で、脂肪を支えきれずにたるみが生じているタイプです。目の下が全体的に重たい印象になり、笑った時などに目の下のふくらみが顕著に変化することがあります。
涙袋が不明瞭になるのも特徴の一つです。
たるみの種類別 見た目の特徴と原因
| タイプ | 主な見た目の特徴 | 考えられる主な原因 |
|---|---|---|
| 脂肪型 | 目の下の局所的なふくらみ、影クマ | 眼窩脂肪の突出 |
| 皮膚たるみ型 | ちりめん状の細かいしわ、皮膚のゆるみ | コラーゲン・エラスチンの減少 |
| 混合型 | ふくらみとしわの両方が目立つ | 複数の原因の組み合わせ |
複数の原因が絡む「混合型」
多くの場合、目の下のたるみは一つの原因だけでなく、「脂肪の突出」と「皮膚のゆるみ」、「筋肉の衰え」などが複雑に絡み合って発生します。
特に年齢を重ねるにつれて、これらの要因が複合的に影響し合う混合型が多くなります。自分の状態がどの要素が強い混合型なのかを見極めることが、対策を考える上で重要です。
今すぐ始めたい!日常生活でできる目の下のたるみ対策
深刻なたるみを予防し、進行を遅らせるためには、日々の地道なケアがとても大切です。毎日の生活習慣の中に、目元をいたわるケアを取り入れていきましょう。
紫外線対策の重要性
紫外線は、肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンを破壊する最大の外的要因です。特に、波長が長く肌の奥深くまで到達するUVAは、たるみの原因に直結します。
季節や天候を問わず、一年中紫外線対策を徹底することが、目元の若々しさを保つ鍵です。
日焼け止めはもちろん、UVカット機能のあるサングラスや帽子、日傘などを活用し、物理的に紫外線をブロックすることも有効です。
紫外線が肌に与える影響
| 紫外線の種類 | 肌への到達深度 | 主な肌への影響 |
|---|---|---|
| UVA(紫外線A波) | 真皮 | しわ、たるみ |
| UVB(紫外線B波) | 表皮 | シミ、日焼け(炎症) |
保湿ケアで見直したいスキンケア習慣
薄くデリケートな目の周りは、顔の他の部分よりも乾燥しやすいため、重点的な保湿が必要です。
セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンといった保湿成分が配合されたアイクリームや美容液を使い、優しく潤いを与えましょう。
スキンケアの際は、指の腹で軽く押さえるようにしてなじませ、摩擦を与えないように注意します。
目元をこすらない優しいクレンジング方法
アイメイクを落とす際の摩擦は、皮膚のたるみや色素沈着の大きな原因になります。ウォータープルーフのマスカラなど、落ちにくいメイクはポイントメイクリムーバーを使いましょう。
優しいクレンジングのポイント
- リムーバーをコットンにたっぷり含ませる
- 数秒間まぶたに当ててメイクを浮かせる
- まつ毛の根元から毛先に向かって優しく拭う
ゴシゴシとこすらなくても、するんとメイクが落ちる状態を目指すことが大切です。
眼輪筋を鍛える表情筋トレーニング
目の周りを囲む眼輪筋を意識的に動かすことで、筋力の低下を防ぎ、目元をすっきりとさせる効果が期待できます。ただし、やりすぎや間違った方法は逆効果になる可能性もあるため、注意が必要です。
皮膚を引っ張らないように気を付けながら、ゆっくりと行いましょう。
例えば、目を大きく見開いて数秒キープし、次にゆっくりと目を閉じていく、という動作を繰り返すだけでも簡単なトレーニングになります。
食生活と睡眠で内側からアプローチするたるみケア
スキンケアなどの外側からのアプローチに加え、体の中から健やかな肌を育むことも、たるみ対策には欠かせません。毎日の食事と睡眠の質を見直してみましょう。
ハリを支える栄養素と食事のポイント
肌の弾力を保つためには、バランスの取れた食事が基本です。
特に、コラーゲンの材料となるタンパク質や、その生成を助けるビタミンC、抗酸化作用のあるビタミンA・Eなどを積極的に摂取しましょう。
目元のハリをサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や筋肉の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、果物 |
| ビタミンA・E | 血行を促進し、抗酸化作用を持つ | ナッツ類、かぼちゃ、アボカド |
良質な睡眠が目元にもたらす好影響
睡眠中は、肌のダメージを修復し、新しい細胞を生み出す成長ホルモンが分泌されるゴールデンタイムです。
睡眠不足は血行不良を招き、クマやむくみを悪化させるだけでなく、肌のターンオーバーを乱し、たるみの原因にもなります。
毎日6〜8時間程度の質の高い睡眠を確保するよう心がけ、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、リラックスできる環境を整えましょう。
注意したい食生活の落とし穴
一方で、たるみを助長してしまう食生活もあります。塩分の多い食事は、体の水分バランスを崩し、むくみの原因となります。むくみが慢性化すると、皮膚が伸びてたるみにつながることもあります。
また、糖質の過剰摂取は、体内でタンパク質と結びついて糖化(AGEsの生成)を引き起こし、コラーゲンを硬化させ、肌の弾力を奪う原因になるため注意が必要です。
水分補給とむくみ対策の関係
むくみを恐れて水分を控えるのは逆効果です。水分が不足すると、体はかえって水分を溜め込もうとするため、むくみやすくなります。
こまめに常温の水や白湯を飲み、体内の巡りを良くすることが大切です。カリウムを多く含むバナナやほうれん草などを食事に取り入れるのも、余分な塩分を排出する助けになります。
セルフケアの限界を感じたら 美容医療という選択肢
日々のセルフケアはたるみの予防や進行を遅らせる上で非常に重要ですが、一度できてしまった構造的なたるみ、特に眼窩脂肪の突出を自力で完全に解消するのは困難です。
セルフケアでは改善が見られない、より確実な効果を求めたいという場合には、美容医療に頼るという選択肢もあります。
目の下のたるみ治療の種類
美容クリニックで行われる目の下のたるみ治療は、大きく分けて「切らない治療法」と「外科的な治療法」の2種類があります。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、個人のたるみの状態やライフスタイル、希望する効果によって適した治療法が異なります。
切らない治療法(ヒアルロン酸・レーザーなど)
メスを使わず、注射や照射によってたるみを目立たなくさせる方法です。ヒアルロン酸注入は、たるみによってできた溝やくぼみを埋めることで、段差を滑らかにします。
レーザーや高周波(RF)治療は、皮膚の深層に熱エネルギーを与えてコラーゲンの生成を促し、肌を引き締める効果を狙います。
ダウンタイムがほとんどなく、手軽に受けられるのが魅力ですが、効果の持続期間には限りがあり、定期的なメンテナンスが必要な場合があります。
外科的な治療法(脱脂術・ハムラ法など)
たるみの根本原因である眼窩脂肪に直接アプローチする手術です。代表的なものに「経結膜脱脂術」があり、これは下まぶたの裏側から小さな穴を開け、余分な眼窩脂肪を取り除く方法です。
皮膚表面に傷が残らないのが大きなメリットです。
皮膚のゆるみが強い場合には、余った皮膚を切除する手術や、突出した脂肪をくぼんだ部分に移動させて再配置する「ハムラ法」などを組み合わせることもあります。
原因を直接取り除くため、効果の持続性が高いのが特徴です。
主な治療法の比較
| 切らない治療法(注入・照射) | 外科的治療法(脱脂術など) | |
|---|---|---|
| アプローチ | 溝を埋める、肌を引き締める | 原因となる脂肪を除去・再配置する |
| ダウンタイム | ほとんどない〜数日 | 数日〜2週間程度 |
| 効果の持続性 | 数ヶ月〜1年程度 | 半永久的(加齢による変化はあり) |
クリニック選びで失敗しないためのポイント
どの治療法を選ぶにしても、最も重要なのは信頼できる医師とクリニックを見つけることです。
カウンセリングで親身に話を聞いてくれるか、治療のメリットだけでなくリスクやデメリットについてもきちんと説明してくれるかなど、慎重に見極める必要があります。
クリニック選びのチェックポイント
| 項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| カウンセリングの質 | 医師が直接診察し、丁寧に説明してくれるか |
| 実績と症例 | 目の下の治療に関する経験が豊富か、症例写真を確認できるか |
| 費用体系の透明性 | 提示された料金以外に追加費用が発生しないか |
目の下のたるみに関するよくある質問
最後に、目の下のたるみに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 一度できた目の下のたるみは自力で治せますか?
-
残念ながら、眼窩脂肪の突出や皮膚の伸びによって生じた構造的なたるみを、セルフケアだけで完全に元に戻すことは非常に困難です。
スキンケアやトレーニングは、あくまでも現状維持や進行を遅らせるための予防的な意味合いが強いと考えましょう。
むくみが原因で一時的に目立っている場合は、マッサージや生活改善で軽減することもあります。
- マッサージはたるみに効果がありますか?
-
目元のマッサージは、血行を促進してむくみやクマを軽減する効果は期待できます。
しかし、やり方を間違えると、薄い皮膚に摩擦や刺激を与えてしまい、逆効果になる危険性があります。
色素沈着やしわ、たるみを助長する可能性があるため、行う場合は必ずクリームやオイルで滑りを良くし、極めて優しい力加減で行うことが重要です。
- 目の下のたるみは遺伝しますか?
-
たるみそのものが直接遺伝するわけではありませんが、骨格や皮膚の質、眼窩脂肪の量といった、たるみやすさに関連する身体的な特徴は遺伝的な影響を受けると考えられます。
ご両親の目元がたるみやすいタイプであれば、ご自身も早い段階から意識してケアを始めるのが良いでしょう。
- 治療後のダウンタイムはどのくらいですか?
-
治療法によって大きく異なります。ヒアルロン酸注入などでは、まれに内出血が出ることがありますが、基本的には直後からメイクも可能です。
一方、経結膜脱脂術などの外科手術では、個人差はありますが、強い腫れや内出血が1〜2週間程度続くのが一般的です。
仕事やプライベートの予定を考慮して、治療計画を立てることが大切です。
参考文献
STUTMAN, Ross L.; CODNER, Mark A. Tear trough deformity: review of anatomy and treatment options. Aesthetic surgery journal, 2012, 32.4: 426-440.
MUPAS-UY, Jacqueline, et al. Age-related eyelid changes. J Cosmet Med, 2017, 1.1: 16-24.
PENG, Hsien‐Li Peter; PENG, Jui‐Hui. Treating the tear trough‐eye bag complex: Treatment targets, treatment selection, and injection algorithms with case studies. Journal of Cosmetic Dermatology, 2020, 19.9: 2237-2245.
CHI, Yarong, et al. Gender-and Age-Related Characterization of Lower Eyelid Morphology: Three-Dimensional Analysis in a Chinese Population. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.19: 4031-4040.
COBAN, Istemihan, et al. Anatomical basis for the lower eyelid rejuvenation. Aesthetic Plastic Surgery, 2023, 47.3: 1059-1066.
JIANG, Jindou, et al. Tear trough deformity: different types of anatomy and treatment options. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 2016, 33.4: 303-308.
TING, Michelle AJ; EZRA, Daniel G. The Tear Trough and Lower Lid Folds: Etiology and Implications for Treatment. International Ophthalmology Clinics, 2023, 63.3: 13-33.
GOLDBERG, Robert Alan, et al. What causes eyelid bags? Analysis of 114 consecutive patients. Plastic and reconstructive surgery, 2005, 115.5: 1395-1402.
BUCHANAN, Dallas R.; WULC, Allan E. Contemporary thoughts on lower eyelid/midface aging. Clinics in plastic surgery, 2015, 42.1: 1-15.