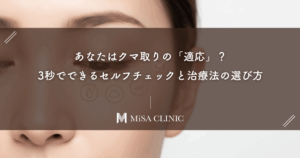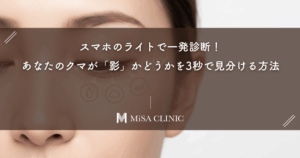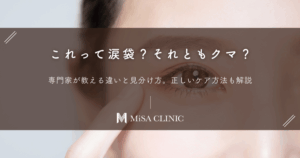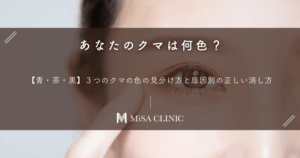「なんだか顔が疲れて見える…」「コンシーラーでも隠しきれない…」その原因、もしかしたら目の下の「クマ」かもしれません。実は、クマにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。
自分のクマがどのタイプか正しく知らないままケアをしても、なかなか改善しないものです。
この記事では、ご自身のクマの種類を判別できるセルフ診断方法から、タイプ別の原因、そして今日から始められる適切なセルフケアまで、専門的な視点からわかりやすく解説します。
あなたのクマはどのタイプ?セルフ診断で見分けよう
目の下のクマを改善するためには、まず自分のクマがどのタイプなのかを正確に把握することが重要です。ここでは、鏡一つで簡単にできるセルフ診断の方法を紹介します。
正しいケアを始めるために、ご自身の目元をじっくりと観察してみましょう。
鏡を使った簡単チェック方法
明るい自然光の入る場所で、手鏡を用意してください。スマートフォンのカメラでも代用できますが、色が正確にわかる鏡の使用が望ましいです。
準備ができたら、以下の手順でチェックしてみましょう。
セルフ診断の手順
- 顔を正面から見て、クマの色を確認します。
- 指でクマの下の皮膚を優しく下に引っ張ってみます。
- 顔を上に向けて、鏡でクマの変化を確認します。
これらの簡単な動作で、クマの色や状態がどのように変化するかを観察することが、タイプを判別する鍵となります。
診断結果のポイント
チェックした際の変化によって、クマのタイプをある程度推測できます。皮膚を引っ張った時にクマの色が薄くなったり動いたりする場合、それは皮膚そのものの色素沈着ではない可能性が高いです。
また、上を向いた時にクマが薄く見えるなら、それは皮膚のたるみが原因かもしれません。
【タイプ別】目の下のクマの種類と主な原因
目の下のクマは、主に「青クマ」「茶クマ」「黒クマ」の3種類に分類されます。また、これらが混在する混合タイプや、特殊な「赤クマ」もあります。
それぞれの特徴と原因を知ることで、より効果的な対策が見えてきます。
青クマの原因と特徴
青クマは、目の下が青黒く見える状態です。特に色白の方や皮膚が薄い方で目立ちやすい傾向があります。
これは、皮膚の下にある毛細血管が透けて見えることで生じます。主な原因は血行不良です。
血行不良が引き起こす青クマ
睡眠不足、疲労、ストレス、体の冷え、長時間のデスクワークによる眼精疲労などが重なると、目の周りの血流が滞りがちになります。
血液中の酸素が不足すると血液は暗い赤色になり、それが薄い皮膚を通して青黒く見えるのが青クマの正体です。
茶クマの原因と特徴
茶クマは、目の下が茶色くくすんで見える状態です。これは主にメラニン色素の沈着が原因で起こります。シミの一種と考えることもできます。
色素沈着が引き起こす茶クマ
目をこする癖、落ちにくいアイメイクを無理に落とす際の摩擦、紫外線ダメージなどが、皮膚に刺激を与えます。
その結果、肌を守ろうとしてメラニンが過剰に生成され、うまく排出されずに色素沈着として残ってしまうのです。アトピー性皮膚炎など、目元にかゆみが生じる疾患も原因となることがあります。
黒クマの原因と特徴
黒クマは、目の下が黒く影のように見える状態です。これは皮膚の色自体に変化があるわけではなく、加齢などによる皮膚構造の変化が原因で生じる「影」です。
たるみや凹みが引き起こす黒クマ
年齢とともに肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンが減少すると、皮膚がたるみます。
また、目の下の脂肪(眼窩脂肪)が前方に突出したり、逆に頬の脂肪が減少して目の下に凹みが生じたりすることで段差ができます。この段差が光を遮り、影となって黒く見えるのが黒クマです。
クマのタイプ別原因まとめ
| クマの種類 | 主な原因 | 特徴的な見た目 |
|---|---|---|
| 青クマ | 血行不良 | 青黒く、日によって濃さが変わりやすい |
| 茶クマ | 色素沈着(メラニン) | 茶色くくすんでいる、シミのようにも見える |
| 黒クマ | 皮膚のたるみ・凹みによる影 | 黒い影のように見え、顔の角度で変化する |
クマの種類の見分け方を詳しく解説
セルフ診断の結果をさらに確かなものにするために、それぞれのクマのより詳しい見分け方を紹介します。簡単なアクションで判別できるので、ぜひ試してみてください。
青クマの見分け方
青クマの最もわかりやすい見分け方は、皮膚を指で軽く引っ張ることです。クマの部分の皮膚を指の腹で優しく横に引っ張ってみてください。
もしクマの色が少し薄くなったり、位置が変わったりすれば、それは皮膚の下の血管が透けて見えている青クマである可能性が高いです。
血行の状態によって日ごとに濃さが変動するのも特徴です。
茶クマの見分け方
茶クマは色素沈着が原因なので、皮膚を引っ張っても色の濃さや位置はほとんど変わりません。また、顔を上に向けて鏡を見ても、色は薄くなりません。
シミのように皮膚自体に色がついている状態をイメージするとわかりやすいでしょう。目尻を軽く引っ張ると皮膚の色がそのまま伸びるように見える場合、茶クマの可能性が高いです。
黒クマの見分け方
黒クマは影なので、光の当たり方で大きく見え方が変わります。手鏡を持ったまま顔を真上に向け、天井の照明が当たるようにしてみてください。
このとき、クマが薄くなったり消えたりすれば、それは黒クマです。たるみや凹みによってできていた影が、顔を上に向けたことで目立たなくなるためです。逆に、正面を向くと影がはっきりと現れます。
クマの見分け方実践ポイント
| アクション | 青クマ | 茶クマ |
|---|---|---|
| 皮膚を下に引っ張る | 色が少し薄くなる | 色は変わらない |
| 上を向く | 変化は少ない | 色は変わらない |
なぜ目の下にクマができるの?共通する要因とは
クマの種類は異なりますが、そもそもなぜ「目の下」という特定の場所にできやすいのでしょうか。
それには、目の周りの皮膚が持つ特有の構造や、私たちの生活習慣が深く関わっています。
目の周りの皮膚の薄さ
目の周りの皮膚は、頬の皮膚の3分の1から4分の1程度の薄さしかありません。非常にデリケートで、皮脂腺も少ないため乾燥しやすいという特徴があります。
皮膚が薄いために、下にある血管の色が透けやすく(青クマ)、摩擦などの外部刺激によるダメージも受けやすい(茶クマ)のです。
生活習慣の乱れ
不規則な生活は、あらゆるタイプのクマの発生や悪化につながります。
特に睡眠不足は、血行不良を招き青クマを悪化させるだけでなく、肌のターンオーバーを乱して茶クマの原因となるメラニンの排出を妨げます。
食生活の乱れも、肌の健康状態に直接影響します。
クマを招く生活習慣の例
| 習慣 | 影響 | 関連するクマ |
|---|---|---|
| 長時間のスマホ・PC作業 | 眼精疲労、血行不良 | 青クマ |
| 睡眠不足 | 血行不良、ターンオーバーの乱れ | 青クマ、茶クマ |
| ストレス | 血行不良、ホルモンバランスの乱れ | 青クマ |
加齢による影響
年齢を重ねることも、クマの大きな要因です。加齢により肌の弾力を保つコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄くなったりたるんだりします。
これにより、血管が透けやすくなって青クマが目立ったり、たるみによる影(黒クマ)が現れたりします。肌のターンオーバー周期も長くなるため、色素沈着(茶クマ)が定着しやすくなります。
自宅でできるクマのタイプ別セルフケア方法
自分のクマのタイプがわかったら、次はその原因に合わせたセルフケアを始めましょう。毎日の少しの工夫で、クマの印象を和らげることが期待できます。
青クマのセルフケア
血行不良が原因の青クマには、「温める」ことと「巡りを良くする」ことが基本です。
目元の血行促進ケア
蒸しタオルや市販のホットアイマスクで目元を温めるのは、手軽で効果的な方法です。血行が促進され、滞っていた血流が改善します。
また、優しくマッサージを行うことも有効ですが、摩擦は茶クマの原因になるため、必ずアイクリームなどを使って滑りを良くしてから行いましょう。
茶クマのセルフケア
色素沈着が原因の茶クマには、「美白ケア」と「刺激を与えない」ことが重要です。
美白成分配合のスキンケアと紫外線対策
ビタミンC誘導体やトラネキサム酸、アルブチンといった美白有効成分が配合されたアイクリームや美容液を選び、継続して使用しましょう。
また、新たな色素沈着を防ぐために、季節を問わず日焼け止めやUVカット機能のあるメガネ、帽子などで紫外線対策を徹底することが大切です。
黒クマのセルフケア
たるみが原因の黒クマはセルフケアでの完全な改善は難しいですが、進行を遅らせたり、目立たなくしたりするための「エイジングケア」が有効です。
ハリを与えるエイジングケア
レチノールやナイアシンアミド、ペプチドなど、肌のハリや弾力をサポートする成分が配合されたスキンケア製品を取り入れましょう。
これらの成分は、コラーゲンの生成を助け、肌の内側からふっくらさせる効果が期待できます。また、表情筋を鍛えるエクササイズも、たるみの予防につながります。
タイプ別セルフケア方法のポイント
| クマのタイプ | ケアのポイント | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 青クマ | 血行促進 | ホットアイマスク、優しいマッサージ |
| 茶クマ | 美白と保湿、紫外線対策 | 美白成分配合アイクリーム、日焼け止め |
| 黒クマ | エイジングケア | レチノール配合化粧品、表情筋エクササイズ |
セルフケアで改善しない場合の美容医療という選択肢
セルフケアを続けてもなかなかクマが改善しない場合や、より根本的な解決を望む場合には、美容医療を検討するのも一つの方法です。
専門のクリニックでは、クマのタイプや状態に合わせて様々な治療法を提案しています。
青クマに対する治療法
血行不良が原因の青クマに対しては、血流を改善する施術や、皮膚に厚みを持たせて血管が透けにくくする治療が考えられます。
例えば、特定の波長の光を照射して血行を促進する光治療(IPL)などがあります。
茶クマに対する治療法
色素沈着である茶クマには、メラニン色素に直接アプローチする治療が効果的です。ピコレーザーやレーザートーニングといった施術は、メラニンを細かく破壊して排出を促します。
また、ケミカルピーリングで肌のターンオーバーを正常化させる方法もあります。
黒クマに対する治療法
たるみや凹みが原因の黒クマには、物理的にその構造を改善する治療が中心となります。
凹みが目立つ場合にはヒアルロン酸注入で段差をなだらかにし、脂肪の突出が原因の場合は、経結膜脱脂術(目の裏側から脂肪を取り除く手術)などが選択されます。
主な美容医療の種類と特徴
| クマのタイプ | 代表的な治療法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 青クマ | 光治療 (IPL) | 血行促進、肌のトーンアップ |
| 茶クマ | レーザートーニング | メラニン色素の破壊・排出促進 |
| 黒クマ | ヒアルロン酸注入、経結膜脱脂術 | 凹凸の改善、影の解消 |
クマを悪化させないための予防と生活習慣
一度改善したクマを再発させないため、また新たなクマを作らないためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。
毎日の小さな心がけが、明るい目元を保つ秘訣です。
質の良い睡眠を確保する
睡眠は、体の疲れを取るだけでなく、肌細胞の修復や再生を行うための大切な時間です。毎日6〜8時間を目安に、質の良い睡眠を確保しましょう。
就寝前にスマートフォンを見るのをやめ、リラックスできる環境を整えることが、深い眠りにつながります。
バランスの取れた食事
健やかな肌と良い血行は、体の中から作られます。
特に、血行を促進するビタミンE、肌のターンオーバーを助けるビタミンA、メラニンの生成を抑えるビタミンC、そして血液の材料となる鉄分などを意識して摂取することが大切です。
血行促進や美肌に役立つ栄養素
- ビタミンE(かぼちゃ、ナッツ類)
- ビタミンC(パプリカ、ブロッコリー、果物)
- 鉄分(レバー、ほうれん草、あさり)
正しいスキンケアと紫外線対策
毎日のスキンケアが、未来の目元を作ります。特にクレンジングの際は、ゴシゴシこすらず、専用のリムーバーを使って優しくメイクを落としましょう。
そして、紫外線は季節や天候に関わらず一年中降り注いでいます。日焼け止めを目元まで丁寧に塗り、日中の塗り直しも忘れないようにしてください。
クマの予防法まとめ
| 項目 | ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 質と量の確保 | 就寝前のスマホを控える、寝室の環境整備 |
| 食事 | ビタミンや鉄分を意識 | 緑黄色野菜やナッツ、レバーなどを食事に取り入れる |
| スキンケア | 摩擦を避ける、紫外線対策 | ポイントメイクリムーバーの使用、毎日の日焼け止め |
目の下のクマに関するよくある質問
最後に、目の下のクマに関して多くの方が抱く疑問にお答えします。正しい知識を身につけ、クマの悩み解消に役立ててください。
- 複数の種類のクマが混在することはありますか?
-
はい、あります。例えば、血行不良による「青クマ」と、たるみによる「黒クマ」が同時に存在することは珍しくありません。これを「混合クマ」と呼びます。
複数の原因が絡み合っているため、セルフケアも多角的なアプローチが必要です。温めて血行を促しつつ、エイジングケアも取り入れるなど、それぞれの原因に対応するケアを組み合わせることが大切です。
- クマを隠すコンシーラーの選び方を教えてください?
-
コンシーラーは、クマの色と反対の色(補色)を選ぶと効果的にカバーできます。自分のクマのタイプに合わせて色を選ぶのがポイントです。
クマを隠すコンシーラーの色選び
クマのタイプ おすすめのコンシーラー色 理由 青クマ オレンジ系、ピーチ系 青色の補色であるオレンジが血色感をプラスする 茶クマ イエロー系 茶色のくすみを飛ばし、肌の色ムラを均一にする 黒クマ 明るいベージュ、オークル系 光で影を飛ばし、凹凸を目立たなくさせる 選ぶ際は、自分の肌色より少しだけ暗い色か同系色を選ぶと、白浮きせず自然に仕上がります。
- 一度できてしまったクマはもう消えませんか?
-
クマの種類や原因、そして個人の肌質や生活習慣によって異なりますが、適切なケアを行えば改善することは十分に可能です。
青クマや軽度の茶クマは、生活習慣の見直しやセルフケアで薄くなることが期待できます。
たるみが原因の黒クマはセルフケアだけでの完全な解消は難しいですが、進行を緩やかにしたり、エイジングケアで目立ちにくくしたりすることはできます。
諦めずに、まずはご自身のクマのタイプに合ったケアを継続することが重要です。
参考文献
SARKAR, Rashmi, et al. Periorbital hyperpigmentation: a comprehensive review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 49.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
IMAM, Mustafa Hussain, et al. Infra-orbital Hyper-pigmentation (Dark Circles): A Study of its Prevalence, Etiology and its Association with Other Dermatological Symptoms among Young Adults. 2025.
PARK, Kui Young, et al. Treatments of infra-orbital dark circles by various etiologies. Annals of dermatology, 2018, 30.5: 522-528.
CHATTERJEE, Manas, et al. A study of epidemiological, etiological, and clinicopathological factors in periocular hyperpigmentation. Pigment International, 2018, 5.1: 34-42.
POUR MOHAMMAD, Arash, et al. The First Systematic Review and Meta‐Analysis of Pharmacological and Nonpharmacological Procedural Treatments of Dark Eye Circles (Periorbital Hyperpigmentations): One of the Most Common Cosmetic Concerns. Dermatologic Therapy, 2025, 2025.1: 9155535.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
FATIN, Amira M., et al. Classification and characteristics of periorbital hyperpigmentation. Skin Research and Technology, 2020, 26.4: 564-570.
PISSARIDOU, Maria Katerina; GHANEM, Ali; LOWE, Nicholas. Periorbital Discolouration diagnosis and treatment: evidence-based review. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2020, 22.6-8: 217-225.
FRIEDMANN, Daniel P.; GOLDMAN, Mitchel P. Dark circles: etiology and management options. Clinics in plastic surgery, 2015, 42.1: 33-50.
クマの種類診断に戻る