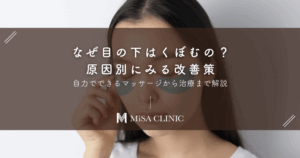目の下にできた深いくぼみは、自分では元気なつもりでも「疲れている?」「寝不足?」と心配されたり、実年齢より上に見られたりする原因になります。
コンシーラーで隠そうとしても、時間が経つとヨレてしまい、かえってくぼみが目立つことも少なくありません。
この目の下のくぼみは、単なるクマとは異なり、骨格や加齢による構造的な問題が関係していることが多く、セルフケアだけでの改善が難しいケースもあります。
この記事では、なぜ目の下に窪みができるのか、その原因を詳しく解説し、今日から始められるセルフケア方法、そして美容クリニックで受けられる効果的な治療法まで、あなたの悩みに寄り添いながら幅広く紹介します。
ご自身のくぼみの原因を理解し、適切な改善策を見つけるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
目の下のくぼみがもたらす印象の変化
目の下のくぼみは、顔の印象に大きな影響を与えます。自分では気づかなくても、他者からの見え方が変わり、意図しない印象を与えてしまうことがあります。
特に「老け見え」や「疲れ顔」といったイメージに直結しやすく、多くの女性が抱える悩みのひとつです。ここでは、目の下のくぼみが具体的にどのような印象の変化をもたらすのかを解説します。
老けて見える「影」の正体
目の下にくぼみがあると、その部分が影になります。この影こそが、老けた印象を与える大きな原因です。顔は、光が当たることで立体感が生まれ、若々しく見えます。
しかし、目の下に凹凸があると、その部分に光が届きにくくなり、暗い影(黒クマ)が落ちます。
この影は、肌の色自体が変化しているわけではないため、ファンデーションやコンシーラーを重ねてもなかなか隠すことができません。
むしろ、メイクで厚塗りすることで、皮膚の質感の違いが際立ち、余計に影が目立ってしまうことさえあります。
年齢とともに顔の脂肪が減少したり、皮膚がたるんだりすることで、このくぼみと影はより顕著になり、見た目年齢を大きく左右する要因となります。
疲れているように見られる原因
目の下のくぼみは、「疲労」のサインとしても認識されがちです。
十分な休息をとっていても、くぼみによる影があるだけで「寝不足ではないか」「体調が悪いのではないか」と周囲に心配される経験を持つ人も少なくないでしょう。
これは、人間が他者の健康状態を判断する際に、無意識に目元の状態を見ているためです。
ハリがあり、明るい目元は健康的な印象を与えますが、くぼんで影がある目元は、活力がなく、疲弊しているような印象を与えます。
本人の体調とは関係なく、外見だけで不健康なイメージを持たれてしまうことは、社会生活において小さなストレスの積み重ねにつながる可能性があります。
メイクでは隠しきれない悩み
メイクアップは、多くの肌悩みをカバーする強力な手段ですが、目の下のくぼみに関しては限界があります。くぼみは、色素沈着のような「色」の問題ではなく、皮膚の凹凸という「形」の問題だからです。
明るい色のコンシーラーを使っても、影を完全に消し去ることは困難です。また、目の下の皮膚は非常に薄く、表情によってよく動く部分でもあります。
そのため、コンシーラーを厚く塗ると、時間とともによれてシワに入り込み、かえってくぼみを強調してしまう結果になりがちです。
多くの人が、様々なコンシーラーやメイクテクニックを試しても満足のいく結果が得られず、根本的な解決策を求めています。
なぜ目の下に窪みができるのか?主な原因を解説
目の下のくぼみは、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。生まれ持った骨格から、年齢を重ねることで起こる変化、そして日々の生活習慣まで、その原因は多岐にわたります。
自分のくぼみがなぜできているのかを知ることは、適切な対策を選ぶ上で非常に重要です。ここでは、目の下のくぼみができる主な原因を詳しく見ていきましょう。
生まれつきの骨格の影響
目の下のくぼみやすさは、生まれ持った顔の骨格に大きく影響されます。
特に、頬骨の位置が低かったり、眼窩(がんか)と呼ばれる眼球が収まっている骨のくぼみが大きかったりすると、若い頃から目の下が窪んで見えやすい傾向があります。
このような骨格の場合、目の下の脂肪(眼窩脂肪)を支える土台が相対的に少なく、皮膚が薄いため、構造的に影ができやすくなります。
ご両親や親族に同じような悩みを持つ方がいる場合、骨格的な要因が強い可能性があります。
これは病気や不健康のサインではなく、あくまで個性ですが、見た目の印象に影響を与えるため、コンプレックスに感じる人もいます。
加齢による皮膚と脂肪の変化
年齢を重ねることも、目の下のくぼみができる大きな原因です。加齢に伴い、私たちの身体にはいくつかの変化が生じます。
まず、肌のハリや弾力を支えているコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄く、たるみやすくなります。さらに、目の周りにある眼輪筋(がんりんきん)という筋肉も衰えていきます。
これにより、眼球をクッションのように支えている眼窩脂肪が、前方へ押し出されやすくなり、目の下にふくらみ(目袋)ができます。
このふくらみのすぐ下がくぼんで見えることで、段差が強調され、深い影が生まれます。
また、同時に頬の脂肪が減少したり、下垂したりすることも、目の下と頬の境界線を際立たせ、くぼみをより深く見せる一因となります。
加齢による目元の主な変化
| 変化する部位 | 変化の内容 | くぼみへの影響 |
|---|---|---|
| 皮膚 | コラーゲン・エラスチンの減少 | ハリが失われ、たるみやすくなる |
| 筋肉(眼輪筋) | 筋力の低下 | 眼窩脂肪を支えきれなくなる |
| 脂肪 | 眼窩脂肪の突出・頬脂肪の減少 | 目の下のふくらみとくぼみの段差が目立つ |
生活習慣がくぼみを悪化させる?
骨格や加齢といった根本的な原因に加え、日々の生活習慣が目の下のくぼみを助長することがあります。
特に、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用は、眼精疲労を引き起こします。眼精疲労は、目周りの血行不良を招き、皮膚の健康状態を悪化させ、くぼみが目立ちやすくなる原因となり得ます。
また、睡眠不足やストレスも血行不良につながり、肌のターンオーバーを乱すため、目元のハリを損なう要因です。
食生活の乱れや喫煙、過度な飲酒も、肌の老化を早め、間接的にくぼみを悪化させる可能性があります。
これらの生活習慣は、すぐにくぼみを作るわけではありませんが、長期的に見ると目元の印象に確実に影響を与えます。
間違ったスキンケアのリスク
良かれと思って行っているスキンケアが、実は目の下のくぼみを悪化させる原因になっている可能性もあります。目の周りの皮膚は、顔の他の部分に比べて非常に薄くデリケートです。
クレンジングや洗顔の際にゴシゴシと強くこすったり、マッサージで過度な圧力をかけたりすると、皮膚にダメージを与え、たるみやシワの原因となります。
また、保湿が不十分だと、皮膚が乾燥して小じわが増え、くぼみがより目立って見えます。アイクリームなどを使用する際も、優しくなじませることが大切です。
日々のスキンケアでは、摩擦を避け、十分な保湿を心がけることが、健やかな目元を保つために重要です。
目の下のくぼみの種類と見分け方
「目の下のクマ」と一括りにされがちですが、実は原因によっていくつかの種類に分けられます。
目の下のくぼみは、主に「黒クマ」と呼ばれるタイプに分類されますが、他の種類のクマと混合している場合も少なくありません。
自分のクマがどのタイプなのかを正しく見分けることで、適切なケア方法を選択できます。ここでは、くぼみの正体である黒クマと、混同されやすい他のクマとの違いについて解説します。
影のように見える「黒クマ」
目の下のくぼみによってできる影が「黒クマ」です。
これは、皮膚の色そのものが変化しているわけではなく、加齢などによって生じた目の下のふくらみ(目袋)とその下のくぼみによる段差が影を作り出している状態です。
そのため、顔の角度や光の当たり方によって、濃さが変わって見えるのが特徴です。簡単なセルフチェックとして、手鏡を持ち、顔を真上に向けた状態で鏡を見てみましょう。
このとき、クマが薄くなったり消えたりする場合は、凹凸による影、つまり黒クマである可能性が高いです。
黒クマは構造的な問題が原因であるため、美白化粧品や血行促進のケアでは改善が難しいとされています。
色素沈着による「茶クマ」との違い
「茶クマ」は、メラニン色素の沈着が原因で、目の下が茶色くくすんで見える状態です。目をこする癖があったり、紫外線対策を怠っていたり、メイク落としが不十分だったりすることが主な原因です。
黒クマとの見分け方は、皮膚を軽く引っ張ってみることです。皮膚を引っ張っても色の濃さが変わらず、クマが一緒に動く場合は茶クマの可能性が高いでしょう。
茶クマのケアは、美白成分の入ったスキンケアや紫外線対策、摩擦を避けることが中心となります。黒クマと茶クマが合併していることもあり、その場合は影と色素沈着の両方へのアプローチが必要です。
血行不良が原因の「青クマ」との違い
「青クマ」は、目の下の薄い皮膚から毛細血管が透けて見える状態です。睡眠不足、疲労、冷えなどによって血行が悪くなると、血液がうっ滞し、青黒く見えます。
色白で皮膚が薄い人は特に目立ちやすい傾向があります。黒クマとの見分け方は、目尻を軽く横に引っ張ってみることです。引っ張って色が少し薄くなるようであれば、青クマの可能性が考えられます。
青クマのケアは、目元を温めたり、マッサージで血行を促進したり、十分な休息をとることが効果的です。くぼみによる黒クマと、血行不良による青クマが同時に現れると、より一層疲れた印象が強くなります。
クマの種類簡易チェック法
| クマの種類 | 主な原因 | 見分け方 |
|---|---|---|
| 黒クマ | 皮膚のたるみ・凹凸 | 上を向くと薄くなる |
| 茶クマ | 色素沈着 | 皮膚を引っ張っても色が薄くならない |
| 青クマ | 血行不良 | 皮膚を引っ張ると色が少し薄くなる |
自宅でできる目の下のくぼみセルフケア
目の下のくぼみを完全に消すことは難しいかもしれませんが、日々のセルフケアを丁寧に行うことで、くぼみを目立ちにくくしたり、将来の悪化を予防したりすることは可能です。
大切なのは、目元にハリと潤いを与え、血行を促進し、健やかな状態を保つことです。
ここでは、自宅で実践できる目の下のくぼみに対するセルフケア方法を紹介します。
保湿とハリを与えるスキンケア成分
目の下の皮膚は乾燥しやすく、乾燥は小じわやくぼみを目立たせる原因になります。
そのため、保湿力の高い成分や、肌にハリを与える成分が配合されたアイクリームなどを日々のスキンケアに取り入れることが重要です。
化粧水や美容液を顔全体につけた後、スキンケアの最後にアイクリームを優しくなじませましょう。薬指の腹を使って、目頭から目尻に向かってポンポンと軽く叩き込むように塗布するのがポイントです。
摩擦は絶対に避け、あくまで優しくケアすることを心がけてください。
目の下のくぼみケアにおすすめの成分
| 成分カテゴリー | 代表的な成分 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸 | 角質層に水分を蓄え、乾燥を防ぐ |
| ハリ・弾力ケア成分 | レチノール、ペプチド | コラーゲンの生成をサポートし、肌にハリを与える |
| エイジングケア成分 | ナイアシンアミド、ビタミンC誘導体 | 肌のコンディションを整え、健やかに保つ |
目の周りの血行を促進するマッサージ
目の周りの血行を良くすることは、青クマの改善だけでなく、皮膚に栄養を届け、健康な状態を保つためにも役立ちます。ただし、間違ったマッサージはたるみの原因になるため、注意が必要です。
必ずアイクリームやオイルなどを塗って、指の滑りを良くしてから行いましょう。
- 目の周りの骨に沿って、指の腹で優しく圧をかける
- ピアノを弾くように、軽いタッチで目の周りをタッピングする
- こめかみを優しくプッシュする
これらの動作を、気持ち良いと感じる程度の力で数回繰り返します。あくまで「こする」のではなく「押さえる」「軽く叩く」ことを意識してください。
蒸しタオルで目元を温めてから行うと、さらに血行が促進されやすくなります。
生活習慣の見直しで内側からケア
外側からのスキンケアと同時に、内側からのケアも大切です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動は、全身の血行を促進し、肌の健康を支えます。
特に、目の下の健康を維持するためには、特定の栄養素を意識して摂取することも有効です。
また、スマートフォンやPCを長時間使用する際は、1時間に1回は休憩を挟み、遠くを見たり、目を閉じたりして、目を休ませる習慣をつけましょう。
寝る時の姿勢も、うつ伏せや横向きは顔に圧力がかかりやすいため、仰向けで寝ることをおすすめします。
目の下の健康を支える栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康維持を助ける | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成に必要 | パプリカ、ブロッコリー、果物 |
| ビタミンE | 血行促進をサポートする | ナッツ類、アボカド、植物油 |
セルフケアの限界と注意点
毎日のセルフケアは、目の下のくぼみの悪化予防や、乾燥による小じわを目立たなくするために有効です。しかし、セルフケアだけでは改善が難しいケースも存在します。
期待しすぎるあまり、効果が出ないと間違ったケアに走ってしまうと、かえって状態を悪化させる可能性もあります。
セルフケアの限界を正しく理解し、次のステップを考えるタイミングを知っておくことが大切です。
骨格やくぼみが深い場合は改善が難しい
生まれつきの骨格が原因で目の下がくぼんでいる場合や、加齢によって皮膚のたるみや脂肪の移動が大きく進んでしまっている場合、スキンケアやマッサージだけで凹凸を平らにすることは物理的に困難です。
化粧品は肌の角質層までしか浸透せず、骨格や脂肪の構造を変えることはできません。
セルフケアはあくまで「現状維持」や「悪化の予防」、「見た目の印象を少し良くする」ためのものと捉え、過度な期待は持たないことが重要です。
長年くぼみに悩んでいる、または年々深くなっていると感じる場合は、セルフケアの限界かもしれません。
間違ったマッサージは逆効果になることも
血行促進に良いとされるマッサージですが、やり方を間違えると大きなリスクを伴います。
目の周りの皮膚は非常に薄く、皮下組織との結合も緩やかであるため、強い力でこすると簡単に伸びてしまい、たるみやシワを助長する原因になります。
「くぼみを押し上げたい」「たるみを引き上げたい」という気持ちから、つい力が入ってしまう人もいますが、これは絶対に避けるべきです。
マッサージを行う際は、あくまで「優しく触れる」「軽く圧をかける」程度にとどめましょう。痛みを感じたり、肌が赤くなったりするようなマッサージは、明らかにやりすぎのサインです。
いつ美容医療を検討すべきか
セルフケアを続けても改善が見られない、メイクで隠すことにも限界を感じている、そして目の下のくぼみがコンプレックスになって日々の生活に影響が出ている、と感じ始めたら、美容医療を検討するタイミングかもしれません。
美容医療は、セルフケアではアプローチできない皮膚の深い層や脂肪の構造に直接働きかけることができるため、より根本的な改善が期待できます。
まずは専門のクリニックでカウンセリングを受け、自分の目の下の状態がどのような原因で起きているのか、そしてどのような治療法が適しているのかを相談してみることから始めましょう。
専門家の意見を聞くことで、自分の悩みを客観的に理解し、解決への道筋が見えてくるはずです。
美容クリニックで受けられる目の下のくぼみ治療法
セルフケアでは改善が難しい目の下のくぼみに対して、美容クリニックでは様々な治療法を提供しています。
これらの治療は、くぼみの原因となっている凹凸を物理的に修正し、目元を平らでなめらかな状態に近づけることを目的とします。
どの治療法が適しているかは、くぼみの原因、深さ、皮膚の状態などによって異なります。ここでは、代表的な治療法とその特徴について解説します。
ヒアルロン酸注入
ヒアルロン酸注入は、くぼんでいる部分にヒアルロン酸製剤を注入し、皮膚を内側から持ち上げて凹みを埋める治療法です。注射による治療なので、メスを使う必要がなく、比較的気軽に受けられるのが特徴です。
施術時間も短く、ダウンタイムもほとんどないため、忙しい方にも選ばれています。ただし、ヒアルロン酸は時間とともに体内に吸収されていくため、効果を持続させるには定期的な再注入が必要です。
また、注入する量や層を誤ると、表面が凸凹したり、青白く透けて見えたり(チンダル現象)するリスクもあるため、経験豊富な医師による施術が重要です。
ヒアルロン酸注入の概要
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 施術内容 | くぼんだ部分にヒアルロン酸を注射 | 凹みを直接埋める |
| ダウンタイム | ほとんどない(内出血の可能性あり) | 施術後すぐにメイク可能 |
| 持続期間 | 約1年〜2年 | 製剤の種類や個人差による |
脂肪注入(脂肪移植)
脂肪注入は、ご自身の太ももやお腹などから採取した脂肪を、目の下のくぼんだ部分に注入する治療法です。自分自身の組織を使うため、アレルギー反応のリスクが極めて低いのが大きな利点です。
注入した脂肪の一部は生着し、半永久的な効果が期待できます。ヒアルロン酸に比べて、より自然な仕上がりになりやすいとも言われています。
ただし、脂肪を採取するために別の部位に小さな傷ができること、そして注入した脂肪の生着率には個人差があることが考慮点です。
また、ヒアルロン酸注入と同様に、医師の技術力が仕上がりを大きく左右します。
脂肪注入の概要
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 施術内容 | 自身の脂肪を採取し、くぼみに注入 | アレルギーのリスクが低い |
| ダウンタイム | 1〜2週間程度の腫れ・内出血 | 脂肪採取部位にもダウンタイムがある |
| 持続期間 | 半永久的(生着した場合) | 生着率には個人差がある |
下眼瞼脱脂術(経結膜脱脂法)
目の下のふくらみ(目袋)が大きく、その下のくぼみが目立っている場合に適応されることが多い治療法です。まぶたの裏側(結膜)を小さく切開し、そこから原因となっている余分な眼窩脂肪を取り除きます。
皮膚の表面に傷ができないため、傷跡が顔に残る心配がありません。ふくらみ自体がなくなることで、くぼみとの段差が解消され、影が目立ちにくくなります。
取り除いた脂肪をくぼんだ部分に移動させる(ハムラ法)こともあります。たるみが主な原因ではなく、脂肪の突出が原因でくぼみができている若い世代にも適した治療法です。
自分に合った治療法の選び方
どの治療法が最適かは、一人ひとりの状態によって異なります。単にくぼみを埋めるだけでなく、ふくらみを取る必要があるのか、皮膚のたるみはどの程度かなど、総合的に判断することが重要です。
カウンセリングでは、医師が目元の状態を正確に診察し、考えられる原因と最適な治療プランを提案してくれます。
自分の希望や、ダウンタイムにかけられる時間、予算などを正直に伝え、医師とよく相談して、納得のいく治療法を選びましょう。
各治療法の比較
| 治療法 | 主な目的 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | くぼみを埋める | 手軽に試したい、ダウンタイムが取れない人 |
| 脂肪注入 | くぼみを埋める(半永久) | 持続性を重視する、アレルギーが心配な人 |
| 下眼瞼脱脂術 | ふくらみ(目袋)を取る | 目の下のふくらみが大きく、影になっている人 |
【目の下のくぼみ】よくある質問
目の下のくぼみ治療を検討するにあたり、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。
カウンセリングを受ける前に、基本的な知識を持っておくと、よりスムーズに相談を進めることができます。
- 治療後のダウンタイムはどのくらいですか?
-
ダウンタイムの期間は、受ける治療によって大きく異なります。
ヒアルロン酸注入の場合、注射針による内出血が起こることがありますが、数日から1週間程度で治まることがほとんどで、メイクでカバーできる場合が多いです。
脂肪注入や下眼瞼脱脂術の場合は、1〜2週間程度の腫れや内出血が見られることが一般的です。大きな腫れは数日で引いていきますが、完全に落ち着くまでには1ヶ月程度かかることもあります。
仕事やプライベートの予定を考慮して、治療計画を立てることが大切です。
- 目の下のくぼみは再発しますか?
-
これも治療法によります。ヒアルロン酸注入は、ヒアルロン酸が徐々に体内に吸収されるため、効果は永続的ではなく、効果を維持するためには再度の注入が必要です。
脂肪注入の場合、生着した脂肪は半永久的にその場にとどまりますが、加齢による変化が再び現れる可能性はあります。
下眼瞼脱脂術で取り除いた脂肪は再生しないため、ふくらみが原因のくぼみに関しては再発のリスクは低いと言えます。
しかし、どの治療法であっても、加齢による肌の変化は続くため、長期的な視点でのケアは引き続き重要です。
- 治療に痛みはありますか?
-
痛みの感じ方には個人差がありますが、各治療で痛みを最小限に抑える工夫がされています。
ヒアルロン酸注入や脂肪注入では、麻酔クリームや局所麻酔を使用するのが一般的です。注射のチクッとした痛みを感じる程度です。
下眼瞼脱脂術のような外科的な手術では、局所麻酔や、希望に応じて静脈麻酔などを併用することで、施術中の痛みを感じることはほとんどありません。
施術後にじんわりとした痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めでコントロールできる範囲です。
- カウンセリングではどのようなことを話しますか?
-
カウンセリングでは、まず医師があなたの目元の状態を診察し、くぼみの原因を診断します。
その上で、あなたの悩みや希望(どのように改善したいか、予算、ダウンタイムなど)を詳しくヒアリングします。
そして、診断結果とあなたの希望を踏まえ、最適な治療法の提案、期待できる効果、考えられるリスクや副作用、費用などについて詳細な説明があります。
疑問や不安な点は、どんな些細なことでも遠慮せずに質問することが大切です。十分に納得した上で、治療に進むかどうかを判断してください。
参考文献
HALEPAS, Steven; CHEN, Xun J.; BANKI, Mohammad. Applied anatomy in blepharoplasty. In: Applied Head and Neck Anatomy for the Facial Cosmetic Surgeon. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 175-181.
NIAMTU, Joe, et al. Orbital Anatomy. Cosmetic Facial Surgery-E-Book, 2022, 345.
LAW, James J.; ZHU, Aretha; BURKAT, Cat N. Advances, Techniques, and Complications Associated with Adjacent Fat Transfer in Lower Blepharoplasty. Advances in Cosmetic Surgery, 2025, 8.1: 153-167.
ELHAMAKY, Tarek Roshdy. Orbital fat graft retroseptal transconjunctival blepharoplasty for treatment of groove in the infraorbital region. International Ophthalmology, 2024, 44.1: 217.
LI, Jingni, et al. Transconjunctival lower blepharoplasty with orbital fat repositioning versus fat grafting for tear trough deformity: A prospective, comparative and randomized study. Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery, 2025, 102320.
JIN, Yunbo, et al. Transconjunctival lower blepharoplasty using midcheek spaces for orbital fat transposition (SOFT). Annals of Plastic Surgery, 2021, 86.6: 620-626.
MAJIDIAN BA, Mandy; KOLLI BS, Hiren; MOY MD, Ronald L. Transconjunctival lower eyelid blepharoplasty with fat transposition above the orbicularis muscle for improvement of the tear trough deformity. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.9: 2911-2916.
KARIMI, Nasser, et al. Minced free fat graft versus pedicle fat flap to efface orbital rim hollow in lower blepharoplasty. Aesthetic Surgery Journal, 2024, 44.1: 12-19.
XU, Wushuang, et al. Enhanced transconjunctival lower blepharoplasty: a novel method for intraorbital fat transposition and stabilization. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.22: 4631-4638.
CARTWRIGHT, Mont J. Opthamology and Aesthetic Surgery Literature Reviews. The American Journal of Cosmetic Surgery, 2001, 18.3: 173-189.