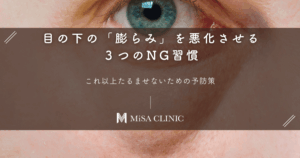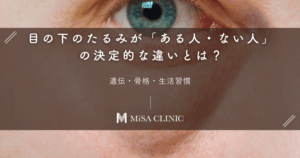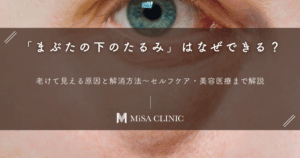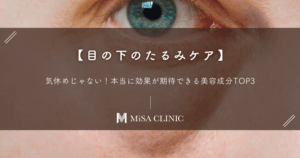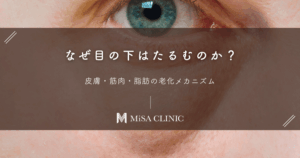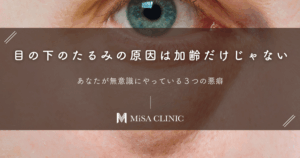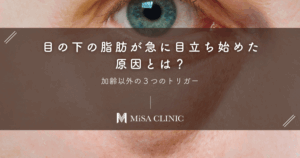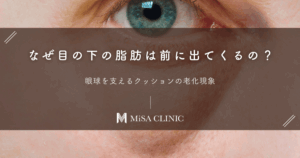鏡を見て「あれ?なんだか急に目の下が膨らんで見える…」と、今まで気にならなかった影やたるみに戸惑っていませんか。
その膨らみは、疲れているように見えたり、実年齢より上に見られたりする原因になり、気分も沈みがちになります。なぜ急に目立ち始めたのか、その原因は一つではありません。
この記事では、目の下の膨らみの正体から、考えられる原因、そして今日からすぐに試せる応急処置までを詳しく解説します。ご自身の状態を正しく理解し、適切なケアを始める第一歩にしてください。
目の下の膨らみ、その正体は?
ふと気づいた目の下の膨らみ。多くの人が「クマ」や「たるみ」と一括りにしてしまいがちですが、その正体を正しく知ることが、改善への近道です。
ここでは、膨らみの根本的な原因について掘り下げていきます。
眼窩脂肪(がんかしぼう)とは
目の下の膨らみの直接的な原因の多くは、「眼窩脂肪」と呼ばれる脂肪です。眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションのような役割を持つ、誰にでもある大切な脂肪です。
本来は、眼窩という骨のくぼみの中に収まっています。これが何らかの要因で前方に押し出されてくることで、皮膚の表面にぽっこりとした膨らみとして現れます。
なぜ脂肪が前に出てくるのか
では、なぜ本来収まっているはずの眼窩脂肪が前に出てきてしまうのでしょうか。主な理由は、眼球の周りにある「ロックウッド靭帯」や「眼輪筋」といった組織の衰えです。
これらの組織は、眼窩脂肪をハンモックのように支える役割を担っています。しかし、加齢や特定の生活習慣によってこれらの支持組織が緩むと、脂肪の重さを支えきれなくなり、前方に突出してしまうのです。
眼窩脂肪を支える組織
| 組織名 | 役割 | 衰える主な要因 |
|---|---|---|
| 眼輪筋 | 目の周りを囲む筋肉。脂肪を内側に押さえる。 | 加齢、PC・スマホの長時間利用による酷使 |
| ロックウッド靭帯 | 眼球と脂肪を下から支える靭帯。 | 加齢による弾力性の低下 |
| 皮膚のハリ | 表面から脂肪の突出を防ぐ。 | 加齢、紫外線、乾燥によるコラーゲン減少 |
クマとの違いを理解する
目の下の悩みとして「クマ」もよく挙げられますが、膨らみとは原因が異なります。タイプを混同すると、間違ったケアをしてしまう可能性もあります。
自分の悩みがどちらのタイプなのか、あるいは両方が混在しているのかを見極めることが重要です。
主なクマの種類と膨らみとの関連性
| タイプ | 主な原因 | 膨らみとの関係 |
|---|---|---|
| 青クマ | 血行不良。皮膚の下の血管が透けて見える。 | 膨らみとは直接関係ないが、併発することもある。 |
| 茶クマ | 色素沈着。目をこする癖や紫外線ダメージ。 | 膨らみとは直接関係ないが、影を濃く見せる要因に。 |
| 黒クマ(影クマ) | 眼窩脂肪の突出による膨らみとその下の凹みが影を作る。 | 膨らみが直接の原因。多くの膨らみはこのタイプを伴う。 |
急に膨らみが目立ち始めた!考えられる主な原因
「昨日までは気にならなかったのに…」と、急に膨らみが目立つようになったと感じるのには、いくつかの要因が重なっている可能性があります。
ここでは、その引き金となり得る主な原因を見ていきましょう。
加齢による皮膚のたるみ
最も大きな原因の一つが、加齢による自然な変化です。年齢を重ねると、肌のハリを保つコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄く、弾力を失っていきます。
同時に、前述した眼輪筋などの筋力も低下します。これにより、これまでかろうじて支えていた眼窩脂肪が、皮膚の表面に押し出されやすくなり、ある日突然、膨らみとして認識されることがあります。
長時間のデジタルデバイス使用
スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続ける生活は、目元の筋肉に大きな負担をかけます。画面に集中するとまばたきの回数が減り、眼輪筋が緊張し続けて血行不良を引き起こします。
この状態が続くと、眼輪筋の衰えを早め、眼窩脂肪を支える力が弱まる一因となります。リモートワークの普及などで、こうした生活習慣が定着した結果、若年層でも膨らみが目立つケースが増えています。
睡眠不足と不規則な生活
睡眠不足は、体の回復機能を低下させ、血行不良を招きます。特に目元は皮膚が薄く、血行の状態が顕著に現れる部位です。血行が悪くなると、細胞の再生が滞り、肌のハリが失われやすくなります。
また、疲労の蓄積は筋肉の緊張を招き、目元の組織全体の衰えを加速させ、膨らみが目立ちやすくなる環境を作ってしまいます。
塩分の多い食生活とむくみ
塩分の多い食事を摂ると、体は水分を溜め込もうとし、「むくみ」が生じます。顔、特に皮膚の薄い目元はむくみの影響を受けやすく、一時的に膨らみが強調されることがあります。
日常的に塩分過多の食生活を送っていると、慢性的なむくみが定着し、それが膨らみを目立たせる要因となります。むくみは血行不良も助長するため、複合的な悪影響を与えます。
生活習慣と目の下の膨らみへの影響
| 生活習慣 | 主な影響 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| デジタルデバイスの多用 | 眼輪筋の衰え、血行不良 | 適度な休憩、目元のストレッチ |
| 睡眠不足 | 肌のターンオーバーの乱れ、血行不良 | 質の良い睡眠の確保 |
| 塩分過多な食事 | むくみによる膨らみの強調 | 食生活の見直し、カリウム摂取 |
自分でできる?目の下の膨らみセルフチェック
自分の目の下の膨らみがどのタイプで、どの程度のものなのかを把握することは、適切なケアを選ぶ上でとても大切です。専門家でなくても、簡単な方法で自分の状態を確認できます。
鏡を使った簡単な確認方法
まず、手鏡を持って、顔を正面から見てください。普段の状態で、目の下に膨らみがあるか、その下に影ができていないかを確認します。
このとき、部屋の照明が顔全体に均一に当たるようにすると、影の状態が分かりやすくなります。
上を向いた時の変化を観察
次に、鏡を持ったまま、顔は正面を向けたまま天井を見るように視線だけを上に動かしてみてください。
もし、この動作で目の下の膨らみが目立たなくなったり、平坦に近くなったりした場合は、その膨らみは眼窩脂肪の突出によるものである可能性が高いです。
これは、上を向くことで脂肪が重力で奥に戻るために起こる変化です。逆に、上を向いても膨らみや色の変化が少ない場合は、色素沈着や血行不良が主な原因かもしれません。
セルフチェックの手順
- 明るい場所で手鏡を用意する。
- 顔を正面に向け、膨らみと影を確認する。
- 天井を見上げ、膨らみが目立たなくなるか確認する。
膨らみの色でタイプを判断
膨らみやその周りの色もヒントになります。膨らみの下が黒っぽく影のように見える場合は「黒クマ(影クマ)」で、眼窩脂肪が原因です。
もし、皮膚を軽く引っ張ると色が薄くなる場合は、血行不良による「青クマ」の可能性もあります。膨らみとクマが併発しているケースは非常に多いため、色と形状の両方から判断することが重要です。
今すぐ試せる!応急処置で見た目印象を改善
根本的な解決にはなりませんが、大事な予定がある日など、一時的にでも膨らみを目立たなくしたい場面はあるでしょう。ここでは、すぐに取り組める応急処置の方法を紹介します。
ただし、これらはあくまで一時的な対策であることを理解しておきましょう。
メイクで上手にカバーするコツ
メイクは、膨らみを視覚的にカモフラージュする最も手軽な方法です。ポイントは「光と影を操る」ことです。
膨らんでいる部分ではなく、その下の影になっている部分に、自分の肌より少し明るいコンシーラーを少量乗せ、指で優しく叩き込むように馴染ませます。
これにより、影が明るくなり、膨らみとの段差が目立ちにくくなります。
メイクアイテムの選び方と使い方
| アイテム | 選び方のポイント | 効果的な使い方 |
|---|---|---|
| コンシーラー | 肌よりワントーン明るい色。硬すぎず伸びの良い質感。 | 膨らみの下の影の部分に細く線状に乗せる。 |
| ハイライト | パール感が強すぎない、肌馴染みの良いもの。 | コンシーラーの上から少量重ね、影を飛ばす。 |
| フェイスパウダー | 細かい粒子で、乾燥しにくいタイプ。 | 最後に軽く押さえてメイク崩れを防ぐ。 |
温冷タオルで血行を促す
むくみや血行不良が膨らみを強調している場合、温冷ケアが有効なことがあります。まず、蒸しタオルで目元をじっくりと温めて血行を良くします。その後、冷たいタオルで軽く引き締めます。
これを2〜3回繰り返すことで、血流が促進され、むくみが一時的に緩和されることがあります。ただし、目元の皮膚はデリケートなので、タオルの温度には十分注意してください。
優しく行うツボ押しとマッサージ
目元の血行を促すツボ押しも応急処置として役立ちます。ただし、強い力でこするのは絶対に避けてください。シワやたるみを悪化させる原因になります。
薬指の腹を使って、優しく押さえる程度の圧で行うのがポイントです。
目元の血行促進に役立つツボ
- 攅竹(さんちく)眉頭の内側のくぼみ。
- 晴明(せいめい)目頭のやや内側の鼻の付け根。
- 承泣(しょうきゅう)瞳の真下、骨の縁のあたり。
これらのツボを、1ヶ所につき5秒ほど、心地よいと感じる程度の圧でゆっくりと押します。アイクリームなどを塗って滑りを良くしてから行うと、肌への負担を軽減できます。
注意点 やりすぎは逆効果に
セルフマッサージやツボ押しは、手軽な一方でリスクも伴います。強い力で押したり、長時間こすり続けたりすると、皮膚が伸びてしまったり、色素沈着を起こしたりする可能性があります。
あくまで「優しく」「短時間で」行うことを徹底し、少しでも違和感があればすぐに中止することが大切です。応急処置は、根本原因である眼窩脂肪をなくすものではない、という事実を忘れないでください。
セルフケアの限界と根本的な改善方法
日々のケアや応急処置は、見た目印象を一時的に良くしたり、悪化を防いだりする上で意味があります。
しかし、一度前に出てきてしまった眼窩脂肪をセルフケアだけで元に戻すことは、残念ながら非常に困難です。ここでは、その理由と、根本的な改善を目指すための選択肢について解説します。
なぜセルフケアだけでは改善が難しいのか
化粧品やマッサージは、主に皮膚の表面や血行に働きかけるものです。
肌にハリを与えたり、むくみを軽減したりする効果は期待できますが、皮膚の内側から物理的に突出している眼窩脂肪そのものを減らしたり、緩んでしまった支持組織(靭帯や筋肉)を元通りに引き締めたりすることはできません。
セルフケアを続けても改善が見られないのは、アプローチする対象が異なるためです。
美容クリニックで受けられる治療法
目の下の膨らみを根本的に改善するためには、美容医療が有効な選択肢となります。クリニックでは、専門の医師が一人ひとりの状態を正確に診断し、原因に直接アプローチする治療を行います。
カウンセリングを通じて、治療法のメリットやデメリット、ダウンタイムなどについて詳しい説明を受け、納得した上で治療に進むことができます。
治療法の種類と特徴
目の下の膨らみ治療には、大きく分けて「切らない治療」と「切る治療」があります。どちらが適しているかは、膨らみの程度や皮膚のたるみ具合、個人の希望によって異なります。
主な治療法の比較
| アプローチ | 代表的な治療法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 切らない治療 | 経結膜脱脂法 | まぶたの裏側から小さな穴を開け、余分な脂肪を取り除く。皮膚表面に傷が残らない。 |
| 切る治療 | ハムラ法・裏ハムラ法 | 脂肪を移動させて凹みを埋める。たるんだ皮膚も同時に切除できる場合がある。 |
| 注入治療 | ヒアルロン酸・脂肪注入 | 膨らみの下の凹みに注入し、段差を滑らかにする。根本治療ではないが、手軽に行える。 |
自分に合った治療法を見つけるために
最適な治療法は人それぞれです。
例えば、膨らみが主で皮膚のたるみが少ない若い世代には経結膜脱脂法が適していることが多い一方、たるみも同時に改善したい場合には切開を伴う方法が選ばれることもあります。
まずは専門医の診察を受け、自分の目の下の状態を正しく評価してもらうことが、後悔のない治療への第一歩です。
後悔しないためのクリニック選びのポイント
根本的な改善を目指して美容医療を受けると決めたなら、どのクリニックを選ぶかが非常に重要になります。
安心して任せられる、信頼できるクリニックを見つけるためのポイントを紹介します。
専門医のカウンセリングを受ける重要性
最も大切なのは、経験豊富な医師によるカウンセリングです。ただ治療法を説明するだけでなく、あなたの悩みや希望を親身に聞き、複数の選択肢を提示してくれるかどうかが重要です。
メリットだけでなく、考えられるリスクやダウンタイムについてもしっかりと説明し、質問にていねいに答えてくれる医師を選びましょう。
カウンセリングは1つのクリニックだけでなく、複数のクリニックで受けて比較検討することをお勧めします。
施術実績と症例写真を確認する
そのクリニックや医師が、目の下の治療をどれだけ手がけてきたかという実績は、技術力を判断する上での大きな指標になります。
公式ウェブサイトなどで、自分と似たような症状の症例写真が豊富に掲載されているかを確認しましょう。
写真を見る際は、施術前後の変化だけでなく、様々な角度から撮影されているか、写真の明るさなどが不自然に加工されていないかもチェックするポイントです。
クリニック選びのチェックポイント
| チェック項目 | 確認する内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| カウンセリングの質 | 医師が直接行うか。丁寧で分かりやすいか。 | 治療への理解と信頼関係の構築に必要。 |
| 施術実績・症例数 | 目の下の治療経験が豊富か。症例写真は多いか。 | 医師の技術力や得意分野を判断する材料になる。 |
| 費用体系の明確さ | 提示された費用に何が含まれるか明確か。 | 後からの追加料金などのトラブルを避けるため。 |
費用とアフターケア体制を比較検討
治療費用はクリニックによって異なります。提示された金額が、診察料、麻酔代、薬代、そして施術後の検診など、すべてを含んだものなのかを事前に必ず確認してください。
また、施術後のフォロー体制も重要です。万が一、何かトラブルがあった場合に迅速に対応してくれるか、定期的な検診は行われるかなど、アフターケアが充実しているクリニックを選ぶと安心です。
日常生活で心がけたい予防と対策
すでに膨らみが気になっている方も、これから予防したい方も、日常生活を見直すことは非常に大切です。
これ以上の悪化を防ぎ、健やかな目元を保つために、今日からできることを始めましょう。
質の良い睡眠を確保する
睡眠は、体のあらゆる部分を修復するためのゴールデンタイムです。特に肌のターンオーバーを正常に保ち、血行を促進するためには、6〜7時間程度の質の良い睡眠を確保することが理想です。
寝る前のスマートフォンの使用を控える、自分に合った寝具を選ぶなど、リラックスできる環境を整えましょう。
バランスの取れた食生活
体の内側からのケアも重要です。むくみの原因となる塩分の多い食事は控えめにし、余分な塩分を排出する働きのあるカリウム(海藻類、バナナ、アボカドなど)を積極的に摂ることをお勧めします。
また、抗酸化作用のあるビタミンA、C、Eや、血行を促進する鉄分などもバランス良く摂取し、健康な肌と体作りを心がけましょう。
目元の保湿と紫外線対策
目元の皮膚は非常にデリケートで乾燥しやすいため、保湿は欠かせません。アイクリームなどを使い、薬指で優しく叩き込むようにして潤いを与えましょう。
また、紫外線は肌のコラーゲンを破壊し、たるみを引き起こす最大の外的要因です。季節を問わず、サングラスや日焼け止め、UVカット機能のある化粧下地などで、目元を紫外線から守る習慣をつけましょう。
目の下の膨らみに関するよくある質問
- 膨らみは一度できたら自然に治りませんか?
-
眼窩脂肪の突出が原因である場合、残念ながら自然に治ることはほとんどありません。
むくみによる一時的な膨らみであれば生活習慣の改善で目立たなくなることもありますが、構造的な問題である脂肪の突出は、セルフケアで元に戻すことは困難です。
悪化させないための予防は可能ですが、根本的な改善には美容医療の検討が必要です。
- 男性でも目の下の膨らみはできますか?
-
はい、できます。目の下の膨らみの原因である眼窩脂肪やそれを支える組織の構造は、男女で違いはありません。
加齢や生活習慣の影響は性別に関係なく受けるため、男性でも悩んでいる方は多くいらっしゃいます。最近では、男性専門のクリニックやメニューも増えています。
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
治療法によって大きく異なります。例えば、経結膜脱脂法のような切らない治療の場合、施術自体は1時間程度で終わることが多いです。
カウンセリングや術後の検診を含めると、通院は数回必要になります。切開を伴う治療の場合は、もう少し時間がかかることもあります。
詳しくは、カウンセリング時に医師に確認することが大切です。
- 治療後のダウンタイムはありますか?
-
はい、どのような治療でもダウンタイムはあります。個人差や治療法によりますが、一般的には腫れや内出血が主な症状です。
切らない治療(経結膜脱脂法など)では、大きな腫れは数日から1週間程度で落ち着くことが多いです。切る治療の場合は、もう少し長くかかる傾向にあります。
仕事や学校など、ご自身のスケジュールに合わせて治療計画を立てることが重要です。
参考文献
VERNER, Ines; GALADARI, Hassan I. Management of Infraorbital Wrinkles and Pigmentation. Hot Topics in Cosmetic Dermatology, An Issue of Dermatologic Clinics, E-Book: Hot Topics in Cosmetic Dermatology, An Issue of Dermatologic Clinics, E-Book, 2023, 42.1: 79-88.
RATHORE, Gyanesh, et al. Clinical assessment, diagnosis, and Management of Infraorbital Wrinkles and Pigmentation. Dermatologic Clinics, 2024, 42.1: 79-88.
JACOBS, Leonie C., et al. Intrinsic and extrinsic risk factors for sagging eyelids. JAMA dermatology, 2014, 150.8: 836-843.
LIPP, Michael; WEISS, Eduardo. Nonsurgical treatments for infraorbital rejuvenation: a review. Dermatologic surgery, 2019, 45.5: 700-710.
BUCAY, Vivian W.; DAY, Doris. Adjunctive skin care of the brow and periorbital region. Clinics in plastic surgery, 2013, 40.1: 225-236.
RAJABI‐ESTARABADI, Ali, et al. Effectiveness and tolerance of multicorrective topical treatment for infraorbital dark circles and puffiness. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.2: 486-495.
TAO, Brendan K., et al. Periocular Aging Across Populations and Esthetic Considerations: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine, 2025, 14.2: 535.
FRANCO, Abigail I.; IBRAHIM, Sherrif F.; VELEZ, Mara Weinstein. Periorbital rejuvenation: Racial/ethnic considerations and expert techniques. In: Cosmetic Procedures in Skin of Color. Elsevier, 2025. p. 206-215.
SHASHIKIRAN, A. R. Clinical Study of Facial Skin Disorders. 2016. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
BHOJANI-LYNCH, Tahera; BERROS, Philippe; SNOZZI, Philippe. Optimizing Infraorbital Hollows Treatment With Hyaluronic Acid Fillers: Overview of Anatomy, Injection Techniques, and Product Considerations. In: Aesthetic Surgery Journal Open Forum. Oxford University Press, 2025. p. ojaf069.