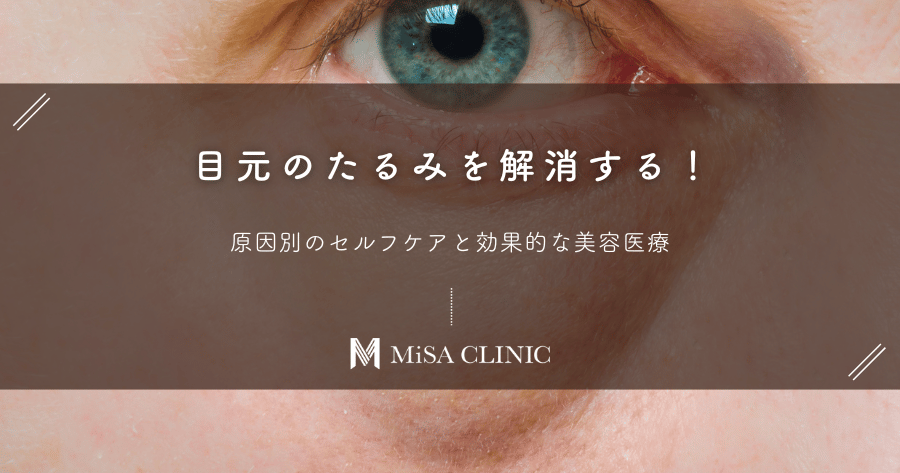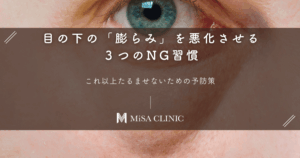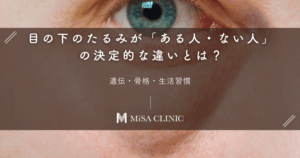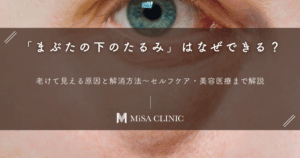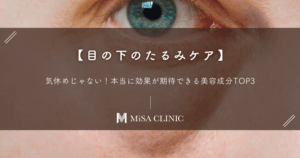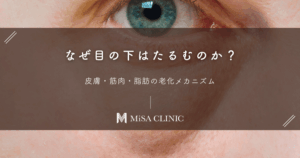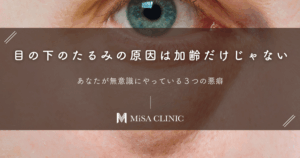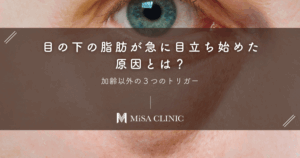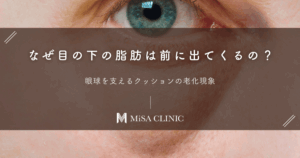ふと鏡を見たときに気になる、目元のたるみ。「疲れているように見える」「老けた印象を与える」など、多くの方が悩みを抱えています。
このたるみは、なぜできてしまうのでしょうか。
実は、その原因は一つではありません。この記事では、目元のたるみが起こる原因を詳しく解説し、ご自身でできるセルフケアの方法から、より効果的な改善を目指すための美容医療まで、幅広くご紹介します。
あなたの悩みに寄り添い、ハリのある明るい目元を取り戻すための情報をお届けします。
目元のたるみとは?その正体と種類
目元のたるみと一言でいっても、その状態は人それぞれです。
まずは、なぜ目元がたるみやすいのか、そしてどのような種類があるのかを理解することが、適切なケアへの第一歩です。
なぜ目元はたるみやすいのか
顔の中でも特に目元の皮膚は薄く、頬の皮膚の3分の1から4分の1程度の厚さしかありません。また、皮脂腺が少なく乾燥しやすいため、外部からの刺激や乾燥の影響を受けやすいデリケートな部分です。
さらに、目の周りには眼球を支えるための脂肪(眼窩脂肪)や、目を囲むように存在する眼輪筋があります。これらの組織が加齢などによって衰えることで、たるみが生じやすくなります。
たるみの種類を見分ける
目元のたるみにはいくつかの種類があり、原因や見た目が異なります。ご自身のたるみがどのタイプかを知ることで、効果的な対策を見つけやすくなります。
たるみの主な種類と特徴
| たるみの種類 | 見た目の特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 皮膚のたるみ | 目の下に細かく薄いシワや、余った皮膚が重なる状態。 | 加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少、乾燥。 |
| 影ぐま(黒くま) | 目の下が黒くくぼんで見える。上を向くと薄くなるのが特徴。 | 眼窩脂肪の突出や、皮膚のへこみによる影。 |
| むくみによるたるみ | 朝方に特に目立つ、一時的なふくらみ。 | 塩分の過剰摂取、睡眠不足、血行不良。 |
放置するとどうなる?
目元のたるみをそのままにしておくと、たるみがさらに進行し、影が深くなることで「老け顔」や「疲れ顔」の印象が定着してしまうことがあります。
また、たるんだ皮膚が視野を狭めたり、ものが二重に見えたりするなど、機能的な問題につながる可能性もゼロではありません。早めに原因を理解し、対策を始めることが重要です。
目元のたるみを引き起こす主な原因
目元のたるみは、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。ここでは、たるみを引き起こす代表的な原因について詳しく見ていきましょう。
加齢による肌の変化
年齢を重ねると、肌のハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、質も低下します。これにより皮膚そのものが弾力を失い、重力に負けてたるみやすくなります。
また、目の周りの眼輪筋も衰えるため、眼窩脂肪を支えきれなくなり、前に押し出されてふくらみ(たるみ)となることがあります。
紫外線の影響
紫外線は肌の老化を加速させる最大の外的要因です。特に波長の長いUVAは、肌の奥深く(真皮層)まで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊します。
日々の紫外線ダメージが蓄積されることで、皮膚のハリが失われ、たるみやシワの原因となります。目元は皮膚が薄いため、特に紫外線の影響を受けやすい部分です。
生活習慣の乱れ
睡眠不足や栄養バランスの偏り、喫煙、過度の飲酒といった生活習慣も、肌の状態に大きく影響します。特に睡眠不足は肌のターンオーバーを乱し、血行不良を招くため、むくみやたるみを悪化させます。
また、スマートフォンやパソコンの長時間利用による眼精疲労も、目元の筋肉を緊張させ、血行を悪くする一因となります。
たるみを助長する生活習慣
| 習慣 | 目元への影響 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 長時間のスマホ・PC作業 | 眼精疲労、血行不良、まばたきの減少による乾燥。 | こまめな休憩、ホットタオルで温める。 |
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、ターンオーバーの乱れ。 | 質の良い睡眠を6〜8時間確保する。 |
| 塩分の多い食事 | 体内の水分バランスが乱れ、むくみが生じやすくなる。 | カリウムを多く含む食品(野菜、果物)を摂る。 |
間違ったスキンケア
クレンジングや洗顔の際に目元をゴシゴシと強くこすることは、薄い皮膚にダメージを与え、たるみを引き起こす原因になります。
また、保湿が不十分で目元が乾燥していると、小じわが増え、それがたるみへとつながることもあります。アイメイクを落とす際は、専用のリムーバーを使い、優しく丁寧にオフすることが大切です。
自宅でできる!原因別セルフケア
目元のたるみは、日々のセルフケアで進行を緩やかにしたり、予防したりすることが可能です。ここでは、原因に合わせた効果的なセルフケア方法を紹介します。
保湿とエイジングケア
目元の乾燥はたるみの大きな原因です。保湿力の高いセラミドやヒアルロン酸などが配合されたアイクリームや美容液を使い、しっかりと潤いを与えましょう。
また、コラーゲンの生成をサポートするレチノールやビタミンC誘導体、ナイアシンアミドなどが配合されたエイジングケア製品を取り入れるのも効果的です。
目元のケアにおすすめの成分
| 成分名 | 期待できる効果 | ポイント |
|---|---|---|
| レチノール | コラーゲン生成促進、ターンオーバーの正常化。 | 刺激を感じる場合があるため、低濃度のものから試す。 |
| ビタミンC誘導体 | コラーゲン生成促進、抗酸化作用。 | 様々な種類があり、肌質に合わせて選ぶことが重要。 |
| ナイアシンアミド | コラーゲン生成促進、セラミド合成促進、シワ改善。 | 比較的刺激が少なく、多くの製品に配合されている。 |
紫外線対策の徹底
紫外線は一年中降り注いでいるため、季節や天候に関わらず、毎日の紫外線対策が必要です。
日焼け止めはもちろん、UVカット機能のあるサングラスや帽子、日傘などを活用して、デリケートな目元を紫外線から守りましょう。
表情筋トレーニング
目の周りにある眼輪筋を鍛えることで、たるみの予防につながります。ただし、やりすぎたり、間違った方法で行ったりすると、かえってシワの原因になることもあるため注意が必要です。
優しく、無理のない範囲で行いましょう。
簡単な眼輪筋トレーニング
- 目をゆっくりと大きく見開き、5秒間キープします。
- ゆっくりと目を閉じ、ぎゅっと力を入れて5秒間キープします。
- この動作を5回ほど繰り返します。
このトレーニングは、あくまで筋肉を意識するためのものであり、皮膚を強く引っ張らないように注意してください。
生活習慣の見直し
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動は、健やかな肌を保つための基本です。特に、抗酸化作用のあるビタミンA、C、Eや、良質なたんぱく質を積極的に摂取することを心がけましょう。
また、温かいタオルで目元を温めて血行を促進することも、むくみや疲れの解消に役立ちます。
セルフケアの限界と美容医療という選択肢
セルフケアはたるみの予防や初期段階のケアには有効ですが、すでに進行してしまったたるみや、骨格、脂肪のつき方が原因のたるみを根本的に改善するのは難しい場合があります。
そのような場合には、美容医療が有効な選択肢となります。
セルフケアで改善できる範囲
セルフケアは、主に皮膚の乾燥や血行不良、軽度の弾力低下に対してアプローチするものです。乾燥による小じわや、むくみによる一時的なたるみであれば、日々のケアで改善を実感できるでしょう。
しかし、眼窩脂肪の突出や、加齢によって大きく伸びてしまった皮膚を元に戻すことは困難です。
セルフケアと美容医療の比較
| 項目 | セルフケア | 美容医療 |
|---|---|---|
| 対象となる悩み | 乾燥、むくみ、ごく初期のたるみ | 皮膚のたるみ、脂肪の突出、くぼみ |
| 効果 | 予防、現状維持、緩やかな改善 | 原因に応じた根本的な改善 |
| 即効性 | 低い(継続が必要) | 比較的高い |
美容医療を検討するタイミング
セルフケアを続けても改善が見られない場合や、たるみによる影が常に気になるようになった時が、美容医療を検討する一つのタイミングです。
また、「メイクで隠しきれない」「実年齢より上に見られることが増えた」といった具体的な悩みが深刻になった場合も、専門のクリニックに相談してみることをお勧めします。
クリニック選びのポイント
美容医療を受ける上で、クリニック選びは非常に重要です。価格だけで選ぶのではなく、医師の経験や実績、カウンセリングの丁寧さ、アフターケアの体制などを総合的に判断しましょう。
- カウンセリングで親身に話を聞いてくれるか
- 治療のメリットだけでなく、リスクやデメリットも説明してくれるか
- 医師の症例写真などを確認できるか
- 院内の清潔感やスタッフの対応はどうか
複数のクリニックでカウンセリングを受け、ご自身が納得できる場所を選ぶことが大切です。
切らない治療法 レーザー・注入
メスを使わずに目元のたるみを改善する治療法は、ダウンタイムが短く、気軽に受けやすいというメリットがあります。ここでは代表的な「切らない治療法」を紹介します。
HIFU(ハイフ)
高密度の超音波エネルギーを皮膚の深層にあるSMAS筋膜に照射し、熱で引き締める治療法です。皮膚の表面を傷つけることなく、内側からリフトアップ効果をもたらします。
コラーゲンの生成も促すため、肌のハリや弾力アップも期待できます。
ヒアルロン酸注入
目の下のくぼみやへこみが原因で影ができ、たるんで見える場合に有効な治療法です。ヒアルロン酸をくぼんだ部分に注入することで、皮膚を内側から持ち上げ、段差をなくし、たるみを目立たなくします。
手軽に行える一方で、医師の技術力が仕上がりを大きく左右します。
主な「切らない治療」の比較
| 治療法 | アプローチ | 向いている悩み |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | 超音波で皮膚の土台を引き締める | 皮膚全体の軽度なたるみ、ハリ不足 |
| ヒアルロン酸注入 | 製剤を注入してくぼみを埋める | 目の下のくぼみ、影ぐま |
| 高周波(RF)治療 | 高周波で真皮層を加熱し、コラーゲン生成を促す | 皮膚の引き締め、小じわ、ハリ感アップ |
その他の照射治療
HIFU以外にも、高周波(RF)やレーザーを用いた治療法があります。これらは真皮層に熱エネルギーを与えてコラーゲンの生成を促し、肌を引き締める効果が期待できます。
どの治療が適しているかは、たるみの状態や肌質によって異なるため、医師との相談が必要です。
本格的な改善を目指す外科的治療
たるみが重度の場合や、脂肪の突出が主な原因である場合は、外科的な治療が根本的な解決につながります。
メスを使うためダウンタイムは長くなりますが、その分、高い効果と持続性が期待できます。
目の下の脂肪取り(経結膜脱脂法)
目の下のふくらみの原因である眼窩脂肪を取り除く手術です。まぶたの裏側(結膜)を小さく切開して脂肪を取り出すため、顔の表面に傷跡が残りません。
脂肪の突出による影ぐま(黒くま)に特に効果的です。
目の下のたるみ取り(皮膚切除)
下まつげのすぐ下で皮膚を切開し、余分な皮膚を取り除いて縫合する手術です。皮膚の伸びが原因のたるみに効果があります。必要に応じて、脂肪の除去や移動を同時に行うこともあります。
傷跡は時間の経過とともに目立ちにくくなります。
脂肪注入
ご自身の体から採取した脂肪を、目の下のくぼんでいる部分に注入する治療法です。脱脂手術と組み合わせることで、ふくらみとくぼみを同時に解消し、より滑らかで自然な目元に整えることができます。
定着した脂肪は半永久的な効果が期待できます。
主な外科的治療の比較
| 治療法 | アプローチ | 向いている悩み |
|---|---|---|
| 経結膜脱脂法 | まぶたの裏から脂肪を取り除く | 脂肪の突出によるふくらみ、影ぐま |
| 皮膚切除 | 皮膚を切開し、余分な皮膚を取り除く | 皮膚の伸びによるたるみ、深いシワ |
| 脂肪注入 | 自身の脂肪を注入してくぼみを埋める | 目の下のくぼみ、脱脂後のへこみ予防 |
美容医療のダウンタイムと費用
美容医療を検討する上で、ダウンタイム(回復期間)と費用は気になる点だと思います。治療法によって大きく異なるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
治療法別のダウンタイム比較
ダウンタイム中の主な症状には、腫れ、むくみ、内出血、痛みなどがあります。症状の程度や期間には個人差がありますが、一般的な目安を知っておくと安心です。
ダウンタイムと費用の目安
| 治療法 | ダウンタイムの目安 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| HIFU | ほぼなし〜数日(軽い赤みや筋肉痛のような鈍痛) | 5万円〜15万円 |
| ヒアルロン酸注入 | 数日〜1週間(内出血、腫れ) | 5万円〜10万円(1本あたり) |
| 経結膜脱脂法 | 1〜2週間(強い腫れ、内出血) | 20万円〜40万円 |
| 皮膚切除 | 2〜4週間(腫れ、内出血、抜糸が必要) | 30万円〜60万円 |
※費用はクリニックや治療範囲によって変動します。あくまで一般的な目安として参考にしてください。
費用の目安
目元のたるみ治療は、基本的に自由診療であり、公的医療保険は適用されません。
費用は全額自己負担となります。クリニックによって料金設定は様々なので、カウンセリングの際に総額でいくらかかるのか、追加料金が発生する可能性はあるのかなどを詳しく確認しましょう。
注意点とアフターケア
治療後は、クリニックの指示に従って適切なアフターケアを行うことが、美しい仕上がりと早期回復のために重要です。
ダウンタイム中は、飲酒や激しい運動、長時間の入浴など、血行を促進する行為は避けましょう。また、治療後のデリケートな肌を紫外線や摩擦から守ることも大切です。
目元のたるみに関するよくある質問
最後に、目元のたるみ治療に関して多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
- どんな治療法が一番効果的ですか?
-
「一番」という治療法は存在せず、その方のたるみの原因、状態、肌質、ライフスタイルによって適した治療法は異なります。
例えば、脂肪の突出が原因の方には経結膜脱脂法が効果的ですが、皮膚のたるみが主な原因の方には皮膚切除や照射治療が向いています。
まずは専門の医師による診察を受け、ご自身の状態に合った治療法を提案してもらうことが重要です。
- 治療の痛みはどのくらいですか?
-
痛みの感じ方には個人差がありますが、多くの治療では麻酔を使用するため、施術中の強い痛みを感じることは少ないです。
注入治療や外科手術では局所麻酔や笑気麻酔、照射治療では麻酔クリームなどを用います。
治療後にじんじんとした痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めでコントロールできる場合がほとんどです。
- 失敗することはありませんか?
-
どのような医療行為にも、リスクや副作用の可能性はゼロではありません。
例えば、注入治療では凹凸ができてしまう、脱脂手術では脂肪を取りすぎてくぼんでしまう、といったリスクが考えられます。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、経験豊富で信頼できる医師を選ぶことが何よりも大切です。
カウンセリングでリスクについてもしっかりと説明を受け、納得した上で治療に臨みましょう。
- 何歳から治療を考えるべきですか?
-
治療を始めるのに決まった年齢はありません。たるみが気になり始めた時が、治療を検討するタイミングと言えます。
20代後半から30代で脂肪によるふくらみが気になる方もいれば、40代以降で皮膚のたるみに悩む方もいます。
年齢に関わらず、ご自身の悩みの深さや、どうなりたいかという希望に応じて、まずはカウンセリングで相談してみることをお勧めします。
参考文献
CHUNG, Sung Tae; RHO, Nark-Kyoung. Surgical and non-surgical treatment of the lower eyelid fat bulging using lasers and other energy-based devices. Medical Lasers, 2017, 6.2: 58-66.
LIPP, Michael; WEISS, Eduardo. Nonsurgical treatments for infraorbital rejuvenation: a review. Dermatologic surgery, 2019, 45.5: 700-710.
SHAH‐DESAI, Sabrina; JOGANATHAN, Varajini. Novel technique of non‐surgical rejuvenation of infraorbital dark circles. Journal of cosmetic dermatology, 2021, 20.4: 1214-1220.
YORDANOV, Y. P. Combined surgical approach for safe and effective rejuvenation of the lower eyelids. Acta Medica Bulgarica, 2025, 52.1: 14-20.
ZAID, Daniel Neamat. Non-Surgical Facial Rejuvenation Techniques. 2021. PhD Thesis. University of Zagreb. School of Medicine.
MALIK, Amina; DENISOVA, Ksenia; BARMETTLER, Anne. Contemporary Management of the Periocular Area. Current Otorhinolaryngology Reports, 2021, 9.4: 448-456.
CHRISTODOULOU, Stylianos, et al. Surgical and Non-Surgical Approach for Tear Trough Correction: Fat Repositioning Versus Hyaluronic Acid Fillers. Journal of Personalized Medicine, 2024, 14.11: 1096.
MIGLIARDI, Renata, et al. Alternative Techniques for Oculofacial Rejuvenation. In: Oculoplastic, Lacrimal and Orbital Surgery: The ESOPRS Textbook: Volume 1. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. p. 513-532.
PARK, Lily, et al. Nonsurgical Periorbital Rejuvenation: An Update. Advances in Cosmetic Surgery, 2025, 8.1: 37-48.
GROVER, Ashok Kumar; THOMAS, Rwituja; SINGH, Garvita. Oculofacial esthetics in ophthalmology. Journal of Ophthalmic Research and Practice, 2023, 1.2: 52-56.