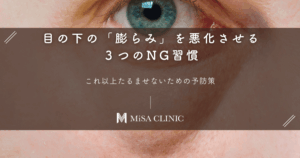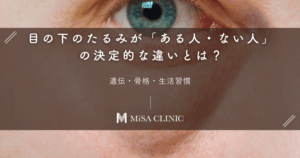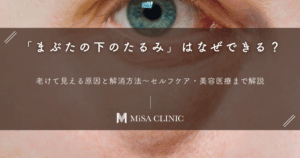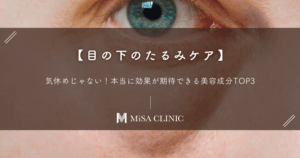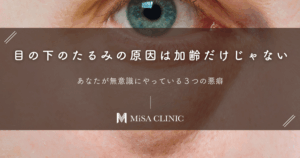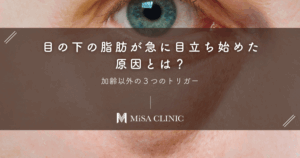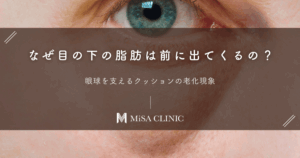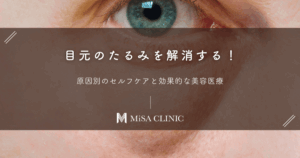鏡を見るたびに気になる、目の下のたるみ。「疲れているように見える」「実年齢より老けて見られる」など、多くの方がこの悩みを抱えています。
このたるみは、単に年齢を重ねたからというだけでなく、私たちの目の周りにある皮膚、筋肉、そして脂肪の複雑な変化が関係しています。
この記事では、なぜ目の下がたるんでしまうのか、その原因を「皮膚」「筋肉」「脂肪」という3つの側面から詳しく解説します。
構造を正しく理解することで、ご自身の状態を知り、今後の適切なケアを選択するための第一歩になります。長年の疑問や不安を解消し、すっきりとした目元を目指すための知識を深めていきましょう。
目の下の構造とたるみの基本
目の下のたるみの原因を探る前に、まず私たちの目元がどのような構造になっているのかを理解することが重要です。
目の周りは顔の他の部分と比べても非常に繊細で、老化の影響が現れやすい特有の構造を持っています。
目の周りの皮膚の薄さと特徴
目の周りの皮膚は、頬の皮膚の約3分の1から4分の1程度の薄さしかありません。皮脂腺が少なく、乾燥しやすいデリケートな部位です。
そのため、外部からの刺激に弱く、水分を保持する力も低いため、乾燥による小じわやハリの低下が起こりやすいのです。また、薄い皮膚は内側の血管の色が透けやすく、クマの原因にもなります。
この薄さが、たるみやしわといったエイジングサインをより顕著に見せる一因となります。
眼窩脂肪と眼輪筋の役割
目の下の構造を理解する上で欠かせないのが、「眼窩脂肪(がんかしぼう)」と「眼輪筋(がんりんきん)」です。
眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションの役割を果たす脂肪です。そして眼輪筋は、目の周りをドーナツ状に取り囲む筋肉で、まばたきをしたり、目を閉じたりする際に働きます。
これらの組織が連携し、若々しい目元を保っています。
各組織の本来の働き
| 組織名 | 主な役割 | 健康な状態 |
|---|---|---|
| 皮膚 | 内部組織の保護 | ハリと弾力があり、滑らか |
| 眼輪筋 | まばたき、眼窩脂肪の支持 | 十分な筋力で脂肪を支える |
| 眼窩脂肪 | 眼球のクッション | 適切な位置に収まっている |
なぜ目元に老化が現れやすいのか
目元は、皮膚の薄さに加えて、1日に1万回以上ともいわれるまばたきや、表情の変化によって常に動き続けています。
この絶え間ない動きが、皮膚や筋肉に負担をかけ、コラーゲン線維などを消耗させます。
さらに、スマートフォンやPCの使用で目を酷使することも、筋肉の疲労や血行不良を招き、老化のサインが現れるのを早める原因となります。
皮膚の老化が引き起こすたるみ
肌のハリや弾力を支えているのは、皮膚の真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンです。
加齢や外部からのダメージによってこれらの成分が減少・変性すると、皮膚は弾力を失い、たるみを引き起こします。
コラーゲンとエラスチンの減少
コラーゲンは皮膚の構造を支える頑丈な線維、エラスチンはそれに絡みついて弾力性を与える線維です。
20代をピークにこれらの生成量は減少し始め、質も低下します。その結果、皮膚は徐々に薄くなり、重力に逆らう力を失ってしまいます。
これが、目の下の皮膚がハリをなくし、たるんでくる大きな原因です。
肌の弾力を司る主要成分
| 成分名 | 特徴 | 減少による影響 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 皮膚の構造を支えるタンパク質線維 | ハリが失われ、深いしわの原因になる |
| エラスチン | コラーゲンを束ねる弾性線維 | 弾力が失われ、たるみや小じわが進む |
| ヒアルロン酸 | 水分を保持するゼリー状の物質 | 乾燥しやすくなり、肌の柔軟性が低下する |
紫外線が与える光老化の影響
たるみの原因は加齢だけではありません。紫外線による「光老化」は、肌の老化を著しく加速させます。
特に、波長の長いUVA(紫外線A波)は、皮膚の深い真皮層まで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊、変性させます。
無防備に紫外線を浴び続けることは、目の下のデリケートな皮膚に深刻なダメージを与え、たるみを早める行為なのです。
乾燥による小じわとたるみの関係
目の周りは皮脂腺が少ないため、もともと乾燥しやすい部位です。乾燥した肌は角質層のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
また、乾燥によってできる表面的な小じわ(ちりめんじわ)を放置すると、やがてそれらが定着し、深いしわやたるみへと進行することがあります。
日々の保湿ケアが、将来のたるみ予防につながるのです。
筋肉の衰えが原因のたるみ
皮膚の下にある筋肉層も、目の下のたるみに深く関わっています。特に眼輪筋の衰えは、目の下の構造を支える力を弱め、たるみを直接的に引き起こす原因となります。
眼輪筋の機能低下
眼輪筋は、眼窩脂肪が前方に飛び出してこないように、ハンモックのように支える重要な役割を担っています。
しかし、加齢やPC作業などで目をあまり動かさない生活が続くと、他の筋肉と同様に眼輪筋も衰えていきます。
筋力が低下すると、眼窩脂肪を支えきれなくなり、脂肪が前方に押し出されて、たるみ(目袋)として現れます。
靭帯のゆるみ
眼窩の骨と皮膚をつなぎ、組織を支えている靭帯(リガメント)も、加齢とともにゆるんできます。この靭帯がゆるむと、皮膚や脂肪を定位置に保持する力が弱まり、全体的に下垂するようになります。
眼輪筋の衰えと靭帯のゆるみが組み合わさることで、たるみはさらに深刻化します。
表情筋の使い方の癖
無意識の表情の癖も、たるみの原因になり得ます。例えば、目を細める癖や、眉をひそめる癖は、特定の筋肉にばかり負担をかけ、しわやたるみを定着させます。
一方で、表情が乏しいと筋肉が使われずに衰えやすくなるため、適度に表情筋を動かすことは重要です。バランスの取れた筋肉の使い方が、若々しい目元を保つ鍵となります。
たるみに関わる筋肉と靭帯
| 名称 | 役割 | 衰えやゆるみによる影響 |
|---|---|---|
| 眼輪筋 | 眼窩脂肪を支える | 眼窩脂肪が突出し、目袋が形成される |
| 靭帯(リガメント) | 皮膚や組織を骨に固定する | 全体の皮膚が下垂し、たるみが悪化する |
脂肪の変化がもたらすたるみとクマ
目の下のたるみの正体ともいえるのが、眼窩脂肪です。この脂肪の量や位置が変化することで、目元の印象は大きく変わります。
加齢による変化は、脂肪の突出だけでなく、くぼみやクマといった悩みも同時に引き起こします。
眼窩脂肪の突出(目袋)
前述の通り、眼輪筋やそれを支える組織がゆるむことで、本来あるべき位置に収まっていた眼窩脂肪が前方にせり出してきます。これが、目の下にできるふくらみ、「目袋」です。
この目袋は、疲れた印象や老けた印象を与える主な原因であり、多くの人が悩むたるみの代表的な症状です。
加齢による脂肪の減少とくぼみ
一方で、加齢とともに顔全体の脂肪は減少する傾向にあります。目の下から頬にかけての脂肪が減少すると、その部分がくぼんできます。
このくぼみと、突出した目袋との間に段差が生まれることで、影ができやすくなります。この影が「影クマ」となり、たるみを一層強調して見せるのです。
たるみの種類と主な原因
| たるみの種類 | 見た目の特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 目袋(眼窩脂肪の突出) | 目の下がふくらんでいる | 筋肉や組織のゆるみ |
| くぼみ | 目の下から頬がへこんでいる | 加齢による皮下脂肪の減少 |
| 影クマ | 目袋と頬の境目に影ができる | 脂肪の突出とくぼみによる段差 |
目の下の骨格の変化
あまり知られていませんが、加齢によって頭蓋骨もわずかに萎縮し、変化します。特に眼球が収まるくぼみである「眼窩」は、加齢とともに拡大する傾向があります。
眼窩が広がると、その中のスペースも広がるため、眼窩脂肪を支える土台が変化し、結果として脂肪が前方に突出しやすくなる、という側面もあります。
皮膚、筋肉、脂肪だけでなく、骨格の変化もたるみの一因なのです。
加齢だけではない!たるみを加速させる生活習慣
目の下のたるみは、加齢による自然な変化だけでなく、日々の生活習慣によっても大きく左右されます。無意識に行っている習慣が、たるみを早めているかもしれません。
ここでは、特に注意したい生活習慣について見ていきましょう。
スマートフォンやPCの長時間利用
スマートフォンやPCの画面を長時間見続けると、まばたきの回数が減少し、眼輪筋が緊張したまま固まってしまいます。これにより、目の周りの血行が悪化し、筋肉の柔軟性が失われます。
血行不良は、肌に必要な栄養素や酸素を届けにくくし、老廃物の排出を滞らせるため、皮膚の老化やくすみ、クマを助長します。結果として、たるみが進行しやすくなるのです。
睡眠不足と血行不良
睡眠は、肌細胞の修復と再生に重要な時間です。睡眠不足が続くと、肌のターンオーバーが乱れ、コラーゲンの生成も滞ります。
また、体の疲れが取れずに血行不良に陥り、目元に十分な栄養が行き渡らなくなります。むくみも生じやすくなり、これも長期的に見るとたるみの原因となります。
喫煙と栄養バランスの乱れ
喫煙は、体内のビタミンCを大量に破壊します。ビタミンCはコラーゲンの生成に必要不可欠な栄養素であり、その欠乏は肌のハリを直接的に低下させます。
また、ニコチンの作用で血管が収縮し、血行が悪化するため、肌の老化を著しく早めます。塩分や糖分の多い食事、栄養バランスの偏りも、むくみや肌の糖化を招き、たるみの原因となります。
たるみ対策のための栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や筋肉の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、柑橘類 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康を保つ | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
間違ったスキンケアと摩擦
良かれと思って行っているスキンケアが、逆効果になることもあります。特に、目元のクレンジングやマッサージで強くこする行為は、薄い皮膚にダメージを与え、たるみの原因となります。
アイメイクを落とす際は専用のリムーバーを使い、優しくなじませて浮かせるようにしましょう。
スキンケア製品を塗る際も、薬指など力の入りにくい指で、そっと押さえるように塗布することが大切です。
自分でできる目の下のたるみ対策
目の下のたるみは、一度現れると完全に元に戻すことは難しいですが、日々のセルフケアで進行を緩やかにしたり、予防したりすることは可能です。
ここでは、今日から始められる対策を紹介します。
正しい保湿ケアの基本
目元のケアの基本は、なんといっても保湿です。乾燥は小じわの直接的な原因となり、たるみへとつながります。セラミドやヒアルロン酸など、保湿効果の高い成分が配合されたアイクリームを使用しましょう。
塗る際は、摩擦を避けるため、指の腹で優しくトントンと置くように馴染ませるのがポイントです。化粧水や乳液といった基本的なスキンケアも、もちろん丁寧に行いましょう。
紫外線対策の重要性
光老化を防ぐため、紫外線対策は年間を通して行う必要があります。SPF/PA値が表示された日焼け止めや、UVカット機能のある化粧下地、ファンデーションを毎日使用する習慣をつけましょう。
特に目元は日焼け止めを塗り忘れやすい部分なので、意識して塗布することが大切です。
- サングラスの着用
- UVカット機能のあるメガネ
- 帽子や日傘の活用
これらのアイテムを併用することで、物理的に紫外線を遮断し、目元の皮膚を守ることができます。
眼輪筋を鍛えるトレーニング
衰えてしまった眼輪筋は、意識的に動かすことで鍛えることができます。ただし、やりすぎや間違った方法は逆効果になる可能性もあるため、注意が必要です。
無理のない範囲で、毎日少しずつ続けることが重要です。
簡単な眼輪筋トレーニング
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 目を大きく見開いて5秒キープ | 眉を上げず、目の周りの筋肉だけを使う意識で |
| 2. ゆっくりと目を細め、5秒キープ | 眩しいものを見るように、じわっと力を入れる |
| 3. 目をぎゅっと閉じて5秒キープ | 顔全体に力を入れすぎないように注意する |
| 4. ゆっくりと力を抜き、リラックス | 1〜3を1セットとし、数回繰り返す |
生活習慣の見直し
これまで述べてきた、たるみを加速させる生活習慣を改善することも有効な対策です。
十分な睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけ、スマートフォンを見る時間を減らすなど、できることから始めてみましょう。
特に、血行を促進するために、軽い運動や入浴で体を温めることもおすすめです。
セルフケアの限界と美容医療という選択肢
日々のセルフケアは、たるみの予防や進行を遅らせる上で非常に重要です。
しかし、すでに現れてしまった構造的なたるみ、つまり筋肉の衰えや脂肪の突出をセルフケアだけで解消するのは、残念ながら限界があります。
セルフケアで改善できる範囲
セルフケアが有効なのは、主に乾燥による小じわや、血行不良による一時的なくすみやむくみです。
保湿によって肌のキメが整い、マッサージやトレーニングで血色が良くなることで、目元の印象が明るくなり、たるみが少し目立たなくなることはあります。
しかし、これらは根本的な解決には至りません。
美容クリニックで相談するメリット
セルフケアで効果を感じられない場合や、より確実な改善を望む場合は、美容クリニックなどの専門機関に相談することを検討するのも一つの方法です。
専門家によるカウンセリングでは、自分のたるみがどのタイプで、何が主な原因なのかを正確に診断してもらえます。原因が分かれば、自分に合った治療法や対処法を知ることができます。
- 正確な原因の診断
- 多様な治療選択肢の提示
- 専門的なアドバイス
専門家による診断の重要性
目の下のたるみと一言でいっても、その原因は人それぞれです。皮膚のゆるみが強いのか、脂肪の突出が問題なのか、あるいはその両方なのか。
自己判断でケアを続けるよりも、一度専門家の視点から客観的に評価してもらうことで、悩みを解決する近道が見つかるかもしれません。
治療を受けるかどうかは別として、まずは自分の状態を正しく知るために、相談してみる価値は十分にあります。
目の下のたるみに関するよくある質問
- 目の下のたるみは一度できてしまったら、もう治らないのでしょうか?
-
セルフケアで完全に元通りにすることは難しいですが、進行を遅らせたり、見た目の印象を改善したりすることは可能です。
保湿や紫外線対策、生活習慣の見直しはたるみの進行予防に役立ちます。また、美容医療にはさまざまなアプローチがあり、たるみの原因や程度に応じて改善を目指すことができます。
- 何歳くらいから、目の下のたるみは目立ち始めますか?
-
個人差が大きいですが、一般的には30代後半から40代にかけて、ハリの低下や脂肪の突出が気になり始める方が多いです。
しかし、生活習慣や遺伝的な要因によっては、20代から予兆が現れることもあります。年齢にかかわらず、早めに予防的なケアを始めることが大切です。
- 男性でも目の下はたるみますか?
-
はい、たるみの基本的な原因は男女で同じであるため、男性も同様に目の下のたるみは生じます。
男性は女性に比べてスキンケアや紫外線対策をしない傾向があるため、かえって老化のサインが早く現れることもあります。基本的なケアは性別を問わず重要です。
- 効果的なマッサージ方法はありますか?
-
目元のマッサージは、血行促進に効果が期待できますが、強い摩擦はたるみを悪化させる原因にもなります。
行う場合は、必ず滑りの良いアイクリームやオイルを使用し、薬指の腹を使って、目頭から目尻に向かって優しくなでる程度にしましょう。強く押したり、こすったりするのは厳禁です。
参考文献
KIM, Junhyung, et al. Ageing of the bony orbit is a major cause of age-related intraorbital fat herniation. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2018, 71.5: 658-664.
PARK, Kui Young, et al. Treatments of infra-orbital dark circles by various etiologies. Annals of dermatology, 2018, 30.5: 522-528.
SAMIZADEH, Souphiyeh. Anatomy and Pathophysiology of Facial Ageing. In: Thread Lifting Techniques for Facial Rejuvenation and Recontouring. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 61-89.
NIAMTU, Joe, et al. Orbital Anatomy. Cosmetic Facial Surgery-E-Book, 2022, 345.
LIPP, Michael; WEISS, Eduardo. Nonsurgical treatments for infraorbital rejuvenation: a review. Dermatologic surgery, 2019, 45.5: 700-710.
DABBOUS, H., et al. Aging of the Orbit and Rejuvenation Options. In: Periorbital Rejuvenation: A Practical Manual. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 35-50.
CODNER, Mark A.; MCCORD JR, Clinton D. (ed.). Eyelid and periorbital surgery. CRC Press, 2016.
FAY, Aaron; DOLMAN, Peter J. Diseases and Disorders of the Orbit and Ocular Adnexa E-Book: Expert Consult. Elsevier Health Sciences, 2016.
COBAN, Istemihan, et al. Anatomical basis for the lower eyelid rejuvenation. Aesthetic Plastic Surgery, 2023, 47.3: 1059-1066.
LAMBROS, Val. Observations on periorbital and midface aging. Plastic and reconstructive surgery, 2007, 120.5: 1367-1376.