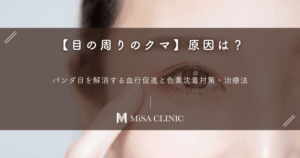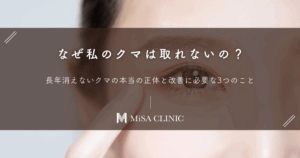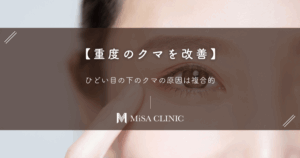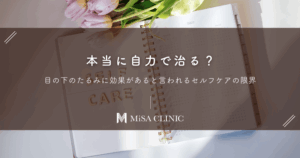鏡を見るたびに気になる、目の下のクマ。「疲れているの?」と聞かれることも多く、メイクで隠すのにも限界を感じていませんか。
目の下のクマは、見た目年齢を大きく左右するだけでなく、不健康な印象を与えてしまう悩みの種です。
この記事では、そんなクマを本気で改善したいと願うあなたのために、クマの正体から自分でできるセルフケア、そして美容医療による専門的なアプローチまで、あらゆる情報を網羅した完全ガイドをお届けします。
あなたのクマのタイプを知り、正しい知識を身につけることが、改善への第一歩です。さあ、一緒に自信の持てる明るい目元を目指しましょう。
そもそも目の下のクマとは?その正体と原因
多くの女性を悩ませる目の下のクマ。まずは、その正体が何なのか、そしてなぜできてしまうのか、基本的な知識から理解を深めていきましょう。
原因を知ることで、自分に合った正しい対策が見えてきます。
疲れて見える原因「クマ」の正体
目の下のクマとは、目の周りの皮膚が黒ずんで見える状態の総称です。皮膚が非常に薄い目元は、その下にある血管や筋肉、脂肪の色が透けて見えやすい部位です。
そのため、血行不良や色素沈着、皮膚の構造的な問題など、わずかな変化でも「クマ」として現れます。クマがあると、顔全体が暗く、疲れた印象になりがちです。
一言でクマといっても、その原因や見た目によっていくつかの種類に分類でき、それぞれ対処法が異なります。
クマができる主な要因
クマが発生する要因は一つではありません。複数の要因が複雑に絡み合って生じることがほとんどです。
主な要因としては、睡眠不足やストレスによる血行不良、紫外線や摩擦によるメラニン色素の沈着、そして加齢に伴う皮膚のたるみや脂肪の突出などが挙げられます。
特に現代人は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、目元の血行が悪化しやすい環境にあります。自分の生活習慣の中に、クマを悪化させる要因が隠れていないか見直すことが重要です。
年齢とともにクマが目立つ理由
若い頃は気にならなかったのに、年齢を重ねるにつれてクマが目立ってきた、と感じる方は少なくありません。
これは、加齢によって肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄く、たるみやすくなるためです。
また、目元を支える眼輪筋という筋肉も衰え、目の下の脂肪(眼窩脂肪)が前方に押し出されやすくなります。この脂肪が影を作り出すことで、黒いクマ(黒クマ)として認識されるのです。
年齢による変化は自然なことですが、適切なケアで進行を緩やかにすることは可能です。
あなたのクマはどのタイプ?4種類のクマの見分け方
効果的なクマ改善のためには、まず自分のクマがどのタイプなのかを正確に把握することが大切です。
ここでは、代表的な4種類のクマの特徴と、簡単な見分け方について解説します。鏡を用意して、ご自身の目元をチェックしてみてください。
青クマ(血管性クマ)の特徴と原因
青クマは、目の下の皮膚が青黒く見えるタイプのクマです。主な原因は、血行不良です。
目の周りには毛細血管が集中していますが、睡眠不足や疲労、ストレス、冷えなどによって血流が滞ると、血液中の酸素が不足し、血液が暗い色になります。
目元の皮膚は非常に薄いため、その暗い血液の色が透けて青黒く見えてしまうのです。目の下を軽く引っ張ると色が薄くなる、または日によって濃さが変わる場合は、青クマの可能性が高いでしょう。
茶クマ(色素沈着型クマ)の特徴と原因
茶クマは、その名の通り、目の下が茶色くくすんで見える状態です。これは、メラニン色素が皮膚に沈着することが原因で起こります。
目をこする癖があったり、クレンジング時の摩擦が強かったりすると、その刺激から肌を守るためにメラニンが過剰に生成されます。
また、紫外線によるダメージや、肌のターンオーバーの乱れも色素沈着を招く要因です。目の下を引っ張っても皮膚と色が一緒に動き、色が薄くならない場合は、茶クマが疑われます。
黒クマ(構造性クマ)の特徴と原因
黒クマは、目の下が黒い影のように見えるタイプで、加齢による影響が大きく関係しています。年齢とともに肌のハリが失われ、目の下の皮膚がたるむことで窪みができます。
また、眼球を支えている眼輪筋が衰えることで、目の下の脂肪(眼窩脂肪)が前方に突出し、ふくらみができます。このたるみによる窪みや、脂肪のふくらみが作り出す影が、黒クマの正体です。
上を向くとクマが薄くなる、または顔に光を当てると影が消える場合は、黒クマの可能性が高いと考えられます。
クマの種類別見分け方まとめ
| クマの種類 | 主な原因 | 見分け方のポイント |
|---|---|---|
| 青クマ | 血行不良 | 皮膚を引っ張ると薄くなる。日によって濃さが違う。 |
| 茶クマ | 色素沈着 | 皮膚を引っ張っても色がなくならない。シミのように見える。 |
| 黒クマ | たるみ・くぼみ | 上を向くと薄くなる。光を当てると影が消える。 |
| 赤クマ | 血行不良と皮膚の薄さ | 目の下のふくらみが赤紫色に見える。 |
赤クマ(炎症性クマ)の特徴と原因
赤クマは、目の下のふくらんでいる部分が赤紫色に見える状態を指します。これは、目の下の脂肪(眼窩脂肪)に圧迫されて、その下にある眼輪筋という筋肉の色が透けて見えることが原因です。
青クマと同様に血行不良も関係していますが、特に眼窩脂肪の突出が大きく影響しています。遺伝的な要因や、長時間のPC作業による眼精疲労も悪化させる要因となります。
黒クマと合併していることも多いのが特徴です。
自宅で始めるクマ改善セルフケア
美容医療に頼る前に、まずは日々の生活の中でできることから始めてみましょう。
ここでは、自宅で実践できるクマ改善のためのセルフケア方法を具体的に紹介します。継続することが、明るい目元への近道です。
血行を促進する生活習慣
特に青クマや赤クマの改善には、体全体の血行を良くすることが重要です。日々の生活に少し工夫を取り入れるだけで、目元の血流は大きく変わります。
血行促進のために意識したいこと
- 湯船に浸かる(38〜40℃のお湯で15分程度)
- 適度な運動(ウォーキングやストレッチなど)
- 体を冷やさない服装や食事
また、蒸しタオルで目元を温めるのも手軽で効果的な方法です。40℃程度に温めたタオルを5分ほど目の上に乗せるだけで、血行が促進され、目の疲れも和らぎます。
食事では、血行を良くするビタミンEや、鉄分を多く含む食材を積極的に摂りましょう。
血行促進に役立つ栄養素と食材
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
| 鉄分 | 血液の材料になる | レバー、ほうれん草、あさり |
| ビタミンC | 鉄分の吸収を助ける | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
クマ対策に有効なスキンケア成分
茶クマの主な原因である色素沈着や、目元の乾燥を防ぐためには、保湿と美白を意識したスキンケアが大切です。
目元はデリケートな部分なので、専用のアイクリームなどを使用し、優しくケアすることを心がけてください。
注目したいスキンケア成分
| 成分名 | 期待できる効果 | どんなクマにおすすめか |
|---|---|---|
| ビタミンC誘導体 | メラニンの生成抑制、排出促進 | 茶クマ |
| レチノール | ターンオーバー促進、コラーゲン生成促進 | 茶クマ、黒クマ |
| セラミド | 保湿、バリア機能のサポート | すべてのクマ(乾燥対策) |
目元のマッサージとツボ押し
血行を促進し、老廃物の排出を助けるマッサージも有効なセルフケアです。ただし、やり方を間違えると逆効果になることもあるため、注意が必要です。
必ずクリームやオイルを使い、肌への摩擦を最小限に抑えながら、優しい力で行いましょう。指の腹を使って、目頭からこめかみに向かって優しく滑らせるようにマッサージします。
また、目の周りにあるツボを優しく押すのも、眼精疲労の緩和に役立ちます。
メイクで上手にクマを隠す方法
根本的な改善には時間がかかりますが、メイクを工夫することで、今あるクマを上手にカバーすることができます。クマを隠すにはコンシーラーが有効ですが、色選びが重要です。
青クマにはオレンジ系のコンシーラー、茶クマにはイエロー系のコンシーラーを選ぶと、色ムラを自然に補正できます。
厚塗りするとかえって目立つため、少量ずつ指で優しく叩き込むように馴染ませるのがポイントです。
セルフケアだけでは改善が難しいクマとは
日々の努力を重ねても、なかなか改善しないクマもあります。セルフケアには限界があることを理解し、次の選択肢を考えることも大切です。
ここでは、セルフケアでの改善が難しいケースについて解説します。
セルフケアの効果の限界
青クマや、でき始めの軽い茶クマであれば、セルフケアで改善が見込める場合があります。
しかし、加齢による皮膚のたるみや脂肪の突出が原因である「黒クマ」や、長年にわたって蓄積された「濃い茶クマ」は、セルフケアだけで完全に解消するのは非常に困難です。
これらは皮膚の構造的な問題や、深い層での色素沈着が原因であるため、表面的なケアだけでは根本的な解決に至りません。
改善が見られない場合のサイン
数ヶ月間、生活習慣の見直しやスキンケアを続けても、クマの状態に全く変化が見られない場合は、セルフケアの限界かもしれません。
特に、朝起きた時だけでなく一日中クマが目立つ、ファンデーションやコンシーラーでも隠しきれない、といった状態であれば、より専門的なアプローチを検討する時期と言えるでしょう。
美容医療を検討するタイミング
クマがコンプレックスになってしまい、人と会うのが億劫になったり、自分の顔を見るのが辛くなったりしているのなら、それは美容医療を検討する一つのタイミングです。
美容医療は、セルフケアでは届かない肌の奥深くや、構造的な問題に直接アプローチできるため、より確実で早い改善が期待できます。
まずは専門のクリニックでカウンセリングを受け、自分のクマの原因と適切な治療法について相談してみることをお勧めします。
美容医療による本格的なクマ改善アプローチ
セルフケアでの改善が難しいクマに対して、美容医療は非常に有効な選択肢となります。ここでは、クマの種類別に、どのような治療法があるのかを具体的に紹介します。
専門医の診断のもと、自分に合った最適な方法を見つけましょう。
クマの種類別に見る治療法の選択肢
美容医療には様々な種類の治療法があり、クマのタイプによって適したアプローチが異なります。
間違った治療を選択すると効果が得られないばかりか、悪化させてしまう可能性もあるため、正確な診断が何よりも重要です。
クマの種類と主な治療法の対応
| クマの種類 | 主な治療法 | アプローチの概要 |
|---|---|---|
| 青クマ | 注入治療、レーザー治療 | 血行促進や皮膚に厚みを持たせる |
| 茶クマ | レーザー・光治療、ピーリング | メラニン色素を破壊・排出する |
| 黒クマ・赤クマ | 脱脂手術、注入治療 | 脂肪の除去や移動、窪みを埋める |
青クマに効果的な治療法
血行不良が原因の青クマには、滞った血流を改善したり、皮膚に厚みを持たせて血管が透けないようにしたりする治療が有効です。
例えば、血行促進作用のある薬剤を注入する方法や、肌のコラーゲン生成を促すレーザー治療などがあります。
また、ヒアルロン酸を注入して皮膚に厚みを出し、物理的に血管を透けにくくする方法も選択肢の一つです。
茶クマに効果的な治療法
色素沈着が原因の茶クマには、メラニン色素にアプローチする治療が中心となります。
代表的なのが、メラニンを破壊する「ピコレーザー」などのレーザー治療や、光のエネルギーでシミやくすみを改善する「IPL(光治療)」です。
また、肌のターンオーバーを促進してメラニンの排出を助ける「ケミカルピーリング」や、ビタミンCやトラネキサム酸などの美白成分を肌の奥に届ける「イオン導入」なども併用されることがあります。
黒クマに効果的な治療法
皮膚のたるみや脂肪のふくらみが原因である黒クマは、構造的な問題を解決する必要があります。最も根本的な治療法は、目の下の余分な脂肪を取り除く「経結膜脱脂術」です。
まぶたの裏側からアプローチするため、顔の表面に傷が残らないのが特徴です。
また、取り除いた脂肪を窪んだ部分に移動させる「ハムラ法」や、ヒアルロン酸やコラーゲンなどを注入して窪みを埋める治療法もあります。
どの方法が適しているかは、脂肪の突出度合いや皮膚のたるみの状態によって異なります。
後悔しないためのクリニック選びのポイント
クマ治療の成否は、クリニック選びにかかっていると言っても過言ではありません。大切な自分の顔を任せるのですから、慎重に選びたいものです。
ここでは、安心して治療を受けるためのクリニック選びのポイントを解説します。
医師の経験と実績を確認する
目の周りの治療は、非常に繊細な技術を要します。そのため、クマ治療に関する医師の経験や実績は必ず確認しましょう。
クリニックのウェブサイトで症例写真を見たり、医師の経歴や所属学会などをチェックしたりすることが参考になります。
カウンセリングの際に、自分が受けたい治療をどのくらいの数こなしてきたのか、直接質問してみるのも良いでしょう。
カウンセリングの丁寧さと相性
カウンセリングは、自分の悩みや希望を伝え、治療に関する詳しい説明を受ける重要な時間です。
医師が親身に話を聞いてくれるか、メリットだけでなくデメリットやリスクについてもきちんと説明してくれるかを確認しましょう。
また、質問しやすい雰囲気か、スタッフの対応は丁寧かなど、クリニック全体の雰囲気と自分との相性も大切な判断材料です。
カウンセリングでの確認事項
| カテゴリ | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 治療内容 | 自分に適した治療法、具体的な手順、期待できる効果 |
| リスク・副作用 | 考えられるリスク、ダウンタイムの期間や症状 |
| 費用 | 総額、追加料金の有無、支払い方法 |
料金体系の明確さ
美容医療は自由診療のため、クリニックによって料金が異なります。
ウェブサイトやカウンセリングで提示された料金に、診察料や薬代、アフターケア代などが全て含まれているのか、追加で費用が発生する可能性はないのかを事前にしっかりと確認することが重要です。
見積もりは書面でもらい、後から「話が違う」ということにならないようにしましょう。
アフターケアの充実度
治療後の経過は個人差があり、時には予期せぬトラブルが起こる可能性もゼロではありません。
万が一の際に、どのような対応をしてくれるのか、アフターケアの体制が整っているクリニックを選ぶと安心です。
術後の検診はいつあるのか、緊急時の連絡先はあるのかなど、治療後のサポートについても確認しておきましょう。
美容医療を受ける前の準備と当日の流れ
実際に治療を受けると決めたら、次は準備です。安心して当日を迎えるために、事前に知っておくべきことや当日の流れを把握しておきましょう。
カウンセリングで伝えるべきこと
カウンセリングでは、自分の状態や希望を正確に医師に伝えることが、満足のいく結果につながります。以下の点を整理しておくと、スムーズに話を進めることができます。
医師に伝えるべき情報リスト
- いつからクマが気になっているか
- アレルギーの有無や既往歴
- 現在服用している薬やサプリメント
- 理想の仕上がりイメージ
- 治療に関して不安に思っていること
施術前の注意点
治療内容によって注意点は異なりますが、一般的に施術前は飲酒や喫煙を控えるよう指示されることが多いです。血行が良くなりすぎると、腫れや内出血のリスクが高まるためです。
また、当日はメイクをせずに来院するか、クリニックでメイクを落とす必要があります。コンタクトレンズを使用している場合は、施術中は外す必要があるため、メガネを持参すると良いでしょう。
施術当日の流れ
当日は、まず最終的な意思確認と同意書へのサインを行います。その後、洗顔をしてから施術室へ移動します。治療内容によっては、麻酔クリームを塗ったり、点滴をしたりすることもあります。
施術時間は治療法によりますが、数十分から1時間程度が一般的です。施術後は、クーリング(冷却)や軟膏の塗布などを行い、しばらく休憩してから帰宅となります。
ダウンタイムと過ごし方
ダウンタイムとは、施術を受けてから通常の生活に戻るまでの回復期間のことです。腫れや内出血、痛みなどの症状が現れることがあります。
症状の程度や期間は治療法や個人差によりますが、できるだけ安静に過ごすことが、回復を早めるポイントです。施術当日は、入浴や運動、飲酒など血行が良くなることは避けましょう。
主な治療法とダウンタイムの目安
| 治療法 | 主な症状 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 軽い腫れ、内出血 | 数日〜1週間程度 |
| レーザー治療 | 赤み、かさぶた | 数日〜1週間程度 |
| 経結膜脱脂術 | 強い腫れ、内出血 | 1〜2週間程度 |
【クマ改善】に関するよくある質問
最後に、クマ改善の美容医療に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。治療への不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すための参考にしてください。
- 施術中の痛みはありますか?
-
治療の種類によって痛みの感じ方は異なります。注入治療やレーザー治療では、チクッとしたり、熱さを感じたりすることがあります。
多くの場合、麻酔クリームや冷却装置を使用することで、痛みは大幅に軽減されます。
脱脂手術のような外科的な治療では、局所麻酔や静脈麻酔を使用するため、施術中に痛みを感じることはほとんどありません。
痛みに不安がある方は、カウンセリングの際に遠慮なく医師に相談してください。
- 治療後、すぐに効果は実感できますか?
-
ヒアルロン酸注入や脱脂手術など、物理的に形を整える治療は、施術直後から変化を実感しやすいです。
ただし、腫れや内出血があるため、最終的な仕上がりはダウンタイムが終わってからとなります。
一方、レーザー治療や光治療のように、肌の再生を促すタイプの治療は、効果が現れるまでに少し時間がかかります。
肌のターンオーバーに合わせて徐々に改善していくため、複数回の治療が必要になることもあります。
- 治療効果はどのくらい持続しますか?
-
効果の持続期間も治療法によって大きく異なります。
ヒアルロン酸注入は、使用する製剤にもよりますが、半年から2年程度で徐々に体内に吸収されていきます。そのため、効果を維持するには定期的な治療が必要です。
一方、脱脂手術は原因となる脂肪そのものを取り除くため、効果は半永久的に持続すると言われています。ただし、加齢による変化が再び現れる可能性はあります。
- 治療後に気をつけることは何ですか?
-
治療後は、肌がデリケートな状態になっています。処方された薬があれば指示通りに使用し、保湿と紫外線対策を徹底することが重要です。
また、ダウンタイム中は、血行が良くなるような激しい運動や長時間の入浴、飲酒は控えましょう。目元を強くこすったり、マッサージしたりするのも避けてください。
何か気になる症状が出た場合は、すぐに治療を受けたクリニックに連絡し、指示を仰ぐことが大切です。
参考文献
SARKAR, Rashmi, et al. Periorbital hyperpigmentation: a comprehensive review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 49.
POUR MOHAMMAD, Arash, et al. The First Systematic Review and Meta‐Analysis of Pharmacological and Nonpharmacological Procedural Treatments of Dark Eye Circles (Periorbital Hyperpigmentations): One of the Most Common Cosmetic Concerns. Dermatologic Therapy, 2025, 2025.1: 9155535.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
AWAL, Guneet, et al. Illuminating the shadows: an insight into periorbital hyperpigmentation. Pigment International, 2024, 11.2: 67-78.
SAWANT, Omkar; KHAN, Tabassum. Management of periorbital hyperpigmentation: An overview of nature‐based agents and alternative approaches. Dermatologic Therapy, 2020, 33.4: e13717.
PISSARIDOU, Maria Katerina; GHANEM, Ali; LOWE, Nicholas. Periorbital Discolouration diagnosis and treatment: evidence-based review. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2020, 22.6-8: 217-225.
AGRAWAL, Sudha. Periorbital hyperpigmentation: Overcoming the challenges in the management. Nepal Journal of Dermatology, Venereology & Leprology, 2018, 16.1: 2-11.
DHILLON, Pranita Daware; DHILLON, Vivek; RUSTAGI, Inder Mohan. A Review of the Efficacy of Different Topical Active Ingredients on Various Periorbital Skin Concerns. CME Journal Geriatric Medicine, 2024, 16: 87-95.
AHMED, Naglaa A.; MOHAMMED, Salma S.; FATANI, Mohammad I. Treatment of periorbital dark circles: comparative study of carboxy therapy vs chemical peeling vs mesotherapy. Journal of cosmetic dermatology, 2019, 18.1: 169-175.