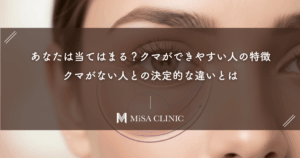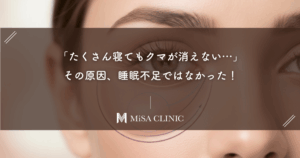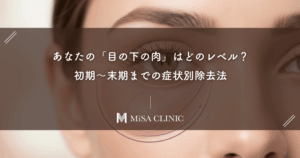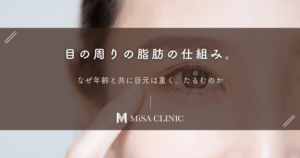「しっかり寝ているはずなのに、目の下のクマが消えない」「コンシーラーで隠しても、夕方にはどんより疲れた印象に…」。そんな目の下のクマに関する悩みを持っていませんか。
多くの人がクマの原因を「寝不足」だと考えていますが、実はそれだけではありません。クマには種類があり、それぞれ異なる原因と仕組みによって現れます。
この記事では、あなたのクマがどのタイプなのかを明らかにし、その本当の原因と、なぜクマができるのかという仕組みを詳しく解説します。
自分のクマの正体を知ることが、効果的なケアへの第一歩です。原因を正しく理解し、悩みを解決するヒントを見つけましょう。
そもそも目の下のクマとは?その正体を解説
目の下のクマは、多くの人が経験する肌の悩みの一つです。しかし、その正体が何であるかを正確に理解している人は少ないかもしれません。
ここでは、クマがどのようにしてできるのか、その基本的な知識を解説します。
目の下が暗く見える状態
目の下のクマとは、病名ではなく、目の周り、特に下まぶたの部分が周囲の肌と比べて暗く、影のように見える状態の総称です。
この暗い部分があることで、顔全体が疲れて見えたり、老けた印象を与えたりすることがあります。
クマの色や見た目は、その原因によって青黒く見えたり、茶色くくすんで見えたり、黒い影のように見えたりと様々です。
これらは、皮膚の下にある血管の色、色素沈着、または皮膚の構造的な変化が関係しています。
皮膚の薄さと血管・筋肉の関係
目の下の皮膚は、顔の他の部分と比較して非常に薄いという特徴があります。その薄さは約0.6mmほどで、頬の皮膚の3分の1から4分の1程度しかありません。
皮膚が薄いため、その下にある毛細血管や、眼輪筋(がんりんきん)という目を囲む筋肉の色が透けて見えやすいのです。
特に血行が悪くなると、血液中の酸素が不足し、血液が暗い赤色(静脈血)になります。その色が薄い皮膚を通して透けることで、青黒い「青クマ」として現れます。
健康的な血色の良い肌では目立たない血管も、血行不良によってその存在が明らかになるのです。
クマがあると疲れて見える理由
人間の目は、相手の顔を見るとき、自然と目元に注目する傾向があります。
そのため、目元にクマのような暗い色や影があると、無意識のうちに「疲労」や「不健康」といったネガティブな印象を相手に与えてしまいます。
明るくハリのある目元は若々しさや元気さを象徴しますが、クマはその逆の印象を作り出します。
たとえ体は元気でも、クマがあるだけで「疲れているの?」「眠れていないの?」と心配されることが多くなるのは、このためです。
年齢とともにクマが目立ちやすくなる背景
年齢を重ねると、肌のハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが自然と減少していきます。これにより、目の下の皮膚はさらに薄くなり、たるみやすくなります。
皮膚がたるむと、目の下に凹凸ができ、影が生まれやすくなります。これが「黒クマ」の主な原因です。
また、加齢によって肌のターンオーバー(新陳代謝)の周期が長くなるため、メラニン色素が排出されにくくなり、色素沈着による「茶クマ」もできやすくなります。
このように、加齢は様々な種類のクマを目立たせる要因となります。
あなたのクマはどのタイプ?3種類のクマの見分け方
効果的なクマ対策を行うためには、まず自分のクマがどのタイプに当てはまるのかを正しく知ることが重要です。
クマは大きく分けて「青クマ」「茶クマ」「黒クマ」の3種類があり、それぞれ原因と見分け方が異なります。簡単なセルフチェックで自分のクマのタイプを確認してみましょう。
青クマ(血管性クマ)の特徴とセルフチェック法
青クマは、目の下が青黒く、または紫色っぽく見えるのが特徴です。主に血行不良によって、皮膚の下にある毛細血管が透けて見えることで発生します。
セルフチェックの方法は簡単です。鏡を見ながら、クマがある部分の皮膚を指で軽く下に引っ張ってみてください。
このとき、クマの色が少し薄くなったり、目立たなくなったりすれば、それは青クマである可能性が高いです。皮膚を伸ばすことで血管への圧力が変わり、一時的に血色がよく見えるためです。
青クマの主な特徴
| 項目 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 色 | 青黒い、暗い紫色 | 血行不良 |
| 見え方 | 日によって濃さが変わりやすい | 寝不足、目の疲れ |
| チェック法 | 皮膚を引っ張ると薄くなる | 冷え、ストレス |
茶クマ(色素沈着性クマ)の特徴とセルフチェック法
茶クマは、目の下が茶色くくすんで見える状態です。これはシミやくすみと同じように、メラニン色素が皮膚に沈着することが原因で起こります。
茶クマのセルフチェックも、皮膚を引っ張る方法で行います。
指でクマの部分を優しく下に引っ張ったとき、クマの色が変わらず、皮膚と一緒に動くように見える場合、茶クマの可能性が高いです。
色素沈着は皮膚そのものに色がついている状態なので、皮膚を動かしても色の見え方は変わりません。
茶クマの主な特徴
| 項目 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 色 | 茶色、くすんだ色 | 色素沈着 |
| 見え方 | シミのように見える | 紫外線、摩擦 |
| チェック法 | 皮膚を引っ張っても色が変わらない | メイク残り、炎症 |
黒クマ(構造性クマ)の特徴とセルフチェック法
黒クマは、目の下が黒い影のように見えるクマです。これは皮膚の色が変わっているわけではなく、加齢などによる皮膚のたるみや、目の下のくぼみによってできる「影」が原因です。
黒クマのセルフチェックは、顔の角度を変えて行います。鏡を持ったまま、顔を真上に向け、天井の光が当たるようにしてみてください。
このとき、クマが薄くなったり消えたりすれば、それは黒クマです。上を向くことでたるみによる凹凸がフラットになり、影が目立たなくなるためです。逆に、顔を下に向けたままだと影がより濃く見えます。
黒クマの主な特徴
| 項目 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 色 | 黒、灰色 | 皮膚のたるみ・凹凸による影 |
| 見え方 | くぼんで見える、疲れた印象 | 加齢、眼窩脂肪の突出 |
| チェック法 | 上を向くと薄くなる・消える | 骨格、コラーゲン減少 |
複数の原因が重なる混合型クマ
実際には、これらのクマが単独で存在するだけでなく、複数のタイプのクマが混在している「混合型」の人も少なくありません。
例えば、血行不良による青クマと、加齢による黒クマが同時に存在しているケースなどです。その場合は、それぞれのクマの原因に対応した、多角的なアプローチが必要になります。
自分のクマがどのタイプに最も近いかを見極め、それぞれの原因に合わせたケアを考えることが大切です。
【青クマの原因】血行不良が引き起こす仕組み
青クマの直接的な原因は「血行不良」です。
目の周りには無数の毛細血管が張り巡らされていますが、何らかの理由で血流が滞ると、血液中の酸素が減少し、二酸化炭素を多く含んだ暗赤色の静脈血が目立つようになります。
この色が、薄い目の下の皮膚から透けて見えることで青クマとなるのです。ここでは、血行不良を引き起こす具体的な生活習慣やその仕組みを掘り下げます。
寝不足や疲労の蓄積
睡眠不足や慢性的な疲労は、血行不良を引き起こす代表的な原因です。私たちの体は、睡眠中に心身の疲れを回復させ、自律神経のバランスを整えています。
しかし、睡眠が不足すると、交感神経が優位な状態が続き、血管が収縮しやすくなります。血管が収縮すると血流が悪くなり、目の周りのうっ血を招きます。
疲労が蓄積している場合も同様の反応が起こり、血行不良を悪化させるため、青クマが濃く現れやすくなります。
長時間続く目の疲れ(PC・スマホ)
パソコンやスマートフォンを長時間使用する現代のライフスタイルは、青クマの大きな原因の一つです。画面を集中して見続けると、目の周りの筋肉(眼輪筋)が緊張し、硬くなります。
筋肉が硬くなると、その周辺の血管を圧迫し、血流を妨げます。また、まばたきの回数が減ることで涙の分泌が減少し、ドライアイを引き起こすことも目の疲れを助長します。
この目の酷使が、目元の血行不良を慢性化させ、青クマを定着させる理由です。
体の冷えと血行の関係
体の冷えも血行不良に直結します。特に女性は筋肉量が少なく、冷えやすい傾向があります。体が冷えると、体温を逃さないように血管が収縮し、全身の血の巡りが悪くなります。
手足の先だけでなく、顔の血行も例外ではありません。オフィスでのエアコンや、冷たい飲み物の摂りすぎ、薄着なども体を冷やす原因となります。
体の冷えは、目元の血行不良を招き、青クマを悪化させる隠れた要因なのです。
ストレスによる自律神経の乱れ
精神的なストレスも、青クマの原因として無視できません。過度なストレスを感じると、体は緊張状態になり、自律神経のうち交感神経が活発になります。
交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、ストレスが続くと血行不良が慢性化します。
リラックスしているときに働く副交感神経への切り替えがうまくいかなくなり、常に体がこわばった状態になることで、血流が滞り、目の下にクマとして現れるのです。
青クマの原因となる生活習慣
| 生活習慣 | 血行不良への影響 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 自律神経の乱れ、血管収縮 | 平均睡眠時間が6時間未満 |
| 眼精疲労 | 目の周りの筋肉の緊張 | 1日4時間以上のPC・スマホ作業 |
| 体の冷え | 全身の血管収縮 | シャワーのみの入浴、薄着 |
【茶クマの原因】色素沈着が起こる仕組み
茶クマは、シミやくすみと同じカテゴリーに分類される肌トラブルです。
その正体は、紫外線や摩擦などの外部からの刺激によって生成されたメラニン色素が、肌のターンオーバーで正常に排出されずに皮膚に沈着してしまったものです。
ここでは、どのような行動が色素沈着を引き起こし、茶クマができる仕組みになっているのかを詳しく見ていきましょう。
摩擦による刺激(目をこする癖)
茶クマの最も一般的な原因は、物理的な摩擦です。花粉症やアレルギーで目がかゆいとき、無意識にゴシゴシと目をこすっていませんか。
また、眠いときや疲れたときに目をこする癖がある人も注意が必要です。目の下の皮膚は非常にデリケートなため、わずかな摩擦でも大きな刺激となります。
この刺激から肌を守ろうとして、メラノサイトという色素細胞が活性化し、メラニン色素を過剰に生成します。このメラニンが排出されずに残ることで、茶色い色素沈着、つまり茶クマになるのです。
紫外線によるメラニン生成
紫外線は、シミの最大の原因として知られていますが、茶クマの原因にもなります。目の周りは顔の中でも骨格的に高く、紫外線を浴びやすい部分です。
日焼け止めを塗る際に、目のキワまで丁寧に塗れていない人も多いのではないでしょうか。紫外線を浴びると、肌はダメージから細胞を守るためにメラニンを生成します。
通常、このメラニンは肌のターンオーバーによって垢とともに剥がれ落ちますが、過剰に生成されたり、ターンオーバーが乱れたりすると、そのまま皮膚に残り、茶クマとして定着してしまいます。
メイク落としの際の強い刺激
毎日のクレンジングも、茶クマの原因となる可能性があります。特に、ウォータープルーフのマスカラやアイライナーを落とす際に、ゴシゴシと強くこすっている場合は要注意です。
落ちにくいポイントメイクを無理に落とそうとすると、必要以上に肌に摩擦を与えてしまいます。この日々の積み重ねが、色素沈着を引き起こすきっかけになります。
ポイントメイクは専用のリムーバーを使い、コットンにたっぷりと含ませて、優しく押さえるようにして浮かせてから拭き取ることが大切です。
- 目を強くこする
- 洗浄力の強すぎるクレンジングの使用
- タオルで顔を拭く際の摩擦
アトピー性皮膚炎などによる炎症
アトピー性皮膚炎や化粧品かぶれなど、目の周りに湿疹や炎症が長期間続いた場合も、茶クマの原因となります。これは「炎症後色素沈着」と呼ばれるものです。
炎症が起こると、肌内部ではメラノサイトが刺激され、メラニンが過剰に作られます。炎症が治まった後も、そのときに作られたメラニンが皮膚に残り、茶色い跡としてくすみやクマになってしまうのです。
皮膚炎がある場合は、まずその治療を優先することが、茶クマの予防と改善につながります。
【黒クマの原因】加齢と骨格による影の正体
黒クマは、青クマや茶クマとは異なり、皮膚に色がついているわけではありません。その正体は、目の下の構造的な変化によって生まれる「影」です。
加齢による肌の変化が主な原因ですが、生まれつきの骨格が影響している場合もあります。ここでは、黒クマができる仕組みについて詳しく解説します。
加齢による皮膚のたるみ
黒クマの最大の原因は、加齢に伴う皮膚のたるみです。年齢を重ねると、肌のハリや弾力を保つために重要な役割を果たすコラーゲンやエラスチンが減少し、質も変化していきます。
これにより、皮膚は弾力を失い、重力に逆らえずにたるんできます。特に薄くて動きの多い目の下の皮膚はたるみやすく、その結果としてできる凹凸が影を作り、黒クマとして認識されるのです。
コラーゲン・エラスチンの減少
真皮層に存在するコラーゲンとエラスチンは、肌を内側から支える柱やバネのような存在です。
しかし、20代をピークにその生成量は減少し始め、紫外線や乾燥などの外部からのダメージによっても破壊・変性されます。
この支持組織が弱くなると、皮膚全体がゆるみ、ハリが失われます。
目の下の皮膚が薄く伸びたような状態になり、下にある脂肪や筋肉の形が浮き彫りになることで、凹凸が強調され、影が目立つようになります。
眼窩脂肪(がんかしぼう)の突出
目の周りには、眼球をクッションのように保護する「眼窩脂肪」という脂肪があります。この眼窩脂肪は、眼輪筋という筋肉によって支えられています。
しかし、加齢によって眼輪筋が衰えたり、皮膚がたるんだりすると、支えきれなくなった眼窩脂肪が前方に押し出されてきます。この突出した脂肪(いわゆる目袋)が、その下に影を作り出します。
この影こそが黒クマの正体であり、疲れた印象や老けた印象を強く与える原因となります。
黒クマを進行させる要因
| 要因 | 肌への影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 加齢 | コラーゲン・エラスチンの減少 | 皮膚のハリ低下、たるみ |
| 紫外線ダメージ | コラーゲン繊維の破壊 | 弾力性の喪失、しわ |
| 筋肉の衰え | 眼窩脂肪を支える力の低下 | 目袋の突出、影の形成 |
生まれつきの骨格の影響
黒クマは加齢だけでなく、生まれつきの骨格が原因で若いうちから目立つこともあります。
例えば、頬骨の位置が低かったり、眼球が収まっているくぼみ(眼窩)が大きかったりすると、構造的に目の下に影ができやすくなります。
このような骨格的な特徴を持つ人は、加齢によるたるみがなくても、涙袋の下にくぼみや影が見られ、黒クマのように感じることがあります。
この場合、年齢を重ねてたるみが加わると、さらに黒クマが目立ちやすくなります。
クマを悪化させる意外な生活習慣
クマの発生には、これまで見てきたように直接的な原因がありますが、日々の何気ない生活習慣が、間接的にクマを悪化させていることも少なくありません。
ここでは、クマの改善を妨げ、さらに濃くしてしまう可能性のある意外な生活習慣について解説します。
食生活の乱れと栄養不足
肌は、私たちが食べたものから作られます。栄養バランスの偏った食事は、肌の健康を損ない、クマを悪化させる原因となります。
特に、血行を促進し、健康な皮膚を維持するために必要な栄養素が不足すると、クマが目立ちやすくなります。
例えば、血液の材料となる鉄分が不足すると、貧血気味になり、血行不良による青クマにつながります。
また、肌のハリを保つコラーゲンの生成を助けるビタミンCや、血行を良くするビタミンEの不足も、クマの原因となり得ます。
クマ対策のための栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 鉄分 | 血液の材料、酸素運搬 | レバー、ほうれん草、あさり |
| ビタミンC | コラーゲン生成促進、抗酸化作用 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
喫煙と飲酒の影響
喫煙は、クマにとって百害あって一利なしの習慣です。タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、全身の血行を著しく悪化させます。
これにより、青クマが直接的に引き起こされます。さらに、喫煙は体内で大量のビタミンCを破壊します。
ビタミンCは、肌のハリを保つコラーゲンの生成や、茶クマの原因となるメラニンの生成を抑制する働きがあるため、その不足は黒クマと茶クマの両方を悪化させます。
アルコールの過剰摂取も、分解のためにビタミンやミネラルを消費し、睡眠の質を低下させるため、クマの間接的な原因となります。
間違ったスキンケア
良かれと思って行っているスキンケアが、実はクマを悪化させているケースもあります。
例えば、保湿不足です。目の周りの皮膚は乾燥しやすく、乾燥すると肌のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
これにより、茶クマの原因となる色素沈着が起こりやすくなります。また、クマを解消しようとして、目の周りを強くマッサージするのも逆効果です。
過度なマッサージは摩擦刺激となり、茶クマを誘発したり、皮膚を伸ばしてたるみの原因となり、黒クマを悪化させる可能性があります。スキンケアは、優しく丁寧に行うことが基本です。
睡眠の質と量の問題
「寝不足がクマの原因」というのは広く知られていますが、単に睡眠時間が長ければ良いというわけではありません。「睡眠の質」も同様に重要です。
浅い眠りが続いていたり、夜中に何度も目が覚めたりすると、たとえ長時間寝ていても体は十分に回復できません。
質の悪い睡眠は、自律神経の乱れや疲労の蓄積につながり、血行不良を招いて青クマを悪化させます。
また、寝る直前までスマートフォンを見ていると、ブルーライトの影響で寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下します。快適な睡眠環境を整え、質の高い睡眠をとることが、クマの予防・改善には大切です。
【種類別】自宅でできるクマのセルフケア入門
自分のクマのタイプと原因がわかったら、次はその対策です。ここでは、それぞれのクマのタイプに合わせて、今日から始められるセルフケアの基本的な方法を紹介します。
専門的な治療も選択肢の一つですが、まずは日々のケアを見直すことから始めましょう。
青クマ対策 温めて血行促進
青クマの主な原因は血行不良なので、ケアの基本は「温めること」です。蒸しタオルや市販のホットアイマスクを使って、目の周りを優しく温めましょう。
血行が促進され、滞っていた血流が改善されることで、クマの色が和らぎます。また、湯船にしっかり浸かって全身を温めることも効果的です。
血行を良くするビタミンEなどが含まれたアイクリームを使い、薬指で優しくマッサージするのも良いでしょう。ただし、力を入れすぎないように注意が必要です。
茶クマ対策 美白成分と保湿ケア
茶クマは色素沈着が原因なので、シミ対策と同様のケアが有効です。まずは、これ以上色素沈着を増やさないために、紫外線対策を徹底しましょう。
日焼け止めは目のキワまで丁寧に塗り、日傘やサングラスも活用します。
スキンケアでは、メラニンの生成を抑える働きのある「ビタミンC誘導体」や「トラネキサム酸」などの美白有効成分が配合された化粧品を取り入れるのがおすすめです。
そして、何よりも重要なのが保湿です。肌が潤っているとターンオーバーが正常に働き、メラニンの排出を助けます。
黒クマ対策 エイジングケアと表情筋トレーニング
黒クマは皮膚のたるみや凹凸による影が原因のため、セルフケアで完全に解消するのは難しい面もありますが、進行を緩やかにするためのケアは可能です。
肌のハリをサポートする「レチノール」や「ペプチド」などが配合された、エイジングケア向けのアイクリームを使い、内側からの弾力アップを目指しましょう。
また、目の周りの筋肉(眼輪筋)を鍛える表情筋トレーニングも、たるみ予防に役立ちます。目を大きく見開いたり、ゆっくり閉じたりする動きを繰り返すなど、無理のない範囲で続けてみましょう。
- 十分な睡眠
- バランスの取れた食事
- 適度な運動
全タイプに共通する基本的な生活改善
どのタイプのクマであっても、その根底には生活習慣の乱れが影響していることが少なくありません。特定のケアに加えて、生活習慣全体を見直すことが、クマの根本的な改善につながります。
栄養バランスの整った食事を心がけ、質の良い睡眠を十分にとり、適度な運動で全身の血行を促進することが大切です。
また、ストレスを溜め込まず、自分なりのリラックス方法を見つけることも、肌の健康を保つ上で重要です。基本的な生活を整えることが、あらゆる肌トラブルの予防と改善の土台となります。
目の下のクマに関するQ&A
最後に、目の下のクマに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が抱く疑問を解消し、クマへの理解をさらに深めましょう。
- 男性と女性でクマの原因に違いはありますか?
-
基本的なクマの種類(青・茶・黒)と、その発生の仕組みに男女差はほとんどありません。ただし、ライフスタイルの違いから、目立ちやすいクマのタイプに傾向が見られることがあります。
例えば、女性はメイクによる摩擦やクレンジング不足で茶クマができやすい傾向があり、一方で男性はスキンケアや紫外線対策を怠りがちで、皮膚の老化が早く進み黒クマが目立ちやすい場合があります。
また、貧血や冷え性は女性に多いため、青クマに悩む女性も多いです。しかし、これらはあくまで傾向であり、原因は個人によって異なります。
- 子供にもクマができるのはなぜですか?
-
子供にクマが見られる場合、いくつかの原因が考えられます。最も多いのは、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎によるものです。
鼻炎で鼻が詰まっていると、目の周りの血流が滞りやすくなり、青クマができることがあります。
また、アトピーなどで目のかゆみが強いと、頻繁に目をこするため摩擦による茶クマ(色素沈着)が起こりやすくなります。
そのほか、生まれつき皮膚が薄い、あるいは骨格的に影ができやすい体質であることも考えられます。気になる場合は、まず小児科や皮膚科に相談することをおすすめします。
- クマは一度できたら自力では消せませんか?
-
クマの種類によります。血行不良が原因の「青クマ」は、睡眠を十分にとったり、体を温めたりするセルフケアで、比較的改善しやすいタイプです。
色素沈着による「茶クマ」も、美白ケアや紫外線対策を根気強く続けることで、少しずつ薄くすることが期待できます。
しかし、たるみや骨格が原因の「黒クマ」は、セルフケアだけで完全に消すことは困難です。
エイジングケアで進行を遅らせることはできますが、根本的な改善を望む場合は、美容クリニックでの治療が選択肢となります。
- コンシーラーでうまく隠すコツはありますか?
-
コンシーラーでクマを自然に隠すには、クマの色に合わせた「補色」を選ぶのがコツです。自分のクマの色と反対の色を重ねることで、色が打ち消し合い、目立たなくなります。
例えば、青クマにはオレンジ系のコンシーラー、茶クマにはイエロー系のコンシーラーがおすすめです。黒クマの場合は、明るいベージュやオークル系で影を飛ばすようにカバーします。
塗る際は、厚塗りを避け、クマの最も濃い部分に少量置き、指やブラシで優しくトントンと叩き込むようになじませるのがポイントです。
クマの種類とコンシーラーの色選び
クマの種類 クマの色 おすすめのコンシーラーの色 青クマ 青黒い、紫色 オレンジ系、ピーチ系 茶クマ 茶色、くすみ イエロー系 黒クマ 黒い影 明るめのベージュ、オークル系
参考文献
CHATTERJEE, Manas, et al. A study of epidemiological, etiological, and clinicopathological factors in periocular hyperpigmentation. Pigment International, 2018, 5.1: 34-42.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
SARKAR, Rashmi, et al. Periorbital hyperpigmentation: a comprehensive review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 49.
HUANG, Yau‐Li, et al. Clinical analysis and classification of dark eye circle. International journal of dermatology, 2014, 53.2: 164-170.
FATIN, Amira M., et al. Classification and characteristics of periorbital hyperpigmentation. Skin Research and Technology, 2020, 26.4: 564-570.
JAGE, Mithali; MAHAJAN, Sunanda. Clinical and dermoscopic evaluation of periorbital hyperpigmentation. Indian Journal of Dermatopathology and Diagnostic Dermatology, 2018, 5.1: 42-47.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
PARK, S. R., et al. Classification by causes of dark circles and appropriate evaluation method of dark circles. Skin Research and Technology, 2016, 22.3: 276-283.
POUR MOHAMMAD, Arash, et al. The First Systematic Review and Meta‐Analysis of Pharmacological and Nonpharmacological Procedural Treatments of Dark Eye Circles (Periorbital Hyperpigmentations): One of the Most Common Cosmetic Concerns. Dermatologic Therapy, 2025, 2025.1: 9155535.
MATSUI, Mary S., et al. Physiological and lifestyle factors contributing to risk and severity of peri-orbital dark circles in the Brazilian population. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90.4: 494-503.
クマの原因・メカニズムに戻る