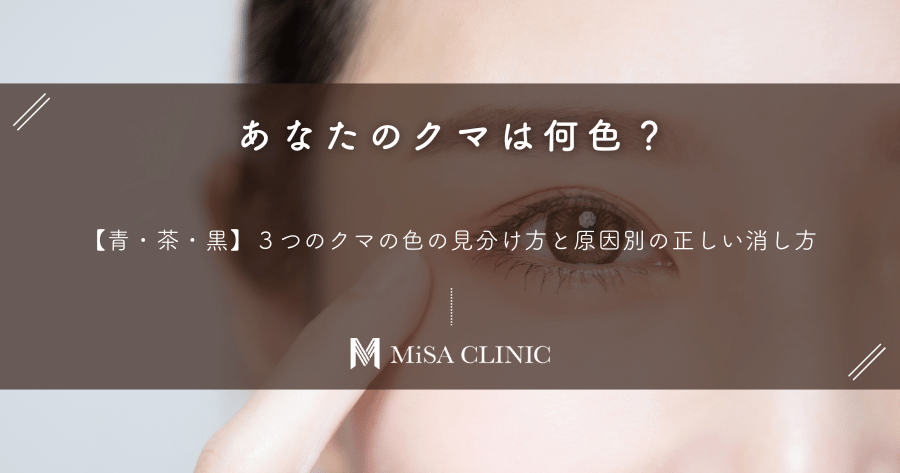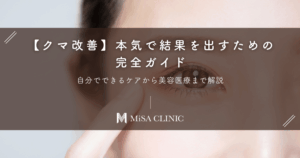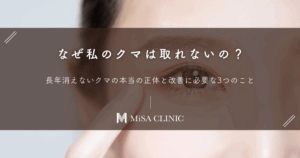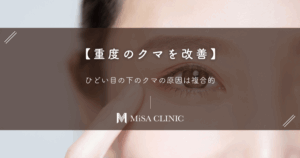ふと鏡を見たときに気になる、目の下のクマ。「疲れているように見える」「老けて見える」など、多くの女性にとって悩みの種です。
しかし、一口にクマといっても、実は「青クマ」「茶クマ」「黒クマ」の3種類があり、それぞれ原因も対処法も全く異なります。自分のクマがどのタイプかを知ることが、効果的なケアへの第一歩です。
この記事では、あなたのクマの色の見分け方から、原因に応じた正しいセルフケア、さらに美容医療の選択肢まで、専門的な情報を分かりやすく解説します。
そもそも目の下のクマとは?3つの種類を理解しよう
多くの人が悩む目の下のクマですが、その正体や種類について正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
まずはクマの基本的な知識と、なぜ自分のクマの種類を知ることが重要なのかを解説します。
目の下が暗く見える「クマ」の正体
目の下のクマとは、目の周りの皮膚が他の部分よりも暗く見える状態の総称です。
目の下の皮膚は非常に薄く、約0.5mm〜0.6mmほどしかありません。これは頬の皮膚の3分の1程度の薄さです。
そのため、皮膚の下にある血管の色が透けて見えたり、色素沈着が目立ったり、皮膚の構造的な変化による影ができやすかったりします。
これらの要因が単独、あるいは複合的に絡み合うことで、「クマ」として現れます。
クマは主に「青クマ」「茶クマ」「黒クマ」の3種類
目の下のクマは、その見た目の色や原因から、主に3つのタイプに分類します。1つ目は、血行不良によって青黒く見える「青クマ」。
2つ目は、メラニン色素の沈着によって茶色く見える「茶クマ」。そして3つ目は、皮膚のたるみやへこみによる影で黒く見える「黒クマ」です。
それぞれのクマは原因が異なるため、改善するためのアプローチも変わってきます。
複数の種類が混在する混合タイプのクマ
実際には、これらのクマが1種類だけではなく、2種類以上が混在しているケースも珍しくありません。例えば、血行不良による青クマと、たるみによる黒クマが合わさっている場合などです。
混合タイプの場合、それぞれのクマの原因に対してアプローチする必要があるため、ケアがより複雑になります。
自分のクマがどのタイプに当てはまるのか、あるいは混合タイプなのかを正確に見極めることが大切です。
なぜクマの色を知ることが大切なのか
クマの色を見極めることは、効果的な対策を行う上で非常に重要です。例えば、血行不良が原因の青クマに対して美白化粧品を使っても、期待する効果は得られません。
逆に、色素沈着が原因の茶クマに血行を促進するマッサージを強く行いすぎると、摩擦でさらに悪化させる可能性があります。
クマの色から原因を正しく推測し、その原因に合ったケアを選択することが、クマ改善への最短ルートといえるでしょう。
3種類のクマ 概要比較
| クマの種類 | 見た目の色 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 青クマ | 青黒い、紫がかっている | 血行不良 |
| 茶クマ | 茶色い、くすんでいる | 色素沈着 |
| 黒クマ | 黒い、灰色っぽい | 皮膚のたるみ・へこみによる影 |
あなたのクマは何色?簡単なセルフチェックで見分ける方法
自分のクマがどのタイプなのかを判断するために、自宅で簡単にできるセルフチェック方法を紹介します。特別な道具は必要ありません。
鏡を使って、あなたのクマの色を見分けてみましょう。
鏡を使った基本的な確認手順
まず、自然光の入る明るい場所で、手鏡または洗面台の鏡の前に立ちます。蛍光灯の下では肌の色が違って見えることがあるため、できるだけ自然光の下で確認するのがおすすめです。
顔の力を抜き、まっすぐ正面を向いて、目の下の色や状態をじっくりと観察してください。
指で皮膚を引っ張って色をチェック(青クマ・茶クマの見分け方)
青クマと茶クマは、簡単な動作で見分けることができます。優しく皮膚を動かして、色の変化を確認してみましょう。
青クマのチェック方法
目の下の皮膚を指で軽く横に引っ張ってみてください。このとき、クマの色が薄くなる、または一時的に消えるようであれば、それは「青クマ」の可能性が高いです。
皮膚を引っ張ることで、滞留していた血液が一時的に移動し、血管が透けて見えにくくなるために色が薄くなります。
茶クマのチェック方法
同じように目の下の皮膚を指で軽く横に引っ張ります。皮膚を引っ張ってもクマの色が変わらない、または皮膚と一緒にクマの色も移動する場合は、「茶クマ」と考えられます。
これは皮膚そのものに色素が沈着しているため、皮膚を動かしても色が変化しないのです。
顔の角度を変えて影をチェック(黒クマの見分け方)
次に、「黒クマ」を見分ける方法です。鏡を持ったまま、顔をまっすぐ前に向けた状態から、ゆっくりと顔を上に向け、天井を見上げるようにします。
このとき、目の下のクマが薄くなる、または消えるように見える場合は、「黒クマ」の可能性が高いです。
顔を上に傾けると、たるみによってできていた影が光によって消えるため、クマが目立たなくなります。逆に、クマの色が変わらない場合は、黒クマ以外の可能性を考えます。
チェック時の注意点とポイント
セルフチェックを行う際は、いくつかの点に注意しましょう。まず、目の周りの皮膚は非常にデリケートなため、絶対に強くこすったり、引っ張りすぎたりしないでください。
あくまで優しく触れる程度に留めます。また、メイクは完全に落とした状態で確認することが重要です。ファンデーションやコンシーラーが残っていると、正確な色を判断できません。
クマの見分け方セルフチェックシート
| チェック項目 | 結果 | 考えられるクマの種類 |
|---|---|---|
| 皮膚を横に引っ張ると色が薄くなる | はい | 青クマ |
| 皮膚を横に引っ張っても色が変わらない | はい | 茶クマ |
| 顔を上に傾けると影が薄くなる | はい | 黒クマ |
【青クマ】血行不良が原因!特徴と改善策
目の下が青黒く見える青クマ。このタイプのクマは、生活習慣が大きく関係しています。原因を理解し、適切なケアを行うことで改善が期待できます。
なぜ目の下が青く見えるのか
青クマの正体は、薄い皮膚から透けて見える毛細血管の色です。目の周りには毛細血管が網目のように張り巡らされています。
睡眠不足や疲労、体の冷えなどによって血行が悪くなると、血液中の酸素が不足し、血液が暗い赤色(静脈血)になります。
この暗い色の血液が、薄い皮膚を通して青黒く、あるいは紫のように見えるのが青クマの仕組みです。
青クマの主な原因は生活習慣にあり
青クマは、日々の生活習慣が原因で起こることがほとんどです。以下のような要因が血行不良を引き起こし、青クマを目立たせます。
睡眠不足と疲労
睡眠不足や心身の疲労が蓄積すると、自律神経のバランスが乱れ、血行が悪くなります。特に睡眠中は体を修復し、疲労を回復させるための重要な時間です。
この時間が不足すると、血行不良が改善されず、クマとなって現れやすくなります。
冷えやストレス
体が冷えると血管が収縮し、血流が滞ります。特に女性は筋肉量が少なく、冷えやすい傾向にあります。また、精神的なストレスも血管を収縮させ、血行不良を招く一因です。
デスクワークで長時間同じ姿勢でいることも、全身の血行を悪化させます。
スマートフォンやPCの長時間利用
スマートフォンやPCの画面を長時間見続けると、目の周りの筋肉が緊張し、血行が悪くなります。これが眼精疲労を引き起こし、青クマを悪化させる原因となります。
定期的に休憩を取り、目を休ませることが重要です。いわゆる「クマが紫に見える」という場合も、この青クマが悪化した状態であることが多いです。
自宅でできる青クマのセルフケア方法
青クマの改善には、血行を促進することが何よりも大切です。日々の生活の中で、手軽に取り入れられるセルフケアを紹介します。
青クマ対策のセルフケア
| ケア方法 | ポイント | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| 目元を温める | 蒸しタオルや市販のホットアイマスクで5分~10分程度温める。40℃前後が適温。 | 1日1回、就寝前など |
| 全身浴 | 38℃~40℃のぬるめのお湯に15分以上浸かり、体を芯から温める。 | 毎日 |
| 軽い運動 | ストレッチやウォーキングなど、血行を促進する軽い運動を取り入れる。 | 毎日少しずつ |
美容医療によるアプローチ
セルフケアで改善が見られない場合や、より早く効果を実感したい場合は、美容医療も選択肢の一つです。血行を促進する成分を直接注入する方法や、レーザー治療などで血行を改善する方法があります。
専門のクリニックで相談し、自分に合った治療法を検討するのも良いでしょう。
【茶クマ】色素沈着が原因!特徴と改善策
目の下が茶色くくすんで見える茶クマ。これは皮膚そのものに色がついてしまっている状態で、青クマとは全く異なるアプローチが必要です。
茶色いクマの原因と正しい消し方について見ていきましょう。
目の下が茶色く見える原因
茶クマの主な原因は、メラニン色素の沈着です。メラニンは、紫外線や摩擦などの刺激から肌を守るために生成される色素です。
通常、肌のターンオーバー(新陳代謝)によって古い角質とともに排出されますが、過剰な刺激が続いたり、ターンオーバーが乱れたりすると、メラニンが排出されずに皮膚の内部に蓄積してしまいます。
これが色素沈着となり、茶クマとして現れます。茶色いクマは、シミやくすみと同じ仕組みで発生するのです。
茶クマを引き起こすNG習慣
日常生活の中に、知らず知らずのうちに茶クマを悪化させる習慣が隠れているかもしれません。心当たりがないかチェックしてみましょう。
目のこすりすぎ
花粉症やアレルギーで目がかゆい時、アイメイクを落とす時、無意識に目をゴシゴシこすっていませんか?
目の周りの皮膚は非常に薄くデリケートなため、摩擦による刺激はメラニンを過剰に生成させる大きな原因となります。これが茶色いクマの原因になります。
紫外線対策の不足
紫外線はメラニンを生成する最大の要因です。顔の中でも特に高い位置にある目の周りは、紫外線の影響を受けやすい部位です。
日焼け止めを塗り忘れたり、サングラスを使わなかったりすると、色素沈着が進み、茶クマが濃くなる原因となります。
間違ったクレンジング
洗浄力の強すぎるクレンジング剤を使ったり、アイメイクを落とす際に強くこすったりすることも、肌への負担となり色素沈着を招きます。
ポイントメイクリムーバーを使い、優しく丁寧に落とすことが大切です。
色素沈着を招く要因
- 紫外線
- 物理的な摩擦
- 肌の乾燥
茶クマに効果的なセルフケアと成分
茶クマのセルフケアは、「メラニンを作らせないこと」と「できてしまったメラニンの排出を促すこと」が基本です。
美白有効成分が配合されたアイクリームなどを取り入れるのが効果的です。
茶クマ対策におすすめの成分
| 成分名 | 期待できる効果 | ポイント |
|---|---|---|
| ビタミンC誘導体 | メラニンの生成抑制、抗酸化作用 | 浸透力の高い製品を選ぶ |
| トラネキサム酸 | メラニン生成を促す情報伝達物質の抑制 | 刺激が少なく、敏感肌にも使いやすい |
| ハイドロキノン | メラニンの生成を強力に抑制 | 医師の指導の下で使用することが望ましい |
美容医療での色素沈着治療
セルフケアでの改善には時間がかかります。より早く、確実に茶クマを改善したい場合は、美容医療が有効です。
メラニン色素を破壊するレーザー治療(ピコレーザーなど)や、肌のターンオーバーを促進するケミカルピーリング、美白成分を肌の深層に届ける導入治療など、様々な選択肢があります。
【黒クマ】たるみが原因!特徴と改善策
疲れた印象や老けた印象を与えがちな黒クマ。その正体は、色ではなく「影」です。黒クマの仕組みと、改善に向けたアプローチについて解説します。
影によって黒く見える黒クマの正体
黒クマは、青クマや茶クマのように皮膚に色がついているわけではありません。
加齢などによって目の下の皮膚がたるんだり、元々の骨格によって目の下に凹凸があったりすることで、影ができて黒く見えている状態です。
特に、目の下の脂肪(眼窩脂肪)が前方に突出することや、その下の部分がくぼむことで段差ができ、その段差が影を生み出すのが典型的なパターンです。
黒クマの主な原因は加齢と骨格
黒クマは、主に加齢による肌構造の変化が原因で現れますが、若い人でも骨格によっては目立つことがあります。
コラーゲンやエラスチンの減少
加齢とともに、肌のハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、質も低下します。これにより皮膚が薄くなり、ハリを失ってたるみが生じます。これが黒クマの大きな原因です。
眼輪筋の衰え
目の周りには眼輪筋というドーナツ状の筋肉があり、眼窩脂肪を支えています。
この眼輪筋が加齢やPCの長時間使用などで衰えると、脂肪を支えきれなくなり、前方に押し出されてふくらみ(目袋)ができます。このふくらみが影を作り、黒クマとなります。
生まれつきの骨格
生まれつき頬骨の位置が低い、あるいは眼球が収まっている窪み(眼窩)が大きいなど、骨格的に目の下に影ができやすい人もいます。
この場合、若い頃から黒クマが目立つことがあります。
黒クマのセルフケアでできること
黒クマは構造的な問題であるため、セルフケアで完全に解消するのは難しいのが現実です。
しかし、エイジングケアやトレーニングによって、これ以上悪化させない、あるいは少しでも目立たなくすることは可能です。
黒クマのセルフケア
| ケアの種類 | 具体的な方法 | 期待できること |
|---|---|---|
| エイジングケア | レチノールやナイアシンアミドなど、ハリを与える成分配合の化粧品を使用する。 | 肌のハリを保ち、たるみの進行を緩やかにする。 |
| 表情筋トレーニング | 眼輪筋を鍛えるトレーニングを行う。ただし、やりすぎはシワの原因になるため注意。 | 目の下のたるみを支える筋肉を強化する。 |
| 徹底した保湿 | セラミドやヒアルロン酸などでしっかり保湿し、乾燥による小じわを防ぐ。 | 肌のキメを整え、影を目立ちにくくする。 |
美容医療での根本的なアプローチ
黒クマを根本的に改善するには、美容医療が最も効果的な選択肢となります。突出した脂肪を取り除く「脱脂術」や、くぼんだ部分にヒアルロン酸や脂肪を注入して段差をなくす治療が一般的です。
これらの治療により、影の原因となる凹凸そのものを解消し、フラットで若々しい目元を目指すことができます。
クマを悪化させないための日常生活の注意点
どのタイプのクマであっても、日々の生活習慣がその見た目に大きく影響します。クマを悪化させず、改善をサポートするために、日常生活で見直したいポイントを解説します。
バランスの取れた食事と栄養素
体は食べたもので作られます。特に血行や肌の状態に影響を与える栄養素を意識的に摂取することが、クマの予防・改善につながります。
クマ対策に役立つ栄養素と食材
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| 鉄分 | 血液の材料となり、貧血による血行不良を防ぐ。 | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |
| ビタミンE | 血行を促進し、抗酸化作用で肌の老化を防ぐ。 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助け、メラニン生成を抑制する。 | パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ |
質の高い睡眠を確保する工夫
睡眠は、肌のターンオーバーを促し、血行を改善するためのゴールデンタイムです。ただ長く寝るだけでなく、「質」を高めることが重要です。
就寝前のスマートフォン操作を控え、リラックスできる環境を整えましょう。自分に合った寝具を選ぶことも、深い眠りにつながります。
正しいスキンケアと紫外線対策の徹底
日々のスキンケアは、クマの予防と改善の基本です。特に「優しさ」と「保湿」を徹底しましょう。
やさしいクレンジングと洗顔
メイクや汚れはしっかり落とす必要がありますが、摩擦は厳禁です。クレンジング剤は十分な量を使い、肌の上で指を滑らせるように優しくなじませます。
洗顔料はよく泡立て、泡で顔を包み込むように洗い、ぬるま湯で丁寧にすすぎましょう。
徹底した保湿ケア
乾燥は肌のバリア機能を低下させ、あらゆる肌トラブルの原因となります。化粧水で水分を与えたら、必ず乳液やクリームで油分を補い、水分が蒸発しないように蓋をします。
特に乾燥しやすい目の周りは、アイクリームを使って重点的にケアするのがおすすめです。
コンシーラーを使った上手なクマの隠し方
すぐにクマを消したい時には、メイクの力を借りるのも一つの方法です。コンシーラーの色選びが成功の鍵を握ります。
自分のクマの色とは反対の「補色」を選ぶと、色ムラを自然にカバーできます。
クマの色別コンシーラー選び
- 青クマ → オレンジ系
- 茶クマ → イエロー系
- 黒クマ → ベージュ系・パール感のあるもの
コンシーラーを塗る際は、厚塗りにならないよう、少量を指やブラシで優しく叩き込むようにのせるのがコツです。
クマの種類別 美容医療の選択肢
セルフケアだけでは改善が難しい目の下のクマに対して、美容医療は効果的な解決策を提示します。ここでは、クマの種類ごとにどのような治療法があるのか、その概要を紹介します。
自分のクマに合った治療法を見つける重要性
前述の通り、クマは種類によって原因が全く異なります。そのため、治療法も原因に合わせて選ぶことが何よりも重要です。
自己判断で治療を選ぶのではなく、まずは経験豊富な医師の診察を受け、自分のクマの種類と状態を正確に診断してもらいましょう。
その上で、自分に合った治療法について相談することが、満足のいく結果への近道です。
青クマに対する美容医療
血行不良が原因の青クマには、血流を改善したり、皮膚の厚みを増して血管が透けにくくしたりする治療が適しています。例えば、血行促進作用のある成分や、肌の再生を促す成分を注入する治療があります。
また、特定の波長の光を照射して血流を改善する光治療なども選択肢の一つです。
茶クマに対する美容医療
色素沈着が原因の茶クマには、メラニン色素に直接アプローチする治療が中心となります。代表的なのは、メラニン色素を細かく破壊して排出を促すレーザー治療です。
肌のターンオーバーを正常化させるケミカルピーリングや、美白成分を肌の奥深くまで届けるイオン導入なども、状態に応じて組み合わせることがあります。
黒クマに対する美容医療
たるみや凹凸による影が原因の黒クマには、その構造的な問題を解決する治療が必要です。
目の下のふくらみの原因である眼窩脂肪を取り除く「経結膜脱脂術」は、根本的な改善が期待できる代表的な治療法です。
また、脂肪によるふくらみと頬の間のくぼみに、ヒアルロン酸や自身の脂肪を注入して段差を滑らかにする方法もあります。これらの治療を組み合わせることで、より自然で美しい仕上がりを目指します。
クマの種類別・代表的な美容医療
| クマの種類 | 治療法の一例 | 治療の主な目的 |
|---|---|---|
| 青クマ | 注入治療、光治療 | 血行促進、皮膚のハリ改善 |
| 茶クマ | レーザー治療、ケミカルピーリング | メラニン色素の除去、ターンオーバー促進 |
| 黒クマ | 経結膜脱脂術、ヒアルロン酸・脂肪注入 | 脂肪によるふくらみの除去、凹凸の平坦化 |
目の下のクマに関するよくある質問
- クマは遺伝しますか?
-
クマそのものが直接遺伝するわけではありませんが、クマができやすい「体質」や「骨格」は遺伝する可能性があります。
例えば、皮膚が薄い、アレルギー体質で目をこすりやすい、骨格的に目の下がくぼんでいる、といった特徴は親から子へ受け継がれることがあります。
これらの要因が、青クマ、茶クマ、黒クマをそれぞれ発症しやすくする可能性があります。
- 男性と女性でクマの原因に違いはありますか?
-
基本的なクマの発生原因(血行不良、色素沈着、たるみ)に男女差はありません。しかし、女性は男性に比べて皮膚が薄く、冷え性である傾向が強いため、青クマが目立ちやすいと言えます。
また、メイクによる摩擦やクレンジング不足が茶クマの原因になることも女性に多い特徴です。
一方、男性はスキンケアや紫外線対策を怠りがちで、それが茶クマや黒クマ(たるみ)の進行を早めることがあります。
- クマ改善のセルフケアはどのくらいで効果が出ますか?
-
効果が現れるまでの期間は、クマの種類や重症度、そして行うケアの内容によって大きく異なります。
血行不良が原因の青クマは、生活習慣の改善によって数週間から1ヶ月程度で変化を感じ始める人もいます。
一方、色素沈着が原因の茶クマや、たるみが原因の黒クマは、肌のターンオーバーや構造に関わるため、セルフケアで目に見える効果を実感するには数ヶ月以上の継続的な努力が必要です。
- 目の下のマッサージはクマに効果的ですか?やりすぎは逆効果?
-
目の周りのマッサージは、血行を促進する目的で青クマの改善にはある程度有効です。しかし、やり方が重要です。
強い力でこするようなマッサージは、摩擦によって色素沈着(茶クマ)を引き起こしたり、皮膚を伸ばしてたるみ(黒クマ)を助長したりするリスクがあり、逆効果です。
マッサージを行う場合は、必ず滑りの良いクリームやオイルを使い、指の腹で優しくツボを押したり、リンパを流すようにソフトに行うことが大切です。
参考文献
HUANG, Yau‐Li, et al. Clinical analysis and classification of dark eye circle. International journal of dermatology, 2014, 53.2: 164-170.
MAC-MARY, Sophie, et al. Identification of three key factors contributing to the aetiology of dark circles by clinical and instrumental assessments of the infraorbital region. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2019, 919-929.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
SARKAR, Rashmi, et al. Periorbital hyperpigmentation: a comprehensive review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 49.
LIM, Hester Gail Y., et al. Periocular dark circles: correlates of severity. Annals of dermatology, 2021, 33.5: 393.
PISSARIDOU, Maria Katerina; GHANEM, Ali; LOWE, Nicholas. Periorbital Discolouration diagnosis and treatment: evidence-based review. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2020, 22.6-8: 217-225.
RAJABI‐ESTARABADI, Ali, et al. Effectiveness and tolerance of multicorrective topical treatment for infraorbital dark circles and puffiness. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.2: 486-495.
FATIN, Amira M., et al. Classification and characteristics of periorbital hyperpigmentation. Skin Research and Technology, 2020, 26.4: 564-570.
CYMBALISTA, Natalia Cymrot; GARCIA, Renato; BECHARA, Samir Jacob. Etiopathogenic classification of infraor-bital dark circles and filling with hyalu-ronic acid: description of a new techni-que using a cannula. New Techniques/Novas Técnicas, 315.