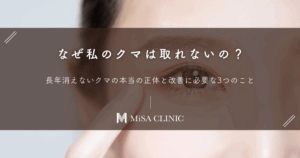コンシーラーで隠しきれない、疲れているように見られてしまう「ひどい目の下のクマ」。
その原因は一つではなく、血行不良、色素沈着、皮膚のたるみといった複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
そのため、セルフケアだけではなかなか改善が見込めず、悩みが深刻化することも少なくありません。
この記事では、なぜあなたのクマがひどくなってしまったのか、その複合的な原因を詳しく解説します。
さらに、セルフケアの限界と、根本的な改善を目指すための最終手段としての美容医療について、具体的な治療法やクリニック選びのポイントまで、あなたの長年の悩みに寄り添いながら丁寧に情報をお届けします。
もうクマで悩まない毎日を目指しましょう。
「ひどい目の下のクマ」その正体と種類
目の下のクマがひどいと感じる状態は、単に寝不足や疲れが原因というだけでは説明がつかないことが多いです。その正体は、皮膚の下で起きている様々な変化が、見た目として現れたものです。
クマが目立つと、顔全体が暗く、老けた印象を与えてしまいます。まずは、ひどいクマの正体と、その種類について正しく理解することが、改善への第一歩です。
なぜクマはひどく見えるのか
目の下の皮膚は、顔の他の部分に比べて非常に薄く、約0.6mmほどしかありません。これは卵の薄皮程度の厚さで、皮脂腺も少ないため、とてもデリケートな部位です。
この薄さゆえに、皮膚の下にある血管の色や、筋肉(眼輪筋)の色が透けて見えやすいのです。
また、加齢や紫外線の影響で皮膚のハリや弾力が失われると、たるみやへこみが生じ、その部分が影となって黒く見えることもあります。
このように、皮膚の薄さという構造的な特徴と、後天的な要因が組み合わさることで、クマは「ひどい」と感じるほど目立ってしまうのです。
クマの主な3つの種類
目の下のクマは、その原因によって大きく3つの種類に分けられます。
複数の種類が混在していることも珍しくありませんが、自分のクマがどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切な対策を考える上で非常に重要です。
クマの種類と主な特徴
| クマの種類 | 見た目の色 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 青クマ | 青黒い・紫がかった色 | 血行不良・睡眠不足・冷え |
| 茶クマ | 茶色い・くすんだ色 | 色素沈着・摩擦・紫外線 |
| 黒クマ | 黒い・影に見える | たるみ・くぼみ・骨格 |
複数の原因が絡み合う「混合型」のクマ
ひどい目の下のクマに悩む人の多くは、一つの原因だけでなく、青クマ、茶クマ、黒クマの要因が複数絡み合った「混合型」であることが多いです。
例えば、加齢によって目の下にたるみ(黒クマ)が生じ、長年のメイクやクレンジングによる摩擦で色素沈着(茶クマ)も併発しているケースです。
また、生まれつき皮膚が薄く血管が透けやすい(青クマ)人が、年齢ととも目の下の脂肪が減ってくぼみ(黒クマ)が目立つようになることもあります。
このように原因が複合的であるため、単一のセルフケアでは効果を実感しにくく、改善が難しいのです。
自分のクマの種類をセルフチェックする方法
鏡を使って簡単なセルフチェックをすることで、自分のクマがどの種類に当てはまるか、ある程度推測できます。正しいケアや治療法を選択するために、まずは自分のクマの状態を観察してみましょう。
- 鏡を正面に持ち、あっかんべーをするように下まぶたを軽く下に引く
- 鏡を顔の正面に持ち、顔は動かさずに目線だけを上に向ける
- スマートフォンなどで目の下の写真を撮り、色や影の状態を客観的に見る
下まぶたを引っぱったときにクマの色が薄くなる、または動かない場合は、皮膚そのものに色がついている「茶クマ」の可能性が高いです。
一方で、皮膚を引っぱっても色が変わらない場合は、血管が透けている「青クマ」が考えられます。
また、顔を上に向けて鏡を見たときに、クマの影が薄くなる、または消える場合は、たるみやへこみが原因の「黒クマ」である可能性が高いでしょう。
これらのチェックで複数の特徴に当てはまる場合は、混合型のクマと考えられます。
なぜあなたのクマはひどいのか?複合的な原因を深掘り
「しっかり寝ているはずなのに、クマが消えない」「高級なアイクリームを使っても効果がない」。
そう感じるひどいクマは、生活習慣だけの問題ではなく、生まれ持った体質や加齢による変化など、様々な原因が複雑に絡み合っています。
ここでは、あなたのクマをひどくしている根本的な原因をさらに深く掘り下げていきます。
遺伝的要因と骨格の影響
実は、目の下のクマの目立ちやすさには、遺伝的な要因も大きく関係しています。親や兄弟にクマが目立つ人がいる場合、自分もクマができやすい体質を受け継いでいる可能性があります。
例えば、もともと皮膚が薄く、血管や筋肉の色が透けて見えやすい人は、若い頃から青クマに悩まされることがあります。
また、頬の骨格が低い、あるいは眼窩(がんか)と呼ばれる眼球が収まるくぼみが大きい骨格の場合、目の下に影ができやすく、黒クマとして現れやすい傾向があります。
遺伝的要因の例
| 要因 | クマへの影響 | 関連するクマの種類 |
|---|---|---|
| 皮膚の薄さ | 血管や筋肉が透けやすい | 青クマ |
| 骨格(頬骨、眼窩) | 目の下に影ができやすい | 黒クマ |
| アレルギー体質 | 目をこする行為で色素沈着 | 茶クマ |
加齢による皮膚構造の変化
年齢を重ねると、私たちの肌には様々な変化が現れます。特に皮膚の薄い目の下は、その影響を受けやすい部位です。加齢は、ひどい目の下のクマ、特に黒クマの最大の原因とも言えます。
肌のハリや弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄く、弱くなります。
さらに、目の周りの筋肉(眼輪筋)も衰え、目の下の脂肪(眼窩脂肪)を支えきれなくなり、前に押し出されてふくらみ(目袋)ができます。
このふくらみと、その下のくぼみが段差となり、影ができて黒クマがひどく見えるのです。
生活習慣がクマを悪化させる
遺伝や加齢といった避けられない要因に加えて、日々の生活習慣がクマをさらに悪化させているケースも少なくありません。
特に、現代人ならではの生活スタイルが、目の下の血行不良や色素沈着を助長しています。心当たりのある習慣がないか、一度見直してみることが大切です。
クマを悪化させる主な生活習慣
| 習慣 | 主な影響 | 悪化しやすいクマ |
|---|---|---|
| 長時間のPC・スマホ作業 | 眼精疲労、血行不良 | 青クマ |
| 睡眠不足、不規則な生活 | 血行不良、ターンオーバーの乱れ | 青クマ、茶クマ |
| 喫煙、過度な飲酒 | 血行不良、肌の乾燥 | 青クマ、黒クマ |
間違ったスキンケアが色素沈着を招く
良かれと思って行っているスキンケアが、実はクマの原因になっていることもあります。特に茶クマは、物理的な刺激によるメラニン色素の沈着が主な原因です。
ゴシゴシと力を入れたクレンジングや洗顔、アイメイクを落とす際の摩擦は、デリケートな目の下の皮膚に大きな負担をかけます。
また、保湿が不十分で肌が乾燥していると、バリア機能が低下し、わずかな刺激でも色素沈着を起こしやすくなります。
紫外線対策の不足も、メラニンの生成を促し、茶クマを濃くする原因となるため注意が必要です。
セルフケアで改善できるクマと限界
ひどい目の下のクマを改善するために、まずは自分でできることから始めたいと考えるのは自然なことです。実際に、クマの種類によってはセルフケアで目立たなくすることも可能です。
しかし、原因によってはセルフケアだけではどうしても太刀打ちできない場合もあります。ここでは、セルフケアで対応できる範囲とその限界について解説します。
血行不良(青クマ)へのアプローチ
青クマの主な原因は血行不良です。そのため、目元の血流を良くすることが改善の鍵となります。
ホットタオルや蒸気で温まるアイマスクを使って目元を温める、優しい力でマッサージを行う、十分な睡眠をとる、湯船に浸かって全身を温める、といったケアが有効です。
また、鉄分やビタミンKなど、血行を促進する栄養素を意識的に摂取することも、内側からのケアとして大切です。
これらのケアは継続することで効果が期待できますが、一時的な対策であり、根本的な解決には至らないことも多いです。
色素沈着(茶クマ)へのアプローチ
茶クマはメラニン色素の沈着が原因なので、美白効果のある成分を含んだスキンケア製品の使用が基本となります。
ビタミンC誘導体やアルブチン、トラネキサム酸などが配合されたアイクリームや美容液を選びましょう。
同時に、これ以上色素沈着を増やさないための対策も重要です。目をこすらない、クレンジングは優しく行う、そして紫外線対策を徹底することが必要不可欠です。
ただし、一度沈着してしまったメラニンをセルフケアだけで完全に消し去ることは難しく、効果を実感するまでには長い時間がかかります。
クマの種類別セルフケアの有効度
| クマの種類 | 主なセルフケア | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 青クマ | 温める、マッサージ、生活習慣改善 | 一時的な改善が見込める |
| 茶クマ | 美白化粧品、紫外線対策、摩擦を避ける | 根気強い継続で多少薄くなる可能性 |
| 黒クマ | 保湿、エイジングケア化粧品 | 進行を緩やかにする程度 |
構造的な問題(黒クマ)にはセルフケアは無力?
黒クマの原因は、目の下のたるみやへこみといった皮膚の構造的な問題です。残念ながら、この構造そのものを化粧品やマッサージといったセルフケアで変えることはできません。
エイジングケア用の化粧品で肌にハリを与え、進行を緩やかにすることはできるかもしれませんが、できてしまったふくらみやへこみをなくすことは困難です。
黒クマや、複数の原因が絡み合った重度の混合型クマを根本的に改善するには、セルフケアの領域を超えたアプローチ、つまり美容医療を検討する必要があります。
最終手段としての美容医療|ひどいクマへの根本的アプローチ
様々なセルフケアを試しても改善しない、ひどい目の下のクマ。その悩みを根本から解決するためには、美容医療が有効な選択肢となります。
美容医療は、クマの原因となっている皮膚の構造的な問題や、根深い色素沈着に直接アプローチできるのが最大の強みです。
ここでは、なぜ美容医療がひどいクマに有効なのか、そして治療を検討する上で大切なポイントを解説します。
美容医療がひどいクマに有効な理由
美容医療では、医師が専門的な知識と技術を用いて、クマの原因に直接働きかけます。
例えば、黒クマの原因である目の下の余分な脂肪を取り除いたり、へこんだ部分にヒアルロン酸などを注入して平らにしたりします。
茶クマに対しては、医療用のレーザーで色素沈着を破壊したり、ターンオーバーを促進する薬剤を使用したりします。
このように、セルフケアでは届かない皮膚の深層部にアプローチし、構造的な問題や細胞レベルでの問題を解決できるため、高い改善効果が期待できるのです。
カウンセリングの重要性
美容医療を受ける上で、最も重要なのが医師によるカウンセリングです。
カウンセリングでは、自分のクマの種類や原因を正確に診断してもらい、どのような治療法が適しているのか、その治療法のメリット・デメリット、リスク、費用などについて詳しい説明を受けます。
自分の希望や不安をしっかりと医師に伝え、納得できるまで話し合うことが、後悔しない治療につながります。この段階で、医師との信頼関係を築けるかどうかも大切な判断基準になります。
- 自分のクマの原因と状態
- 提案された治療法の詳細な内容
- 期待できる効果と持続期間
- 考えられるリスクや副作用
- ダウンタイムの期間と症状
- 必要な費用総額と内訳
信頼できるクリニック選びのポイント
目の下のクマ治療は、非常に繊細な技術を要するため、クリニック選びは慎重に行う必要があります。
ウェブサイトの情報だけでなく、実際にカウンセリングに足を運び、自分の目で確かめることが大切です。安さだけで選ぶのではなく、安全性や信頼性を重視しましょう。
クリニック選びのチェックポイント
| チェック項目 | 確認するポイント | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 医師の実績・専門性 | 症例数は豊富か、専門医資格はあるか | 繊細な部位のため高い技術力が必要 |
| カウンセリングの丁寧さ | 時間をかけて丁寧に説明してくれるか | 患者の不安や疑問に寄り添う姿勢 |
| リスクやデメリットの説明 | 良いことだけでなくリスクも説明するか | 誠実で信頼できるかどうかの指標 |
【種類別】重度のクマに用いられる代表的な美容医療
ひどい目の下のクマに対する美容医療には、様々な選択肢があります。どの治療法が最適かは、クマの種類、症状の程度、そして個人のライフスタイルなどによって異なります。
ここでは、クマの種類別に、代表的な治療法を紹介します。カウンセリングを受ける前の予備知識として参考にしてください。
影クマ(黒クマ)に対する治療法
黒クマは、目の下の脂肪によるふくらみや、その下のくぼみが原因です。治療の目的は、この段差をなくし、目の下を平滑にすることです。
原因に応じて、脂肪を取り除く、脂肪を移動させる、あるいは足りない部分を補うといったアプローチがあります。
黒クマの主な治療法
| 治療法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 脱脂術(経結膜脱脂法) | まぶたの裏側から余分な脂肪を取り除く | 皮膚表面に傷が残らない |
| 脂肪注入 | 自身の脂肪を採取し、くぼみに注入する | 定着すれば効果は長期間持続 |
| ヒアルロン酸注入 | くぼんだ部分にヒアルロン酸を注入する | 施術時間が短く、ダウンタイムが少ない |
色素沈着(茶クマ)に対する治療法
茶クマの原因であるメラニン色素に直接アプローチする治療が中心となります。医療用のレーザーや光治療で色素を破壊したり、薬剤を使って肌の再生を促したりします。
セルフケアよりも効果的に色素沈着を薄くすることが可能です。
血行不良(青クマ)に対する治療法
青クマの根本的な原因は血行不良ですが、皮膚が薄くて血管が透けていることが問題を深刻にしています。
そのため、皮膚のすぐ下にボリュームを持たせて血管が透けにくくする治療や、血行を促進する治療が行われます。多くの場合、他のクマと併発しているため、複合的な治療が選択されます。
混合型のクマに対する複合治療
ひどいクマの多くは、黒クマ・茶クマ・青クマの要因が混在した混合型です。
そのため、最良の結果を得るためには、単一の治療ではなく、複数の治療法を組み合わせる「複合治療」が必要になることがよくあります。
例えば、脱脂術で黒クマの原因であるふくらみを取り除いた後、脂肪注入やヒアルロン酸注入でくぼみを埋め、さらにレーザー治療で茶クマの色素沈着を改善するといった方法です。
医師が症状を正確に見極め、一人ひとりに合った治療計画を立てることが、満足のいく結果につながります。
美容医療を受ける前に知っておきたい注意点とダウンタイム
目の下のクマ治療は効果的な一方で、医療行為である以上、リスクやダウンタイムが伴います。治療を決断する前に、これらの注意点を十分に理解し、心づもりをしておくことが大切です。
安心して治療を受け、スムーズな回復期間を過ごすために、事前に知っておくべき情報をまとめました。
治療に伴うリスクや副作用
どのような治療にも、リスクや副作用の可能性はゼロではありません。目の下の治療で起こりうる一般的なものとして、腫れ、内出血、痛み、左右差、感染症などが挙げられます。
ほとんどは一時的なもので、時間の経過とともに軽快しますが、まれに長引くこともあります。
カウンセリングの際に、自分が受ける治療で起こりうるすべてのリスクについて、医師から詳しく説明を受け、理解しておくことが重要です。
ダウンタイムの期間と過ごし方
ダウンタイムとは、施術を受けてから、腫れや内出血などが落ち着き、通常の生活に戻れるまでの回復期間のことです。期間や症状の程度は、治療法や個人の体質によって大きく異なります。
注入治療のように数日で落ち着くものから、手術を伴う治療のように1~2週間ほどかかるものまで様々です。この期間中は、飲酒や激しい運動、長時間の入浴など、血行が良くなる行為は避けるように指示されることが一般的です。
仕事やプライベートの予定も考慮して、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
主な治療法とダウンタイムの目安
| 治療法 | 主な症状 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 軽い腫れ、内出血、針穴 | 数日〜1週間程度 |
| レーザー治療 | 赤み、かさぶた(機種による) | 数日〜1週間程度 |
| 脱脂術 | 強い腫れ、内出血 | 1〜2週間程度 |
治療後のアフターケア
治療効果を最大限に引き出し、長持ちさせるためには、治療後のアフターケアが重要です。クリニックからの指示をしっかりと守り、処方された薬があれば正しく使用しましょう。
また、治療後は肌がデリケートな状態になっているため、保湿や紫外線対策を普段以上に徹底することが大切です。目をこすったり、強いマッサージをしたりするのも避けましょう。
生活習慣を見直し、クマができにくい環境を維持することも、再発防止につながります。
よくある質問
- 目の下のクマ治療は痛いですか?
-
治療法によって痛みの程度は異なります。
ヒアルロン酸注入などの注射による治療では、チクッとした痛みを感じることがありますが、多くのクリニックでは麻酔クリームや極細の針を使用することで、痛みを最小限に抑える工夫をしています。
脱脂術などの外科的な手術の場合は、局所麻酔や静脈麻酔を使用するため、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。
術後に痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めでコントロールできる場合が多いです。
- 治療の効果はどのくらい持続しますか?
-
効果の持続期間も治療法によって大きく異なります。ヒアルロン酸注入は、製剤の種類にもよりますが、一般的に半年から1年半ほどで徐々に体内に吸収されていきます。
そのため、効果を維持するには定期的な再注入が必要です。一方、脱脂術で取り除いた脂肪は再生しないため、効果は半永久的とされています。
ただし、加齢によって再び皮膚がたるむなど、別の原因でクマが現れる可能性はあります。
- 治療に失敗することはありませんか?
-
医療である以上、失敗のリスクはゼロではありません。
目の下の治療における「失敗」とは、例えば脂肪を取りすぎて目の下がへこんでしまった、注入したヒアルロン酸が凸凹になった、左右差が目立つ、といった結果を指します。
このようなリスクを避けるためには、目の下の構造を熟知し、高い技術力と豊富な経験を持つ医師を選ぶことが何よりも重要です。
信頼できるクリニックで、事前のカウンセリングを十分に行うことが、満足のいく結果につながります。
- 治療後すぐにメイクはできますか?
-
これも治療法によります。ヒアルロン酸注入の場合、針を刺した部分を避ければ、当日からメイクが可能なことが多いです。
レーザー治療の場合は、肌の状態が落ち着くまで数日間メイクを控えるように指示されることがあります。
脱脂術などの手術後は、腫れや内出血があるため、1週間程度はアイメイクを控えるのが一般的です。詳しいタイミングについては、必ず担当医の指示に従ってください。
参考文献
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
POUR MOHAMMAD, Arash, et al. The First Systematic Review and Meta‐Analysis of Pharmacological and Nonpharmacological Procedural Treatments of Dark Eye Circles (Periorbital Hyperpigmentations): One of the Most Common Cosmetic Concerns. Dermatologic Therapy, 2025, 2025.1: 9155535.
PARK, Kui Young, et al. Treatments of infra-orbital dark circles by various etiologies. Annals of dermatology, 2018, 30.5: 522-528.
MAC-MARY, Sophie, et al. Identification of three key factors contributing to the aetiology of dark circles by clinical and instrumental assessments of the infraorbital region. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2019, 919-929.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
IMAM, Mustafa Hussain, et al. Infra-orbital Hyper-pigmentation (Dark Circles): A Study of its Prevalence, Etiology and its Association with Other Dermatological Symptoms among Young Adults. 2025.
FRIEDMANN, Daniel P.; GOLDMAN, Mitchel P. Dark circles: etiology and management options. Clinics in plastic surgery, 2015, 42.1: 33-50.
SARKAR, Rashmi, et al. Periorbital hyperpigmentation: a comprehensive review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 49.
PISSARIDOU, Maria Katerina; GHANEM, Ali; LOWE, Nicholas. Periorbital Discolouration diagnosis and treatment: evidence-based review. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2020, 22.6-8: 217-225.
RAJABI‐ESTARABADI, Ali, et al. Effectiveness and tolerance of multicorrective topical treatment for infraorbital dark circles and puffiness. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.2: 486-495.