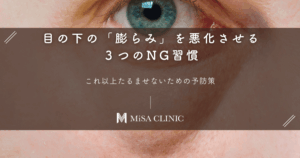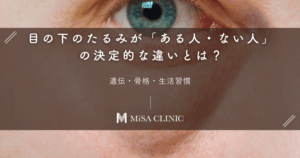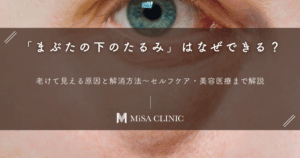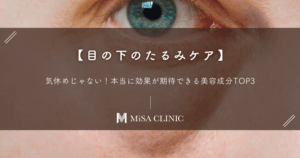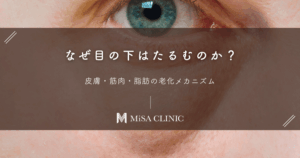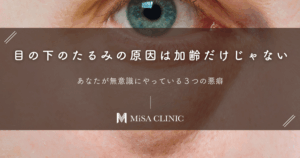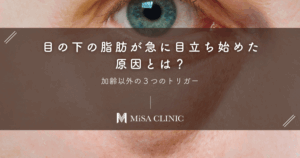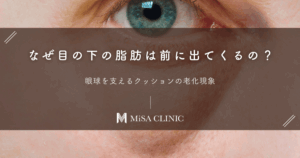鏡を見るたびに気になる、目の下のたるみ。「疲れているように見える」「老けて見られる」といった悩みを抱え、様々な改善方法を試してきた方も多いのではないでしょうか。
しかし、良かれと思って続けているその習慣が、実はたるみを悪化させる原因になっているかもしれません。
本気で目の下のたるみを改善したいと願うなら、まず見直すべきは日々の「悪習慣」です。
この記事では、たるみの根本原因に触れながら、今すぐやめるべき3つの具体的な悪習慣と、その改善方法について詳しく解説します。あなたの長年の悩みに、新たな光を当てるきっかけとなるはずです。
目の下のたるみ、その正体と主な原因
目の下のたるみ改善を目指す第一歩は、敵を知ることから始まります。なぜ、目の下はたるみやすいのでしょうか。
その構造的な特徴と、たるみを引き起こす主な原因を理解することが、適切な対策への近道です。
加齢による構造的な変化
年齢を重ねると、私たちの体には様々な変化が現れます。特に目元は、その影響を受けやすい部分です。皮膚の弾力を支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、肌のハリが失われていきます。
また、目の周りにある「眼輪筋(がんりんきん)」という筋肉も衰え、皮膚やその下にある脂肪を支える力が弱まります。これらの複合的な要因が、たるみとなって現れるのです。
眼窩脂肪の突出
目の下のたるみの直接的な原因として最も大きいのが「眼窩脂肪(がんかしぼう)」の存在です。眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションの役割を果たしています。
この脂肪は、先述した眼輪筋や、ロックウッド靭帯という組織によって支えられていますが、加齢などによりこれらの支持組織が緩むと、眼窩脂肪が前方に押し出されてきます。
これが、目の下のふくらみ、いわゆる「目袋」の正体です。
眼窩脂肪とクマの関係
| クマの種類 | 原因 | たるみとの関連 |
|---|---|---|
| 黒クマ | たるみによる影 | たるみ(眼窩脂肪の突出)が直接の原因。影となって黒く見える。 |
| 赤クマ | 眼輪筋の透け | 突出した脂肪に圧迫され、下の筋肉が透けて赤く見えることがある。 |
| 茶クマ | 色素沈着 | 物理的な刺激や紫外線によるメラニンが原因。たるみとは別の要因。 |
皮膚の弾力低下
目元の皮膚は非常にデリケートで、他の部位の皮膚と比較して著しく薄いという特徴があります。皮脂腺も少なく乾燥しやすいため、外部からの刺激や紫外線の影響をダイレクトに受けてしまいます。
こうしたダメージが蓄積すると、皮膚自体のハリが失われ、薄い布が伸びてしまうようにたるんでしまいます。眼窩脂肪の突出がなくても、皮膚がたるむだけで疲れた印象を与えることがあります。
骨格や遺伝的要因
生まれつきの骨格も、目の下のたるみの見え方に影響します。
例えば、頬骨の位置が低い、あるいは後退している場合、目の下の脂肪を支える土台が不足するため、若いうちからたるみが目立ちやすくなる傾向があります。
また、皮膚の質や筋肉のつき方など、遺伝的な要素が関与することも少なくありません。家族に同じような悩みを抱えている方がいる場合は、体質的にたるみやすい可能性があります。
【悪習慣①】目元への無意識な物理的刺激
日常の何気ない行動が、デリケートな目元の皮膚にダメージを与え、たるみを加速させている可能性があります。特に、無意識に行っている癖や習慣には注意が必要です。
ここでは、今すぐやめるべき物理的な刺激について具体的に見ていきましょう。
目をこする癖
花粉症やアレルギー、目の疲れなどから、つい目をゴシゴシとこすってしまうことはありませんか。この「こする」という行為は、目の下のたるみ改善において最も避けるべき行動の一つです。
薄い皮膚を摩擦することで、コラーゲン線維が傷ついたり、炎症を引き起こしたりします。これが色素沈着(茶クマ)の原因になるだけでなく、皮膚を支える組織を弱め、たるみを助長してしまうのです。
強すぎるクレンジングやマッサージ
アイメイクを落とす際に、力を入れてこすっていませんか。また、たるみ改善を期待して、自己流の強いマッサージを行っていませんか。
良かれと思って行っているスキンケアが、逆効果になっているケースは非常に多いです。アイメイクは専用のリムーバーを使い、優しくなじませて浮かせるように落とすことが重要です。
マッサージも、強い圧は避け、滑りの良いクリームなどを使って、あくまで優しく行う必要があります。
スキンケア時の注意点
| NG行動 | 推奨される行動 | 理由 |
|---|---|---|
| ゴシゴシ洗い | 優しくなじませる | 摩擦による皮膚へのダメージを避けるため。 |
| 熱いお湯での洗顔 | ぬるま湯(32℃前後) | 必要な皮脂まで奪い、乾燥を招くのを防ぐため。 |
| タオルで強く拭く | 優しく押さえるように拭く | 拭く際の摩擦も、たるみの原因になりうるため。 |
うつぶせ寝の習慣
睡眠中の姿勢も、目の下のたるみに影響を与えます。特にうつぶせ寝は、長時間にわたって顔の片側に圧力がかかり、目元にシワやたるみを作り出す原因となります。
また、リンパの流れが滞り、むくみにもつながります。目の下のたるみ改善のためには、できるだけ仰向けで寝ることを心がけ、枕の高さなども自分に合ったものを選ぶことが大切です。
【悪習慣②】たるみを加速させる生活習慣
体の内側からのケアも、目の下のたるみ改善には欠かせません。日々の生活習慣が乱れると、血行不良や栄養不足を招き、肌の健康状態を悪化させます。
あなたの生活に潜む、たるみの原因を見直してみましょう。
睡眠不足と質の低下
睡眠は、肌のターンオーバーを促し、日中に受けたダメージを修復するための重要な時間です。睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、肌細胞の再生が滞ります。
これにより、肌のハリが失われるだけでなく、血行不良によるクマも目立ちやすくなり、たるんだ印象をさらに強めてしまいます。
栄養バランスの偏り
肌は、私たちが食べたものから作られています。偏った食生活は、肌の健康を損なう直接的な原因です。
特に、インスタント食品やジャンクフードに偏った食事は、糖質や脂質過多になりがちで、肌の「糖化」や「酸化」を促進します。糖化は肌の弾力を失わせ、酸化は細胞を傷つけ老化を早めます。
目の下のたるみ改善には、バランスの取れた食事が基本です。
肌のハリをサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や筋肉の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンA | 皮膚の健康を維持する | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
喫煙と過度な飲酒
喫煙は、目の下のたるみ改善を目指す上で大きな障害となります。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血行を悪化させます。
また、大量の活性酸素を発生させ、肌のハリを保つビタミンCを破壊してしまいます。過度な飲酒も、利尿作用による脱水で肌の乾燥を招いたり、睡眠の質を低下させたりするため、たるみの原因となり得ます。
【悪習慣③】良かれと思って行うまちがったスキンケア
毎日行うスキンケアは、目の下のたるみ改善の味方にも敵にもなります。正しい知識で行わないと、肌の状態をかえって悪化させてしまう危険性があります。
ここでは、陥りがちなスキンケアの落とし穴について解説します。
保湿不足による乾燥
目元の皮膚は皮脂腺が少なく、非常に乾燥しやすい部位です。肌が乾燥すると、角質層のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
また、乾燥による小じわ(ちりめんじわ)が目立つようになり、これが将来的な深いたるみへとつながることもあります。
化粧水だけでなく、セラミドやヒアルロン酸などが配合された保湿効果の高い美容液やクリームを使い、しっかりと水分を閉じ込めることが重要です。
- 皮膚が薄い
- 皮脂腺が少ない
- まばたきなどで動きが多い
紫外線対策の怠り
紫外線は、肌の老化を招く最大の外的要因であり、「光老化」と呼ばれます。紫外線の中でも特にUVA(紫外線A波)は、肌の奥深く(真皮)まで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊してしまいます。
これにより肌の弾力が失われ、たるみやシワの原因となります。紫外線対策は夏だけでなく一年中必要です。室内でも窓から紫外線は入ってくるため、日頃から日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。
紫外線の種類と肌への影響
| 種類 | 特徴 | 肌への影響 |
|---|---|---|
| UVA(紫外線A波) | 雲や窓ガラスを通過し、肌の奥深くに届く | たるみ、シワの原因(光老化) |
| UVB(紫外線B波) | 主に肌の表面に作用し、エネルギーが強い | 日焼け(炎症)、シミの原因 |
アイケア製品の誤った使い方
目の下のたるみ改善を目的としたアイクリームは数多く販売されています。しかし、使い方を間違えると十分な効果を得られません。
例えば、使用量が少なすぎると塗布する際の摩擦が大きくなり、逆効果です。逆に多すぎても肌に浸透しきれず、べたつきの原因になります。
製品に記載されている使用量を守り、薬指の腹を使って、目頭から目尻に向かって優しくなじませるのが基本です。
セルフケアだけで目の下のたるみ改善が難しい理由
ここまで紹介した悪習慣を改善することは、たるみの予防や進行を遅らせる上で非常に重要です。
しかし、すでに目立ってしまったたるみを、セルフケアだけで完全に元に戻すのは、残念ながら非常に難しいのが現実です。その理由を理解しておきましょう。
たるみの根本原因にアプローチできない
セルフケアの主な目的は、皮膚の表面的なコンディションを整えることです。保湿によって乾燥小じわを目立たなくしたり、マッサージで一時的にむくみを解消したりすることは可能です。
しかし、たるみの根本原因である「眼窩脂肪の突出」や「支持組織の緩み」に対して、化粧品やマッサージで直接アプローチすることはできません。
セルフケアと美容医療の比較
| アプローチ | セルフケア(化粧品・マッサージ) | 美容医療 |
|---|---|---|
| 対象 | 皮膚の表面(角質層) | 皮膚の深層、筋肉、脂肪組織 |
| 期待できること | 保湿、血行促進、予防 | 脂肪の除去、皮膚の引き締め、構造の改善 |
| 即時性 | 穏やか | 比較的高い |
一度伸びた皮膚は元に戻らない
長年にわたる脂肪の突出や弾力の低下によって一度伸びてしまった皮膚は、風船がしぼんだ後のように、元通りのハリを取り戻すことは困難です。
セルフケアでコラーゲンの生成を促すことはできますが、それはあくまで肌質の改善や予防の範囲内であり、伸びた皮膚を縮めるほどの効果は期待できません。
美容クリニックで相談できる目の下のたるみ改善法
セルフケアの限界を知り、より積極的な目の下のたるみ改善方法を求めるなら、美容クリニックでの専門的な治療が選択肢となります。ここでは、代表的な治療法をいくつか紹介します。
専門の医師と相談し、自分に合った方法を見つけることが大切です。
切らない治療法
「経結膜脱脂法(けいけつまくだっしほう)」は、まぶたの裏側(結膜)を小さく切開し、そこから原因となっている余分な眼窩脂肪を取り除く治療法です。
皮膚の表面に傷が残らないため、ダウンタイムが比較的短く、人気の高い治療法です。皮膚のたるみが少ない、比較的若い世代の方に適しています。
皮膚のたるみも改善する治療法
脂肪の突出と同時に皮膚のたるみも強い場合には、下まつげの生え際に沿って皮膚を切開し、余分な脂肪と皮膚を取り除く治療法があります。
「ハムラ法」や「裏ハムラ法」は、突出した脂肪を凹んでいる部分に移動させて固定することで、目の下の凹凸を平らにならす、より高度な技術を要する治療法です。
代表的な外科的治療法の概要
| 治療法 | アプローチ方法 | 主な適応 |
|---|---|---|
| 経結膜脱脂法 | まぶたの裏から脂肪を除去 | ふくらみが主で、皮膚のたるみが少ない方 |
| 皮膚切開法 | 目の下を切開し脂肪と皮膚を除去 | ふくらみと皮膚のたるみが強い方 |
| ハムラ法(裏ハムラ法) | 脂肪を凹みへ移動・再配置 | ふくらみと凹みが混在している方 |
その他の治療選択肢
外科的な治療に抵抗がある場合や、軽度のたるみには、他の選択肢もあります。
ヒアルロン酸をたるみの下の凹んでいる部分(ゴルゴラインなど)に注入し、段差を目立たなくする方法や、高周波(RF)や超音波(HIFU)などを用いて皮膚の深層に熱エネルギーを与え、コラーゲンの生成を促して肌を引き締めるレーザー治療などがあります。
ただし、これらは根本的な改善というよりは、症状を緩和・改善する方法です。
目の下のたるみ改善に関するよくある質問
最後に、目の下のたるみ改善や治療に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
- 悪習慣をやめれば、たるみは自然に治りますか?
-
悪習慣をやめることは、たるみの進行を防ぎ、現状の悪化を食い止めるために非常に重要です。
しかし、すでに突出してしまった眼窩脂肪や伸びてしまった皮膚が、生活習慣の改善だけで完全に元に戻ることは難しいと考えられます。
予防と進行抑制には効果的ですが、根本的な改善には美容医療の検討が必要です。
- 治療後にたるみが再発することはありますか?
-
経結膜脱脂法などで一度取り除いた脂肪が、もとと同じ量まで再生することは基本的にありません。そのため、再発のリスクは低いと言えます。
しかし、加齢による変化は誰にでも起こるため、長い年月が経過すれば、残っている脂肪が前に出てきたり、皮膚のたるみが再び現れたりする可能性はあります。
- ダウンタイムはどのくらい必要ですか?
-
ダウンタイムの長さは、治療法によって大きく異なります。経結膜脱脂法のような切らない治療では、大きな腫れや内出血は数日から1週間程度で落ち着くことが多いです。
皮膚を切開する治療法では、抜糸までに1週間程度、腫れや内出血が完全に引くまでには数週間から1ヶ月以上かかる場合もあります。
仕事や生活スタイルに合わせて、医師とよく相談することが大切です。
- 経結膜脱脂法:約1週間
- 皮膚切開法:約2週間〜1ヶ月
- どの年代の人が多く治療を受けていますか?
-
目の下のたるみは、20代後半から気になり始め、30代、40代、50代と年齢が上がるにつれて悩みを持つ方が増えていきます。
治療を受ける方の年齢層も幅広く、原因や症状によって適した治療法が異なるため、年齢だけで判断するのではなく、まずは専門のクリニックでカウンセリングを受け、ご自身の状態を正確に診断してもらうことが改善への第一歩です。
参考文献
PARK, Kui Young, et al. Treatments of infra-orbital dark circles by various etiologies. Annals of dermatology, 2018, 30.5: 522-528.
IMAM, Mustafa Hussain, et al. Infra-orbital Hyper-pigmentation (Dark Circles): A Study of its Prevalence, Etiology and its Association with Other Dermatological Symptoms among Young Adults. 2025.
MATSUI, Mary S., et al. Physiological and lifestyle factors contributing to risk and severity of peri-orbital dark circles in the Brazilian population. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90.4: 494-503.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
RATHORE, Gyanesh, et al. Clinical assessment, diagnosis, and Management of Infraorbital Wrinkles and Pigmentation. Dermatologic Clinics, 2024, 42.1: 79-88.
VERNER, Ines; GALADARI, Hassan I. Management of Infraorbital Wrinkles and Pigmentation. Hot Topics in Cosmetic Dermatology, An Issue of Dermatologic Clinics, E-Book: Hot Topics in Cosmetic Dermatology, An Issue of Dermatologic Clinics, E-Book, 2023, 42.1: 79-88.
KOŁODZIEJCZAK, Anna; ROTSZTEJN, Helena. The eye area as the most difficult area of activity for esthetic treatment. Journal of Dermatological Treatment, 2022, 33.3: 1257-1264.
SARKAR, Rashmi. Idiopathic cutaneous hyperchromia at the orbital region or periorbital hyperpigmentation. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2012, 5.3: 183-184.
AWAL, Guneet, et al. Illuminating the shadows: an insight into periorbital hyperpigmentation. Pigment International, 2024, 11.2: 67-78.