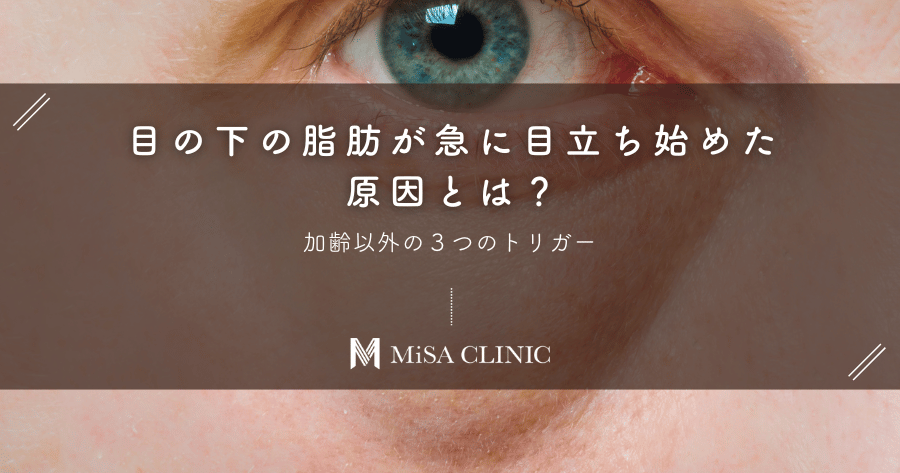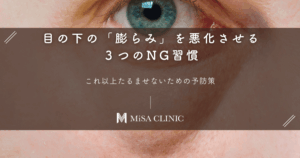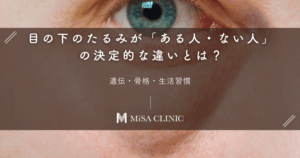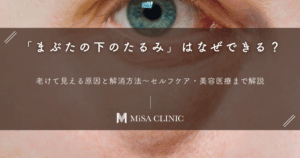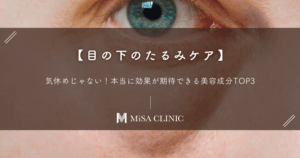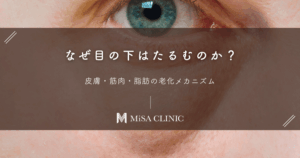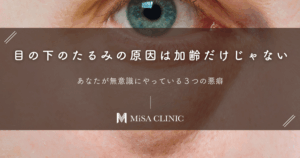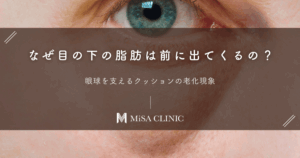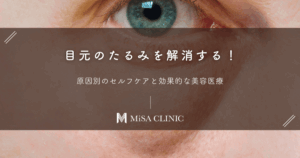「最近、なんだか急に目の下のふくらみが目立ってきた」「疲れているように見られることが増えた」と感じていませんか。
鏡を見るたびに気になる目の下の脂肪は、多くの方が「年齢のせい」と考えがちです。しかし、実はその原因は加齢だけではありません。
私たちの日常生活に潜む何気ない習慣が、知らず知らずのうちに目の下の脂肪を目立たせる引き金になっていることがあります。
この記事では、加齢という大きな要因に加えて、見過ごされがちな3つのトリガーに焦点を当て、その原因と対策を詳しく解説します。
ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、目の下の悩みを解消するヒントを見つけていきましょう。
そもそも目の下の脂肪とは?その正体と目立つ仕組み
目の下のふくらみが気になると、多くの人は「クマ」や「たるみ」と考えます。しかし、その根本には「脂肪」の存在があります。なぜ、本来は奥にあるはずの脂肪が目立ってくるのでしょうか。
ここでは、その正体と表面に現れてくる基本的な仕組みを解説します。
目の下のふくらみの正体は「眼窩脂肪」
目の下のぽっこりとしたふくらみの正体は、「眼窩脂肪(がんかしぼう)」と呼ばれる脂肪です。眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションのような役割を果たしています。
眼球の周りを覆うように存在しており、誰にでもある大切な組織です。本来は目の周りの骨(眼窩)の中に収まっていますが、何らかの原因で前方に押し出されてくると、皮膚の表面にふくらみとして現れます。
眼窩脂肪を支える組織のゆるみ
眼窩脂肪は、ロックウッド靭帯というハンモック状の組織と、眼輪筋(がんりんきん)という目の周りを囲む筋肉によって支えられています。
これらの支持組織がピンと張っている状態であれば、眼窩脂肪は適切な位置に保持されます。しかし、これらの組織がゆるんだり、衰えたりすると、重力に負けて眼窩脂肪が前方に突出しやすくなります。
これが、目の下のふくらみとなって現れるのです。
目の下の構造とふくらみの関係
| 構成要素 | 役割 | ふくらみへの影響 |
|---|---|---|
| 眼窩脂肪 | 眼球を保護するクッション | 前方に突出することでふくらみそのものになる |
| 眼輪筋 | 目を閉じたり開いたりする筋肉 | 衰えることで脂肪を支えきれなくなる |
| ロックウッド靭帯 | 眼球や脂肪を支える靭帯 | ゆるむことで脂肪が下がり、前方に押し出される |
皮膚のハリ低下がふくらみを強調する
目の下の皮膚は非常に薄く、デリケートな部位です。そのため、肌全体のハリや弾力が失われると、内側からの圧力を受けやすくなります。
肌のハリが低下すると、押し出されてきた眼窩脂肪の形がよりくっきりと表面に現れ、ふくらみや影が強調されてしまいます。
つまり、脂肪の突出と皮膚のハリ低下という2つの要因が重なることで、悩みはより深刻に見えるのです。
目の下の脂肪が目立つ最大の要因は「加齢」
目の下の脂肪が目立つ原因として、最も広く知られているのが加齢です。年齢を重ねることで身体に様々な変化が現れるように、目元も例外ではありません。
ここでは、加齢がどのように目の下の脂肪に影響を与えるのかを具体的に見ていきましょう。
コラーゲンとエラスチンの減少
肌のハリや弾力を保つために重要な役割を果たすのが、コラーゲンとエラスチンです。これらは真皮層に存在する線維状のタンパク質で、肌を内側から支える土台となっています。
しかし、20代をピークにこれらの生成量は減少し始め、質も低下します。これにより、皮膚は薄くなり、弾力を失います。
結果として、眼窩脂肪の重みを支えきれなくなり、たるみやふくらみとして現れやすくなるのです。
眼輪筋の衰え
眼輪筋は、目の周りをドーナツ状に取り囲んでいる筋肉です。まばたきをしたり、表情を作ったりする際に使われますが、身体の他の筋肉と同様に、年齢とともに衰えていきます。
眼輪筋が衰えると、その内側にある眼窩脂肪を支える力が弱まります。ダムが決壊するように、弱った筋肉の隙間から脂肪が前方に押し出され、ふくらみとなって現れます。
加齢による目元の変化
| 変化する部位 | 具体的な変化 | 結果として現れる症状 |
|---|---|---|
| 皮膚(真皮層) | コラーゲン・エラスチンが減少 | ハリ・弾力の低下、皮膚の菲薄化 |
| 筋肉(眼輪筋) | 筋力の低下 | 眼窩脂肪を支える力が弱まる |
| 支持組織(靭帯) | 支持力が低下し、ゆるむ | 眼窩脂肪の前方への突出 |
加齢による骨格の変化
あまり知られていませんが、加齢によって頭蓋骨もわずかに変化します。特に目の周りの骨である眼窩は、年齢とともに少しずつ拡大する傾向があります。
眼窩の空間が広がると、その中にある眼窩脂肪が前や下に移動しやすくなり、結果として目の下のふくらみやたるみの原因の一つになることがあります。
【トリガー1】生活習慣の乱れが引き起こす影響
加齢だけでなく、日々の生活習慣も目の下の脂肪を目立たせる大きな要因です。
特に睡眠、食事、喫煙といった基本的な習慣の乱れは、血行不良やむくみ、肌質の低下を招き、目元の印象を大きく左右します。
自分では気づかないうちに、悩みを深刻化させているかもしれません。
睡眠不足と血行不良の関係
睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが乱れ、全身の血行が悪くなります。特に目の周りは皮膚が薄く、毛細血管が多いため、血行不良の影響が顕著に現れます。
血流が滞ると、酸素や栄養が十分に行き渡らず、肌のターンオーバーが乱れてハリが失われます。
また、うっ血することでクマが悪化し、脂肪のふくらみによる影と相まって、より一層疲れた印象を与えます。
塩分・アルコールの過剰摂取とむくみ
塩分の多い食事やアルコールの飲み過ぎは、体内の水分バランスを崩し、「むくみ」を引き起こします。体内に余分な水分が溜まると、顔、特に皮膚の薄い目元はむくみやすくなります。
一時的なむくみであれば時間とともにある程度解消しますが、慢性的にむくんだ状態が続くと、皮膚が伸びてしまい、たるみの原因になります。
このむくみが、元々ある脂肪のふくらみをさらに強調してしまうのです。
むくみを引き起こす食事と対策
| 原因となるもの | 身体への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 塩分の過剰摂取 | 体内に水分を溜め込みやすくなる | カリウム(野菜、果物)を摂取し排出を促す |
| アルコールの摂取 | 血管が拡張し、水分が漏れやすくなる | 適量を心がけ、チェイサー(水)を一緒に飲む |
| 水分不足 | 身体が水分を保持しようとしてむくむ | こまめに常温の水を飲む |
栄養バランスの偏りが肌に与えるダメージ
私たちの肌は、日々の食事から摂取する栄養素によって作られています。特にタンパク質、ビタミン、ミネラルは、健康な肌を維持するために重要です。
ファストフードや加工食品に偏った食事では、これらの栄養素が不足しがちです。栄養不足は、コラーゲンの生成を妨げ、肌のハリを低下させます。
その結果、目の下の皮膚が薄くなり、脂肪のふくらみが目立ちやすくなります。
肌の健康に必要な栄養素
- タンパク質
- ビタミンC
- ビタミンA
- ビタミンE
- 鉄分
喫煙がコラーゲンを破壊する
喫煙は、肌の老化を加速させる大きな要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血行を悪化させます。これにより、肌細胞に必要な酸素や栄養が届きにくくなります。
さらに、喫煙によって体内で大量に発生する活性酸素は、肌のハリを保つコラーゲンやエラスチンを破壊します。
これらの影響が複合的に作用し、目の下の皮膚の弾力性を著しく低下させ、脂肪のふくらみを目立たせる原因となります。
【トリガー2】デジタルデバイスの長時間利用と目の疲れ
現代の生活では、スマートフォンやパソコンが欠かせません。しかし、これらのデジタルデバイスの長時間利用は、私たちが思う以上に目元へ大きな負担をかけています。
目の疲れやそれに伴う無意識の行動が、目の下の脂肪を目立たせる原因となっているのです。
PC・スマホによる眼精疲労
小さな画面を長時間見続けると、目のピントを調節する筋肉(毛様体筋)が緊張し続けます。この状態が続くと、眼精疲労を引き起こし、目の周りの血行が悪化します。
血行不良は、肌の栄養不足や老廃物の蓄積につながり、皮膚の健康状態を損ないます。これが目の下のハリを失わせ、脂肪のふくらみを支える力を弱める一因となります。
眼精疲労のサイン
| 目の症状 | 身体の症状 |
|---|---|
| 目がかすむ、ぼやける | 肩こり、首のこり |
| 目が乾く、しょぼしょぼする | 頭痛、めまい |
| ピントが合いにくい | 吐き気、倦怠感 |
まばたきの減少が眼輪筋を弱らせる
何かに集中しているとき、特にデジタルデバイスの画面を見ているとき、私たちのまばたきの回数は通常時の半分以下にまで減少すると言われています。
まばたきは、眼輪筋を使って行われる運動です。その回数が減るということは、眼輪筋を使う機会が減ることを意味します。日常的に眼輪筋が使われなくなると、筋肉は徐々に衰えていきます。
眼輪筋の衰えは、前述の通り、眼窩脂肪を支えきれなくなる直接的な原因です。
ブルーライトがもたらす肌への影響
スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠の質を低下させることが知られています。
夜間にブルーライトを浴びることで、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
良質な睡眠は、日中に受けた肌ダメージを修復するための大切な時間です。
睡眠の質が低下すると、肌の再生能力が落ち、コラーゲンの生成も滞るため、結果的に目の下のたるみやふくらみを助長することにつながります。
【トリガー3】無意識の行動や誤ったスキンケア
良かれと思って行っているスキンケアや、無意識にしてしまっている癖が、実はデリケートな目元の皮膚にダメージを与え、目の下の脂肪を目立たせる原因になっていることがあります。
毎日の小さな積み重ねが、大きな悩みにつながる可能性を理解することが大切です。
目をこする癖の危険性
花粉症やアレルギー、あるいは目の疲れから、無意識に目をこすってしまうことはありませんか。目の周りの皮膚は非常に薄く、摩擦による刺激にとても弱い部分です。
目をゴシゴシとこする行為は、皮膚の下にある毛細血管を傷つけ、色素沈着(茶クマ)の原因になるだけでなく、皮膚を支えるコラーゲン線維にダメージを与え、皮膚を伸びさせてしまいます。
伸びてしまった皮膚は元に戻りにくく、たるみとなって脂肪のふくらみをより一層目立たせます。
避けるべき目元への物理的刺激
| 行動 | 目元への影響 |
|---|---|
| 目を強くこする | 皮膚のたるみ、色素沈着の原因 |
| うつぶせ寝 | 長時間圧迫され、シワやたるみの原因に |
| タオルで顔を強く拭く | 摩擦により皮膚にダメージを与える |
強すぎるマッサージやクレンジング
目元の血行促進やリフトアップを目的としたマッサージも、方法を誤ると逆効果です。
強い力で皮膚を引っ張ったり、押し込んだりするマッサージは、皮膚やそれを支える組織を傷つけ、たるみを悪化させる原因となります。
同様に、アイメイクを落とす際のクレンジングも注意が必要です。落ちにくいアイライナーやマスカラをゴシゴシとこすって落とす行為は、目をこする癖と同じように皮膚にダメージを与えます。
アイメイクによる目元への負担
アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、つけまつげなど、アイメイクは目元を華やかに見せてくれますが、同時に目元に負担をかけている側面もあります。
特に、ウォータープルーフタイプの化粧品は落とす際に強いクレンジングが必要になりがちです。また、ビューラーでまつげを上げる際にまぶたを強く引っ張ることも、皮膚への負担となります。
毎日のメイクとクレンジングの積み重ねが、少しずつ目元の老化を早めている可能性があることを認識しましょう。
自宅でできる!目の下の脂肪を目立たなくするセルフケア
目の下の脂肪が気になり始めたとき、まずは自宅でできるセルフケアから試してみましょう。
これらのケアは、脂肪そのものをなくすことはできませんが、血行を促進し、肌にハリを与えることで、ふくらみを目立ちにくくする効果が期待できます。
大切なのは、継続することと、やりすぎないことです。
目元を温めて血行を促進する
目元の血行不良は、クマやむくみを悪化させ、脂肪のふくらみを強調します。蒸しタオルや市販のホットアイマスクを使って目元を温めることは、手軽で効果的な血行促進方法です。
40℃程度の心地よい温度で5分から10分ほど温めると、目の周りの筋肉の緊張がほぐれ、血流が良くなります。リラックス効果もあるため、一日の終わりの習慣にするのがおすすめです。
セルフケア方法の比較
| ケア方法 | 期待できる効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| ホットタオル・アイマスク | 血行促進、眼精疲労の緩和 | やけどに注意し、適温で行う |
| 保湿ケア | 乾燥による小じわの改善、ハリ感アップ | 肌に合った製品を選び、優しく塗布する |
| 眼輪筋トレーニング | 筋肉の衰え予防 | やりすぎはシワの原因になるため注意 |
目元の保湿ケアを徹底する
目の周りの皮膚は乾燥しやすく、乾燥は小じわやハリ不足の直接的な原因となります。保湿を徹底することで、肌のバリア機能を高め、ふっくらとしたハリを保つことができます。
セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどが配合された、目元専用のアイクリームや美容液を使用しましょう。
塗布する際は、薬指の腹を使って、目頭から目尻に向かって優しくなじませるようにします。決して強くこすりつけないでください。
生活習慣の見直しと改善点
これまで見てきたように、生活習慣は目元の状態に大きく影響します。まずは十分な睡眠時間を確保し、質の良い睡眠を心がけることが基本です。
食事では、塩分を控えめにし、カリウムやビタミンが豊富な野菜や果物を積極的に摂りましょう。また、こまめな水分補給もむくみ予防に有効です。
定期的に休憩を取り、PCやスマホから目を離す時間を作ることも、眼精疲労の軽減につながります。
取り入れたい生活習慣
- 6〜8時間の質の良い睡眠
- バランスの取れた食事
- 適度な運動
- 禁煙・節酒
- こまめな水分補給
眼輪筋トレーニングの注意点
眼輪筋を鍛えるトレーニングは、筋肉の衰えを防ぐ上で有効な場合があります。しかし、自己流で過度に行うと、かえってシワを深くしてしまうリスクもあります。
トレーニングを行う際は、鏡を見ながら、目的の筋肉だけを動かすように意識し、皮膚を強く引っ張らないように注意が必要です。
あくまで予防的なケアと位置づけ、無理のない範囲で取り入れるのが良いでしょう。
根本的な解決を目指すなら美容クリニックという選択肢
セルフケアは症状の悪化を防いだり、目立ちにくくしたりする上で重要ですが、一度前に出てきてしまった眼窩脂肪を元に戻すことは困難です。
目の下の脂肪によるふくらみを根本的に解決したいと考えるなら、美容クリニックでの専門的な治療が有効な選択肢となります。
ここでは、なぜ専門的な治療が必要なのか、その理由と主な治療法について解説します。
セルフケアでは脂肪自体はなくならない
マッサージや化粧品などのセルフケアは、あくまで皮膚のコンディションを整えたり、血行を促進したりする対症療法です。
ふくらみの原因である眼窩脂肪そのものを取り除いたり、元の位置に戻したりする効果はありません。そのため、セルフケアを続けても期待するほどの変化が得られない場合が多いのです。
根本的な改善には、脂肪に直接アプローチする医療的な介入が必要になります。
専門医によるカウンセリングの重要性
目の下の状態は、脂肪の突出度合い、皮膚のたるみ、骨格など、人それぞれ異なります。
自己判断でケアを続けるよりも、まずは専門の医師によるカウンセリングを受け、自分の目の下がどのような状態なのかを正確に診断してもらうことが重要です。
医師は、あなたの状態を的確に評価し、最も適した治療法を提案してくれます。悩みや不安、予算などを率直に相談し、納得した上で治療に進むことが、満足のいく結果への第一歩です。
主な治療法の種類と特徴
目の下の脂肪に対する主な治療法には、いくつかの種類があります。どの方法が適しているかは、個人の症状によって異なります。
医師とのカウンセリングを通じて、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選択します。
代表的な治療法
| 治療法 | 特徴 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 経結膜脱脂法 | まぶたの裏側から脂肪を取り除く。皮膚表面に傷が残らない。 | 皮膚のたるみが少なく、脂肪の突出が主な原因の場合。 |
| ハムラ法 | 突出した脂肪を凹んでいる部分に移動させて固定する。 | 脂肪の突出と目の下の凹みが混在している場合。 |
| 注入治療(ヒアルロン酸など) | 凹んでいる部分に注入し、段差を目立たなくする。 | 軽度のふくらみや影、外科手術に抵抗がある場合。 |
目の下の脂肪に関するよくある質問
- 目の下の脂肪は遺伝しますか?
-
骨格や皮膚の質、脂肪のつきやすさといった体質は遺伝的要因が影響することがあります。
そのため、ご両親やご親族に目の下の脂肪が目立つ方がいる場合、ご自身も同じような傾向を持つ可能性は考えられます。
しかし、すべての原因が遺伝というわけではなく、後天的な生活習慣やケアも大きく関わってきます。
- 一度治療で脂肪を取ったら、もう二度と再発しませんか?
-
治療で取り除いた脂肪細胞が再生することはありませんので、基本的には再発しにくいと言えます。しかし、加齢による変化が完全に止まるわけではありません。
残っている脂肪を支える組織がゆるんだり、皮膚のたるみが進行したりすることで、将来的に再びふくらみが気になる可能性はゼロではありません。
長期的に良い状態を保つためには、治療後も健康的な生活習慣を心がけることが大切です。
- 何歳くらいから目の下の脂肪は目立ち始めますか?
-
個人差が非常に大きいですが、一般的には30代後半から40代にかけて気になり始める方が多いです。しかし、早い方では20代からふくらみが目立つこともあります。
これは、前述の通り、骨格的な要因や生活習慣が影響するためです。年齢に関わらず、気になった時が相談のタイミングと言えるでしょう。
- 男性でも同じ原因で目の下の脂肪は目立ちますか?
-
はい、原因は男女で基本的に同じです。加齢による眼輪筋の衰えや皮膚のハリの低下、そして生活習慣などが原因で眼窩脂肪が突出します。
男性は女性に比べてスキンケアに関心が低い傾向があるため、紫外線ダメージや乾燥対策が不十分で、皮膚の老化が早く進むこともあります。
近年は、男性でも目の下のふくらみを気にして相談に来られる方が増えています。
- 太ると目の下の脂肪も増えますか?
-
全身の体重増加と目の下の眼窩脂肪の量が直接的に比例するわけではありません。
目の下のふくらみは、脂肪の「量」が増えることよりも、脂肪を支える組織がゆるんで前方に「突出」することが主な原因です。
そのため、痩せている方でもふくらみが目立つことは珍しくありません。ただし、急激な体重増加はむくみの原因となり、ふくらみを一時的に強調することはあります。
参考文献
SAMIZADEH, Souphiyeh. Anatomy and Pathophysiology of Facial Ageing. In: Thread Lifting Techniques for Facial Rejuvenation and Recontouring. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 61-89.
DABBOUS, H., et al. Aging of the Orbit and Rejuvenation Options. In: Periorbital Rejuvenation: A Practical Manual. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 35-50.
TAO, Brendan K., et al. Periocular Aging Across Populations and Esthetic Considerations: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine, 2025, 14.2: 535.
RATHORE, Gyanesh, et al. Clinical assessment, diagnosis, and Management of Infraorbital Wrinkles and Pigmentation. Dermatologic Clinics, 2024, 42.1: 79-88.
MARTEN, Timothy; ELYASSNIA, Dino. Periorbital fat grafting: a new paradigm for rejuvenation of the eyelids. Facial Plastic Surgery Clinics, 2021, 29.2: 243-273.
DUTTON, Jonathan; PROIA, Alan; TAWFIK, Hatem. Comprehensive textbook of eyelid disorders and diseases. Lippincott Williams & Wilkins, 2022.
VASHI, Neelam A.; MAYMONE, Mayra Buainain De Castro; KUNDU, Roopal V. Aging differences in ethnic skin. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2016, 9.1: 31.
CHEONG, Sousan, et al. Correction of Infraorbital Dark Circles Using Autologous Adipose-Derived Collagen Filler: A Novel Regenerative Option. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.22: 4693-4701.
CESTARI, Tania Ferreira; DANTAS, Lia Pinheiro; BOZA, Juliana Catucci. Acquired hyperpigmentations. Anais brasileiros de dermatologia, 2014, 89: 11-25.
SHERRIS, David A.; OTLEY, Clark C.; BARTLEY, George B. Comprehensive treatment of the aging face—cutaneous and structural rejuvenation. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 1998. p. 139-146.