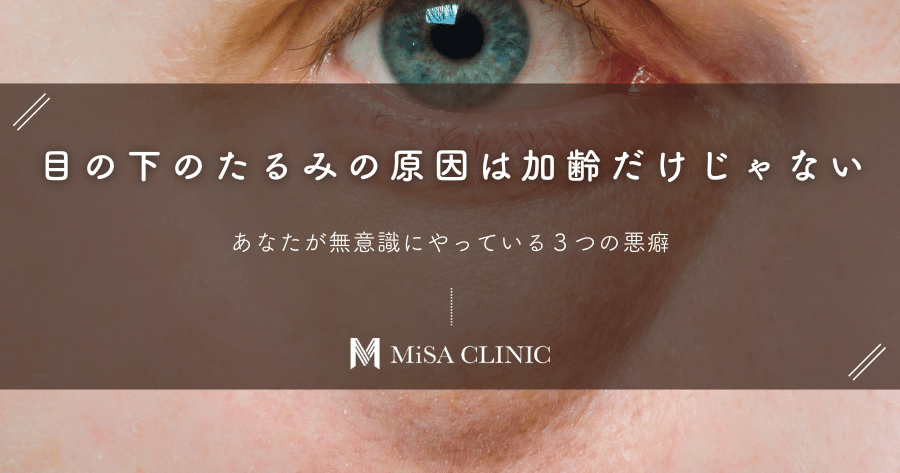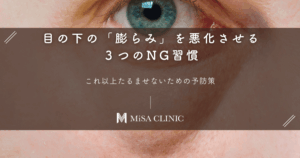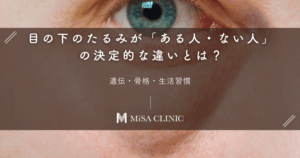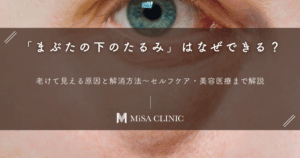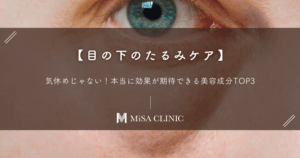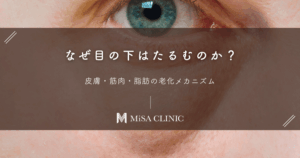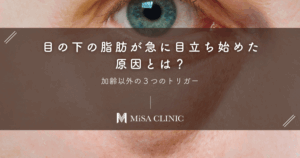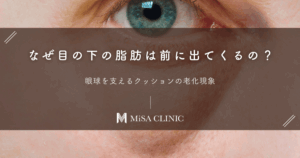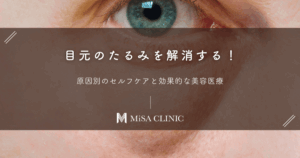「目の下のたるみ」は、見た目年齢を大きく左右する要因の一つです。多くの方が加齢によるものだと諦めていますが、実はそれだけが原因ではありません。
今、あなたが無意識のうちに毎日繰り返している生活習慣、つまり悪癖が、たるみを加速度的に進行させている可能性があるのです。この悪癖を特定し、改善することが、たるみ対策の非常に重要な鍵となります。
この記事では、「目の下のたるみ 原因」で悩むあなたのために、たるみのメカニズムを分かりやすく解説するとともに、知らず知らずのうちに皮膚の弾力やハリを奪っている「3つの悪癖」とその具体的な改善策を、読者に寄り添った親切丁寧な情報として詳しくご紹介します。
たるみ対策は、加齢に対抗するだけでなく、日々の意識を変えることから始まります。
目の下のたるみが生む印象と構造的な理解
目の下のたるみは、単に疲れて見えるというだけでなく、実年齢よりも老けて見える大きな原因となります。目の下に影ができることでクマとして認識されたり、顔全体の印象を暗く見せたりします。
まず、たるみがどのようにして発生するのか、その構造を理解することが、適切な対策を講じる上で重要です。
たるみはなぜ「老け顔」に見せてしまうのか
目の下のたるみが目立つと、光が当たらずに影が生まれます。この影こそが、いわゆる「影クマ」や「黒クマ」と呼ばれるものです。
この影は、表情筋の衰えや眼窩脂肪の突出によって目の下に段差ができることで発生します。この段差が大きいほど、顔の立体感が失われ、疲労感や老けた印象を強く与えてしまうのです。
目の周りの皮膚は非常に薄く、他の部位よりも乾燥しやすく、ダメージを受けやすい特性を持っています。
目の下のたるみの主要な構成要素
目の下のたるみは、皮膚、眼輪筋、眼窩脂肪という三つの要素が複雑に絡み合って形成されます。年齢を重ねると、これらの組織が徐々に変化し、たるみとして表面に現れます。
特に、眼球を支えているロックウッド靭帯や、脂肪を支える眼窩隔膜が緩むと、内部の脂肪が前に押し出され、たるみとなって現れます。
目の下のたるみのタイプ別特徴
| たるみのタイプ | 主な原因 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| 脂肪突出型 | 眼窩隔膜の緩み、眼窩脂肪の突出 | 下まぶたが膨らみ、目袋のように見える |
| 皮膚のたるみ型 | コラーゲン・エラスチンの減少、乾燥 | 皮膚表面に細かいシワやたるみが目立つ |
| むくみ型 | 血行不良、水分や老廃物の滞留 | 朝や疲れている時に一時的に膨らむ |
たるみの主な原因 加齢と皮膚の構造的変化
「目の下のたるみ 原因」を考える上で、加齢が最大の要素であることは間違いありません。
しかし、その加齢による変化が具体的に何を指しているのかを正しく理解し、悪癖による進行を防ぐことが大切です。
真皮層のコラーゲンとエラスチンの変質
皮膚のハリや弾力は、真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといったタンパク質によって維持されています。コラーゲンは皮膚の土台を築き、エラスチンはバネのように弾力を与える役割を担っています。
しかし、加齢とともにこれらの生成能力は低下し、既存の繊維も変性していきます。弾力を失った皮膚は重力に逆らえなくなり、たるみとして現れるのです。
眼輪筋の筋力低下と表情筋の衰え
目の周りをドーナツ状に取り囲んでいる眼輪筋は、まばたきや涙の排出、表情を作るために重要な筋肉です。この眼輪筋が衰えると、重い眼窩脂肪を支えきれなくなり、前に押し出される原因となります。
また、頬の脂肪や筋肉も連動して衰えるため、全体的な顔のたるみが目の下を引っ張り、たるみを強調することもあります。
筋力低下は、加齢だけでなく、表情筋を使わない生活習慣によっても進行します。
眼窩脂肪の突出と移動
眼窩脂肪は、眼球を衝撃から守るクッションの役割を果たしていますが、加齢によってその脂肪を覆っている膜(眼窩隔膜)や支え(ロックウッド靭帯)が弱くなります。
その結果、脂肪が重力に従って前方に押し出され、下まぶたに「目袋」と呼ばれる膨らみを作り出します。
この膨らみと、その下にある頬の脂肪が痩せてできる「ゴルゴ線」との段差が、たるみとして認識されるのです。
無意識にやっている悪癖その1 摩擦と刺激によるダメージ
目の周りの皮膚は、ティッシュペーパーよりも薄いと言われるほどデリケートです。
このデリケートな皮膚に対して、日々の摩擦や刺激は、加齢よりも早くコラーゲンやエラスチンを破壊する大きな悪癖となります。
メイクオフ時の過剰な摩擦
アイメイクを落とす際、つい力を入れてゴシゴシとこすっていませんか。この強い摩擦は、皮膚のバリア機能を破壊し、炎症を引き起こします。
炎症は、皮膚の老化を早める酸化ストレスを生み出し、真皮層のコラーゲン繊維を断裂させる原因となります。クレンジング剤をたっぷり使い、指の腹で優しくなでるようにメイクを溶かし出すことが重要です。
花粉症などによる目の掻きすぎ
アレルギーや花粉症で目がかゆいとき、強く目をこすることも悪癖の一つです。掻くという行為は、皮膚の表層だけでなく深層にも衝撃を与え、線維芽細胞の働きを低下させます。
その結果、ハリを生み出すコラーゲンやエラスチンの生成が妨げられ、皮膚の弾力が急速に失われてしまいます。
かゆみが強い場合は、冷やしたタオルで鎮静させる、または点眼薬を使うなどして、物理的な摩擦を避けてください。
摩擦が引き起こす皮膚構造の破壊活動
| 摩擦の行為 | 皮膚への直接的影響 | たるみへの影響 |
|---|---|---|
| クレンジングで強くこする | 皮膚のバリア機能破壊 | 乾燥、炎症によるコラーゲン断裂 |
| 目を強く掻く、触る | 物理的な衝撃と微細な炎症 | 線維芽細胞の機能低下、弾力性喪失 |
| タオルで顔を強く拭く | 皮膚表面の角層剥離 | 乾燥、シワの発生とたるみの進行 |
紫外線による光老化の蓄積
紫外線は、皮膚の老化を加速させる最も強力な要因です。特に目の周りは日焼け止めを塗り忘れやすい部位であり、無意識のうちに光老化を進行させています。
紫外線A波(UVA)は真皮層にまで到達し、コラーゲンやエラスチンを分解する酵素(MMP)を過剰に生成させます。この酵素は、皮膚のハリを保つ構造を内部から破壊し、たるみを引き起こします。
外出時はもちろん、室内でも窓際では紫外線対策が大切です。
無意識にやっている悪癖その2 目の酷使と血行不良
現代の生活において、目を酷使する機会は増える一方です。この目の使いすぎからくる眼精疲労と血行不良は、たるみやクマを悪化させる二つ目の大きな悪癖です。
長時間にわたるスマホ・PC操作
スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続けることは、目の周りの筋肉を緊張させ、血行不良を引き起こします。
眼輪筋やその周辺の筋肉が疲労でこり固まると、リンパの流れも悪くなり、老廃物や余分な水分が滞留します。これがむくみとして現れ、一時的なたるみを作ったり、恒常的なたるみを強調したりします。
瞬きの回数の減少と眼輪筋のサボり
画面に集中している間は、無意識のうちに瞬きの回数が大幅に減少します。瞬きは、目の周りの筋肉(眼輪筋)を動かし、血行を促進し、涙を分泌させる重要な運動です。
瞬きが減ると、眼輪筋は運動不足に陥り、筋力が低下します。前述した通り、眼輪筋の筋力低下は眼窩脂肪を支えられなくなり、たるみを進行させる直接的な原因となります。
意識的に休憩を挟み、遠くを見たり、大きく瞬きをしたりすることが必要です。
睡眠不足による血行の停滞
睡眠は、体と皮膚が修復される大切な時間です。睡眠が不足すると、自律神経のバランスが乱れ、全身の血行が悪化します。特に目の下は毛細血管が多く集まる場所であるため、血行不良がすぐに現れます。
酸素不足になった血液が滞留することで、青クマが発生し、それが目の下の影を強調し、たるみを目立たせることになります。質の良い睡眠を確保することは、たるみ対策に非常に重要です。
目の酷使と血行不良の悪影響
| 悪影響 | 関連する習慣 | 結果としてのたるみ |
|---|---|---|
| 眼輪筋の緊張・こり | 長時間ディスプレイを見る | リンパ滞留によるむくみ、一時的なたるみ |
| 瞬きの減少 | 画面への集中 | 眼輪筋の筋力低下、脂肪突出の促進 |
| 血管の拡張と停滞 | 睡眠不足、目の冷却不足 | 青クマの発生、影クマの強調 |
無意識にやっている悪癖その3 姿勢と生活習慣の乱れ
目の下のたるみは、顔だけの問題だと考えがちですが、実は全身の姿勢や食生活といった生活習慣全体が深く関わっています。
特に、重力の影響を最大限に受けてしまう習慣は、三つ目の悪癖として見過ごせません。
猫背やうつむき姿勢の常態化
スマートフォンを見るときなど、頭を前に突き出す猫背やうつむき姿勢は、顔の皮膚や脂肪に通常よりも強い重力負荷をかけます。
頭の重さは約5kgもあり、この重さを首だけで支えようとすると、皮膚組織が下へ引っ張られ、たるみを加速させます。
また、この姿勢は首や肩のこりを引き起こし、顔への血流やリンパの流れを悪化させるため、むくみやたるみを複合的に引き起こします。背筋を伸ばし、ディスプレイは目線の高さに調整することが大切です。
塩分過多と水分の停滞
濃い味付けや塩分の多い食事を日常的に摂ると、体内の塩分濃度を薄めるために水分を溜め込もうとします。特に夜間の塩分摂取は、朝の顔のむくみとして現れやすく、目の下にも水分が集中して停滞します。
この頻繁なむくみは、皮膚組織を繰り返し伸ばし、最終的に皮膚の弾力を失わせる原因となります。低塩分の食事を心がけ、利尿作用のあるカリウムを摂取することが役立ちます。
横向きやうつ伏せでの睡眠
寝る姿勢も重要な悪癖の一つです。特に一方向を向いて寝る横向き寝や、顔を下にするうつ伏せ寝は、枕や布団に顔が押し付けられ、目の下に長時間強い圧力をかけます。
この圧力は、皮膚がよれてシワになるだけでなく、リンパの流れを阻害し、片側だけのむくみやたるみを引き起こすことがあります。
理想的なのは仰向けでの睡眠ですが、難しい場合は、低反発で顔に負担の少ない枕を選ぶ工夫が必要です。
姿勢・生活習慣とたるみの関係
| 悪癖となる行動 | 体への影響 | 目の下への影響 |
|---|---|---|
| 猫背・うつむき姿勢 | 首・肩のこり、重力負荷の増大 | 皮膚の物理的な引っ張り、たるみの加速 |
| 高塩分・高糖質の食事 | 体内の水分滞留 | 朝のむくみ、皮膚組織の繰り返し伸展 |
| 横向き・うつ伏せ寝 | 顔への局所的な圧迫 | シワの定着、片側のみのリンパ停滞 |
たるみのタイプ別セルフケアと注意点
たるみの原因は複合的ですが、ご自身のたるみがどのタイプに近いのかを把握することで、より効果的なセルフケアが可能になります。
自己判断だけで全てを解決しようとせず、あくまでも日常生活のサポートとして捉えてください。
脂肪突出型へのアプローチ
目袋のように脂肪が前に膨らんでいるタイプは、皮膚や筋肉の力だけでは改善が難しいのが現実です。
セルフケアとしては、目の周りの血行を良くし、むくみを軽減させることで膨らみを少しでも目立たなくさせることに焦点を当てます。
温かいタオルと冷たいタオルを交互に当てる温冷ケアは、血行促進に役立ちます。また、表情筋のエクササイズで眼輪筋を強化することも大切です。
皮膚のたるみ型へのアプローチ
皮膚が薄くなり、細かいシワやハリの低下が目立つタイプには、徹底した保湿と紫外線対策が重要です。セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分をたっぷり与え、皮膚のバリア機能を維持してください。
さらに、コラーゲン生成をサポートするレチノールやビタミンC誘導体を含むスキンケア製品を取り入れることも有効です。
ただし、これらの成分は刺激が強い場合があるため、必ず少量から試す必要があります。
むくみ型・血行不良型へのアプローチ
一時的なむくみや、青みがかったクマを伴う血行不良型は、生活習慣の改善で最も効果が出やすいタイプです。
温かい蒸しタオルで目元を温めて血行を促したり、リンパの流れを意識したマッサージを行うことが有効です。
マッサージは、必ず摩擦を与えないよう、アイクリームやオイルを十分に使い、軽い力で行ってください。
目元マッサージの基本原則
| 原則 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 摩擦の徹底排除 | コラーゲン繊維の破壊防止 | クリームやオイルを必ず使用する |
| リンパの流れ意識 | 老廃物の排出促進 | 目頭からこめかみ、耳下腺へ流す |
| 力の加え方 | 皮膚に負担をかけない | 人差し指ではなく中指・薬指の腹を使う |
悪癖を断ち切るための具体的な改善策
目の下のたるみを進行させる悪癖は、意識することで必ず改善できます。今日からできる具体的な行動を習慣化し、たるみに負けない目元を作ってください。
悪癖1対策 摩擦レスなスキンケアの徹底
最も重要なのは、目の周りを触る回数と強度を減らすことです。メイクオフは専用のリムーバーを使い、コットンで優しく押さえるだけに留めてください。
スキンケアを塗布する際も、叩き込むのではなく、体温で温めたクリームをそっと皮膚にのせるように優しくなじませてください。
皮膚の弾力維持に重要な栄養素
体の中から皮膚の構造をサポートする栄養素も重要です。
- コラーゲン生成を助けるビタミンC
- 抗酸化作用のあるビタミンE
- 細胞の再生を促す亜鉛
これらの栄養素を意識して摂取することで、悪癖によるダメージからの回復を早め、真皮層の健康維持をサポートします。
悪癖2対策 意識的な休憩とアイケア
ディスプレイ作業の際は、一時間に一度は目を休ませる「20-20-20ルール」(20分ごとに20フィート=約6m先を20秒間見る)を実行してください。
また、目の下の血行を即座に改善するために、市販のアイマスクやホットタオルで目元を温める習慣を夜に取り入れてください。
これにより、眼輪筋の緊張がほぐれ、老廃物の排出がスムーズになります。
ディスプレイ作業中のアイケア習慣
| 習慣 | 頻度 | 効果 |
|---|---|---|
| 遠くを見る休憩 | 60分に一度 | ピント調節筋の緊張緩和 |
| 意識的な瞬き | 作業中随時 | 眼輪筋の運動、目の乾燥予防 |
| 蒸しタオルでの加温 | 就寝前 | 血行促進、青クマの改善 |
悪癖3対策 姿勢の矯正と質の高い睡眠
姿勢の改善は、たるみ予防だけでなく、肩こりや頭痛の改善にもつながります。座る際は、椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、ディスプレイと目線が水平になるよう調整してください。
また、仰向けで寝ることを習慣化し、寝具は首のカーブを適切に支えるものを選んでください。質の高い睡眠は、成長ホルモンによる皮膚の修復を促すため、悪癖によって失われたハリを取り戻すために必要です。
たるみ予防のための睡眠環境の見直し
| 改善ポイント | 目的 | 行動指針 |
|---|---|---|
| 寝る姿勢 | 重力負荷と摩擦の回避 | 仰向けでの睡眠を習慣化する |
| 枕の高さ | 首のカーブの適切な保持 | 低すぎず高すぎない枕を選ぶ |
| 就寝前の環境 | 質の高い睡眠の確保 | スマホ操作を避け、部屋を暗くする |
よくある質問
目の下のたるみについて、読者の方がよく抱く疑問とその回答をまとめます。
- たるみ対策に効果的な食べ物はありますか?
-
特定の食品だけでたるみを完全に消すことは難しいですが、皮膚の弾力をサポートする栄養素を積極的に摂取することは大切です。
コラーゲンの生成に欠かせないビタミンCを多く含む柑橘類やパプリカ、肌の酸化を防ぐビタミンEを豊富に含むナッツ類やアボカドなどがおすすめです。
また、タンパク質は皮膚の構成要素そのものですから、良質なタンパク質を毎食欠かさず摂るようにしてください。バランスの取れた食事が、肌の健康を維持する基礎となります。
- 目の下のマッサージは毎日行っても大丈夫ですか?
-
マッサージは血行促進に役立ちますが、過度な摩擦はかえってたるみを悪化させる悪癖につながります。
毎日行うこと自体は問題ありませんが、必ずアイクリームやオイルをたっぷり使い、皮膚の表面を動かさないように、骨に沿って優しくリンパを流す程度の弱い力加減で行ってください。
特に目の周りの皮膚を強く引っ張るようなマッサージは、コラーゲン繊維を断裂させるリスクがあるため避ける必要があります。
少しでも刺激を感じたら、マッサージではなくホットタオルなどで温めるケアに切り替えるなど、デリケートに対応してください。
- 目の下のクマとたるみはどのように見分けることができますか?
-
クマとたるみは密接に関係していますが、厳密には区別できます。たるみによる影クマ(黒クマ)は、顔を上に向けて鏡を見たときに、目の下の影が薄くなるのが特徴です。
これは、膨らみと窪みの段差が重力の影響で解消されるためです。一方、血行不良による青クマは、皮膚を軽く横に引っ張っても色が変わらず、疲労や寝不足で濃くなります。
色素沈着による茶クマは、皮膚を引っ張ると色が薄くなります。ご自身のクマがどのタイプなのかを把握することが、原因を特定し、適切な対策を考えるために必要です。
- 若いうちからたるみ対策は必要ですか?
-
目の下のたるみは、加齢だけでなく、摩擦、血行不良、姿勢の乱れといった悪癖によって若いうちから進行します。特に、紫外線による光老化は皮膚の土台を静かに破壊し続けます。
若いうちから徹底した紫外線対策と、この記事で解説した3つの悪癖を断ち切る生活習慣を確立することは、将来のたるみを大きく予防するために重要です。
皮膚のハリや弾力がまだ十分にある20代、30代からの「予防的なケア」が、最も効果的なたるみ対策となります。
参考文献
UGRADAR, Shoaib, et al. Photochemical collagen cross-linking reverses elastase-induced mechanical degradation of upper eyelid tarsus. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 2020, 36.6: 562-565.
MANTA, Alexandra I., et al. Photochemical Crosslinking of Tarsal Collagen as a Treatment for Eyelid Laxity: Evaluation in Ex Vivo Human Tissue. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 2025, 41.1: 28-35.
SCHLÖTZER-SCHREHARDT, Ursula, et al. The pathogenesis of floppy eyelid syndrome: involvement of matrix metalloproteinases in elastic fiber degradation. Ophthalmology, 2005, 112.4: 694-704.
DABBOUS, H., et al. Aging of the Orbit and Rejuvenation Options. In: Periorbital Rejuvenation: A Practical Manual. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 35-50.
TAO, Brendan K., et al. Periocular Aging Across Populations and Esthetic Considerations: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine, 2025, 14.2: 535.
LIPP, Michael; WEISS, Eduardo. Nonsurgical treatments for infraorbital rejuvenation: a review. Dermatologic surgery, 2019, 45.5: 700-710.
BRISCOE, Daniel, et al. Age-related changes of the eyelid and surgery of eyelids in aging. In: Aging in Ophthalmology. Academic Press, 2026. p. 13-34.
DUTTON, Jonathan; PROIA, Alan; TAWFIK, Hatem. Comprehensive textbook of eyelid disorders and diseases. Lippincott Williams & Wilkins, 2022.
FATHI, Ramin; PFEIFFER, Margaret L.; TSOUKAS, Maria. Minimally invasive eyelid care in dermatology: medical, laser, and cosmetic therapies. Clinics in dermatology, 2015, 33.2: 207-216.
NG, Alison, et al. Impact of eye cosmetics on the eye, adnexa, and ocular surface. Eye & contact lens, 2016, 42.4: 211-220.