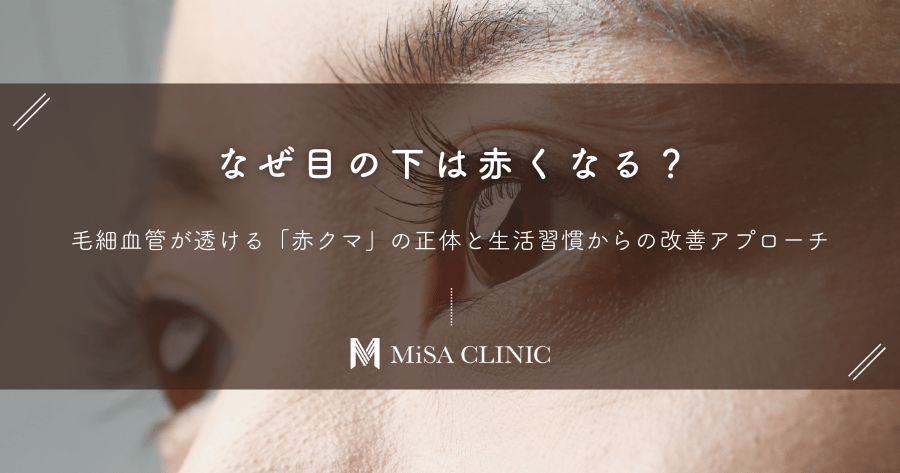目の下がほんのり赤く見えて、疲れているように思われたり、ファンデーションやコンシーラーで隠しきれなかったりする経験はありませんか。
そのお悩みの原因は、皮膚の下にある毛細血管が透けて見える「赤クマ」かもしれません。赤クマは、寝不足や目の疲れによる血行不良、もともとの皮膚の薄さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って現れます。
この記事では、多くの女性を悩ませる赤クマの正体と、その根本的な原因となる生活習慣について詳しく解説します。
さらに、今日からご自身で始められるセルフケアや食事による改善策、そして美容クリニックでの対処法まで、具体的な改善アプローチを丁寧に紹介していきます。
あなたを悩ませる「赤クマ」の正体とは
鏡を見るたびに気になる目の下の赤み。これが「赤クマ」と呼ばれる状態です。多くの人がクマと聞くと青黒い色や茶色い色素沈着を想像しますが、赤みを帯びたクマも存在します。
まずは、この赤クマがどのようなものなのか、その基本的な知識を深めていきましょう。
目の下が赤く見える仕組み
目の下の皮膚は、顔の中でも特に薄くデリケートな部分です。その厚さは、頬の皮膚の3分の1程度しかありません。
この薄い皮膚の下には、「眼輪筋(がんりんきん)」という目を囲む赤い筋肉や、無数の毛細血管が網目のように張り巡らされています。
通常、これらの組織は皮膚の下に隠れていますが、何らかの原因で血流が滞ると、毛細血管がうっ血して膨張します。
その結果、薄い皮膚を通して血管や筋肉の色が透けて見え、目の下が赤く見えてしまうのです。これが赤クマの正体です。
赤クマと他のクマ(青クマ・茶クマ・黒クマ)との違い
クマにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や見た目が異なります。赤クマは、青クマと同じく血行不良が主な原因で発生する「血管性」のクマに分類されます。
青クマは血液中の酸素が不足し、血液が暗い色になることで青黒く見える状態です。一方、赤クマはうっ血により毛細血管そのものが透けて見える状態を指します。
他のクマとの違いを理解することが、適切なケアへの第一歩です。
主なクマの種類と特徴
| クマの種類 | 主な色 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 赤クマ | 赤みがかっている | 血行不良による毛細血管のうっ血・透け |
| 青クマ | 青黒い・紫色 | 血行不良による還元ヘモグロビンの増加 |
| 茶クマ | 茶色・くすんだ色 | メラニン色素の沈着(摩擦、紫外線など) |
| 黒クマ | 黒い・影に見える | 加齢による皮膚のたるみ・くぼみ |
自分のクマが赤クマかどうかのセルフチェック方法
自分のクマがどのタイプか判断に迷うこともあるでしょう。簡単なセルフチェックで、赤クマの可能性を確認できます。まず、鏡の前で目の下の皮膚を指で優しく下に引っ張ってみてください。
このとき、クマの色が薄くなる、または一時的に消えるようであれば、皮膚の下の血管が透けて見えている青クマや赤クマの可能性が高いです。
逆に、引っ張っても色の濃さが変わらない場合は、色素沈着による茶クマ、上を向くと薄くなる場合はたるみによる黒クマが考えられます。
赤クマは、特に目の下のふくらみのすぐ下あたりに赤みとして現れやすい傾向があります。
赤クマができやすい人の特徴
赤クマは誰にでもできる可能性がありますが、特になりやすい体質や生活習慣があります。例えば、もともと皮膚が薄く、色白の人は、血管や筋肉の色が透けやすいため赤クマが目立ちやすいです。
また、デスクワークで長時間パソコンと向き合う人や、スマートフォンを頻繁に使う人は、眼精疲労から血行不良に陥りやすく、赤クマのリスクが高まります。
ご自身の生活習慣や体質が当てはまるか、一度見直してみるのも良いでしょう。
なぜ赤クマはできるのか?主な原因を探る
赤クマが血管の透けによって起こることは分かりましたが、なぜそのような状態になってしまうのでしょうか。その背景には、日々の生活に潜むさまざまな原因が隠されています。
ここでは、赤クマを引き起こす主な原因を具体的に探っていきます。
血行不良と眼精疲労
赤クマの最大の原因は、目元の血行不良です。特に、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用は、目を酷使し、まばたきの回数を減少させます。
これにより、目の周りの筋肉が緊張し、血流が滞りやすくなります。血流が滞ると、毛細血管に血液が溜まってしまい、うっ血した状態になります。
このうっ血した血管が、薄い皮膚を通して赤く見えてしまうのです。度の合わないメガネやコンタクトレンズの使用も、目に負担をかけ、眼精疲労と血行不良を招く一因となります。
皮膚の薄さと遺伝的要因
目の下の皮膚の薄さは、生まれつきの体質や遺伝的な要因も大きく関係します。
ご両親や親族に、もともと皮膚が薄い方やクマが目立ちやすい方がいる場合、ご自身もその体質を受け継いでいる可能性があります。
皮膚が薄いと、健康な状態でも血管や筋肉の色が透けやすく、少しの血行不良でも赤クマとして顕著に現れてしまいます。
これは努力で変えることが難しい部分ですが、自分の肌質を理解し、より一層丁寧なケアを心がけることが大切です。
睡眠不足と不規則な生活
睡眠は、体の疲れを回復させ、血行を正常に保つために非常に重要な時間です。睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが乱れ、血管の収縮・拡張のコントロールがうまくいかなくなります。
その結果、全身の血行が悪化し、特に皮膚が薄い目元に影響が現れやすくなります。夜更かしや交代勤務など、不規則な生活リズムも同様に自律神経を乱す原因となり、赤クマを悪化させる要因です。
赤クマにつながる生活習慣チェック
| チェック項目 | 解説 | 改善の方向性 |
|---|---|---|
| 毎日PCやスマホを長時間使う | 眼精疲労を招き、目元の血行不良を引き起こす。 | 定期的な休憩、ブルーライトカット対策。 |
| 睡眠時間が6時間未満の日が多い | 自律神経の乱れから血行が悪化する。 | 睡眠時間の確保、就寝環境の整備。 |
| ストレスをため込みやすい | 緊張状態が続き、血管が収縮し血行不良に。 | リラックスできる時間を作り、趣味などで発散する。 |
ストレスとホルモンバランスの乱れ
精神的なストレスも、赤クマの大きな原因の一つです。ストレスを感じると、体は緊張状態になり、交感神経が優位になります。交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、血行が悪化しやすくなります。
また、過度なストレスはホルモンバランスの乱れにもつながります。
特に女性は、月経周期やライフステージの変化によってホルモンバランスが変動しやすく、血行不良や肌のコンディションに影響が出やすいです。
仕事や家庭での悩みなど、心当たりがある場合は、ストレスケアも赤クマ改善の一環として考える必要があります。
生活習慣を見直す 赤クマ改善への第一歩
赤クマの原因が日常生活に潜んでいる以上、その改善には生活習慣の見直しが欠かせません。特別な治療を始める前に、まずは日々の暮らし方を見直すことから始めてみましょう。
少しの工夫と意識が、赤クマの目立たない健やかな目元へと導きます。
質の良い睡眠を確保するための工夫
単に長く眠るだけでなく、「質の良い睡眠」をとることが重要です。質の良い睡眠は、心身の疲労を回復させ、自律神経のバランスを整え、血行を促進します。
就寝前は、スマートフォンやパソコンの画面を見るのを控えましょう。画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させ、寝つきを悪くする原因となります。
代わりに、温かい飲み物を飲んだり、好きな音楽を聴いたりしてリラックスする時間を設けるのがおすすめです。寝室の温度や湿度、寝具なども、快適な睡眠環境を整える上で大切な要素です。
バランスの取れた食事と栄養素
体は、私たちが食べたもので作られています。健やかな肌と良い血行を保つためには、バランスの取れた食事が基本です。
特に、体を温める食材や血行を促進する栄養素を積極的に摂ることが、赤クマの改善につながります。逆に、体を冷やす食べ物や飲み物は、血行を悪化させる可能性があるため、摂りすぎには注意が必要です。
インスタント食品や偏った食事は避け、多様な食材から栄養を摂ることを心がけましょう。具体的な食材については後の章で詳しく解説します。
効果的なストレス解消法
現代社会でストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に発散する方法を見つけることは可能です。自分に合ったストレス解消法をいくつか持っておくと、心身のバランスを保ちやすくなります。
例えば、軽い運動は血行を促進し、気分転換にもなります。ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、無理なく続けられるものから始めてみましょう。
また、趣味に没頭する時間や、友人と話す時間も、心をリフレッシュさせるのに役立ちます。一日の終わりにゆっくり湯船に浸かることも、心身のリラックスと血行促進の両方に効果的です。
喫煙と飲酒が与える影響
喫煙は、赤クマ改善を目指す上で大きな妨げとなります。タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、全身の血行を著しく悪化させます。
特に、目元のような細い毛細血管は影響を受けやすく、赤クマを悪化させる直接的な原因となります。
また、喫煙は肌のビタミンCを大量に破壊し、肌のハリや弾力を失わせるため、長期的に見ても美容への悪影響は計り知れません。
アルコールの過剰摂取も、睡眠の質を低下させたり、体内の水分バランスを崩したりするため、適量を心がけることが大切です。
自宅でできる赤クマ対策セルフケア
生活習慣の見直しと並行して、日々のセルフケアで目元に直接アプローチすることも効果的です。高価な化粧品や器具がなくても、自宅で手軽に始められるケアはたくさんあります。
ここでは、赤クマ改善に役立つ具体的なセルフケア方法を紹介します。
目元を温めるホットタオルの効果
目元の血行不良を改善する最も手軽で効果的な方法の一つが、ホットタオルで温めることです。蒸しタオルで目元をじんわりと温めることで、緊張した筋肉がほぐれ、滞っていた血流がスムーズになります。
これにより、うっ血が緩和され、赤クマが目立ちにくくなります。リラックス効果も高いため、一日の終わりの疲れ目ケアとして習慣にするのがおすすめです。
ホットタオルの作り方と使い方
| 手順 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| タオルを水で濡らし、固く絞る | 水が滴らない程度にしっかりと絞ります。 | – |
| 電子レンジで30秒~1分ほど加熱 | ラップで包むか、耐熱皿に乗せて加熱します。 | 加熱しすぎに注意。やけどしない温度か確認する。 |
| 閉じたまぶたの上に優しく乗せる | 心地よいと感じる温度で5分ほどリラックスします。 | 熱すぎると感じたら、少し冷ましてから使用する。 |
優しく行う目元のマッサージ方法
マッサージは血行促進に有効ですが、目の周りの皮膚は非常にデリケートなため、やり方には注意が必要です。強い力で擦ると、かえって皮膚にダメージを与え、色素沈着(茶クマ)の原因になりかねません。
必ず、滑りを良くするためのアイクリームや乳液、オイルなどを使い、薬指の腹で優しく行うのがポイントです。
ピアノを弾くようなタッチで、目頭からこめかみに向かって優しくツボを押したり、リンパを流すように滑らせたりする程度に留めましょう。
保湿と紫外線対策の重要性
目の周りの皮膚が乾燥すると、バリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。また、肌の透明感が失われることで、下の血管がより目立ちやすくなることもあります。
アイクリームなどを使って、目元の保湿を徹底しましょう。セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分が配合されたものがおすすめです。
さらに、紫外線は肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンを破壊し、皮膚を薄くする原因になります。
季節を問わず、日中外出する際は、日焼け止めやUVカット機能のあるサングラス、帽子などで目元の紫外線対策を忘れないようにしましょう。
赤クマを隠すメイクのコツ
根本的な改善には時間がかかりますが、メイクを工夫することで赤クマを上手にカバーし、見た目の印象を明るくすることができます。
赤みを補正するためには、反対色である「グリーン」や、肌なじみの良い「イエロー」系のコントロールカラーやコンシーラーを使うのが効果的です。
コンシーラーを塗る際は、厚塗りにならないよう注意してください。クマの部分に少量置き、指の腹で優しく叩き込むようにしてなじませると、自然にカバーできます。
ファンデーションは薄めに仕上げ、ハイライトを効果的に使うと、光で影を飛ばし、より明るい目元を演出できます。
食事からアプローチする赤クマ改善
外側からのケアだけでなく、内側からのケア、つまり食事も赤クマ改善には非常に重要です。特定の栄養素を意識して摂ることで、血行を促進し、健やかな肌を育むことができます。
ここでは、赤クマ対策に役立つ食べ物や栄養素について詳しく見ていきましょう。
血行促進に役立つ食べ物
血行を良くするためには、体を温め、血液をサラサラに保つ食材を積極的に食事に取り入れることが大切です。特に、香味野菜やスパイスは血行促進効果が期待できます。
また、ビタミンEは血管を広げて血流を改善する働きがあるため、赤クマに悩む方にはぜひ摂ってほしい栄養素です。
血行促進が期待できる食材
| 食材カテゴリ | 具体的な食材例 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 香味野菜 | 生姜、ニンニク、ネギ、玉ねぎ | 体を温め、血の巡りを良くする。 |
| ビタミンE | アーモンド、かぼちゃ、アボカド | 血管を拡張させ、血流を改善する。 |
| 青魚(EPA・DHA) | サバ、イワシ、アジ | 血液をサラサラに保つ。 |
貧血予防と鉄分の摂取
貧血気味で血液中のヘモグロビンが不足すると、体は効率よく酸素を運べなくなり、血行不良に陥りやすくなります。これが青クマや赤クマの原因となることがあります。
特に女性は月経により鉄分が不足しがちなので、意識的に摂取することが重要です。鉄分には、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と、野菜や豆類に含まれる「非ヘム鉄」があります。
ヘム鉄の方が吸収率が高いですが、非ヘム鉄もビタミンCと一緒に摂ることで吸収率がアップします。
抗酸化作用のある栄養素
私たちの体は、呼吸するだけでも活性酸素を発生させ、細胞を酸化させてしまいます。
この酸化が、肌の老化や血行不良の一因となります。ビタミンCやビタミンA、ポリフェノールといった抗酸化作用のある栄養素は、この活性酸素から体を守り、若々しい血管と肌を保つのに役立ちます。
色の濃い緑黄色野菜や果物に多く含まれているので、日々の食事に彩りを加えることを意識してみましょう。
体を冷やす食べ物と飲み物への注意
血行を促進する食材がある一方で、体を冷やし、血行を悪化させてしまう食べ物もあります。特に、夏野菜や南国の果物、冷たい飲み物や食べ物は、摂りすぎると内臓から体を冷やしてしまいます。
もちろん、全く食べてはいけないわけではありませんが、赤クマが気になる場合は、食べる量や頻度を調整したり、加熱調理するなどの工夫をすると良いでしょう。
体を冷やしやすい食品の例
| カテゴリ | 具体的な食品例 | 取り入れる際の工夫 |
|---|---|---|
| 夏野菜 | きゅうり、トマト、なす | 加熱調理する(スープ、炒め物など) |
| 南国の果物 | バナナ、パイナップル、マンゴー | 常温で食べる、量を控えめにする |
| 冷たい飲食物 | アイスクリーム、冷たいジュース | 温かい飲み物を選ぶ、氷を入れない |
美容クリニックで相談できる赤クマの対処法
セルフケアや生活習慣の改善を続けてもなかなか赤クマが良くならない場合や、より積極的に改善したい場合は、美容クリニックに相談するという選択肢もあります。
専門家の診断のもと、自分の状態に合った対処法を提案してもらえます。ここでは、一般的に行われる赤クマへのアプローチをいくつか紹介します。
カウンセリングの重要性
まず大切なのは、専門の医師によるカウンセリングを受けることです。自己判断で「赤クマ」だと思っていても、実際には他の種類のクマが混在しているケースや、別の原因が隠れている可能性もあります。
医師が肌の状態や骨格、生活習慣などを総合的に診察し、なぜクマができているのかを正確に診断してくれます。
その上で、どのような対処法が適しているのか、メリットやデメリット、費用などについて詳しく説明を受け、納得した上で方針を決めることが重要です。
光治療(IPL)によるアプローチ
IPL(Intense Pulsed Light)という特殊な光を肌に照射する治療法です。この光は、赤みの原因であるヘモグロビンに反応し、余分な毛細血管にダメージを与えて目立ちにくくする効果が期待できます。
また、IPLは肌全体のコラーゲン生成を促す効果もあるため、肌にハリが出て、血管が透けにくくなるという副次的な効果も見込めます。
ダウンタイムがほとんどなく、施術後すぐにメイクができる手軽さも特徴です。
レーザー治療の選択肢
レーザー治療も、特定の波長を持つ光を使って赤みの原因にアプローチする方法です。
光治療よりもターゲットに対してピンポイントで作用させることができ、血管の状態によってはより高い効果が期待できる場合があります。
使用するレーザーの種類によって特徴が異なるため、医師が肌の状態やクマの原因を診断し、最適な機器を選択します。施術後は一時的に赤みや腫れが出ることがありますが、通常は数日で落ち着きます。
クリニックでの主な対処法の比較
| 対処法 | アプローチの概要 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 光治療(IPL) | 幅広い波長の光を照射し、血管やメラニンに穏やかに作用させる。 | ダウンタイムが少ない。肌全体の改善も期待できる。 |
| レーザー治療 | 特定の波長の光で、原因となる血管に直接アプローチする。 | よりピンポイントな効果が期待できる。 |
| 注入治療 | ヒアルロン酸などを注入し、皮膚に厚みを出す、または窪みを埋める。 | 血管を物理的に隠す。たるみが原因の黒クマにも有効。 |
注入治療(ヒアルロン酸など)の可能性
赤クマの原因が、皮膚の薄さや加齢による目の下のくぼみにもある場合、ヒアルロン酸などの注入治療が選択肢になることもあります。
目の下の皮膚と血管の間にヒアルロン酸を注入することで、物理的に皮膚に厚みを持たせ、血管が透けて見えるのを防ぎます。
また、くぼみを埋めることで影(黒クマ)も同時に改善できる場合があります。ただし、注入する量や位置には繊細な技術が求められるため、経験豊富な医師のもとで施術を受けることが大切です。
赤クマ改善のために知っておきたいこと
赤クマの改善には、原因を理解し、適切なケアを継続することが大切です。焦らず、じっくりと自分の体と向き合っていく姿勢が、最終的なゴールへの近道となります。
最後に、改善を目指す上で心に留めておきたいポイントをいくつかお伝えします。
改善には時間が必要
生活習慣の改善やセルフケアを始めても、赤クマはすぐに消えるわけではありません。体の内側から体質を改善していくアプローチは、効果が現れるまでに数週間から数ヶ月単位の時間が必要です。
すぐに結果が出ないからといって諦めず、根気強くケアを続けることが何よりも重要です。日々の小さな変化を見つけながら、楽しみながら取り組むと続けやすくなるでしょう。
専門家への相談タイミング
セルフケアを続けても一向に改善しない、むしろ悪化しているように感じる、あるいはクマのせいで精神的に大きなストレスを感じているといった場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することを検討しましょう。
皮膚科や美容クリニックの医師は、クマに関する多くの知識と経験を持っています。客観的な視点からアドバイスをもらうことで、新たな解決策が見つかるかもしれません。
再発防止のための継続的なケア
一度赤クマが改善しても、原因となった生活習慣に戻ってしまえば、再発する可能性があります。改善された状態を維持するためには、良い習慣を継続することが大切です。
赤クマの改善を通して得た知識や習慣は、目元だけでなく、全身の健康や美容にとってもプラスになります。
再発防止のポイント
- 十分な睡眠時間を確保する
- バランスの取れた食事を心がける
- 定期的に目元を温めて血行を促す
- ストレスを上手に発散する
- 目元の保湿と紫外線対策を徹底する
心身の健康が美しさにつながる
目の下のクマは、体からのサインであるとも言えます。疲れや不調が、目に見える形で現れているのです。赤クマのケアは、単に見た目を良くするためだけのものではありません。
自分の生活習慣や健康状態を見つめ直す良い機会です。心と体の両方が健康であってこそ、本当の美しさは生まれます。
目元のケアをきっかけに、ご自身の体を大切にするライフスタイルを築いていきましょう。
赤クマに関するよくある質問
ここでは、赤クマに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- Q. 赤クマは自然に治りますか?
-
原因が一時的な寝不足や眼精疲労である場合、十分な休息をとることで自然に軽快することはあります。
しかし、慢性的な血行不良や生活習慣の乱れ、遺伝的な皮膚の薄さが原因の場合、何もしなければ改善は難しいことが多いです。
生活習慣の見直しや適切なセルフケアを行うことで、改善を目指すことが大切です。
- 赤クマに効く市販のアイクリームはありますか?
-
市販のアイクリームの中には、血行促進効果が期待できるビタミンE誘導体や、保湿効果の高いセラミド、ヒアルロン酸などが配合されているものがあります。
これらは赤クマのセルフケアの一環として有効です。ただし、クリームだけで根本的に治すことは難しく、あくまで生活習慣の改善と併用することが基本となります。
選ぶ際は、保湿力を重視し、肌に刺激の少ないものを選びましょう。
- 子供にも赤クマはできますか?
-
はい、子供にも赤クマはできます。子供は大人に比べて皮膚が薄いため、もともと血管が透けて見えやすいです。
アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎などで目元をこする癖があると、その刺激でうっ血し、赤クマや茶クマの原因になることがあります。
また、夜更かしやゲームのしすぎによる眼精疲労も原因となり得ます。気になる場合は、まず小児科や皮膚科に相談することをおすすめします。
- 赤クマを悪化させる行動はありますか?
-
目元を強くこする、擦るという行為は最も避けるべきです。摩擦は皮膚にダメージを与え、色素沈着(茶クマ)を併発させる原因になります。
また、体を冷やすこと、長時間のデジタルデバイス使用、睡眠不足、ストレスを溜め込むことなどは、すべて血行不良につながり、赤クマを悪化させる可能性があります。
クレンジングやマッサージの際は、とにかく優しく触れることを徹底してください。
参考文献
PARK, Kui Young, et al. Treatments of infra-orbital dark circles by various etiologies. Annals of dermatology, 2018, 30.5: 522-528.
CHATTERJEE, Manas, et al. A study of epidemiological, etiological, and clinicopathological factors in periocular hyperpigmentation. Pigment International, 2018, 5.1: 34-42.
VRCEK, Ivan; OZGUR, Omar; NAKRA, Tanuj. Infraorbital dark circles: a review of the pathogenesis, evaluation and treatment. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2016, 9.2: 65-72.
MAC-MARY, Sophie, et al. Identification of three key factors contributing to the aetiology of dark circles by clinical and instrumental assessments of the infraorbital region. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2019, 919-929.
GOLDMAN, Alberto; GOLDUST, Mohamad; WOLLINA, Uwe. Periorbital hyperpigmentation—Dark circles under the eyes; treatment suggestions and combining procedures. Cosmetics, 2021, 8.2: 26.
JAGE, Mithali; MAHAJAN, Sunanda. Clinical and dermoscopic evaluation of periorbital hyperpigmentation. Indian Journal of Dermatopathology and Diagnostic Dermatology, 2018, 5.1: 42-47.
FATIN, Amira M., et al. Classification and characteristics of periorbital hyperpigmentation. Skin Research and Technology, 2020, 26.4: 564-570.
MATSUI, Mary S., et al. Physiological and lifestyle factors contributing to risk and severity of peri-orbital dark circles in the Brazilian population. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90.4: 494-503.
RAJABI‐ESTARABADI, Ali, et al. Effectiveness and tolerance of multicorrective topical treatment for infraorbital dark circles and puffiness. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.2: 486-495.
AWAL, Guneet, et al. Illuminating the shadows: an insight into periorbital hyperpigmentation. Pigment International, 2024, 11.2: 67-78.