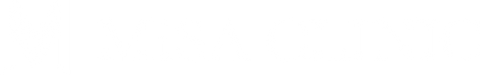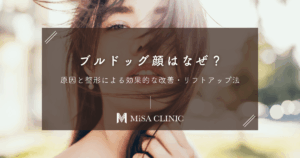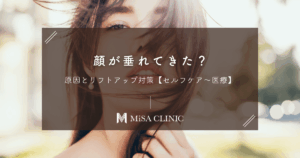顔のたるみを取る意外な習慣とは?今日から見直せる改善ポイント

フェイスラインのぼやけや、ほうれい線は年齢のせいだと諦めがちですが、実は顔のたるみは日々の何気ない習慣が原因で進行している可能性があります。
この記事では、顔のたるみがなぜ起こるのかという根本的な原因から、無意識に行っている意外なNG習慣、そして今日から始められる改善策までを詳しく解説します。
顔のたるみが生まれる根本的な原因
顔のたるみは単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。
肌の内部で何が起こっているのかを理解することが、効果的な対策への近道です。ここでは、たるみを引き起こす主な原因について掘り下げていきます。
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
肌のハリや弾力は、皮膚の真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといった線維状のたんぱく質によって支えられています。これらは肌の構造を保つ重要な土台です。
しかし、年齢を重ねると、これらのたんぱく質を生成する線維芽細胞の働きが衰えてきます。
その結果、コラーゲンの質が低下し、エラスチンも変性・減少するため肌の弾力が失われ、重力に逆らえずにたるみが生じるのです。
肌の構造とハリの関係
| 構造 | 特徴 |
|---|---|
| 表皮 | 肌の最も外側。バリア機能を持つ。 |
| 真皮 | 表皮の内側。コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸が存在し、肌のハリを司る。 |
| 皮下組織 | 真皮のさらに奥。主に脂肪細胞からなり、クッションの役割を持つ。 |
紫外線が肌の弾力に与える影響
紫外線は、たるみの大きな原因の一つとして知られています。なかでも波長の長いUVA(紫外線A波)は、雲や窓ガラスを通り抜けて肌の奥深く、真皮層にまで到達します。
このUVAが、肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンを破壊、または変性させてしまうのです。この現象を「光老化」と呼びます。
長年にわたり紫外線を浴び続けると肌の弾力は徐々に失われ、深いたるみやシワとして現れます。
表情筋の衰えとたるみの関係
顔には約30種類以上もの表情筋があり、これらの筋肉が皮膚や皮下脂肪を支えています。
しかし、日常生活で使われる表情筋は全体の約30%程度といわれています。あまり使われない筋肉は、体の筋肉と同じように年齢とともに衰えていきます。
表情筋が衰えるとその上にある皮膚や脂肪を支えきれなくなり、雪崩のように垂れ下がってしまうのです。
口角が下がったり、フェイスラインがもたついたりするのは、表情筋の衰えが大きく関係しています。
たるみの原因別の特徴
| 原因 | 特徴 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 加齢 | 肌全体のハリが失われ、細かいシワも目立つ。 | エイジングケア成分配合の化粧品、栄養バランスの良い食事。 |
| 紫外線 | ゴワつきや深いシワを伴うたるみ。 | 日焼け止めの徹底、帽子や日傘の活用。 |
| 表情筋の衰え | フェイスラインのもたつき、ほうれい線が目立つ。 | 表情筋エクササイズ、意識して表情を動かす。 |
皮下脂肪の増減と分布の変化
顔の皮下脂肪も、たるみに大きく影響します。若い頃は頬の高い位置にある皮下脂肪が加齢とともに減少し、下垂するため、ほうれい線やマリオネットラインを目立たせます。
また、急激な体重増加で脂肪がつきすぎると、その重みで皮膚が伸びてたるみの原因になります。逆に、無理なダイエットで急激に痩せると脂肪が減った分だけ皮膚が余ってしまい、たるんでしまうケースもあります。
脂肪の量だけでなく、その分布の変化もたるみの重要な要因です。
【要注意】無意識にたるみを加速させる意外な生活習慣
自分では良かれと思ってやっていることや、無意識の癖が実は顔のたるみを進行させているかもしれません。
ここでは、日常生活に潜む意外な落とし穴を指摘します。心当たりがないか、ご自身の習慣をチェックしてみましょう。
スマートフォンやPCの長時間利用が招く「スマホ顔」
スマートフォンやパソコンを長時間使う際、多くの人がうつむき加減の姿勢になります。
この姿勢を続けると首から顎にかけての筋肉が常に緊張し、血行が悪化します。また、下を向くことで重力の影響を強く受け、頬や顎の肉が下がりやすいです。
さらに、画面を凝視すると無表情な時間が長くなり、表情筋が使われずに衰える原因にもなります。
これらの要因が重なり、フェイスラインのもたつきや二重あご、首のシワといった「スマホ顔」と呼ばれる状態を引き起こします。
片側だけで噛む癖が顔の歪みとたるみを生む
食事の際に、無意識にいつも同じ側でばかり噛んでいる方もいらっしゃいます。
片側だけで噛む癖があると、よく使う側の筋肉ばかりが発達し、使わない側の筋肉は衰えていきます。この筋肉のアンバランスが顔の左右差、つまり歪みを生み出します。
そして、衰えた側の筋肉は皮膚や脂肪を支える力が弱まるため、片側の頬だけがたるんだり、ほうれい線が深くなったりする原因になります。
顔の歪みは、見た目の印象を大きく左右する重要な問題です。
たるみを招くNG習慣チェック
| 習慣 | たるみへの影響 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| 長時間のスマホ操作 | 下向き姿勢による重力の影響、無表情による筋力低下。 | PC・スマホの目線を上げる、定期的に休憩する。 |
| 片側噛み | 顔の筋肉のアンバランス、片側のたるみ。 | 左右均等に噛む意識、ガムを噛んで練習する。 |
| うつ伏せ・横向き寝 | 肌への物理的圧迫、コラーゲン線維の乱れ。 | 仰向けで寝る、シルクなどの摩擦が少ない枕カバーを選ぶ。 |
うつ伏せ寝・横向き寝が肌にかける物理的圧力
睡眠中の姿勢も、たるみに影響を与えます。特に、うつ伏せ寝や横向き寝は、長時間にわたって顔の片側に圧力がかかり続けます。
この圧迫により肌のハリを保つコラーゲン線維が押しつぶされたり、乱れたりして、シワやたるみの原因になります。
朝起きたときに顔に寝跡がくっきりとついているときは、肌の弾力が低下しているサインかもしれません。
理想的なのは、顔に圧力がかからない仰向けの姿勢で寝ることです。
急激なダイエットによる皮膚のたるみ
短期間で大幅に体重を落とすような無理なダイエットは、体に大きな負担をかけるだけでなく、顔のたるみを引き起こす大きな原因です。
体重が急激に減少すると皮下脂肪は減りますが、一度伸びた皮膚はすぐには収縮しません。風船が一度膨らむとしぼんでもシワシワになるように、皮膚が余ってしまい、たるみとして現れるのです。
特に、食事制限だけのダイエットは、肌の材料となるたんぱく質やビタミンが不足しがちで、肌のハリを一層失わせる結果につながります。
食生活から見直す!ハリのある肌を作る栄養素
美しい肌は外側からのケアだけでなく、内側からの栄養によっても作られます。日々の食事が、肌の土台を築きます。
たんぱく質|不足はコラーゲンの材料不足に直結
肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンは、たんぱく質の一種です。そのため食事からのたんぱく質摂取が不足すると肌の材料が足りなくなり、新しいコラーゲンを生成できなくなります。
肉や魚、卵や大豆製品、乳製品など、良質なたんぱく質を毎食バランス良く取り入れるのが大切です。
特に、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質を偏りなく摂取するように心がけましょう。
ビタミンC|抗酸化作用とコラーゲン生成のサポート
ビタミンCはコラーゲンの生成に必要不可欠な栄養素です。たんぱく質を摂取しても、ビタミンCが不足していると、効率的にコラーゲンを合成できません。
また、ビタミンCには強力な抗酸化作用があり、紫外線やストレスによって発生する活性酸素から肌を守り、光老化を防ぐ働きも期待できます。
パプリカやブロッコリー、キウイフルーツや柑橘類などに多く含まれています。
ハリを作る栄養素と多く含まれる食品
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | コラーゲン・エラスチンの材料になる。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの合成を助け、抗酸化作用を持つ。 | パプリカ、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンA | 肌のターンオーバーを促進し、ヒアルロン酸の生成を助ける。 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
ビタミンA|肌のターンオーバーを整える
ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康を維持するために重要な働きをします。肌の生まれ変わりであるターンオーバーを正常に保ち、ごわつきを防ぎます。
また、真皮でのヒアルロン酸の生成を促し、肌の水分量を高める効果も期待できるため、乾燥によるたるみの予防にもつながります。
レバーやうなぎ、緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃなど)から摂取できます。
イソフラボン|女性ホルモン様作用でハリを保つ
大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造と働きを持つことで知られています。
エストロゲンはコラーゲンの生成を促し、肌のハリや潤いを保つ働きがあります。年齢とともにエストロゲンが減少すると、肌のたるみが進行しやすくなります。
このため、納豆や豆腐、豆乳などの大豆製品を日常的に摂取すると、肌の弾力維持をサポートすることが期待できます。
今すぐできる!顔のたるみ改善セルフケア
専門的な治療を受ける前に、日常生活の中でできることはたくさんあります。
コストをかけずに今日からすぐに始められるセルフケアを習慣にすると、たるみの進行を食い止め、若々しい印象を保てます。
正しい姿勢を意識するだけで顔の印象は変わる
猫背で頭が前に突き出た姿勢は首や肩の血行を悪くするだけでなく、顔のたるみを助長します。
頭の重さは約5kgもあり、この重さを首周りの筋肉だけで支えるため大きな負担がかかります。
意識して背筋を伸ばし、耳と肩が一直線になるような正しい姿勢を保つと首への負担が減り、フェイスラインがすっきりとします。
デスクワーク中は特に意識して、時々立ち上がってストレッチをするなど工夫しましょう。
表情筋を鍛える簡単エクササイズ
普段あまり使わない表情筋を意識的に動かし、衰えを防ぎましょう。
過度なマッサージは肌への摩擦になりますが、筋肉そのものを動かすエクササイズが有効です。無理のない範囲で、毎日少しずつ続けることが大切です。
表情筋エクササイズ
| エクササイズ名 | ターゲット | 方法 |
|---|---|---|
| あいうえお体操 | 顔全体の筋肉 | 口を大きく開けて「あ・い・う・え・お」とゆっくり発音する。 |
| 頬ぷくぷく体操 | 頬の筋肉(頬筋) | 口を閉じて、頬を左右交互に風船のように膨らませる。 |
| 舌回し体操 | 口周り、フェイスライン | 口を閉じたまま、歯茎の表面をなぞるように舌をゆっくり回す。 |
保湿ケアの徹底が乾燥による小じわ・たるみを防ぐ
肌が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
また、乾燥した肌はハリを失い、細かい「ちりめんじわ」ができやすくなります。この小じわが、やがて深いたるみへとつながるケースも多いです。
洗顔後はすぐに化粧水で水分を補給し、乳液やクリームなどの油分でしっかりと蓋をして、水分が蒸発するのを防ぎましょう。
セラミドやヒアルロン酸など、保湿効果の高い成分が配合されたスキンケア製品を選ぶのがおすすめです。
紫外線対策は一年中行うのが基本
たるみの大きな原因である「光老化」を防ぐためには、紫外線対策が何よりも重要です。
紫外線は夏だけでなく、一年中降り注いでいます。曇りの日でも、室内でもUVAは届きます。そのため季節や天候に関わらず、毎日日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。
紫外線対策のポイント
- SPF・PA表示のある日焼け止めを毎日使用する
- 2〜3時間おきに塗り直す
- 帽子、日傘、サングラスなども併用する
- 顔だけでなく、首やデコルテも忘れずにケアする
スキンケア製品の選び方と正しい使い方
毎日のスキンケアは、たるみ予防・改善の基本です。しかし、ただ高価な製品を使えば良いというわけではありません。
自分の肌の状態に合った成分を知り、正しい方法で使うことが、効果を最大限に引き出すポイントです。
たるみケアに有効な成分
たるみケアを目的とする場合、肌のハリや弾力に働きかける成分が配合されたスキンケア製品を選ぶことが重要です。
化粧品の成分表示を確認し、目的に合ったものを選びましょう。
たるみケアに有効なスキンケア成分
| 成分名 | 期待される効果 |
|---|---|
| レチノール(ビタミンA) | ターンオーバー促進、コラーゲン・エラスチン生成サポート |
| ビタミンC誘導体 | コラーゲン生成サポート、抗酸化作用 |
| ナイアシンアミド | コラーゲン生成促進、バリア機能改善 |
| ペプチド | コラーゲンやエラスチンの働きをサポート |
化粧水や美容液の浸透を高めるハンドプレス
化粧水や美容液を肌につける際、パンパンと叩き込むようにパッティングするのは逆効果です。肌への刺激となり、赤みや色素沈着の原因になる場合があります。
おすすめは、顔全体に優しくなじませた後、手のひらで顔を包み込むようにして軽く押さえる「ハンドプレス」です。
手のぬくもりで血行が促進され、角質層への成分の浸透を助けます。数秒間、ゆっくりと圧をかけるように行いましょう。
肌を摩擦しない優しいクレンジング・洗顔方法
肌への摩擦は、たるみを悪化させる大きな要因です。毎日のクレンジングや洗顔でゴシゴシとこするのは絶対にやめましょう。
クレンジング剤は十分な量を使い、指の腹で優しく円を描くようになじませます。洗顔料はしっかりと泡立て、泡をクッションにして肌の上を転がすように洗うのがポイントです。
熱いお湯は肌の乾燥を招くため、洗い流す際も32~34℃程度のぬるま湯を使い、シャワーを直接顔に当てるのは避けましょう。
タオルで水分を拭き取る時も、押さえるように優しく行います。
ストレスや睡眠不足が「お疲れ顔」を作る?心の状態と肌のつながり
肌は「内臓の鏡」ともいわれますが、実は「心の鏡」でもあります。
忙しい毎日の中で見過ごしがちなストレスや睡眠不足が、知らず知らずのうちに肌の老化を加速させ、疲れた印象の「お疲れ顔」、つまりたるみを作っているかもしれません。
コルチゾールが肌の老化を早める
人間はストレスを感じると、対抗するために「コルチゾール」というホルモンを分泌します。
コルチゾールは短期的には体を守る働きをしますが、慢性的なストレスによって過剰に分泌され続けると、コラーゲンの生成を抑制したり、分解を促進したりすることが分かっています。
これによって肌の弾力が失われ、たるみやシワの進行が早まる可能性があります。仕事や人間関係のストレスが、肌年齢に直接影響を与えているのです。
ストレスが肌に与える影響
| 要因 | 体内で起こること | 肌への影響 |
|---|---|---|
| 精神的ストレス | コルチゾールの過剰分泌 | コラーゲン減少、肌の弾力低下 |
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下 | 肌の修復・再生が滞る、ターンオーバーの乱れ |
| 自律神経の乱れ | 交感神経が優位になる | 血管収縮、血行不良、くすみ、栄養不足 |
睡眠中の成長ホルモンが肌再生の鍵
私たちの肌は、眠っている間に修復・再生されます。
入眠後の最初の3時間ほどの深いノンレム睡眠中に多く分泌される「成長ホルモン」が、日中に受けたダメージを修復し、肌のターンオーバーを促進する重要な役割を担っています。
睡眠時間が不足したり眠りが浅かったりすると、この成長ホルモンの分泌が十分に行われません。
その結果、肌の再生が滞り、たるみやくすみ、肌荒れなどのトラブルにつながるのです。「睡眠は最高の美容液」といわれるのは、このためです。
リラックスできる時間を作り、心と肌をいたわる
たるみケアのためには、スキンケアだけでなく「メンタルケア」も重要です。毎日数分でも、自分が心からリラックスできる時間を作りましょう。
好きな音楽を聴く、温かいお風呂にゆっくり浸かる、アロマを焚く、深呼吸をするなど、方法は問いません。
心を落ち着かせ、ストレスをリセットするとコルチゾールの過剰分泌を抑え、肌への悪影響を減らすことにつながります。
自分の心と体をいたわる時間が、結果的にハリのある肌を育むのです。
自律神経の乱れが血行不良とくすみにつながる
ストレスや不規則な生活は、自律神経のバランスを乱します。
自律神経は、体を活動的にする交感神経と、リラックスさせる副交感神経から成り立っています。ストレス状態が続くと交感神経が優位になり、血管が収縮して血行が悪化します。
血行不良になると、肌細胞に必要な酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなり、老廃物の排出も滞ります。
この状態が、顔色を悪く見せるくすみや、肌のハリ低下、たるみの原因となるのです。
美容医療という選択肢を考える前に知っておきたいこと
セルフケアを続けても改善が見られない場合や、より積極的な改善を望む場合、美容医療が選択肢の一つになります。
しかし、治療を受ける前には、その役割や種類、注意点について正しく理解しておくことが重要です。ここでは、美容医療を検討する上での基礎知識を解説します。
セルフケアの限界と美容医療の役割
セルフケアは、たるみの「予防」や「進行を遅らせる」上で非常に重要です。
しかし、すでに深く刻まれたシワや、大きく垂れ下がってしまったたるみを、化粧品やマッサージだけで元の状態に戻すには限界があります。
美容医療は、セルフケアでは働きかけられない肌の奥深く(真皮層や筋膜、脂肪層など)に直接働きかけ、たるみの根本原因を改善することを目的とします。
セルフケアを土台としつつ、必要に応じて美容医療を組み合わせると、より効果を実感しやすいです。
たるみ治療の種類と特徴の概要
たるみ治療には、様々な方法があります。それぞれに特徴やダウンタイム(回復期間)、期待できる効果が異なります。
代表的な治療法を確認し、自分の悩みや生活スタイルに合ったものがどれかを考えましょう。
主な美容医療の比較(概要)
| 治療法 | アプローチ方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| レーザー・光治療 | 熱エネルギーでコラーゲン生成を促す | 肌のハリ改善、比較的ダウンタイムが短い |
| 高周波(RF) | 高周波で真皮層を加熱し、引き締める | 肌の引き締め、タイトニング効果 |
| ハイフ(HIFU) | 超音波で筋膜(SMAS)に熱を与え、引き上げる | リフトアップ効果、フェイスラインの改善 |
信頼できるクリニック選びのポイント
美容医療を受ける上で最も重要なのが、信頼できるクリニックと医師を選ぶことです。
価格の安さだけで選ぶのではなく、安全性や技術力、カウンセリングの質などを総合的に判断する必要があります。
クリニック選びのチェックポイント
- カウンセリングが丁寧で、悩みや希望をしっかり聞いてくれるか
- 治療のメリットだけでなく、リスクやデメリットも説明してくれるか
- 医師が皮膚や解剖学に関する知識と経験を豊富に持っているか
- 院内の衛生管理が徹底されているか
顔のたるみに関するよくある質問(Q&A)
顔のたるみを取るためには、毎日のコツコツとした努力の積み重ねが大切です。
姿勢の改善やエクササイズ、紫外線対策や保湿、正しい洗顔方法など、どれもぜひ取り入れていきたいところです。
ただ、いちどにすべてをやろうとすると負担となりやすいので、できることから少しづつ始めてみると良いでしょう。
- マッサージはたるみに効果がありますか?
-
やり方によっては効果も期待できますが、注意が必要です。強い力でゴシゴシこするようなマッサージは、肌への摩擦となり、かえってたるみや色素沈着を悪化させる可能性があります。
もし行う際は必ず滑りの良いクリームやオイルを使用し、非常に優しい力で、リンパの流れを意識して行う程度に留めましょう。
自己流の強いマッサージよりも、表情筋を鍛えるエクササイズの方が安全で効果的な場合があります。
- 若い年代でもたるみはできますか?
-
若い年代でもできます。たるみは加齢だけの問題ではありません。
20代や30代でも、長時間のスマートフォン使用による「スマホ顔」や、急激なダイエット、紫外線対策の不足や不規則な生活習慣などが原因で、たるみが現れるケースがあります。
特にフェイスラインのもたつきや、ほうれい線の始まりは、若年層でも見られるたるみのサインです。早いうちから生活習慣を見直すと、将来のたるみ予防につながります。
- たるみやすい人の特徴はありますか?
-
もともと皮膚が薄く柔らかい人、丸顔で皮下脂肪が多い人は、脂肪の重みでたるみやすい傾向があります。
また、姿勢が悪く猫背気味の人、紫外線対策を怠りがちな人、表情が乏しい人もたるみやすいといえます。
さらに、喫煙習慣は血行を悪化させ、肌の老化を加速させるため、たるみの大きなリスク要因です。
これらの特徴に当てはまる場合は、より意識的なケアが必要です。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
LIU, Xuan-jun; SULTAN, Muhammad Tipu; LI, Guang-shuai. Obesity, glycemic traits, lifestyle factors, and risk of facial aging: a Mendelian randomization study in 423,999 participants. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.5: 1005-1015.
GUNN, D. A., et al. Lifestyle and youthful looks. British Journal of Dermatology, 2015, 172.5: 1338-1345.
KIVILUOMA, Leena. Vital Face: Facial Exercises and Massage for Health and Beauty. Singing Dragon, 2013.
GUNN, David A.; CHRISTENSEN, Kaare. Skin aging and health. In: Textbook of Aging Skin. Springer, Berlin, Heidelberg, 2017. p. 551-562.
GUNN, David A.; CHRISTENSEN, Kaare. Skin aging and health. In: Textbook of Aging Skin. Springer, Berlin, Heidelberg, 2017. p. 551-562.
GLASGOW, A. M.; OVER, CHEEKS; ALEX, ASK. Understanding facial tissue ageing: A comprehensive approach to cell optimisation.
ADDOR, Flávia Alvim Sant’Anna; COTTA VIEIRA, Juliana; ABREU MELO, Camila Sirieiro. Improvement of dermal parameters in aged skin after oral use of a nutrient supplement. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2018, 195-201.
KNAGGS, Helen. Skin aging in the Asian population. In: Skin aging handbook. William Andrew Publishing, 2009. p. 177-201.