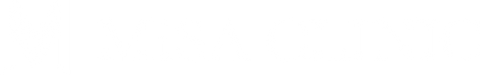顎の下のたるみを撃退!原因と効果的な改善方法【二重あご解消】

「なんだか顎のラインがぼやけてきた」「太っていないのに二重あごに見える」と感じてクリニックにいらっしゃる方が多いです。
そのお悩みの正体は、顎の下のたるみかもしれません。このたるみは、老けた印象や疲れた表情の原因となり、多くの方を悩ませます。
この記事では、顎の下にたるみが生じる原因を詳しく解説し、ご自身で取り組める効果的な改善方法から、美容クリニックでの専門的な治療まで、幅広くご紹介します。
正しい知識を身につけ、シャープなフェイスラインを取り戻しましょう。
顎の下のたるみによる印象とセルフチェック
顎の下のたるみは、美容面においてさまざまなネガティブな印象を与えてしまいます。
まずは、たるみが具体的にどのような影響を及ぼすのか、そしてご自身のたるみ度合いを客観的に把握する方法を確認していきましょう。
老けて見える・太って見える顔の印象
フェイスラインは顔の印象を大きく左右する重要なパーツです。顎の下がたるむと顔と首の境界線が曖昧になり、全体的にぼんやりとした印象を与えます。
このため実年齢よりも老けて見えたり、体重は変わらないのに太って見えたりするときがあります。
シャープなフェイスラインは若々しく、すっきりとした印象の基本です。
写真写りが気になる瞬間
普段はあまり気にならなくても、ふとした角度で撮影された写真を見て、顎の下のもたつきに愕然とするときがあるのではないでしょうか。
特に、少しうつむいた時や横から撮影された写真では、たるみが強調されやすいです。
集合写真で自分だけ顔が大きく見えたり、昔の写真と比べてフェイスラインの変化を感じたりするのも、たるみが原因かもしれません。
指でつまめる?たるみの簡単チェック方法
ご自身の顎の下のたるみ具合を確認してみましょう。簡単にできるセルフチェックです。
- 姿勢を正し、まっすぐ前を見る
- 顎の下の皮膚を、親指と人差し指で優しくつまむ
- つまんだ部分の厚みを確認する
このとき、2cm以上の厚みがある場合は、脂肪の蓄積や皮膚のたるみが進行している可能性があります。
あくまで目安ですが、現状を把握するきっかけとして試してみてください。
なぜできる?顎の下のたるみの原因
顎の下のたるみは単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。主な原因を理解すると、ご自身に合った対策を見つけやすくなります。
加齢による皮膚の弾力低下
私たちの皮膚のハリや弾力は、真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといった成分によって支えられています。
しかし、加齢に伴いこれらの成分は減少し、質も低下します。その結果、皮膚は弾力を失い、重力に逆らえずに垂れ下がってしまいます。
特に顎の下は皮膚が薄く、たるみの影響が現れやすい部位です。
加齢による肌の変化
| 変化する要素 | 20代との比較 | たるみへの影響 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 量・質ともに低下 | 肌のハリが失われる |
| エラスチン | 変性・減少し硬くなる | 弾力性が低下する |
| 皮下脂肪 | 位置が下がる・つきやすくなる | 重みでたるみを助長する |
姿勢の悪さが招く「スマホ首」
スマートフォンやパソコンの長時間利用で、無意識に頭を前に突き出した姿勢になっている方も多いでしょう。
このうつむき姿勢は「スマホ首」とも呼ばれ、首や肩への負担だけでなく、顎の下のたるみにも直結します。
首の前面にある広頸筋(こうけいきん)という筋肉が常に縮こまり、顎の下の皮膚が寄り集まるため、たるみやシワが定着しやすくなります。
体重の増減と脂肪の蓄積
顎の下は、もともと脂肪がつきやすい部位です。体重が増加すると顎の下にも皮下脂肪が蓄積し、その重みで皮膚が伸びてたるみが生じます。
また、急激なダイエットなどで体重が減少した場合、脂肪が減っても伸びてしまった皮膚はすぐには元に戻らず、たるみとして残ってしまうケースがあります。これを「皮膚の余り」と呼びます。
表情筋の衰えとリンパの滞り
顔には多くの表情筋がありますが、日常生活で使われるのはその一部です。特に顎周りの筋肉は意識しないと衰えがちです。
筋肉が衰えると、その上にある皮膚や脂肪を支える力が弱まり、たるみにつながります。
また、運動不足や姿勢の悪さは、首周りのリンパの流れを滞らせる原因にもなります。リンパの流れが悪いと老廃物や余分な水分が溜まり、むくみやたるみを引き起こします。
たるみを悪化させる習慣|生活習慣の見直し
何気なく行っている日常の習慣が、知らず知らずのうちに顎の下のたるみを助長している可能性があります。改善を目指すなら、まずは悪化させる原因となる習慣の見直しが重要です。
食事中の咀嚼回数が少ない
柔らかいものばかり食べていたり、よく噛まずに飲み込んだりする食生活は、口周りの筋肉、特に顎の筋肉を使う機会を減らしてしまいます。
咀嚼(そしゃく)は、顔全体の筋肉を動かす重要な運動です。噛む回数が減ると筋肉が衰え、フェイスラインがぼやける原因となります。
注意したい生活習慣と改善の方向性
| 悪化させる習慣 | 具体的な行動 | 改善の方向性 |
|---|---|---|
| 咀嚼不足 | 早食い、柔らかい食事中心 | 一口30回噛む、歯ごたえのある食材を選ぶ |
| 姿勢の悪さ | 猫背、スマホ首、頬杖 | 背筋を伸ばす、画面を目線の高さに |
| 合わない枕 | 高すぎる、または低すぎる枕 | 首のS字カーブを保てる高さの枕を選ぶ |
うつむき姿勢での長時間作業
デスクワークやスマートフォンの操作中に背中が丸まり、頭が前に出た姿勢を続けているかどうかも確認しましょう。この姿勢は、顎の下に常に圧力をかけ、皮膚をたるませる直接的な原因です。
定期的に休憩を取り、ストレッチをしたり、パソコンのモニターやスマートフォンの位置を目の高さに調整したりする工夫が必要です。
睡眠時の枕の高さが合っていない
毎日使う枕も、顎のたるみに影響を与えます。高すぎる枕は寝ている間ずっと顎を引いた状態になり、首の前面にシワやたるみを作り出します。
逆に低すぎる枕は頭に血が上りやすく、顔のむくみの原因になる場合があります。
理想的なのは、リラックスした状態で立った時のように、首の自然なS字カーブを保てる高さの枕です。
自宅でできる!セルフケアによる改善方法
専門的な治療を受ける前に、まずは自宅でできるケアから始めてみましょう。
継続するとたるみの予防と軽度の改善が期待できます。毎日少しずつでも続けることが大切です。
顎周りの筋肉を鍛える表情筋トレーニング
普段あまり使わない顎周りや首の筋肉を意識的に動かし、衰えを防ぎましょう。
過度なトレーニングは逆効果になる場合もあるため、無理のない範囲で行うと良いです。
おすすめ表情筋トレーニング
| トレーニング名 | 主な効果 | 方法 |
|---|---|---|
| 天井見上げ「あ・い・う・え・お」 | 首の前側の筋肉(広頸筋)を伸ばす | ゆっくり天井を見上げ、口を大きく開けて「あ・い・う・え・お」と発声する |
| 舌回しトレーニング | 舌骨筋群を鍛え、二重あごを内側から引き締める | 口を閉じたまま、歯茎の外側を舌でゆっくりとなぞるように回す(右回り・左回り) |
滞りを流すリンパマッサージ
リンパの流れを促して溜まった老廃物や水分を排出し、むくみを解消して、すっきりとしたフェイスラインを目指します。
マッサージを行う際は必ずクリームやオイルを使い、肌への摩擦を避けてください。
- 耳の下から鎖骨に向かって、首筋を優しくなでおろす
- 顎の骨に沿って、中心から耳の下に向かって指を滑らせる
- 最後に、再び耳の下から鎖骨へ流す
正しい姿勢を意識する
セルフケアの中で最も重要とも言えるのが、正しい姿勢の維持です。
立っている時も座っている時も、頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで、背筋をすっと伸ばしましょう。
特にスマートフォンを見る際は、画面を顔の高さまで持ち上げるように意識するだけで、顎の下への負担は大きく変わります。
スキンケアによる保湿とハリ対策
顔のスキンケアと同様に、首からデコルテにかけても保湿を徹底しましょう。
乾燥は肌のバリア機能を低下させ、あらゆる肌トラブルの原因となります。
コラーゲンやエラスチンの生成をサポートするレチノールやビタミンC誘導体、ペプチドなどが配合されたエイジングケア化粧品を首元まで使うのもハリを保つ上で効果的です。
たるみの種類によって適した方法は異なる?タイプ別見極め方
「顎の下のたるみ」と一言で言っても、実はその原因によっていくつかのタイプに分けられます。
ご自身のたるみがどのタイプに当てはまるかを知ると、より効果的な対策をとりやすいです。
脂肪の蓄積が目立つ「脂肪型」
このタイプは年齢に関わらず、体重の増加とともに顎の下に脂肪が蓄積するのが主な原因です。
比較的若い方にも見られ、指でつまむと厚みのある柔らかい脂肪を感じられます。フェイスライン全体が丸みを帯び、太った印象を与えがちです。
食事管理や運動によるダイエットが改善の基本となりますが、部分的に脂肪を減らすのは難しい場合もあります。
皮膚のゆるみが原因の「皮膚たるみ型」
加齢や紫外線ダメージによって皮膚のコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚そのものが弾力を失って伸びてしまった状態です。
体重は変わらないのに、顎の下の皮膚だけが薄く垂れ下がっているのが特徴で、つまむと皮膚が伸びやすい感覚があります。
急激なダイエット後に見られるケースもあります。このタイプは、肌のハリを取り戻すケアが重要です。
筋肉の衰えによる「筋肉低下型」
顎の下から首にかけての筋肉(広頸筋や顎舌骨筋など)が衰え、皮膚や脂肪を支えきれなくなってたるんでいる状態です。
姿勢の悪さや加齢が主な原因で、口角が下がっていたり、首に横ジワが目立ったりする方も多いです。
顔全体の筋肉を鍛えるトレーニングや、正しい姿勢を保つ心がけが改善につながります。
あなたのたるみはどのタイプ?
| タイプ | 主な特徴 | セルフチェック |
|---|---|---|
| 脂肪型 | 全体的に丸く、厚みがある | つまむと厚い脂肪を感じる |
| 皮膚たるみ型 | 皮膚が薄く、しわっぽい | つまむと皮膚だけが伸びる |
| 筋肉低下型 | フェイスラインがぼやけている | 口角が下がり気味 |
実際には、これらの原因が複数組み合わさった「混合型」の方がほとんどです。
例えば、「加齢で筋肉が衰え(筋肉低下型)、さらに皮膚も弾力を失い(皮膚たるみ型)、たるみが目立つ」といった具合です。
ご自身の状態を多角的に捉え、複数の方法を組み合わせることが改善への近道です。
セルフケアの限界と美容クリニックでの治療選択肢
セルフケアはたるみの予防や軽度の改善に有効ですが、すでに進行してしまったたるみや、脂肪が厚くついている場合など、自力での改善には限界があります。
より確実で早い効果を求めるのであれば、美容クリニックでの専門的な治療が有効な選択肢となります。
セルフケアで改善が見込めない場合
数ヶ月間セルフケアを続けても変化が見られない、またはセルフケアだけでは満足のいく結果が得られないと感じる場合は、一度専門医への相談をおすすめします。
自己判断で間違ったケアを続けると、かえって肌を傷つけたり、たるみを悪化させたりする可能性もあります。
プロの目で原因を正確に診断してもらうことが重要です。
主な美容医療
| 治療法 | アプローチ方法 | 主な対象 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | 超音波でSMAS筋膜を引き締める | 皮膚のゆるみ、軽度の脂肪 |
| 脂肪溶解注射 | 薬剤で脂肪細胞を破壊・排出 | 部分的な脂肪の蓄積 |
| 糸リフト | 突起のついた糸で皮膚を引き上げる | 中度以上のたるみ |
HIFU(ハイフ)によるリフトアップ
高密度焦点式超音波(High-Intensity Focused Ultrasound)の略で、皮膚の深い層にあるSMAS筋膜に熱エネルギーをピンポイントで照射し、熱収縮による引き締め効果と、創傷治癒過程でのコラーゲン生成促進効果を狙う治療です。
メスを使わずにリフトアップが可能で、ダウンタイムがほとんどないのが大きな特徴です。
脂肪溶解注射で部分的にアプローチ
脂肪を溶解する作用のある薬剤を、気になる部分に直接注入する治療法です。破壊された脂肪細胞は、老廃物として体外へ排出されます。
二重あごのように、特定の部位の脂肪だけを減らしたい場合に適しています。
複数回の治療が必要な場合が多いですが、ダウンタイムが比較的短いのが利点です。
糸リフトによる引き上げ
コグ(突起)のついた特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚や脂肪組織を物理的に引き上げる治療です。たるみを強力にリフトアップする効果が期待できます。
使用する糸は時間とともに体内に吸収されるものが主流で、糸が吸収される過程でコラーゲン生成が促進され、肌のハリ向上にもつながります。
美容医療を受ける前に知っておきたいこと
美容医療は効果的な選択肢ですが、治療を受ける前にはいくつかの重要な点を確認し、十分に理解しておく必要があります。
後悔しないためにも、事前の情報収集と準備を怠らないようにしましょう。
カウンセリングの重要性
最も重要なのが、信頼できる医師によるカウンセリングです。ご自身の悩みや希望を正確に伝え、医師から治療法の詳細な説明を受けましょう。
カウンセリングで確認しておく項目
- 治療のメリットだけでなく、リスクやデメリット
- 考えられる合併症や副作用
- ご自身のたるみのタイプに合った治療法の提案
- 治療後の経過や必要なアフターケア
治療後のダウンタイムと注意点
治療法によって、ダウンタイム(腫れや内出血などが治まり、通常の生活に戻れるまでの期間)は異なります。
ご自身の生活スタイルを考慮し、どのくらいの休みが取れるかなどを考えた上で治療法を選択する必要があります。
治療後の過ごし方によって仕上がりが左右されるケースもあるため、クリニックからの指示は必ず守りましょう。
費用相場の理解
美容医療は自由診療のため、クリニックによって費用が大きく異なります。
提示された金額に何が含まれているのか(麻酔代、薬代、アフターケアなど)を事前にしっかり確認しましょう。
複数のクリニックでカウンセリングを受け、費用と内容を比較検討するのも一つの方法です。
主な治療法の費用相場
| 治療法 | 一般的な費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | 5万円~15万円 | 照射範囲や機種による |
| 脂肪溶解注射 | 1ccあたり5,000円~1万円 | 必要量や薬剤の種類による |
| 糸リフト | 1本あたり3万円~8万円 | 使用する糸の種類や本数による |
たるみ改善をサポートする栄養と食事
体の内側からたるみに働きかける習慣も、健やかな肌とフェイスラインを保つためには重要です。
日々の食事で、肌の材料となる栄養素をバランス良く摂取するように心がけましょう。
ハリを支えるコラーゲンとビタミンC
肌のハリを保つコラーゲンは、食事から摂取したタンパク質を元に体内で合成されます。この合成を助けるのがビタミンCです。
タンパク質とビタミンCをセットで摂取すると、効率的なコラーゲン生成につながります。
鶏肉や魚、大豆製品などの良質なタンパク質と、パプリカやブロッコリー、キウイフルーツなどのビタミンCが豊富な食品を積極的に摂りましょう。
むくみ対策に役立つカリウム
塩分の多い食事は体内に余分な水分を溜め込み、むくみの原因となります。カリウムには、体内のナトリウム(塩分)を排出する働きがあります。
むくみが気になる方は、カリウムを多く含むバナナやアボカド、ほうれん草や海藻類などを食事に取り入れると良いでしょう。
たるみ改善のための栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | コラーゲンの材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの合成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、柑橘類 |
| ビタミンE | 血行を促進し、抗酸化作用を持つ | ナッツ類、アボカド、植物油 |
血行を促進するビタミンE
「若返りのビタミン」とも呼ばれるビタミンEには、血行を促進する作用があります。血行が良くなると、肌の隅々まで栄養素が行き渡り、ターンオーバーが整います。
これは、健康な肌を育む上で大切です。アーモンドなどのナッツ類やアボカド、かぼちゃなどに多く含まれています。
よくある質問
さいごに、顎の下のたるみに関して患者さんからよくいただくご質問とその回答をまとめました。
- マッサージはどれくらいの頻度で行うべきですか?
-
毎日続けるのが理想ですが、無理は禁物です。1日1回、お風呂上がりなどのリラックスした時間に行うのがおすすめです。
大切なのは頻度よりも、肌をこすりすぎないように優しく、正しい方法で行うことです。やりすぎはかえって皮膚を傷つけ、たるみの原因になるときもあるので注意が必要です。
- 体重を減らせば顎の下のたるみは解消しますか?
-
脂肪の蓄積が主な原因である「脂肪型」のたるみの場合、適度な減量で改善が見られる方もいます。
しかし、加齢による皮膚のたるみや筋肉の衰えが原因の場合、体重を減らすだけでは解消が難しく、かえって皮膚が余ってたるみが目立つケースもあります。ご自身のたるみのタイプを見極めることが重要です。
- 美容医療に痛みはありますか?
-
治療法によって痛みの程度は異なります。例えば、HIFUはチクチクとした熱感、注射は針を刺す痛みを感じる場合があります。多くのクリニックでは、痛みを軽減するために麻酔クリームや冷却装置を使用します。
痛みに不安がある方は、カウンセリングの際に正直に伝え、どのような対策が可能か相談しましょう。
- 治療後、効果はどのくらい持続しますか?
-
効果の持続期間も治療法や個人差によって異なります。一般的に、HIFUは半年から1年、脂肪溶解注射は半永久的(リバウンドしない限り)、糸リフトは1年から2年程度が目安とされます。
しかし、どの治療も加齢による変化を完全に止められません。効果を長持ちさせるためには、治療後もセルフケアや健康的な生活習慣を続けていきましょう。
参考文献
ARORA, Gulhima, et al. Tackling submental fat–A review of management strategies. Cosmoderma, 2023, 3.
LIPNER, Shari R. Cryolipolysis for the treatment of submental fat: review of the literature. Journal of cosmetic dermatology, 2018, 17.2: 145-151.
JONES, Evan A.; STURM, Angela. Selecting the Right Technique for the Treatment of Submental Adiposity. Facial Plastic Surgery, 2025.
PARK, Soo Yeon, et al. Lipolytic agents for submental fat reduction. Skin Research and Technology, 2024, 30.2: e13601.
HOGAN, Sara, et al. Submental fat contouring: a comparison of deoxycholic acid, cryolipolysis, and liposuction. Advances in Cosmetic Surgery, 2019, 2.1: 75-87.
DONG, Joanna; AMIR, Yasmin; GOLDENBERG, Gary. Advances in minimally invasive and noninvasive treatments for submental fat. Cutis, 2017, 99.1: 20-23.
BHOJWANI, A. Addressing the” Double Chin:” Trends in Submental Contouring. Journal of Dermatology and Cosmetology, 2016, 1.10: 15406.
HAMMAD, Gamal, et al. Assessment of Double Chin with Exercises and Mesotherapy. Benha Journal of Applied Sciences, 2023, 8.12: 31-37.