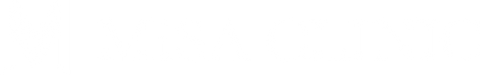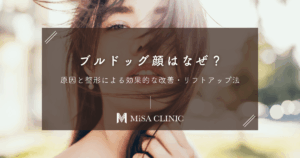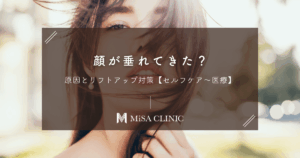顔がたるみやすい人の特徴とは?根本原因と効果的な予防・改善策

ふとした瞬間に、以前はなかったフェイスラインのゆるみやほうれい線に気づき、ショックを受けた経験のある方もいるのではないでしょうか。
顔のたるみは、年齢を重ねると誰にでも起こりうる悩みですが、実は生活習慣や環境によってその進行速度は大きく変わります。
この記事では、顔がたるむ根本的な原因を皮膚の構造から解き明かし、たるみやすい人の特徴、そして今日から始められる効果的な予防・改善策まで、専門的な視点から詳しく解説します。
なぜ顔はたるむのか?皮膚構造から見る根本原因
顔がたるむのは、皮膚の弾力を支えるコラーゲンの減少や、顔の土台であるSMAS筋膜のゆるみなど、皮膚の内部構造が加齢とともに変化するのが根本的な原因です。
これらの変化がどのようにしてたるみを引き起こすのか、詳しく見ていきましょう。
皮膚の弾力を支える3つの柱
私たちの皮膚は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」という層で構成されています。
特に、肌のハリや弾力に深く関わるのが、皮膚の本体ともいえる「真皮」です。
真皮には肌の弾力を保つコラーゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)、そして潤いを保つヒアルロン酸が存在し、これらが肌の土台をしっかりと支えています。
皮膚の基本構造と各層の役割
| 層 | 主な構成要素 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 表皮 | 角質層、メラノサイトなど | 外的刺激からの保護、水分の蒸発防止 |
| 真皮 | コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸 | 肌のハリ・弾力・潤いの維持 |
| 皮下組織 | 皮下脂肪、血管など | 衝撃の吸収、断熱、エネルギー貯蔵 |
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
肌のハリを支えるベッドのスプリングのような役割を持つコラーゲンと、それを束ねるゴムのような役割のエラスチンは、線維芽細胞という細胞によって生成されます。
しかし、加齢とともに線維芽細胞の働きは衰え、コラーゲンやエラスチンの産生量が減少します。
さらに質も低下し、古く硬くなった線維が蓄積すると肌が弾力を失い、重力に逆らえずにたるんでいきます。
SMAS(スマス)筋膜のゆるみとは
皮膚のさらに下には、表情筋を覆うSMAS(表在性筋膜群)という薄い膜状の組織があります。
SMASは皮膚と筋肉をつなぎ、顔全体の構造を支える土台のような存在です。
このSMASが加齢や重力の影響でゆるむと、その上にある皮下脂肪や皮膚も一緒に下垂し、フェイスラインのもたつきやほうれい線といった大きなたるみを引き起こす原因となります。
皮下脂肪の増減と移動
皮下組織にある脂肪もたるみに大きく影響します。加齢によって顔の皮下脂肪は減少しやすい部分と、逆に増えて下垂しやすい部分が出てきます。
例えば、こめかみや頬の脂肪は減少しやすい一方、あご下や口横の脂肪は増えやすい傾向があります。
この脂肪の分布バランスが崩れるため顔に凹凸ができ、たるんだ印象を強めてしまいます。
【セルフチェック】顔がたるみやすい人の生活習慣
長時間のスマホ操作による悪い姿勢、糖質の多い食生活、睡眠不足や無表情といった生活習慣は、血行不良や肌の老化を招き、顔のたるみを加速させます。
ご自身の習慣に当てはまるものがないか、一つひとつ確認してみましょう。
姿勢の悪さが招く顔への影響
長時間スマートフォンを操作したり、デスクワークで猫背になったりする姿勢は、首や肩の血行不良を招きます。
この血行不良は顔に必要な栄養や酸素が届きにくくなる原因となり、肌のターンオーバーを乱し、ハリを低下させます。
また、下を向く姿勢は常に重力が顔にかかり、あご下のたるみ(二重あご)やフェイスラインのもたつきを助長します。
たるみを招く生活習慣チェック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 姿勢 | 長時間スマホを見たり、猫背でPC作業をしたりする |
| 食事 | 甘いものや炭水化物が好きでよく食べる |
| 睡眠 | 睡眠時間が6時間未満の日が多い |
| 癖 | 気づくと口が開いている、あまり表情を変えない |
食生活の乱れと糖化・酸化ストレス
糖質の過剰摂取は、「糖化」という現象を引き起こします。これは、体内の余分な糖がタンパク質と結びつき、AGEs(最終糖化産物)という老化物質を生成する反応です。
AGEsがコラーゲン線維に蓄積すると肌の弾力が失われ、硬く黄色いくすみのある肌になります。
また、紫外線やストレス、喫煙などによって発生する「活性酸素」は細胞を傷つけ「酸化」させます。
この酸化もコラーゲンやエラスチンにダメージを与え、たるみの原因となります。
睡眠不足が肌再生を妨げる
私たちの肌は、睡眠中に分泌される成長ホルモンによってダメージを修復し、再生します。
睡眠時間が不足したり眠りの質が低かったりすると、この成長ホルモンの分泌が十分に行われません。その結果、日中に受けたダメージが回復せず、肌のハリや弾力が徐々に失われていきます。
慢性的な睡眠不足はたるみだけでなく、さまざまな肌トラブルの原因となります。
無表情や口呼吸の癖
顔には多くの表情筋があり、これらが動くことで豊かな表情が作られます。
しかし、人と話す機会が減ったり、PCやスマホの画面を無表情で見続けたりして表情筋が衰えると、その上にある皮膚や脂肪を支えきれなくなり、たるみに繋がります。
また、口呼吸の癖があると口周りの筋肉(口輪筋)がゆるみ、口角の下がりやほうれい線の原因になる場合があります。
紫外線だけじゃない!たるみを加速させる意外な外的要因
顔のたるみは紫外線の他に、PCやスマホから出るブルーライト、空気の乾燥、肌を強くこするなどの物理的刺激、そして急激なダイエットといった外的要因によっても加速します。
それぞれがどのように影響するのかを確認し、対策を立てましょう。
ブルーライトと肌への影響
スマートフォンやPC、LED照明から発せられるブルーライトは紫外線に近い性質を持ち、長時間浴びると肌の奥深く、真皮層にまで到達することが分かっています。
このブルーライトが肌の酸化ストレスを誘発し、コラーゲンやエラスチンを破壊する一因になると考えられています。
夜間にブルーライトを浴びると体内時計を乱し、肌再生を妨げる可能性も指摘されています。
乾燥が引き起こすハリの低下
肌が乾燥すると表皮のバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。また、肌表面の水分が失われるためキメが乱れ、小じわが発生します。
この乾燥状態が続くと肌全体のハリが失われ、たるみが目立ちやすくなります。
特にエアコンの効いた室内など、乾燥しやすい環境に長時間いる場合は注意が必要です。
たるみを加速させる要因
- 紫外線(UVA・UVB)
- ブルーライト
- 乾燥
- 摩擦などの物理的刺激
間違ったスキンケアとマッサージ
良かれと思って行っているスキンケアやマッサージが、逆にたるみを悪化させているケースも少なくありません。
例えば、洗浄力の強すぎるクレンジングや洗顔、肌を強くこするようなパッティングは肌のバリア機能を損ない、乾燥や炎症を引き起こします。
また、自己流の強いマッサージは皮膚を支えるコラーゲン線維やSMAS筋膜を伸ばしてしまい、たるみを助長する危険性があります。
急激なダイエットのリスク
短期間で大幅に体重を落とすような無理なダイエットは、顔のたるみを招く大きな原因です。
急激に皮下脂肪が減少すると皮膚がその変化に対応できず、風船がしぼんだように余ってしまいます。
この皮膚のたるみは、一度できてしまうとセルフケアで元に戻すのは非常に困難です。
ダイエットを行う際は、栄養バランスの取れた食事と運動を組み合わせ、月に1〜2kg程度の緩やかなペースで進めるのが大切です。
その「むくみ」、実はたるみのサインかも
一時的なものと思われがちな「むくみ」ですが、慢性化すると水分や老廃物の重みで皮膚が伸び、弾力を失って本格的な「たるみ」へと移行する可能性があります。
むくみとたるみの関係を正しく理解し、早めに対処すると将来のたるみ予防に繋がります。
たるみとむくみの見分け方
むくみは、体内の余分な水分や老廃物が皮下に溜まった状態です。一方、たるみは皮膚やその下の組織が重力によって下垂した状態を指します。
見分け方としては、指で押したときの反応が参考になります。
むくみは指で押すと跡が残りやすく、時間とともに元に戻りますが、たるみは皮膚そのものが伸びているため押してもあまり変化がありません。
むくみとたるみの主な違い
| 項目 | むくみ | たるみ |
|---|---|---|
| 原因 | 余分な水分・老廃物の停滞 | コラーゲン減少、SMASのゆるみなど |
| 特徴 | 一時的で、日内変動がある | 慢性的で、改善が難しい |
| 対処法 | 血行促進、塩分を控える | 専門的な治療が必要な場合も |
なぜむくみがたるみに繋がるのか
むくみが慢性化すると、皮膚は常に水分で膨らんだ状態になります。この状態が長く続くと、水の重みで皮膚が徐々に伸ばされていきます。
風船を長時間膨らませておくと、空気を抜いても元に戻りにくくなるのと同じ原理です。
この皮膚の伸展がコラーゲン線維やエラスチン線維にダメージを与え、弾力性を失わせて、むくみが解消された後も皮膚が元に戻らず、たるみとして定着してしまうのです。
リンパの流れと顔の老廃物
私たちの体には血液とは別にリンパ管が張り巡らされており、体内の老廃物や余分な水分を回収して運ぶ役割を担っています。
しかし、運動不足やストレス、体の冷えなどによってリンパの流れが滞ると老廃物が顔に溜まり、むくみを引き起こします。
特に顔周りには多くのリンパ節が集中しているため、流れが滞りやすい部位です。この状態の放置が、たるみへの移行リスクを高めます。
むくみやすい人の体質的特徴
塩分の多い食事が好きな人、長時間同じ姿勢でいることが多い人、運動不足の人、体が冷えやすい人は、むくみやすい傾向にあります。
これらの生活習慣は体内の水分バランスを崩し、血行やリンパの流れを悪化させます。
むくみの原因となる習慣を改善する取り組みが、将来のたるみ予防において非常に重要です。
自宅でできる!たるみ予防・改善のためのセルフケア
たるみの予防・改善には、保湿や紫外線対策といった基本的なスキンケア、表情筋を鍛えるエクササイズ、バランスの取れた食事、そして質の良い睡眠といった日々のセルフケアが効果的です。
今日から始められる具体的な方法を見ていきましょう。
正しい保湿と紫外線対策
スキンケアの基本は保湿です。肌の乾燥はあらゆる肌トラブルの引き金となり、たるみを助長します。
セラミドやヒアルロン酸、コラーゲンといった保湿成分が配合された化粧水や美容液、クリームを使って肌の潤いをしっかりと守りましょう。
また、紫外線は一年中降り注いでいます。たるみの最大の外的要因である「光老化」を防ぐため、季節や天候に関わらず日焼け止めを毎日塗る習慣を徹底してください。
紫外線対策のポイント
- SPF・PA表示のある日焼け止めを毎日使用する
- 2〜3時間おきに塗り直す
- 帽子、日傘、サングラスなども活用する
表情筋を鍛えるエクササイズ
顔の筋肉である表情筋を意識的に動かすと筋力の低下を防ぎ、たるみを予防する効果が期待できます。
ただし、やりすぎや間違った方法はシワの原因にもなるため、注意が必要です。
鏡を見ながら、ゆっくりと正しい動きで行いましょう。
口周りのたるみに効くエクササイズ
| 流れ | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 口を大きく開けて「あ」の形にする | 目も大きく見開く |
| 2 | 口を横に大きく引いて「い」の形にする | 首に筋が浮き出るくらい力を入れる |
| 3 | 唇を前に突き出して「う」の形にする | 顔のパーツを中心に集めるイメージ |
| 4 | 口角を上げて「え」の形で笑顔を作る | 上の歯を見せるように |
| 5 | 口を縦に大きく開けて「お」の形にする | ほうれい線を伸ばすイメージ |
※各5秒ずつキープし、1セットとして1日数回行います。
たるみに効果的な栄養素と食事
美しい肌は内側から作られます。たるみ予防のためには、バランスの取れた食事が重要です。
特に、肌の材料となるタンパク質、コラーゲンの生成を助けるビタミンC、抗酸化作用のあるビタミンA・E、ポリフェノールなどを積極的に摂取しましょう。
たるみケアにおすすめの栄養素と食品
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や筋肉の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲン生成を促進、抗酸化作用 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンA/E | 強い抗酸化作用、肌の健康維持 | 緑黄色野菜、ナッツ類、アボカド |
質の良い睡眠をとるための工夫
肌のゴールデンタイムといわれる午後10時から午前2時にこだわる必要はありませんが、質の高い睡眠を十分にとる工夫は美肌に必要です。
就寝前のスマートフォン操作を控え、リラックスできる環境を整えましょう。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、好きな香りのアロマを焚いたりするのも効果的です。
自分に合った方法で心身をリラックスさせ、スムーズな入眠を心がけてください。
美容皮膚科でのたるみ治療という選択肢
セルフケアでは改善が難しい進行したたるみには、SMAS筋膜に働きかけるハイフ(HIFU)や、ボリュームを補う注入治療、物理的に引き上げる糸リフトなど、美容皮膚科での専門的な治療が有効です。
セルフケアの限界と専門治療の必要性
セルフケアは主に皮膚の最も外側にある表皮や、真皮層の浅い部分に働きかけるものです。
しかし、たるみの根本原因であるSMAS筋膜のゆるみや、皮下脂肪の移動、深く刻まれたシワに対しては、セルフケアだけでアプローチするには限界があります。
美容医療では、これらの深い層に直接働きかけられるため、セルフケアでは得られない改善効果が期待できます。
ハイフ(HIFU)治療の仕組み
HIFU(高密度焦点式超音波)は、超音波の熱エネルギーをSMAS筋膜や皮下組織にピンポイントで照射する治療法です。
熱によってタンパク質が収縮してゆるんだ筋膜が引き締まり、リフトアップ効果が得られます。
また、熱刺激によってコラーゲンの生成が促進されるため、中長期的に肌のハリや弾力がアップします。
メスを使わずに土台から引き上げられるのが大きな特徴です。
注入治療(ヒアルロン酸・コラーゲンなど)
ヒアルロン酸やコラーゲンなどを、たるみやシワが気になる部分に直接注入する治療法です。加齢によって失われたボリュームを補い、くぼみや溝を目立たなくさせます。
例えば、ほうれい線やマリオネットラインの溝を埋めたり、こけてしまった頬をふっくらさせたりして若々しい印象を取り戻します。
比較的ダウンタイムが短く、手軽に受けられる点が魅力です。
糸リフト(スレッドリフト)の特徴
コグ(とげ)の付いた特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚を物理的に引き上げる治療法です。
フェイスラインのもたつきや頬のたるみなど、下垂した組織を直接持ち上げるため、即時的なリフトアップ効果を実感しやすいのが特徴です。
また、挿入された糸が周辺組織を刺激し、コラーゲンの生成を促す効果も期待できます。
主な美容医療によるたるみ治療法
| 治療法 | アプローチする層 | 主な効果 |
|---|---|---|
| ハイフ(HIFU) | SMAS筋膜、皮下組織 | 土台からのリフトアップ、引き締め |
| 注入治療 | 真皮、皮下組織 | ボリュームアップ、溝を埋める |
| 糸リフト | 皮下組織 | 物理的なリフトアップ、即効性 |
自分に合った治療法の選び方
自分に合ったたるみ治療を選ぶには、たるみの種類や進行度を医師に正しく診断してもらい、期待する効果や許容できるダウンタイム、そして費用と持続期間のバランスを総合的に判断することが重要です。
また、クリニック選びのポイントも押さえておきましょう。
たるみの種類と進行度で選ぶ
たるみは、その原因によっていくつかのタイプに分けられます。
例えば、皮膚のハリが失われて生じる小じわや毛穴の開きが気になる初期段階であれば、レーザー治療や光治療が適している場合があります。
SMASのゆるみが原因のフェイスラインのもたつきにはハイフが、脂肪の下垂が目立つ場合は糸リフトが効果的です。
まずは医師の診察を受け、ご自身のたるみがどのタイプで、どの程度進行しているのかを正確に診断してもらうと良いでしょう。
期待する効果とダウンタイムを考慮する
治療法によって、得られる効果の現れ方や持続期間、そしてダウンタイム(回復期間)が異なります。
すぐに効果を実感したい場合は糸リフトが、自然な変化を望むならハイフや注入治療が良いでしょう。
また、仕事やプライベートの予定を考慮し、どのくらいのダウンタイムなら許容できるかも重要な判断基準です。
赤みや腫れ、内出血などのリスクについても事前にしっかり確認しましょう。
費用と持続期間のバランス
たるみ治療は自由診療のため、クリニックによって費用は大きく異なります。
1回あたりの費用だけでなく、その効果がどのくらい持続するのかも考慮して、コストパフォーマンスを判断することが必要です。
安さだけで選ぶのではなく、使用する機器や製剤、医師の技術力なども含めて総合的に検討しましょう。
信頼できるクリニック選びのポイント
- カウンセリングが丁寧で、質問しやすい雰囲気か
- メリットだけでなく、リスクやデメリットも説明してくれるか
- 医師の経験や実績が豊富か
- 料金体系が明確であるか
よくある質問
「顔がたるみやすい人の特徴が分かれば、将来自分がたるむのかどうかを予測できるかも」と考える方は意外と少なくないようです。
筋肉の衰えや肌の弾力低下、脂肪の変化や姿勢のゆがみ、紫外線の影響や肌の酸化・糖化、慢性的なむくみなど、たるみの原因はさまざまであり、複合的に絡み合っているケースがほとんどです。
「こういう骨格の人がたるみやすい」というよりは「こういう生活をしている人がたるみやすい」といったことが言えますが、裏を返すと、生活習慣やケアに気をつけるとたるみの予防が可能ということです。
顔のたるみが気になり始めた方や、将来のたるみへの不安がある方ほど、この機会にご自身の生活習慣を振り返ってみましょう。
- たるみ治療は何歳から始めるべきですか?
-
たるみ治療に「何歳から」という明確な決まりはありません。たるみが気になり始めた時が、治療を検討するタイミングです。
20代後半から30代で予防的にハイフなどを受ける方もいれば、40代、50代以上で本格的なたるみ改善を目指す方もいます。年齢よりも、ご自身の肌の状態に合わせて適切な治療を選ぶほうが重要です。
早期にケアを始めると、将来的なたるみの進行を緩やかにする効果も期待できます。
- 治療後に気をつけることはありますか?
-
治療内容によって異なりますが、一般的には治療当日の激しい運動、長時間の入浴、飲酒など、血行が良くなる行為は控えるように指示される場合が多いです。
また、治療後の肌はデリケートな状態になっているため、保湿と紫外線対策をいつも以上に徹底する心がけが大切です。マッサージなど、肌への強い刺激も一定期間は避ける必要があります。
詳細は治療を受けるクリニックの指示に従いましょう。
- 一度治療すれば、たるみは再発しませんか?
-
残念ながら、一度の治療で永久にたるまなくなるわけではありません。美容医療は時計の針を戻すようなものですが、治療後も加齢による変化は続いていきます。
そのため、効果を維持してより良い状態を保つためには、定期的なメンテナンス治療や、日々のセルフケアを継続することが大切です。
治療効果の持続期間は治療法や個人差によって異なりますので、カウンセリング時に確認しましょう。
- 痛みやダウンタイムはどのくらいですか?
-
痛みやダウンタイムの程度は、治療法によって大きく異なります。ハイフは骨に近い部分で熱感や鈍い痛みを感じる場合があります。
注入治療は針を刺す痛みがありますが、麻酔クリームを使用すると軽減できます。糸リフトは局所麻酔を行いますが、術後に数日間、腫れや痛み、引きつれ感が出るケースがあります。
ダウンタイムについても、赤みや腫れが数時間で引くものから、内出血が1〜2週間続くものまで様々です。
ご自身の生活スタイルに合わせて、医師と相談しながら治療法を選びましょう。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
RYU, Min-Hee, et al. Reframing the etiology of facial sagging from a facelift perspective. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2018, 6.7: e1831.
NAM, Geewoo, et al. Novel conformation of hyaluronic acid with improved cosmetic efficacy. Journal of Cosmetic Dermatology, 2023, 22.4: 1312-1320.
LIU, Xuan-jun; SULTAN, Muhammad Tipu; LI, Guang-shuai. Obesity, glycemic traits, lifestyle factors, and risk of facial aging: a Mendelian randomization study in 423,999 participants. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.5: 1005-1015.
ROWE, David J.; GUYURON, Bahman. Environmental and genetic factors in facial aging in twins. In: Textbook of Aging Skin. Springer, Berlin, Heidelberg, 2017. p. 723-731.
ZHANG, Zhanyi, et al. Genetically proxied autoimmune diseases and the risk of facial aging. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2024, 981-991.
SAMIZADEH, Souphiyeh. Anatomy and Pathophysiology of Facial Ageing. In: Thread Lifting Techniques for Facial Rejuvenation and Recontouring. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 61-89.
RAMAZANOVA, I.; KURBANKADIEVA, B. Case Study on a Multi-Layer Approach to Skin Rejuvenation: Effects of Energy-Based Devices and Injectable Biostimulatory Therapies. Journal of Applied Cosmetology, 2025, 43.2: of print-of print.
HONG, Seongwon, et al. Clinical Evaluation of Skin Rejuvenation Using a Radiofrequency/Ultrasound Composite Device. Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea, 2025, 51.2: 175-185.