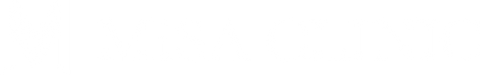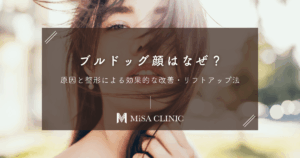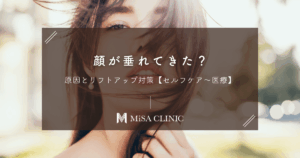顔のたるみ解消!効果的なストレッチ・体操・トレーニング

顔のたるみは、多くの方が直面する悩みの一つです。鏡を見るたびに気になるフェイスラインのゆるみやほうれい線に、「年齢のせいだから仕方ない」と諦めてしまうのはもったいないです。
実は、顔のたるみには様々な原因が複雑に絡み合っており、正しい知識に基づいたセルフケアで改善が期待できます。
この記事では、顔のたるみの根本原因を解き明かし、ご自宅で今日から実践できる効果的なストレッチや体操、トレーニングやツボ押しまで、具体的な方法を詳しく解説します。
そもそも顔のたるみはなぜ起こるのか?
顔のたるみは、主に加齢による肌の弾力低下、紫外線ダメージの蓄積、表情筋の衰えという3つの要因が複合的に絡み合って起こります。
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
肌のハリや弾力は、真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといった線維状のタンパク質によって支えられています。
しかし、加齢とともにこれらの生成能力は低下し、質も変化していきます。その結果、肌の土台がゆるみ、重力に逆らえなくなってたるみが生じます。
特に30代後半から40代にかけて、その変化を実感しやすくなります。
紫外線ダメージの蓄積
紫外線は肌の老化を加速させる最大の外的要因です。なかでも波長の長いUVAは肌の奥深く真皮層まで到達し、コラーゲンやエラスチンを変性させたり、破壊したりします。
長年にわたって紫外線を浴び続けるとダメージが蓄積し、肌の弾力が失われ、深いたるみへとつながります。
日々の紫外線対策が将来のたるみ予防には重要です。
表情筋の衰えと姿勢の乱れ
顔には約30種類以上の「表情筋」があり、これらの筋肉が複雑に動くため豊かな表情が作られます。
しかし、日常生活で使う表情筋は全体の3割程度ともいわれ、使われない筋肉は年齢とともに衰えていきます。筋肉が衰えるとその上にある皮膚や脂肪を支えきれなくなり、たるみを引き起こします。
また、スマートフォン操作などで長時間うつむく姿勢は首や顔の筋肉に負担をかけ、フェイスラインの崩れや二重あごの原因となります。
たるみの主な原因と特徴
| 原因の種類 | 主な特徴 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 加齢 | 肌全体の弾力が低下し、乾燥しやすくなる | 保湿ケア、エイジングケア化粧品の活用 |
| 紫外線 | シミやシワも同時に目立つことが多い | 年間を通した紫外線対策、抗酸化作用のある食事 |
| 筋肉の衰え | フェイスラインがぼやけ、ほうれい線が深くなる | 表情筋の体操・トレーニング、姿勢の改善 |
急激な体重変動の影響
短期間で大幅なダイエットを行うと脂肪が急激に減少して皮膚が余り、たるんでしまうケースがあります。
これは、皮膚の収縮が脂肪の減少スピードに追いつかないために起こります。
「きれいなボディライン早く手に入れたい」「辛いダイエットを短期間で終わらせたい」といった気持ちも分かりますが、をたるみを防ぐ上では、健康的な肌を保ちながら体重をコントロールする工夫が大切です。
顔のたるみと頭皮の意外な関係性
顔のたるみは、一枚の皮膚でつながっている頭皮の硬さや血行不良が大きく影響します。
頭皮が凝り固まって下に落ち込むと顔全体の皮膚を引き下げてしまうため、頭皮ケアがたるみ解消の重要な鍵となります。
一枚の皮膚でつながる顔と頭皮
顔の皮膚と頭皮は別々のパーツではなく、一枚の皮膚で連続しています。
おでこの上から後頭部までを覆う頭皮が凝り固まって弾力を失うと、その重みで顔全体の皮膚を引き下げてしまうのです。
特に、前頭筋(おでこ)や側頭筋(こめかみ)といった筋肉は顔の表情筋と連動しており、頭皮の硬直はダイレクトに目元やフェイスラインのたるみとして現れます。
頭皮の血行不良が顔のたるみを引き起こす
頭皮の血行不良は、髪の毛に栄養が届きにくくなるため薄毛の原因となるだけでなく、顔色をくすませて肌のハリを奪う要因にもなります。
血行が悪いと老廃物が溜まりやすくなり、むくみやたるみにつながります。
頭皮マッサージなどで血行を促進するケアは、健やかな髪を育むと同時に、顔のリフトアップにも効果が期待できるのです。
あなたの頭皮は大丈夫?硬さセルフチェック
| チェック項目 | 硬いサイン | 理想の状態 |
|---|---|---|
| 指の腹で頭皮を動かす | 頭蓋骨に張り付いてほとんど動かない | 前後左右にスムーズに動く |
| 頭頂部をつまむ | 硬くてつまめない、または痛みを感じる | 柔らかくつまむことができる |
| 指で押した感覚 | 弾力がなく、ブヨブヨしている感じがする | 適度な弾力と厚みがある |
頭皮の硬さによる影響
硬い頭皮は、顔のたるみ以外にも様々な不調のサインです。肩こりや首こり、眼精疲労、さらには頭痛の原因となる場合もあります。
頭皮を健やかな状態に保つ習慣は、美容面だけでなく、健康面においても非常に重要です。顔のケアと同じように、頭皮のケアにも意識を向けてみてください。
顔のストレッチ・体操を始める前に知っておきたい基本
顔のたるみ対策としてストレッチや体操を始めるなら、やみくもに行うのではなく、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
正しい方法で行うと、効果を最大限に引き出し、肌への負担を減らせます。
リラックスできる環境で行う
顔の筋肉は非常にデリケートです。心身ともにリラックスした状態で行うと筋肉の緊張がほぐれ、ストレッチや体操の効果が高まります。
お風呂上がりで血行が良くなっている時や、就寝前のリラックスタイムなどがおすすめです。
慌ただしい時間帯を避け、ゆっくりと自分と向き合う時間を作りましょう。
ケアを始める前の準備
| 準備項目 | 目的 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 手を清潔にする | 顔への雑菌付着を防ぐ | 石鹸で丁寧に洗う |
| 鏡を用意する | 正しい動きを確認する | 顔全体が映る大きさの鏡を正面に置く |
| 肌を保湿する | 摩擦による肌への負担を軽減する | 化粧水やクリームを塗布する |
無理のない範囲でゆっくりと
早く効果を出したいからといって力を入れすぎたり、長時間やりすぎたりするのは逆効果です。筋肉を傷めたり、かえってシワを深くしたりする原因にもなりかねません。
一つひとつの動きを「痛気持ちいい」と感じる程度の強さで、ゆっくりと丁寧に行うように心がけてください。
回数や時間よりも、質の高い動きを意識することが大切です。
継続が何よりも重要
顔の体操やトレーニングは、一度行っただけですぐに効果が現れるものではありません。
筋力トレーニングと同じで、継続すると少しずつ表情筋が鍛えられ、効果を実感できるようになります。
毎日完璧にできなくても構いません。まずは「一日5分でも続ける」という気持ちで、生活の一部として習慣化することを目指しましょう。
【部位別】気になるたるみを集中ケア!効果的な顔の体操
顔のたるみは、現れる場所によって印象が大きく変わります。
ほうれい線や二重あご、目元のたるみなど、特に気になる部分に集中して働きかけられる体操を取り入れましょう。
ほうれい線を目立たなくする口周りの体操
ほうれい線は、頬のたるみや口周りの筋肉(口輪筋)の衰えが主な原因です。口輪筋を鍛え、頬の肉を支える力を取り戻す体操を行いましょう。
頬の内側から舌でほうれい線を押し出すようにマッサージするのも効果的です。
- 口を大きく開けて「あ・い・う・え・お」と発声する
- 口の中に空気を含んで頬を左右交互に膨らませる
- 舌を口の中で大きく回す
二重あごをすっきりさせる首とフェイスラインの運動
フェイスラインのもたつきや二重あごは、首周りの筋肉の衰えや姿勢の悪さが影響します。
あごの下から首にかけて広がる広頚筋や、舌の筋肉を意識した運動が効果的です。普段の姿勢を見直すのも忘れないようにしましょう。
フェイスラインすっきり運動
| 運動名 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 天井見上げキープ | ゆっくりと天井を見上げ、首の前側を伸ばした状態で5秒キープ | 唇を「う」の形に突き出すとより効果的 |
| 舌出し運動 | 天井を見上げたまま、舌を真上に突き出し5秒キープ | あごの下の筋肉に力が入るのを感じる |
| 「イー」の口運動 | 口を横に大きく開き「イー」の形を作り、首筋を意識して5秒キープ | 首に筋が浮き出るくらい力を入れる |
目元のたるみやクマに働きかける眼輪筋ストレッチ
目元の皮膚は非常に薄く、たるみやシワが現れやすい部位です。目の周りを囲む「眼輪筋」を鍛えると、すっきりとした目元を目指せます。
スマートフォンやPCの長時間利用で凝り固まった眼輪筋をほぐす意識で行いましょう。
指の腹でこめかみを軽く引き上げながらゆっくりとまばたきを繰り返す運動や、目を大きく見開いて5秒キープし、次にゆっくりと目を閉じる運動がおすすめです。
表情筋を鍛える!顔全体のたるみにアプローチするトレーニング
部分的なケアと並行して、顔全体の筋肉をバランスよく鍛えるトレーニングも取り入れましょう。
表情筋全体を動かせば血行が促進され、顔色が明るくなる効果も期待できます。
顔ヨガでしなやかな表情筋を作る
顔ヨガは、顔の筋肉を大きく動かしてストレッチとトレーニングを同時に行うものです。
普段使わない筋肉まで刺激することで顔全体の血行を促進し、リフトアップを目指します。
代表的なポーズに「ライオンの顔」があります。
息を吸いながら顔のパーツをすべて中心に集めるように力を入れ、息を吐きながら目と口を大きく開き、舌を思い切り下に出します。この動きを数回繰り返しましょう。
割り箸を使った口角トレーニング
口角が下がっていると、不機嫌に見えたり老けた印象を与えたりします。
口角を上げる筋肉を鍛える簡単なトレーニングとして、割り箸を使った方法があります。
割り箸を横にして奥歯で軽く噛み、口角を割り箸のラインよりも高く上げるのを意識して「イー」と発声します。この状態を30秒キープし、数回繰り返します。
鏡を見ながら左右の口角が均等に上がっているか確認しながら行いましょう。
顔の筋トレ頻度とポイント
| トレーニング種類 | 推奨頻度 | 意識するポイント |
|---|---|---|
| 顔ヨガ | 毎日5分程度 | 呼吸を止めず、リラックスして行う |
| 口角トレーニング | 1日1回(30秒×3セット) | 口角をしっかり引き上げることを意識する |
| 舌回し体操 | 1日左右20回ずつ | ゆっくり、大きく回す |
舌回し体操で内側から引き締める
口の中で舌を大きく回す「舌回し体操」は、ほうれい線や二重あご、フェイスラインのたるみに効果的なトレーニングです。
口を閉じた状態で、歯茎の外側に沿って舌をゆっくりと大きく回します。右回りを20回、左回りを20回を1セットとして行います。
初めはきつく感じるかもしれませんが、続けると舌の付け根にある筋肉が鍛えられ、顔の内側からリフトアップする効果が期待できます。
すきま時間でOK!顔の血行を促すツボ押しケア
顔や頭部には、美容効果が期待できるツボが数多く存在します。ツボを刺激すると、滞りがちな血流やリンパの流れを促進し、むくみやたるみの改善をサポートします。
仕事の合間やテレビを見ながらなど、すきま時間で手軽に行えるのが魅力です。
たるみに効く代表的な顔のツボ
ツボを押す際は指の腹を使って「痛気持ちいい」と感じる強さで、ゆっくりと5秒ほどかけて押し、ゆっくりと離します。
これを数回繰り返します。肌を強くこすらないように注意してください。
顔の主要なツボと期待できる効果
| ツボの名前 | 場所 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 攅竹(さんちく) | 眉頭の内側のくぼみ | 目元のたるみ、眼精疲労 |
| 太陽(たいよう) | こめかみのくぼみ | 目尻のシワ、頭痛 |
| 頬車(きょうしゃ) | 耳の付け根とエラの間のくぼみ | 二重あご、フェイスラインのたるみ |
| 顴髎(けんりょう) | 頬骨の下のくぼみ | 頬のたるみ、むくみ |
| 地倉(ちそう) | 口角のすぐ外側 | ほうれい線、口角の下がり |
| 承漿(しょうしょう) | 下唇の中央下のくぼみ | フェイスラインの引き締め |
頭皮マッサージで顔全体をリフトアップ
顔の皮膚と頭皮は一枚で繋がっています。そのため、頭皮が凝り固まって血行が悪くなると顔の皮膚を引き上げる力が弱まり、たるみの原因になります。
シャンプーの際などに、指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐす習慣をつけましょう。
特に側頭部や頭頂部を重点的にマッサージすると、フェイスラインのリフトアップに繋がります。
ツボ押しを行う際の注意点
ツボ押しは手軽なケアですが、注意点もあります。体調が優れない時や、肌に炎症やニキビなどのトラブルがある場合は避けましょう。
また、食後すぐや飲酒後も控えるのが賢明です。あくまでセルフケアの一環として、心地よい範囲で行うと良いです。
【要注意】セルフケアの落とし穴
良かれと思って続けているセルフケアや、無意識の癖が、実は顔のたるみを助長している可能性があります。
効果的なケアを行うと同時に、たるみを悪化させるNG習慣を見直すことも、若々しい印象を保つためには重要です。
強すぎるマッサージや美顔ローラー
たるみを解消したい一心で力を込めて顔をマッサージしたり、美顔ローラーを強く押し当てたりしている方も見受けられます。
強い摩擦は肌のバリア機能を傷つけ、炎症を引き起こす可能性があります。この炎症が続くと真皮のコラーゲンが破壊され、かえってたるみやシワを深刻化させる「摩擦黒皮症」という色素沈着の原因にもなります。
マッサージを行う際は必ず滑りの良いクリームやオイルを使用し、肌をこすらずに優しく圧をかける程度に留めましょう。
セルフケアのOKとNG
| ケアの種類 | OKな方法 | NGな方法 |
|---|---|---|
| 洗顔 | たっぷりの泡で優しく洗う | ゴシゴシこする、熱いお湯ですすぐ |
| マッサージ | クリーム等を使い、優しい圧で行う | 乾いた肌に強い力で摩擦する |
| 顔の体操 | 鏡を見て正しい動きで行う | 長時間やりすぎる、痛みを我慢する |
表情筋トレーニングのやりすぎ
表情筋を鍛えるのはたるみ改善に有効ですが、特定の筋肉だけを過剰に鍛えたり間違った方法で行ったりすると、新たなシワを刻む原因になります。
例えば、おでこにシワを寄せる癖がある人が眉を上げるトレーニングをやりすぎると、おでこの横ジワが定着してしまいます。
トレーニングは顔全体の筋肉をバランスよく使うように意識し、鏡で不自然なシワが寄っていないか確認しながら行いましょう。
片側だけで噛む癖や頬杖
食事の際にいつも同じ側で噛んでいたり、無意識に頬杖をついたりする癖がある方もいるでしょう。これらの行為は顔の左右のバランスを崩し、片側だけのたるみや歪みを引き起こします。
顔の筋肉や骨格に不均等な圧力がかかり続けるため、片方のほうれい線だけが深くなるなどの原因になります。
意識して両方の歯で噛むようにしたり、頬杖をつかないようにしたりと、日々の小さな癖を見直すことが大切です。
内側からハリを育む!たるみ予防のための生活習慣
顔のたるみ対策は外側からのケアだけでは十分ではありません。健やかな肌と筋肉は、日々の食事や睡眠といった生活習慣によって育まれます。
体の内側からハリのある肌を作るためのポイントを押さえ、トータルでたるみにくい状態を目指しましょう。
バランスの取れた食事と摂取したい栄養素
肌の材料となるタンパク質や、コラーゲンの生成を助けるビタミンC、抗酸化作用のあるビタミンEなどを積極的に摂取する工夫が大切です。
特定の食品に偏るのではなく、様々な食材からバランスよく栄養を摂るように心がけましょう。
加工食品や糖質の多い食事は体内で「糖化」を引き起こし、肌の弾力を失わせる原因になるため、摂りすぎには注意が必要です。
たるみケアにおすすめの栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 肌や筋肉の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンA | 皮膚の健康を維持する | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
質の高い睡眠の確保
睡眠中には、肌のダメージを修復して再生を促す「成長ホルモン」が分泌されます。特に、入眠後最初の3時間は成長ホルモンの分泌が最も活発になるゴールデンタイムです。
睡眠不足が続くと修復作業が十分に行われず、肌のターンオーバーが乱れ、たるみやくすみの原因となります。
寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、質の高い睡眠を確保するための工夫をしましょう。
正しい姿勢を意識する
猫背やストレートネックなど、姿勢の悪さは顔のたるみに直結します。
背中が丸まっていると頭が前に突き出て首や肩の筋肉に負担がかかり、血行が悪化します。この状態が続くと、顔のむくみやフェイスラインのたるみを引き起こします。
普段から背筋を伸ばし、あごを軽く引いた正しい姿勢を意識すると、間接的な顔のたるみトレーニングになります。
- 長時間同じ姿勢を続けない
- デスクワーク中は時々立ち上がってストレッチする
- 歩くときは頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージを持つ
顔のたるみケアに関するよくある質問
顔のたるみは、筋肉トレーニングやストレッチ、ツボ押しなどを毎日少しずつ続けると改善効果が期待できます。
また、たるみの原因となっている習慣や姿勢を見直すのも良い方法といえます。
ただし、原因によってはセルフケアだけで限界があるケースもありますので、「自分でいろいろ試してみたけど改善しない」「ケアを続けているけどたるみがひどくなっている気がする」といったときは、クリニックに相談してみるのも一つの方法です。
- ストレッチや体操の効果は、どのくらいで実感できますか?
-
効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には毎日継続して1〜3ヶ月ほどで顔がすっきりした、むくみにくくなった、などの変化を感じ始める方が多いです。
早く効果を実感したい気持ちも分かりますが、すぐに結果を求めず、焦らずに続ける努力が大切です。筋肉の変化はゆっくりと現れるため、長期的な視点で取り組んでいきましょう。
- 毎日続けないと意味がありませんか?
-
毎日行うのが理想的ですが、無理をしてストレスになるようであれば、週に3〜4日でも問題ありません。大切なのは「継続を断念しないこと」です。
疲れている日は簡単なツボ押しだけにするなど、ご自身のペースで生活に組み込んでいくと長続きしやすいでしょう。一度やめてしまっても、また気付いた時から再開すれば大丈夫です。
- ケアの最中に痛みを感じた場合はどうすればよいですか?
-
痛みを感じる場合は、力が強すぎるか、方法が間違っている可能性があります。すぐに中止してください。
筋肉の軽い張りや伸びを感じる「痛気持ちいい」程度が適切な強さです。
特に首周りなどデリケートな部分は、無理に動かすと筋を痛める危険性もあります。決して痛みを我慢して続けないでください。
- セルフケアだけでたるみは完全になくなりますか?
-
セルフケアは、たるみの進行を緩やかにし、見た目の印象を改善するために非常に有効な手段です。
しかし、加齢によって深く刻まれたシワや、大きくたるんでしまった皮膚をセルフケアだけで完全になくすのは難しい場合があります。
より積極的な改善を望む場合や、セルフケアの効果に限界を感じた場合は、美容皮膚科などの専門機関に相談するのも一つの選択肢です。専門家は、個々の状態に合わせた適切な治療法を提案できます。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
VAN BORSEL, John, et al. The effectiveness of facial exercises for facial rejuvenation: a systematic review. Aesthetic surgery journal, 2014, 34.1: 22-27.
DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.
GARCIA, Aline de Souza Massulo, et al. Manual therapy in the treatment of facial wrinkles and sagging: a quantitative-qualitative randomized clinical trial. Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal, 2020, 17: 0-0.
LIM, Hyoung Won. Effects of facial exercise for facial muscle strengthening and rejuvenation: systematic review. The Journal of Korean Physical Therapy, 2021, 33.6: 297-303.
HWANG, Ui-jae, et al. Effect of a facial muscle exercise device on facial rejuvenation. Aesthetic surgery journal, 2018, 38.5: 463-476.
M. SMITH, Abigail, et al. Non-traditional and non-invasive approaches in facial rejuvenation: a brief review. Cosmetics, 2020, 7.1: 10.
MOHIUDDIN, Abdul Kader. Skin aging & modern age anti-aging strategies. Int. J. Clin. Dermatol. Res, 2019, 7: 209-240.
PARK, Kui Young; LÓPEZ GEHRKE, Ingrid. Combined multilevel anti‐aging strategies and practical applications of dermocosmetics in aesthetic procedures. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2024, 38: 23-35.