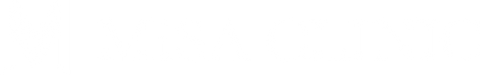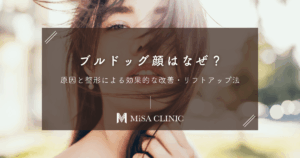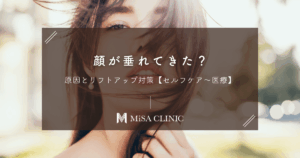顔のたるみ、場所別に徹底対策!原因と効果的な改善方法まとめ

おでこや頬、フェイスラインのたるみといった年齢とともに深まるこの悩みは、見た目年齢を大きく左右するだけでなく、気分まで沈ませてしまう場合があります。
この記事では、顔のたるみが起きる根本的な原因から、おでこ、まぶた、頬、フェイスラインといった場所別の具体的な原因と対策を詳しく解説します。
ご自身でできるセルフケアから、美容皮膚科で行う専門的な治療法まで、あなたのたるみの悩みを解決するための情報を網羅的にまとめます。
顔のたるみが起きる根本的な原因
顔のたるみは、単一の原因で起こるわけではありません。皮膚や脂肪、筋肉や骨といった顔を構成する複数の組織が、加齢や外部からのダメージによって複合的に変化して現れます。
これらの組織は顔のハリや立体感を支える土台であり、その構造が崩れるとたるみとして表面に現れるのです。
皮膚の弾力低下
肌のハリや弾力は、真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといった線維状のタンパク質によって支えられています。
しかし、加齢や紫外線の影響でこれらの線維は減少したり、変性したりします。その結果、皮膚は弾力を失い、重力に逆らえなくなり、たるみとして現れるのです。
ヒアルロン酸の減少も、肌の水分保持能力を下げ、乾燥やハリの低下を招きます。
肌の弾力を支える3大要素
| 成分 | 役割 | 加齢による変化 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 肌の構造を支える丈夫な線維 | 減少し、硬くなる(変性) |
| エラスチン | 肌に弾力を与えるゴムのような線維 | 減少し、弾力性が失われる |
| ヒアルロン酸 | 水分を保持し、肌の潤いを保つ | 減少し、肌が乾燥しやすくなる |
皮下脂肪の増減と下垂
顔の皮下脂肪は肌にハリを与え、クッションのような役割を果たしています。しかし、この脂肪も加齢とともに変化します。
若い頃は適切な位置にあった脂肪が、年齢を重ねるとともに減少し、重力の影響で下の方へ移動(下垂)します。
この変化によって頬がこけたり、逆に口元やフェイスラインに脂肪がたまったりする原因となり、顔全体のたるみにつながります。
表情筋の衰えと靭帯のゆるみ
顔には多くの表情筋があり、皮膚や脂肪を支えています。しかし、身体の筋肉と同じように、表情筋も使わないと衰えていきます。
日常的にあまり動かさない筋肉が衰えると、その上にある皮膚や脂肪を支えきれなくなり、たるみを引き起こします。
また、皮膚や脂肪を骨に固定しているリガメント(靭帯)が加齢によってゆるむのもたるみを深刻化させる大きな要因です。
【場所別】おでこ・眉上のたるみ
おでこのたるみは自分では気づきにくいものの、進行すると眉が下がり、眠たそうな印象や不機嫌な表情に見える原因となります。目元やまぶたのたるみにも直結する重要な部分です。
前頭筋の衰えと皮膚の変化
おでこを上下に動かす筋肉である「前頭筋」が衰えると、おでこの皮膚全体を支える力が弱まります。その結果、皮膚が重力に負けて下がり、眉の位置が下がってきます。
また、加齢によるコラーゲンやエラスチンの減少で、おでこの皮膚自体の弾力が失われる状態もたるみを助長します。
無意識の癖と紫外線ダメージ
目を大きく見開こうとするときに、無意識におでこの筋肉を使っている方は注意が必要です。
この癖が続くと前頭筋が過剰に緊張し、横じわの原因になるだけでなく、長期的に見るとたるみにもつながります。
また、おでこは顔の中でも紫外線を浴びやすい部位であり、光老化によるダメージが蓄積しやすい場所でもあります。
おでこのたるみ対策
| 対策の種類 | 具体的な方法 | 期待できること |
|---|---|---|
| トレーニング | 眉を動かさずに目を開閉する練習 | 前頭筋への過度な負担を減らす |
| スキンケア | 保湿と紫外線対策の徹底 | 皮膚の弾力低下を防ぐ |
| マッサージ | 頭皮を優しく引き上げるマッサージ | 前頭筋の緊張を和らげる |
頭皮の硬さとの関連性
顔の皮膚は頭皮と一枚でつながっています。そのため、頭皮が凝り固まっていると顔全体の皮膚を引き上げる力が弱まり、おでこやフェイスラインのたるみにつながります。
長時間のデスクワークやストレスは頭皮の血行不良を招き、硬くなる原因になるため、意識的にほぐす工夫が大切です。
【場所別】まぶたのたるみ
まぶたのたるみは、見た目年齢に最も影響を与えやすい部分の一つです。目が小さく見えたり、視界が狭くなったりと、美容面だけでなく機能面でも悩みが生じる場合があります。
眼輪筋の衰え
まぶたを開閉する役割を持つ「眼輪筋」が衰えると、まぶたの皮膚や脂肪を支えきれなくなります。この影響で上まぶたが垂れ下がり、重たい印象を与えます。
特に、PCやスマートフォンの長時間使用によるまばたきの減少は、眼輪筋の衰えを加速させる一因です。
皮膚の薄さと外部からの刺激
まぶたの皮膚は非常に薄くデリケートで、顔の他の部位に比べて外部からの刺激に弱い特徴があります。
アイメイクを落とす際のゴシゴシ洗い、コンタクトレンズの着脱、花粉症などで目をこする癖などは皮膚の伸縮を繰り返し、コラーゲン線維にダメージを与え、たるみの原因となります。
まぶたのたるみを引き起こす要因
| 内的要因 | 外的要因 |
|---|---|
| 加齢による筋肉の衰え | 目をこするなどの物理的刺激 |
| 遺伝的な要因 | 紫外線によるダメージ |
| コラーゲン・エラスチンの減少 | 乾燥による弾力低下 |
眼瞼下垂との違い
単なる皮膚のたるみだけでなく、まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)の働きが弱まったり、その筋肉とまぶたをつなぐ腱膜がゆるんだりして、まぶたが上がりにくくなる状態を「眼瞼下垂」と呼びます。
これは加齢だけでなく、ハードコンタクトレンズの長期使用などでも起こるケースがあります。たるみと眼瞼下垂が合併している場合もあり、専門的な診断が必要です。
【場所別】頬のたるみ
頬のたるみは、ほうれい線やマリオネットラインといった深いしわを目立たせ、顔全体の印象を疲れさせて見せる大きな要因です。頬の位置が下がると、顔の立体感が失われてしまいます。
頬を支える構造のゆるみ
頬は、皮下脂肪や表情筋、そしてそれらを骨に固定するリガメント(靭帯)によって立体的に支えられています。
加齢により表情筋が衰え、リガメントが伸びてゆるんでしまうと、頬全体の組織を支えきれなくなり雪崩のように垂れ下がってきます。これが頬のたるみの正体です。
皮下脂肪の変化
頬の脂肪は、浅い層にあるものと深い層にあるものに分かれます。加齢によって、これらの脂肪が萎縮したり、逆に重力で下垂したりします。
頬の高い位置にあった脂肪が下がると、ほうれい線の上に乗っかるような形になり、影が深くなってしまいます。
頬のたるみが引き起こすサイン
| サイン | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 小鼻の脇から口角にかけての線 | 頬の脂肪の下垂 |
| ゴルゴライン | 目頭の下から頬の中央を斜めに走る線 | 皮下脂肪の減少と筋肉の衰え |
| マリオネットライン | 口角からあごにかけての線 | 口角周りの脂肪の下垂 |
骨の萎縮による影響
あまり知られていませんが、加齢とともに顔の骨も萎縮していきます。特に、頬骨や上あごの骨が痩せると、その上の皮膚や脂肪を支える土台が小さくなります。
テントの支柱が短くなるように、土台が縮むことで表面の布(皮膚)が余ってしまい、たるみとして現れるのです。
【場所別】フェイスライン・あご下のたるみ
フェイスラインのもたつきや二重あごは、顔の輪郭をぼやけさせ、太った印象や老けた印象を与えます。すっきりとした輪郭は、若々しさの象徴とも言えます。
広頸筋の衰えと皮膚のもたつき
首からあごにかけて広がる薄い筋肉「広頸筋」が衰えると、フェイスライン全体を引き上げる力が弱まり、もたつきの原因となります。
この筋肉は皮膚と直接つながっているため、衰えがたるみとして現れやすい特徴があります。
脂肪の蓄積とリンパの滞り
あご下は脂肪がつきやすい部位です。体重の増加だけでなく、加齢によって代謝が落ちることでも脂肪が蓄積しやすくなります。
また、首周りのリンパの流れが滞ると老廃物や余分な水分がたまり、むくみとなってたるみをさらに悪化させます。この脂肪の蓄積が、いわゆる二重あごの主な原因です。
- 広頸筋の衰え
- 脂肪の蓄積
- リンパの滞り
- 姿勢の悪さ
姿勢がフェイスラインに与える影響
猫背やスマートフォンを見る際のうつむいた姿勢は、フェイスラインのたるみに大きな影響を与えます。頭の重さは約5kgもあり、うつむくと首やあご周りの筋肉に大きな負担がかかります。
この状態が続くと、あご下の皮膚がたるみやすくなるだけでなく血行不良を招き、顔全体のくすみやむくみの原因にもなります。
フェイスラインのたるみ原因
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| 筋肉の衰え | フェイスライン全体がぼやける |
| 脂肪の蓄積 | あご下に脂肪がつき、二重あごになる |
| 姿勢の悪さ | あご下の皮膚がゆるみ、たるみが進行する |
たるみは年齢だけが原因?生活習慣に潜む意外な落とし穴
顔のたるみは加齢だけでなく、スマートフォンを見る姿勢、食いしばりの癖、食事内容、睡眠の質といった日々の生活習慣によっても大きく加速します。
これらの無意識の行動が、肌の土台を内側から崩している可能性があるため、一度ご自身の生活を見直してみましょう。
「スマホ首」がフェイスラインを崩す
スマートフォンやPCを長時間、うつむいた姿勢で見続ける方も多いのではないでしょうか。この姿勢は「スマホ首」とも呼ばれ、首への負担だけでなく、顔のたるみにも深刻な影響を及ぼします。
頭の重みで首からあごにかけての筋肉(広頸筋)が常に引き伸ばされ、弾力を失います。その結果、フェイスラインがぼやけ、二重あごになりやすくなるのです。
意識的に画面を目線の高さに合わせ、定期的に休憩を挟む心がけが重要です。
食いしばり・歯ぎしりがもたらす顔への影響
ストレスや集中しているときに、無意識に歯を食いしばる癖がある方も見受けられます。また、睡眠中に歯ぎしりをしている方も多いようです。
これらの癖は、あごの筋肉(咬筋)を過剰に緊張させます。
咬筋が発達しすぎるとエラが張って顔が大きく見えるだけでなく、口角を引き下げる筋肉にも力が入り、マリオネットラインやフェイスラインのたるみを助長する場合があります。
たるみを招く生活習慣チェック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 姿勢 | 長時間うつむいてスマホやPCを見る |
| 癖 | 無意識に歯を食いしばっている |
| 食事 | 甘いものや加工食品をよく食べる |
| 睡眠 | 睡眠時間が短い、または眠りが浅い |
糖化と酸化が肌のハリを奪う
食事の内容も肌の老化に直結します。糖質の過剰な摂取は、体内で余った糖がタンパク質と結びついて「AGEs(最終糖化産物)」という老化物質を生成する「糖化」を引き起こします。
これが肌のコラーゲンで起こると、コラーゲンが硬くなり弾力を失います。
また、ストレスや紫外線、不規則な生活によって発生する活性酸素は、細胞を傷つける「酸化」を招きます。
糖化と酸化は、肌のたるみを内側から進行させる大きな要因です。
たるみ改善のための美容皮膚科での治療法
セルフケアでは改善が難しい進行したたるみには、美容皮膚科での専門的な治療が有効です。
たるみの原因となる皮膚、脂肪、筋肉の各層に直接働きかけて効果的なリフトアップを目指します。
HIFU(ハイフ)-超音波によるリフトアップ
高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)の略で、超音波の熱エネルギーを皮膚の深層にあるSMAS(筋膜)層にピンポイントで照射します。
SMAS層は皮膚の土台となる部分で、ここに熱を加えて組織を収縮させ、強力なリフトアップ効果をもたらします。
メスを使わずに土台から引き上げられるのが大きな特徴です。
高周波(RF)治療-肌の引き締め
高周波(ラジオ波)の熱エネルギーを真皮層に与えてコラーゲン線維を収縮させ、即時的な引き締め効果を生み出します。
さらに、熱刺激によって線維芽細胞が活性化され、新たなコラーゲンの生成を促進するため、長期的なハリ・弾力アップにつながります。皮膚の浅い層の引き締めに特に効果的です。
代表的な美容治療法の比較
| 治療法 | アプローチする層 | 主な効果 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | SMAS(筋膜)層 | リフトアップ(土台からの引き上げ) |
| 高周波(RF) | 真皮層・皮下脂肪層 | スキンタイトニング(肌の引き締め) |
| 糸リフト | 皮下組織 | 物理的な引き上げとコラーゲン生成 |
注入治療と糸リフト
ヒアルロン酸注入は、たるみによってできた溝や影(ほうれい線など)を埋めたり、ボリュームが減少した部分(頬やこめかみなど)を補ったりしながら顔全体のバランスを整えます。
一方、糸リフト(スレッドリフト)はコグ(とげ)のついた特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ組織を物理的に引き上げる治療です。
どちらも医師の技術とデザイン力が結果を大きく左右します。
治療を受ける前に知っておきたいこと
自分に合ったたるみ治療を受け、満足のいく結果を得るためには、治療前の情報収集とクリニック選びが非常に重要です。
後悔しないためにも、カウンセリングの質や費用の透明性などを事前に確認しましょう。
医師の経験とカウンセリング
たるみ治療は一人ひとりの骨格や脂肪のつき方、たるみの原因を見極めて、適切な治療法を選択するオーダーメイドの取り組みが必要です。そのため、たるみ治療の経験が豊富な医師を選ぶことが大切です。
また、カウンセリングで自分の悩みをしっかりと聞き、治療法のメリットだけでなく、デメリットやリスクについても丁寧に説明してくれるクリニックを選びましょう。
費用と治療内容の透明性
治療にかかる費用が明確であることは、安心して治療を受けるための基本です。提示された金額に、診察料やアフターケアの費用などがすべて含まれているかを確認します。
複数の治療法を組み合わせる提案をされた場合は、なぜその組み合わせが必要なのか、それぞれの治療がどのような役割を果たすのかを納得できるまで質問すると良いでしょう。
アフターケアの充実度
治療後の経過は個人差があり、予期せぬ症状が現れる可能性もゼロではありません。
万が一の際に、迅速かつ適切に対応してくれる体制が整っているか、治療後の診察や相談がしやすい環境であるかを確認しておきましょう。
アフターケアがしっかりしているクリニックは、患者さんを第一に考えている証拠とも言えます。
顔のたるみに関するよくある質問
顔のたるみは肌の表面だけでなく、真皮層のタンパク質や表情筋、骨といった深い部分の衰えによって起こります。
もともとの体質や肌質なども関係しますが、生活習慣や癖、姿勢やスキンケアの仕方などがたるみを助長しているケースが多いです。
気になるたるみを改善するためにまずは普段の生活を振り返り、レチノールやビタミンC、ナイアシンアミドやペプチドなどの美容成分が含まれた化粧品を使用するのも有効です。
ただし、セルフケアには限界がありますので、より積極的に顔のたるみを解消したい方は美容医療を検討してみても良いでしょう。
- セルフケアだけでたるみは改善します
-
セルフケアだけで一度できてしまったたるみを完全に元に戻すのは難しいですが、予防や進行を遅らせる点では非常に重要です。
保湿や紫外線対策、表情筋トレーニング、マッサージなどは、たるみの進行を防ぎ、肌の健康を保つ助けになります。
しかし、SMAS(筋膜)のゆるみや脂肪の下垂といった根本的な原因に働きかけるためには、美容医療の力が必要になるケースが多いです。
- 治療の効果はどのくらい続きますか?
-
効果の持続期間は、受けた治療の種類や個人の体質、そして生活習慣によって大きく異なります。
例えば、HIFUや高周波治療は半年から1年程度、糸リフトは1年から2年程度が目安とされる場合が多いです。
効果を長持ちさせるためには、治療後も日々の紫外線対策や保湿ケアを続け、健康的な生活習慣を心がけましょう。
- 治療後のダウンタイムはありますか?
-
ダウンタイムの有無や程度は治療法によって様々です。
HIFUや高周波治療のようにメスを使わない治療は、赤みや軽い腫れが出る場合はありますが、ダウンタイムはほとんどなく、施術後すぐにメイクをして帰宅できる方が多いです。
一方、糸リフトや注入治療では、内出血や腫れが数日から1週間程度続くことがあります。
カウンセリングの際に、ご自身の生活スタイルを伝え、ダウンタイムについて詳しく確認しておくと安心です。
- 自分に合った治療法がわかりません。
-
ご自身に合った治療法を見つけるためには、専門家である医師の診断を受けるのが一番の近道です。たるみの原因は一人ひとり異なるため、自己判断で治療法を決めるのは難しいものです。
経験豊富な医師は、あなたの顔の状態を正確に診察し、たるみの原因を特定した上で、希望や予算、生活スタイルに合わせた治療プランを提案してくれます。
まずは気軽にカウンセリングで相談してみると良いでしょう。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
RYU, Min-Hee, et al. Reframing the etiology of facial sagging from a facelift perspective. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2018, 6.7: e1831.
EZURE, T., et al. Sagging of the cheek is related to skin elasticity, fat mass and mimetic muscle function. Skin Research and Technology, 2009, 15.3: 299-305.
TSUKAHARA, Kazue, et al. Comparison of age-related changes in facial wrinkles and sagging in the skin of Japanese, Chinese and Thai women. Journal of dermatological science, 2007, 47.1: 19-28.
PANDA, Arun Kumar; CHOWDHARY, Aarti. Non-surgical modalities of facial rejuvenation and aesthetics. In: Oral and maxillofacial surgery for the clinician. Singapore: Springer Nature Singapore, 2021. p. 661-689.
ALLAHYARI FARD, Shahab. Surgical and non-surgical methods in facial rejuvenation. 2018.
D’SOUZA, Alwyn R.; NG, Chew Lip. Non-surgical facial rejuvenation. Oxford Textbook of Otolaryngology, 2025, 309.
CHOE, W. J., et al. Thread lifting: a minimally invasive surgical technique for long-standing facial paralysis. Hno, 2017, 65.11: 910-915.
HAYKAL, Diala, et al. A Systematic Review of High-Intensity Focused Ultrasound in Skin Tightening and Body Contouring. Aesthetic Surgery Journal, 2025, 45.7: 690-698.