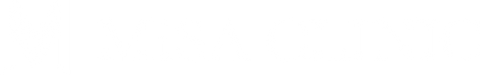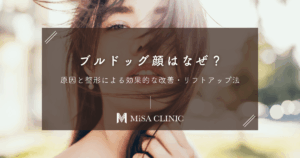顔が垂れてきた?原因と今すぐできるリフトアップ対策【セルフケア~医療】

ふと鏡を見たときに「なんだか顔が垂れてきたかも…」と感じたことはありませんか?
頬の位置が下がったり、フェイスラインがぼやけたりすると、年齢以上に疲れた印象を与えてしまいます。顔が垂れ下がる状態は、見た目の印象を大きく左右する深刻な悩みです。
この記事では、なぜ顔が垂れてきたと感じるのか、その主な原因を解説し、今日から始められるセルフケアから美容クリニックで行う本格的なリフトアップ治療まで、幅広く対策を紹介します。
なぜ「顔が垂れてきた」と感じるのか?たるみのサイン
「顔が垂れてきた」と感じるのは、皮膚やその下の組織が重力の影響で下がってくる「たるみ」のサインです。
ほうれい線が目立つ、フェイスラインがぼやける、毛穴が縦に開くなど、初期の兆候を早期に発見し対策を始めることが重要です。
鏡でチェックするたるみの初期症状
たるみはゆっくりと進行するため、日々の小さな変化に気づきにくいものです。しかし、特定のサインに注目すると、初期段階でも顔の垂れを自覚できます。
例えば、以前は気にならなかったほうれい線が目立つようになった、頬の一番高い位置が下がってきた、フェイスラインがはっきりしなくなった、などが挙げられます。
特に朝よりも夕方になると顔が疲れて見える、影が目立つと感じる場合は、たるみが始まっている可能性があります。
たるみのセルフチェックポイント
| チェック項目 | 主な症状 | 関連部位 |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 以前より深く、長くなった | 頬、口元 |
| フェイスライン | あご周りがぼんやりしてきた | あご、首 |
| 毛穴の形 | 丸ではなく、涙型(縦)に開いている | 頬 |
顔が垂れ下がると生じる見た目の変化
顔が垂れ下がると、見た目に様々な変化が現れます。最も顕著なのは、顔全体の重心が下がることで、若々しさが失われる点です。
頬が下がるとほうれい線やマリオネットライン(口角からあごにかけての線)が深くなります。また、フェイスラインのもたつきは二重あごのように見える原因にもなります。
目元も例外ではなく、上まぶたが垂れ下がると目が小さく見えたり、目の下の皮膚がたるむとクマや影ができやすくなったりします。
たるみとシワの違いとは
たるみとシワは混同されがちですが、根本的に異なります。
シワは、主に皮膚の表面(表皮)が乾燥したり、表情の癖で折り目がついたりするために発生します。
一方、たるみは皮膚のさらに奥深く(真皮)や、皮下脂肪、筋肉といった顔の構造全体が重力や加齢の影響で緩み、下がってくる状態を指します。
「顔が垂れてきた」と感じる場合、それは表面的なシワだけでなく、より深刻なたるみが原因であるケースが多いのです。
年齢だけではない!顔が垂れる要因
たるみの最大の要因は加齢ですが、それだけではありません。若い方でも「顔が垂れてきた」と感じるケースは増えています。
紫外線対策を怠る(光老化)、スマートフォンの長時間使用によるうつむき姿勢、急激なダイエットによる皮膚の余り、さらには食生活や睡眠不足といった生活習慣の乱れも、顔が垂れる要因となります。
これらの要因が複合的に絡み合うと、たるみの進行を早めてしまいます。
顔が垂れる主な原因を徹底解説
顔が垂れ下がる主な原因は、加齢によるコラーゲン減少、表情筋の衰え、紫外線ダメージ、そして生活習慣の乱れです。これらの要因が複合的に絡み合い、皮膚やその下の構造に変化を引き起こします。
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
私たちの肌のハリや弾力は、皮膚の真皮層に存在するコラーゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)によって支えられています。
コラーゲンが肌の構造をしっかりと保ち、エラスチンがその構造に柔軟性を与えています。
しかし、加齢とともにこれらの線維を生み出す「線維芽細胞」の働きが衰えます。その結果、コラーゲンやエラスチンが減少し、質も低下します。
肌を支える力が弱まると皮膚は重力に耐えきれず、顔が垂れてきた状態になります。
肌の弾力を支える主要成分
| 成分名 | 主な役割 | 加齢による変化 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 肌の構造を支える(ハリ) | 量・質ともに低下する |
| エラスチン | 肌に弾力を与える(弾力) | 減少し、変性する |
| ヒアルロン酸 | 水分を保持する(うるおい) | 産生量が減少する |
表情筋の衰えと顔の構造
顔の皮膚や脂肪は、「表情筋」という筋肉によって支えられています。体の筋肉と同様に、表情筋も使わなければ衰えます。
特に現代人は、会話の減少や無表情でいる時間が長くなることにより、表情筋を使う機会が減りがちです。表情筋が衰えると、その上にある脂肪や皮膚を支えきれなくなり、顔が垂れ下がってしまいます。
また、加齢により筋肉自体も痩せていくため、たるみを助長します。
紫外線(光老化)が肌に与えるダメージ
たるみの原因として、加齢と同じくらい深刻なのが「光老化」、すなわち紫外線によるダメージです。
紫外線の中でも特に波長の長いUVA(紫外線A波)は、皮膚の奥深く、真皮層にまで到達します。そして、肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンを変性させ、破壊します。
長年にわたって紫外線を浴び続けるとダメージが蓄積し、年齢以上に顔の垂れが進行します。日焼け止めを塗る習慣がない、または塗り直しをしない人は、光老化のリスクが非常に高くなります。
生活習慣の乱れとたるみの関係
日々の何気ない生活習慣も、顔が垂れてきたと感じる原因になります。例えば、睡眠不足は肌のターンオーバー(再生)を妨げ、線維芽細胞の働きを鈍らせます。
栄養バランスの偏った食事、特に糖質の過剰摂取は、体内で「糖化」を引き起こします。糖化はコラーゲンを硬く、もろくするため、肌の弾力を奪います。
喫煙も血行を悪化させ、肌に必要な栄養や酸素が届きにくくなるため、たるみを促進します。
たるみを加速させる生活習慣
| 習慣 | たるみへの影響 |
|---|---|
| うつむき姿勢(スマホ) | あご周りの筋肉が緩み、フェイスラインがもたつく |
| 睡眠不足 | 肌の修復・再生機能が低下する |
| 糖質の過剰摂取 | 「糖化」によりコラーゲンが硬くなる |
【セルフケア編】今すぐ始めたいリフトアップ対策
「顔が垂れてきた」と感じ始めたら、まずはセルフケアの見直しが必要です。
紫外線対策や保湿、表情筋トレーニングや食生活の改善など、日々の積み重ねによってたるみの進行を遅らせ、現状維持を目指しましょう。
日常でできる紫外線対策の基本
光老化を防ぐ習慣は、リフトアップ対策の基本中の基本です。紫外線は一年中、天候に関わらず降り注いでいます。外出時はもちろん、室内でも窓際で過ごす場合は日焼け止めを使用する習慣をつけましょう。
SPF値だけでなく、たるみの原因となるUVAを防ぐ「PA値」にも注目し、PA++++など効果の高いものを選ぶのがおすすめです。
また、汗や摩擦で落ちてしまうため、2〜3時間おきに塗り直すと良いです。
たるみを防ぐ保湿スキンケア
肌が乾燥するとバリア機能が低下し、紫外線などの外的ダメージを受けやすくなります。これがたるみの遠因となります。
また、乾燥は小ジワを目立たせ、たるみを一層強調します。スキンケアでは化粧水で水分を与えるだけでなく、必ず乳液やクリームなどの油分でフタをし、水分蒸発を防ぎましょう。
コラーゲンやエラスチンの生成をサポートするレチノールやビタミンC誘導体、保湿力の高いセラミドやヒアルロン酸が配合されたエイジングケア化粧品を取り入れるのも効果的です。
顔の筋肉を鍛える表情筋トレーニング
皮膚や脂肪を支える土台である表情筋を鍛える取り組みも、顔が垂れ下がるのを防ぐ対策になります。
ただし、やみくもに動かすと逆にシワの原因になる場合もあるため、正しい方法で行う必要があります。
- 口角を上げる(「いー」と「うー」を繰り返す)
- 頬を膨らませる・すぼめる
- 目を大きく見開く・閉じる
これらの動きを、鏡を見ながらゆっくりと、意識して行うのがポイントです。
食生活で見直したいポイント
体は食べたもので作られています。肌のハリを保つためにも、栄養バランスの取れた食事が重要です。
特に、コラーゲンの材料となるタンパク質(肉、魚、大豆製品、卵)と、その合成を助けるビタミンC(野菜、果物)を積極的に摂取しましょう。
また、抗酸化作用のあるビタミンA(緑黄色野菜)やビタミンE(ナッツ類、アボカド)も、肌の老化を防ぐのに役立ちます。
逆に、糖化を進める甘いお菓子やジュース、ジャンクフードは控えるよう心がけましょう。
【セルフケア編】マッサージと美顔器の正しい使い方
マッサージや美顔器は、正しく使えばセルフケアの効果を高めますが、使い方を誤るとたるみを悪化させる危険もあります。摩擦を避け、適切な方法と頻度を守りましょう。
やりすぎ禁物!顔マッサージの注意点
顔のマッサージは血行やリンパの流れを促進し、むくみ解消やくすみの改善に役立ちます。
しかし、強い力でこすったり長時間やりすぎたりすると、肌に摩擦ダメージを与えてしまいます。この摩擦が、たるみやシミの原因になるときもあります。
マッサージを行う際は、必ずクリームやオイルをたっぷり使い、滑りを良くした状態で行いましょう。指の腹を使い、「こする」のではなく「優しく圧をかける」「流す」程度の力加減が大切です。
リンパの流れを意識したケア方法
顔が垂れてきたと感じる原因の一つに、老廃物が溜まって起こる「むくみ」があります。むくみが定着すると、その重みでたるみが助長されます。
リンパマッサージは、この老廃物を排出するのに効果的です。顔の中心から外側へ、そして耳の下から鎖骨に向かって、リンパ節に優しく流していくイメージで行います。
特にフェイスラインやあごの下は老廃物が溜まりやすいので、丁寧に行いましょう。
美顔器の種類と選び方
家庭用美顔器には様々な種類があり、機能によって期待できる効果が異なります。顔が垂れ下がる悩みに働きかける主な機能を紹介します。
主な家庭用美顔器の機能
| 機能 | 主な働き | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| EMS | 電気刺激で表情筋を動かす | 筋肉の引き締め、トレーニング |
| RF(ラジオ波) | 高周波で肌の奥を温める | 血行促進、ハリ感アップ |
| イオン導入 | 微弱な電流で美容成分を浸透させる | 保湿、美白(使用する美容液による) |
たるみ対策としては、表情筋に作用するEMSや、肌の奥を温めてハリを出すRF(ラジオ波)が人気です。自分の肌悩みや生活スタイルに合ったものを選びましょう。
美顔器使用時のポイントと頻度
美顔器は、毎日使えばよいというものではありません。製品ごとに推奨される使用頻度(週に2〜3回など)が定められています。過度な使用は肌の負担になるため、必ず説明書を守りましょう。
また、使用する際は、専用のジェルや美容液を使うのが重要です。これらは、電気や熱を効率よく伝えたり、肌の摩擦を防いだりする役割があります。
自己判断で水や他の化粧品を使うと、効果が出ないばかりか、肌トラブルの原因にもなります。
美容皮膚科でのリフトアップ治療(照射・注入)
セルフケアで改善が難しい顔のたるみには、美容皮膚科での治療が有効です。
メスを使わないHIFU(ハイフ)などの「照射治療」や、ヒアルロン酸などの「注入治療」が、ダウンタイムが少なく人気を集めています。
照射治療(HIFU・高周波)の特徴
照射治療は、超音波や高周波(RF)などのエネルギーを肌に照射し、たるみを引き締める治療法です。
特にHIFU(ハイフ)は、高密度焦点式超音波を用い、皮膚の土台であるSMAS(スマス)筋膜に直接熱エネルギーを加えて引き締められます。メスを使わずに深い層に作用するのが特徴です。
高周波(RF)治療は主に真皮層を加熱し、コラーゲンの産生を促して肌のハリを引き出します。
主な照射治療の比較
| 治療法 | アプローチ層 | 主な効果 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | SMAS筋膜・皮下脂肪 | 土台からの引き上げ、引き締め |
| 高周波(RF) | 真皮層・皮下脂肪 | 肌の引き締め、ハリ感アップ |
| レーザー | 表皮・真皮浅層 | 肌表面のハリ、キメ改善 |
注入治療(ヒアルロン酸・ボトックス)の役割
注入治療は、薬剤を注射してシワやたるみを改善します。
ヒアルロン酸注入は、加齢によって減少したボリューム(頬のこけ、こめかみの凹みなど)を補ったり、ほうれい線などの溝を埋めたりするのに用います。
顔が垂れ下がって生じた影を目立たなくさせ、若々しい印象を取り戻します。
一方、ボトックス(ボツリヌス・トキシン)注入は、筋肉の動きを一時的に抑える作用があります。
主に表情ジワ(眉間、目尻)に使われますが、あご周りの筋肉(広頚筋)の働きを弱めてフェイスラインをすっきりさせる治療にも応用されます。
治療のダウンタイムと持続期間
照射治療や注入治療の多くは、メスを使わないためダウンタイム(回復期間)が短いか、ほとんどない点がメリットです。
HIFUや高周波は施術直後に多少の赤みやほてりが出る場合がありますが、数時間〜数日で治まる方が多く、すぐにメイクも可能です。
注入治療もまれに内出血が出るときがありますが、メイクで隠せる程度です。
効果の持続期間は治療法や個人差によりますが、HIFUは半年〜1年程度、ヒアルロン酸は製剤によりますが半年〜2年程度が目安です。
自分に合う治療法の見つけ方
顔が垂れてきた原因やたるみの程度は人それぞれです。「頬の脂肪が多い」「皮膚が薄い」「骨格が影響している」など、状態によって適した治療は異なります。
HIFUが適している人もいれば、ヒアルロン酸でボリュームを補う方が効果的な人もいます。自己判断せず、経験豊富な医師の診察を受け、自分のたるみのタイプを見極めてもらいましょう。
美容整形(外科手術)によるリフトアップ
進行したたるみや、他の治療法で満足できない場合には、外科手術が根本的な改善策となります。
SMAS筋膜から引き上げる「フェイスリフト」や、糸で組織を引っ張り上げる「糸リフト」が主な方法です。
フェイスリフト手術とは
フェイスリフトは耳の前後などの目立たない部分の皮膚を切開し、皮膚だけでなくSMAS筋膜を引き上げて固定し、余分な皮膚を切除する手術です。
顔が垂れてきた原因である土台の緩みを直接修正するため、リフトアップ効果を非常に実感しやすく、持続期間も長いのが特徴です。
頬やフェイスライン、首のたるみまで広範囲に改善が期待できます。効果を感じやすい反面、他の治療に比べてダウンタイムは長くなります。
糸リフト(スレッドリフト)の効果と特徴
糸リフト(スレッドリフト)は、コグ(トゲ)のついた特殊な医療用の糸を皮下に挿入し、組織を引っかけて引き上げる治療です。
切開を伴うフェイスリフトに抵抗がある方でも受けやすいのが特徴です。糸の挿入による刺激で、コラーゲン生成が促進される効果も期待できます。
使用する糸の種類や本数によって、引き上げ効果や持続期間が変わります。挿入する糸は、時間とともに体内に吸収されるものが主流です。
外科的リフトアップの比較
| 治療法 | 切開の有無 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| フェイスリフト | あり | SMAS筋膜から引き上げる。効果・持続性を実感しやすい。 |
| 糸リフト | なし(針穴のみ) | 糸のトゲで組織を引っ張り上げる。ダウンタイムが短い。 |
外科手術のメリットとデメリット
外科手術の最大のメリットは、一度の施術で得られる変化の大きさと、効果の持続性です。特にフェイスリフトは、他の方法では難しい首のたるみにも良い効果を発揮します。
一方、デメリットとしては、必ずダウンタイムが生じる点です。フェイスリフトでは、大きな腫れや内出血が引くまでに数週間を要する場合があります。
また、切開を伴うため、傷跡が残るリスク(通常は目立たなくなります)や、費用が高額になる点も考慮が必要です。
クリニック選びで重要なこと
外科手術は医師の技術と経験が結果を大きく左右します。顔が垂れ下がるといっても、その状態は人によって異なります。
自分の希望をしっかりと聞いた上で、顔全体のバランスを見て適した術式を提案してくれる医師を選ぶようにしましょう。
- 解剖学的な知識が豊富か
- 症例数が多く、実績があるか
- リスクやデメリットも隠さず説明するか
これらの点を確認し、複数のクリニックでカウンセリングを受けて比較検討するのがおすすめです。
たるみ治療のリスクとアフターケア
美容医療によるたるみ治療は効果が期待できる一方、副作用などのリスクも伴います。
治療のリスクを理解し、ダウンタイム中の過ごし方や治療後のセルフケアといったアフターケアを徹底すると、安全で満足のいく結果につながります。
治療後に起こり得る副作用やトラブル
どのような治療にも、副作用やリスクは存在します。美容医療は医療行為であり、100%安全とは言い切れません。
治療別の主なリスク
| 治療分類 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|
| 照射治療 (HIFU等) | 赤み、腫れ、ほてり、一時的な神経鈍麻、まれに火傷 |
| 注入治療 | 内出血、腫れ、痛み、左右差、まれにアレルギーや血流障害 |
| 外科手術 (糸・切開) | 強い腫れ、内出血、痛み、感染、傷跡、ひきつれ感、左右差 |
これらの多くは一時的なものですが、万が一、強い痛みや通常とは異なる症状が続く場合は、すぐに施術を受けたクリニックに連絡してください。
ダウンタイム中の正しい過ごし方
ダウンタイムをいかに安静に過ごすかが、仕上がりを左右します。特に外科手術後は、医師の指示を厳守しましょう。
- 施術当日は飲酒、長時間の入浴、激しい運動を避ける(血行が良くなると腫れが悪化するため)
- 処方された薬(抗生剤や痛み止め)は正しく服用する
- 患部を強くこすったり、マッサージしたりしない
- 紫外線対策を徹底する(治療後の肌はデリケートなため)
照射治療や注入治療でも、施術後しばらくは肌が敏感になっています。過度な刺激を避け、保湿と紫外線対策を心がけてください。
治療効果を長持ちさせるセルフケア
クリニックでの治療は顔が垂れ下がる状態を一時的に改善するものですが、その後の老化を止めるものではありません。治療効果をできるだけ長く維持するためには、日々のセルフケアが必要です。
紫外線対策と保湿は、治療前と同様に最も重要です。
また、HIFUや高周波でコラーゲン生成を促した場合、その材料となるタンパク質やビタミンCを食事からしっかり摂取する工夫も効果の維持に役立ちます。
生活習慣を整え、たるみの原因となる行動(うつむき姿勢、喫煙、睡眠不足)を避ける努力も続けましょう。
信頼できる医師との相談の重要性
美容医療は、医師との信頼関係の上で成り立つものです。自分の顔の垂れの悩みを正確に伝え、医師はそれに対して実現可能な治療法と、その限界やリスクを正直に説明する必要があります。
カウンセリングで、メリットばかりを強調したり、高額な治療ばかり勧めたりするクリニックは注意が必要です。
自分の不安や疑問に丁寧に答えてくれ、万が一トラブルが起きた際にも誠実に対応してくれる医師を選ぶと、安心して治療を受けられるでしょう。
顔が垂れてきた悩みに関するよくある質問
顔が垂れてきたと感じると、それがコンプレックスとなり人に会うのを避けてしまう方もいます。
初期の段階であればセルフケアでもある程度の改善が見込めますので、まずは紫外線対策や保湿、生活習慣の改善などを徹底してみましょう。
努力していてもたるみが良くならない、進行していると感じるときは、美容医療を検討する良いタイミングです。
- 顔のたるみはセルフケアだけで改善できますか?
-
残念ながら、一度垂れてしまったたるみをセルフケアだけで完全に元に戻すのは困難です。
セルフケアの主な目的は、たるみの「予防」と「進行を遅らせる」です。保湿や紫外線対策、表情筋トレーニングは、肌の健康を保ち、これ以上顔が垂れ下がるのを防ぐために非常に重要です。
しかし、すでに深く刻まれたほうれい線や、SMAS筋膜の緩みによる根本的なたるみを改善するには、美容医療の力が必要になる場合が多いです。
- HIFU(ハイフ)はどのくらいの頻度で受けるのが良いですか?
-
目安として、半年に1回から1年に1回程度を推奨するクリニックが多いです。
HIFUは施術直後から引き締まりを感じる場合もありますが、熱ダメージによってコラーゲンが再構築される1〜3ヶ月後に最も効果を実感します。効果は半年から1年ほど持続するといわれます。
頻繁に受けすぎると、逆に組織が硬くなったり、顔がこけてしまったりするリスクもあるため、医師が肌の状態を見て判断する適切な間隔を守りましょう。
- 糸リフトは何本くらい入れるのが一般的ですか?
-
挿入する本数は、たるみの程度や引き上げたい範囲、使用する糸の種類によって大きく異なります。
一概には言えませんが、フェイスライン全体を引き上げる場合、片側で4本〜6本程度(両側で8本〜12本程度)を使用するのが一つの目安となります。
ただ、本数が多ければ多いほど良いというわけではありません。たるみの状態や骨格に合わせて、適切な位置に適切な本数を挿入する医師の技術が求められます。
カウンセリングでご自身の状態に何本必要かを確認してください。
- たるみ治療は痛いですか?
-
治療法によって痛みの感じ方は異なります。HIFUは、骨に近い部分や神経の近くで「ズーンと響くような痛み」や「熱感」を感じるときがあります。
注入治療は、針を刺すチクッとした痛みや、薬剤が入る時の鈍い痛みを感じる場合があります。
糸リフトや外科手術は、局所麻酔や静脈麻酔を使用するため、施術中の痛みはほとんどありませんが、麻酔が切れた後に数日間は痛みや違和感が続くケースがあります。
多くの治療では、痛みを軽減するために麻酔クリームや冷却などの対策を行いますので、痛みが不安な方は事前に医師にご相談ください。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
GARCIA, Aline de Souza Massulo, et al. Manual therapy in the treatment of facial wrinkles and sagging: a quantitative-qualitative randomized clinical trial. Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal, 2020, 17: 0-0.
EZURE, T., et al. Sagging of the cheek is related to skin elasticity, fat mass and mimetic muscle function. Skin Research and Technology, 2009, 15.3: 299-305.
MUIZZUDDIN, Neelam. Change in facial morphology with age.
LIM, Hyoung Won. Effects of facial exercise for facial muscle strengthening and rejuvenation: systematic review. The Journal of Korean Physical Therapy, 2021, 33.6: 297-303.
M. SMITH, Abigail, et al. Non-traditional and non-invasive approaches in facial rejuvenation: a brief review. Cosmetics, 2020, 7.1: 10.
CUNHA, MG da; PARAVIC, Francisca Daza; MACHADO, Carlos A. Histological changes of collagen types after different modalities of dermal remodeling treatment: a literature review. Surg Cosmet Dermatol, 2015, 7.4: 285-92.
KO, E. J., et al. Efficacy and safety of non‐invasive body tightening with high‐intensity focused ultrasound (HIFU). Skin Research and Technology, 2017, 23.4: 558-562.
AYATOLLAHI, Azin, et al. Systematic review and meta-analysis of safety and efficacy of high-intensity focused ultrasound (HIFU) for face and neck rejuvenation. Lasers in Medical Science, 2020, 35.5: 1007-1024.