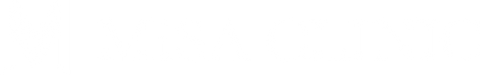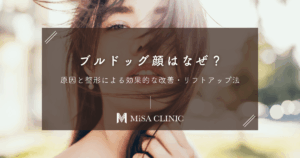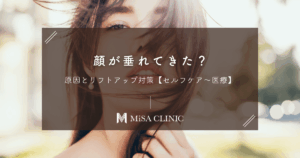顔の下半分の皮膚たるみ改善!原因と効果的なリフトアップ法を紹介

顔の下半分は年齢が出やすく、皮膚のたるみが目立ち始めると、一気に老けた印象や疲れた印象を与えてしまいます。
ほうれい線や頬のたるみ、フェイスラインのもたつきを改善したいと来院される方は少なくありません。
この記事では、なぜ顔の下半分の皮膚がたるむのか、その原因を深く掘り下げるとともに、ご自身でできる予防策から美容クリニックで受けられる効果的なリフトアップ法まで、詳しく解説します。
顔の下半分がたるむとは?初期サインを見逃さないで
顔の下半分がたるむと、ほうれい線が深くなったりマリオネットラインが現れたり、フェイスラインがぼやけたりする初期サインが見られます。対策を行うためには、初期サインを見逃さないようにしましょう。
ほうれい線が目立ってきた
ほうれい線は、小鼻の横から口角にかけて伸びるシワです。もともとは誰にでもあるものですが、頬の皮膚がたるむと、この線が深く長くなったように感じます。
ファンデーションが溜まりやすくなったり、無表情でも線がくっきり見えたりする場合は、顔の皮膚たるみの初期サインかもしれません。
マリオネットライン(口角のシワ)が気になる
マリオネットラインは、口角からあご先に向かって伸びる線です。まるで腹話術の人形(マリオネット)の口元のように見えるためこの名がつきました。
口角が下がり、不機嫌そうな印象を与える原因にもなります。これも頬や口周りの皮膚、そして脂肪が下垂すると現れるたるみのサインです。
フェイスラインがぼやけてきた
以前はシャープだったあごのライン(フェイスライン)が、ぼんやりとしてきた、あるいは二重あごのようになったと感じる場合、それは顔の下半分のたるみが進行している証拠かもしれません。
頬やあご下の皮膚がゆるみ、重力に従って下がるため顔と首の境界線が曖昧になります。正面からだけではなく、横顔のチェックも重要です。
たるみの初期サインセルフチェック
| チェック項目 | 状態 | 主な原因 |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 以前より深く、長くなった | 頬の皮膚・脂肪の下垂 |
| マリオネットライン | 口角から下に線が見える | 口周りの皮膚のゆるみ |
| フェイスライン | あごのラインがぼんやりした | 頬・あご下の皮膚の下垂 |
なぜ顔の下半分はたるみやすいのか?主な原因
顔の下半分がたるみやすいのは、加齢によるコラーゲン減少、表情筋やSMAS(筋膜)のゆるみ、紫外線ダメージの蓄積、さらには骨格の萎縮といった複数の要因が複雑に重なり合うためです。
加齢によるコラーゲン・エラスチンの減少
肌のハリや弾力を支えているのは、真皮層にあるコラーゲン(膠原線維)とエラスチン(弾性線維)です。これらは肌の「バネ」や「ゴム」のような役割を果たします。
しかし、加齢とともに、これらを生成する線維芽細胞の働きが低下し、コラーゲンやエラスチンは質・量ともに減少、変性していきます。結果として肌は弾力を失い、重力に逆らえずにたるんでいきます。
表情筋の衰えとSMAS(筋膜)のゆるみ
顔の皮膚は、その下にある表情筋と連動しています。しかし、加齢や無表情の習慣化によって表情筋は衰えます。
さらに重要なのが、皮膚と筋肉の間にある「SMAS(スマス)層」という筋膜の存在です。SMAS層は顔の皮膚や脂肪を支える土台のようなものですが、加齢によりこのSMAS層もゆるみます。
土台がゆるむと、その上にある皮膚や脂肪も一緒に下垂し、顔の下半分のたるみとして現れます。
紫外線ダメージの蓄積
たるみの最大の外的要因の一つが紫外線です。特にUVA(紫外線A波)は、肌の奥深く真皮層にまで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊、変性させます(光老化)。
日焼け止めを塗る習慣がなかったり対策が不十分だったりすると、長年の紫外線ダメージが蓄積し、肌の弾力低下を早めてたるみを引き起こします。
骨格の変化(骨の萎縮)
あまり知られていませんが、加齢によって顔の骨(特に頬骨や下あごの骨)も萎縮し、痩せていきます。
骨は皮膚や脂肪を支える「柱」の役割を担っています。その柱が小さくなると、支えを失った皮膚や脂肪は行き場をなくし、たるみとなって現れます。
特に下あごの骨が萎縮すると、フェイスラインのもたつきが顕著になります。
顔のたるみを引き起こす要因
| 要因の層 | 具体的な原因 | たるみへの影響 |
|---|---|---|
| 皮膚(表皮・真皮) | コラーゲン・エラスチンの減少 | 肌のハリ・弾力の低下 |
| 皮下脂肪 | 脂肪の増減・下垂 | ボリュームの変化、重みによるたるみ |
| 筋膜(SMAS) | SMAS層のゆるみ | 皮膚・脂肪を支える力の低下 |
| 筋肉(表情筋) | 表情筋の衰え | 皮膚を支える力の低下 |
| 骨格 | 加齢による骨の萎縮 | 土台となる支持構造の減少 |
生活習慣以外の隠れた要因
顔のたるみは加齢や紫外線だけでなく、噛み合わせの悪さ、肩こりや首こりによる血流停滞、無意識の表情のクセ、睡眠中の姿勢といった見落としがちな生活習慣の中の要因も影響を与えています。
噛み合わせや歯並びの影響
噛み合わせが悪い、あるいは歯並びが乱れていると、食事の際に使う筋肉に偏りが生じます。片方だけで噛むクセがある場合も同様です。よく使う側の筋肉は発達し、使わない側の筋肉は衰えます。
この左右のアンバランスが、顔のゆがみや片側だけのほうれい線が目立つといった、顔の下半分のたるみにつながるケースがあります。
また、歯を失ったまま放置すると骨格の変化を招き、たるみの原因となります。
肩こり・首こりと血流の関係
顔と首、肩はすべてつながっています。現代人に多い長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、慢性的な肩こりや首こりを引き起こします。
首や肩の筋肉が緊張し硬くなると、顔への血流やリンパの流れが滞ります。血流やリンパの流れが滞ると顔の皮膚の新陳代謝が悪化し、老廃物が蓄積しやすくなります。
結果として、顔がむくみやすくなり、その重みでたるみが助長される場合があります。
こりとたるみの関係性
| 部位 | 状態 | 顔への影響 |
|---|---|---|
| 首・肩 | 筋肉の緊張・こり | 血流・リンパの停滞 |
| 顔 | 老廃物の蓄積・むくみ | 代謝低下・たるみの助長 |
無意識の表情のクセ
普段、無意識に口角が下がっていませんか?スマートフォンを見ているとき、集中して仕事をしているとき、多くの人が真顔、あるいは口角が下がった「不機嫌顔」になりがちです。
口角を下げる筋肉(口角下制筋)ばかりが使われ、口角を上げる筋肉(口角挙筋など)が衰えると、口元のたるみやマリオネットラインが定着しやすくなります。
睡眠中の姿勢が与える影響
毎日の睡眠時間、どのような姿勢で寝ているか振り返ってみましょう。
横向きやうつ伏せで寝る習慣があると、長時間にわたって顔の片側に圧力がかかり続けます。この圧迫が、特定の部位のシワやたるみを固定化させてしまう可能性があります。
また、高すぎる枕はあごが引けた状態になり、首のシワや二重あごの原因にもなり得ます。
セルフケアでできること|日常生活での予防と対策
顔の下半分のたるみは、一度現れるとセルフケアだけで元に戻すのは難しいのが現状です。しかし、日々の習慣を見直すと、たるみの進行を遅らせ、予防できます。
美容クリニックでの治療を考える前に、まずは基本となるセルフケアを見直しましょう。
保湿と紫外線対策の徹底
肌の乾燥はあらゆる肌トラブルの引き金になります。肌が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなるだけでなく、ハリも失われます。
化粧水で水分を与えた後は、乳液やクリームでしっかりと油分を補い、水分が蒸発するのを防ぎましょう。
そして、何よりも重要なのが紫外線対策です。前述の通り、紫外線は肌の弾力を奪う最大の敵です。季節や天候に関わらず、年間を通して日焼け止めの使用を習慣にしてください。
表情筋トレーニングの正しいやり方
衰えた表情筋を鍛えると、たるみ予防に一定の効果が期待できます。特に、口周りの筋肉(口輪筋)や頬の筋肉(大頬骨筋など)を意識して動かすと良いです。
ただし、自己流の誤ったトレーニングは、かえってシワを深くする原因にもなります。鏡を見ながら、鍛えたい筋肉だけを動かす意識で、無理のない範囲で行いましょう。やりすぎは禁物です。
セルフケアのポイント
| ケアの種類 | 具体的な方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| スキンケア | 保湿(水分と油分)、紫外線対策(毎日) | 肌をこすりすぎない |
| トレーニング | 口角を上げる、頬を膨らませるなど | やりすぎない、シワが寄らないように |
| 生活習慣 | バランスの良い食事、十分な睡眠 | タンパク質やビタミンを意識する |
バランスの取れた食事と良質な睡眠
健康な肌は健康な体から作られます。肌の材料となるタンパク質、肌の調子を整えるビタミン(A, C, Eなど)やミネラルのバランス良い摂取が大切です。ジャンクフードや過度な糖質は避けましょう。
また、睡眠中は成長ホルモンが分泌され、肌の修復や再生が行われます。質の良い睡眠を十分にとる工夫も、たるみ予防には必要です。
マッサージや美顔器の限界
顔のマッサージは、血行を促進し、むくみを改善する効果は期待できます。
しかし、強い力で肌をこすると摩擦によって肌を傷めたり、皮膚を支える線維を伸ばしてしまったりする可能性があります。マッサージを行う際は必ずクリームやオイルを使用し、優しい力で行いましょう。
家庭用美顔器も様々な種類がありますが、その多くは肌の浅い層への働きかけが中心です。
SMAS層のゆるみや骨格の変化といった、たるみの根本的な原因にまで働きかけるのは難しく、あくまで予防や現状維持のサポートとして捉えるのがよいでしょう。
美容クリニックでのリフトアップ法|概要と比較
美容クリニックでは顔の下半分のたるみに対し、メスを使わない「切らない治療」(照射・注入・糸)と、メスを使う「切る治療」(フェイスリフト)の大きく分けて2種類の方法を提供しており、症状や希望に応じて選択します。
切らない治療法(照射・注入・糸)
メスを使わずに、たるみを改善する治療法です。ダウンタイム(回復期間)が短い、あるいはほとんどないものが多く、気軽に受けやすいのが特徴です。
- 照射治療(ハイフ、高周波など)
- 注入治療(ヒアルロン酸、ボトックスなど)
- 糸リフト(スレッドリフト)
これらの治療は、皮膚の引き締め、ボリュームの調整、あるいは物理的な引き上げによってたるみに働きかけます。
切る治療法(フェイスリフト)
メスを使い、ゆるんだ皮膚やSMAS層を直接引き上げて固定する手術です。たるみに対する効果を最も実感しやすく、持続期間も長いのが特徴です。
その反面、体への負担が大きく、ダウンタイムも長く必要とします。たるみが重度の場合や、根本的な改善を望む場合に選択されます。
主な治療法の比較(概要)
| 治療法 | 主なアプローチ | ダウンタイム |
|---|---|---|
| 照射治療 (ハイフなど) | 熱エネルギーでSMASや真皮を引き締める | ほぼなし〜数日 |
| 注入治療 (ヒアルロン酸) | ボリュームを補い、たるみを持ち上げる | ほぼなし〜数日 |
| 糸リフト | トゲのついた糸で物理的に引き上げる | 数日〜2週間程度 |
| フェイスリフト (切開) | 皮膚とSMASを直接切除・引き上げ | 2週間〜数ヶ月 |
治療法選びのポイント
どの治療法が自分に合っているかは、たるみの程度や原因、予算やどのくらいのダウンタイムが許容できるかによって異なります。
例えば、軽度のたるみであれば照射治療、特定のくぼみが気になるなら注入治療、しっかり引き上げたいが手術は避けたいなら糸リフト、根本的に解決したいならフェイスリフト、といった具合です。
複数の治療を組み合わせるケースもあります。医師の診断のもと、ご自身の希望をしっかり伝えて相談しましょう。
切らないリフトアップ法(照射治療)
照射治療は、ハイフ(HIFU)や高周波(RF)などの機器を使い、肌の内部に熱エネルギーを加えてたるみを引き締める方法です。肌表面を傷つけず、ダウンタイムが短い点が特徴です。
ハイフ(HIFU)高密度焦点式超音波
HIFU(ハイフ)は、高密度の超音波エネルギーをSMAS層にピンポイントで照射し、熱凝固させる治療です。SMAS層が熱によって収縮するため、土台からのリフトアップが期待できます。
また、真皮層にも熱を加え、コラーゲンの生成を促して肌のハリも改善します。フェイスラインのもたつきや頬のたるみに効果的です。
高周波(RF)サーマクールなど
高周波(ラジオ波)治療は、皮膚の真皮層から皮下脂肪層にかけて高周波の熱エネルギーを広範囲に加える治療です。
主に真皮層のコラーゲン線維を収縮させ、即時的な引き締め効果をもたらします。さらに、熱刺激による創傷治癒の過程で長期的にコラーゲンが新しく作られ、肌のハリや弾力がアップします。
ハイフが「点」で深く効くのに対し、高周波は「面」で広く効くイメージです。
照射治療の比較(ハイフ vs 高周波)
| 項目 | ハイフ (HIFU) | 高周波 (RF) |
|---|---|---|
| 主なターゲット層 | SMAS層 (深い) | 真皮層・脂肪層 (浅い〜中間) |
| 主な効果 | リフトアップ (引き上げ) | タイトニング (引き締め) |
| 適した悩み | フェイスラインのもたつき、頬のたるみ | 肌全体のゆるみ、ハリ不足 |
糸リフト(スレッドリフト)
糸リフトは、厳密には照射治療ではありませんが、「切らない」リフトアップ法として人気です。
コグ(トゲ)のついた医療用の溶ける糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚や脂肪を物理的に引き上げる治療法です。
特にマリオネットラインやフェイスラインのたるみに対して、即時的なリフトアップ効果を実感しやすいのが特徴です。挿入された糸の刺激により、コラーゲン生成が促進される効果もあります。
切らないリフトアップ法(注入治療)
注入治療は、注射によって有効な成分を皮下に注入し、シワやたるみを改善する治療法です。施術時間が短く、ダウンタイムもほとんどないため、手軽に受けられる治療として定着しています。
ヒアルロン酸注入
ヒアルロン酸は、もともと体内に存在する保湿成分です。これを、たるみによってできた溝やくぼみ(ほうれい線やマリオネットラインなど)に注入して肌を内側から持ち上げ、シワを目立たなくします。
また、こめかみや頬、あごなどに注入してボリュームを補い、顔全体のバランスを整えてリフトアップしたように見せることも可能です(リフトアップポイントへの注入)。
ボトックス(ボツリヌス)注射
ボトックス(ボツリヌストキシン)は、筋肉の働きを一時的に弱める作用があります。
これを利用して、口角を下に引っ張る筋肉(口角下制筋)の働きを弱めると相対的に口角を上げる筋肉が働きやすくなり、口角がキュッと上がった印象になります。
また、フェイスラインの筋肉(広頸筋)に注入すれば、首からあごにかけてのラインをシャープに見せることもできます。
注入治療の使い分け
| 治療法 | 主な作用 | 適した悩み |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | ボリュームを補う、溝を埋める | ほうれい線、マリオネットライン、頬のこけ |
| ボトックス | 筋肉の働きを弱める | 下がった口角、フェイスラインのもたつき |
その他の注入剤(コラーゲンブースターなど)
最近では、ヒアルロン酸やボトックス以外にも、自身のコラーゲン生成を強力に促進する「コラーゲンブースター」と呼ばれる注入剤も注目されています。
PCL(ポリカプロラクトン)やPLLA(ポリ乳酸)などを主成分とし、肌のハリや弾力を根本から改善していくことを目的とします。即時的な変化よりも、長期的な肌質の改善を望む方に適しています。
切るリフトアップ法(フェイスリフト手術)
フェイスリフト手術は、たるみが重度な場合に適した外科的な治療法です。
耳の前後などを切開し、たるみの原因であるSMAS層と余分な皮膚を直接引き上げて固定するため、根本的な改善と長期の持続が期待できます。
フェイスリフトとは
フェイスリフトは、一般的に耳の前や後ろ、あるいは髪の生え際などを切開し、そこから皮膚とSMAS層を剥離します。そして、ゆるんだSMAS層を引き上げて固定し、余った皮膚を切除して縫合します。
たるみの土台であるSMAS層からしっかりと引き上げるため、リフトアップ効果を最も実感しやすく、その効果も長期間持続します。
ミニリフトとフルフェイスリフトの違い
切開の範囲によって、いくつかの種類に分けられます。
ミニリフトは、耳の前など、切開範囲を比較的小さく抑えた方法です。主に口元やフェイスラインなど、顔の下半分のたるみを局所的に改善するのに適しています。
フルフェイスリフトは、こめかみから耳の前後、襟足まで広範囲に切開し、頬やフェイスライン、首のたるみまで顔全体を強力に引き上げる方法です。
どちらが適しているかは、たるみの範囲や程度によって医師が判断します。
フェイスリフトの種類と特徴
| 種類 | 切開範囲 | 主な対象 |
|---|---|---|
| ミニリフト | 耳の前など(比較的小さい) | 顔の下半分(頬、フェイスライン) |
| フルフェイスリフト | こめかみ〜耳〜襟足(広範囲) | 顔全体〜首 |
手術のメリットとダウンタイム
最大のメリットは、他のどの治療よりも確実でリフトアップ効果を実感しやすい点と、長期的な持続性(5年〜10年程度と言われる場合が多い)です。
一方、デメリットはダウンタイムです。術後は腫れや内出血が強く出ます。大きな腫れが引くまでに最低でも2週間程度は必要とし、完全に馴染むまでには数ヶ月かかります。
また、切開を伴うため、傷跡が残るリスク(通常は目立たなくなる)や、神経損傷などの合併症のリスクもゼロではありません。
手術を受ける際は、これらのリスクを十分に理解し、経験豊富な医師のもとで受けましょう。
顔の下半分のたるみに関するよくある質問
「顔の皮膚にたるみがある」「顔の下半分でたるみが目立つ」と感じると、少しでも早く何とかしたいと思うのも無理はありません。
まずは保湿や紫外線対策、レチノールやペプチドといったハリの改善に有効な成分が含まれた化粧品の使用、表情筋トレーニングなどを実践してみましょう。
ただし、進行してしまったたるみには美容医療が良い選択肢となります。無料カウンセリングを行うクリニックも多いので、いちど足を運んでみることをおすすめします。
- たるみ治療はどのくらいの年齢から始めるべきですか?
-
一概に何歳から、という明確な基準はありません。たるみ治療を始めるタイミングは、ご自身が「たるみが気になり始めた」と感じたときが適切です。
たるみの進行度は、遺伝的な要因やこれまでの生活習慣(特に紫外線対策)によって個人差が大きいためです。
軽度のたるみであれば予防的な治療を、明らかにたるみが進行している場合は、その状態に合わせた治療法を選択します。
早すぎる必要はありませんが、たるみが軽度なうちからケアを始めるほうが良い状態を維持しやすい傾向はあります。
- 治療の効果はどのくらい持続しますか?
-
治療法によって大きく異なります。例えば、ヒアルロン酸注入は製剤の種類にもよりますが数ヶ月から2年程度、糸リフトは糸の種類や本数によりますが1年から2年程度が目安です。
ハイフや高周波などの照射治療は、効果のピークは数ヶ月後で、半年から1年おきに継続して受けるように推奨する場合が多いです。
切開フェイスリフトが最も持続性が高く、5年から10年程度と言われますが、どの治療も加齢による変化を完全に止められません。
- ダウンタイムが取れないのですが、どの治療がおすすめですか?
-
照射治療や注入治療が適しています。ハイフ(HIFU)や高周波(RF)などの照射治療は、肌表面に傷をつけないため、ダウンタイムはほとんどありません。施術直後からメイクも可能です。
ヒアルロン酸やボトックスなどの注入治療も、まれに内出血が出る場合がありますが、数日から1週間程度で治まる方がほとんどです。
お仕事や日常生活への影響を最小限に抑えたい方には、これらの「切らない治療」から検討するのがおすすめです。
- 治療後に気をつけることはありますか?
-
A. 治療内容によって異なりますが、基本的なスキンケアは共通して重要です。
照射治療や糸リフトの後は肌が一時的に敏感になっているため、過度なマッサージや摩擦を避け、保湿と紫外線対策を徹底してください。
注入治療の後も、注入部位を強く押したりこすったりしないように注意が必要です。切開フェイスリフトの場合は、腫れや痛みの管理、傷口のケアなど医師の指示に厳密に従う必要があります。
いずれの治療も、術後の経過で不安な点があれば、すぐにクリニックに相談してください。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
LEE, Sung Ha, et al. An Approach to Selection of Face-Lift Techniques for Different Types of Faces: An Analysis of 1000 Asian Patients Over 9 Years. Annals of Plastic Surgery, 2024, 93.2: 153-162.
GOKALP, Hilal. Efficacy of monopolar radiofrequency in middle and lower face laxity. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 2017, 24.3.
SHOME, Debraj, et al. Use of micro-focused ultrasound for skin tightening of mid and lower face. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2019, 7.12: e2498.
OHJIMI, Hiroyuki. Antiaging Checkup: Perceived (Skin) Age. In: Anti-Aging Medicine: Basics and Clinical Practice. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. p. 553-556.
DOBOS, G., et al. Evaluation of skin ageing: a systematic review of clinical scales. British Journal of Dermatology, 2015, 172.5: 1249-1261.
YANG, Daping; YANG, Jenny F. Special considerations in Chinese face-lift procedure: insights from a 15-year experience of 1026 cases. Annals of Plastic Surgery, 2021, 86.3S: S244-S252.
MIFTAH AREEF, Abdulathim Amhimmid; ALI, Ahmed Mohamed; ANANI, Raafat Abdullatif. The Efficacy of the Absorbable Polydioxanone (PDO) Thread Lift in Lower Face (Marionette Line) Rejuvenation. Zagazig University Medical Journal, 2024, 30.7: 3481-3494.
KAMINER, Michael S.; GWINN, Courtney; DOVER, Karen J. Nonsurgical skin tightening. Procedures in Cosmetic Dermatology: Lasers, Lights, and Energy Devices-E-Book, 2022, 104.