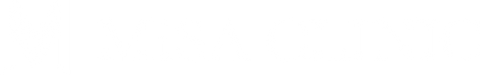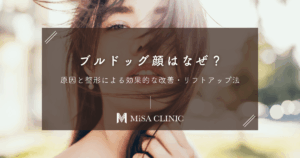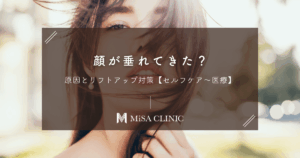顔の皮膚たるみの原因を徹底分析!今日からできる改善・予防ケア完全ガイド

顔の皮膚のたるみは、年齢を重ねるとともに多くの人が直面する悩みです。しかし、その原因は加齢だけではありません。
この記事では、顔の皮膚たるみを引き起こす様々な原因を深く掘り下げ、日常生活で今すぐ始められる改善・予防ケアから、美容クリニックでの専門的な治療まで幅広く解説します。
なぜ起こる?顔の皮膚のたるみが起こる根本原因
顔の皮膚がたるむのは単に年齢だけでなく、皮膚内部のコラーゲンの減少、表情筋の衰え、皮下脂肪の変化という3つの構造的な変化が根本的な原因として関わっています。
皮膚の弾力を支えるコラーゲン・エラスチンの減少
私たちの皮膚の真皮層には、肌のハリや弾力を保つために重要な役割を果たす「コラーゲン」と「エラスチン」という線維状のタンパク質が存在します。
コラーゲンは皮膚に強度を与え、エラスチンはゴムのように伸縮して弾力をもたらします。しかし、加齢や後述する紫外線の影響によって、これらの線維は減少し、質も低下します。
結果として、皮膚は自らの重みを支えきれなくなり、重力に従って下方へと垂れ下がってしまうのです。
顔の土台となる表情筋の衰え
皮膚や皮下脂肪を支えているのは、その下にある「表情筋」です。表情筋は、喜怒哀楽を表現するために使われる細かい筋肉の集まりであり、日常生活では全体の約30%程度しか使われていないとも言われます。
加齢や、無表情でいる時間が長い生活習慣によって表情筋が衰えると、その上にある脂肪や皮膚を支える力が弱まります。これが、特に頬や口角周辺のたるみとなって現れます。
顔の主な筋肉とたるみやすい部位
| 筋肉名 | 主な役割 | 衰えるとたるみやすい部位 |
|---|---|---|
| 前頭筋 | 眉を上げる、額にシワを寄せる | まぶた、額 |
| 眼輪筋 | 目を開閉する | 目の下、目尻 |
| 大頬骨筋・小頬骨筋 | 口角を引き上げる(笑顔) | 頬、ほうれい線 |
皮下脂肪の増減と位置の変化
皮下脂肪も顔のたるみに大きく関わります。若い頃の脂肪は適切な位置にあり、リガメント(靭帯)によって支えられています。
しかし、加齢によってリガメントが緩むと、脂肪は重力に負けて下垂し始めます。
また、急激なダイエットによる脂肪の減少や、逆に体重増加による脂肪の蓄積も、皮膚が余ったり重みで垂れ下がったりする原因となります。
特に頬やあご下に脂肪が蓄積すると、フェイスラインの崩れや二重あごとして目立ちやすくなります。
見落としがちな「生活習慣」とたるみの関係
顔のたるみには加齢や体質だけでなく、日々の何気ない生活習慣も大きく影響します。
姿勢の悪さや睡眠中の圧迫、食事の偏りなど、無意識のうちにたるみを助長している可能性のある行動について確認しておきましょう。
姿勢の悪さ(スマートフォン操作・デスクワーク)
スマートフォンやパソコンを長時間使用する際、無意識のうちに首を前に突き出し、猫背になっていないでしょうか。この「うつむき姿勢」は、首からあごにかけての皮膚や筋肉に常に負担をかけ続けます。
首の筋肉(広頸筋)が弱まるとフェイスラインの皮膚を支える力が低下し、あご下のたるみや「スマホ首」と呼ばれる首のシワの原因にもなります。
デスクワーク中も画面の高さを調整し、背筋を伸ばす意識が大切です。
睡眠中の「圧迫」と「乾燥」
睡眠の質や寝相もたるみに影響を与えます。特にうつ伏せ寝や横向き寝は、長時間にわたって顔の片側に圧力をかけ、シワやたるみの原因となるときがあります。
枕に顔を押し付けると皮膚が歪み、その状態が続くとコラーゲン線維に癖がついてしまうのです。
また、睡眠不足は肌のターンオーバーを乱し、修復機能を低下させます。寝室の乾燥にも注意し、肌の水分が奪われない環境を整える工夫も重要です。
たるみを招く可能性のある生活習慣
| 習慣 | たるみへの影響 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 長時間のうつむき姿勢 | あご下や首のたるみを助長する | 画面を目線の高さに調整する |
| 横向き・うつ伏せ寝 | 片側の顔に圧力がかかり歪む | できるだけ仰向けで寝る |
| 喫煙 | 血行不良、ビタミンC破壊、活性酸素増加 | 禁煙を心がける |
食事の偏りと咀嚼回数の減少
肌の健康は、日々の食事から得る栄養素によって支えられています。ジャンクフードや糖質の多い食事に偏ると、体内で「糖化」という反応が起こります。
糖化によって生成されるAGEs(最終糖化産物)はコラーゲンを硬くもろくし、肌の弾力を失わせます。
また、柔らかい食べ物ばかりを好み咀嚼回数が減ると、口周りの筋肉(口輪筋など)が衰え、口角の下がりやほうれい線の原因になります。
年齢だけではない!たるみを加速させる外的要因
顔のたるみは加齢による内部変化に加え、外部からの環境要因によっても加速します。
なかでも「紫外線」による光老化と、皮膚のバリア機能を低下させる「乾燥」が、たるみを深刻化させる主な外的要因です。
最大の敵「紫外線」が引き起こす光老化
顔のたるみの最大の外的要因は、紫外線による「光老化」です。紫外線にはUVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)があります。
UVBが肌表面に炎症(日焼け)を起こすのに対しUVAは波長が長く、皮膚の奥深く真皮層にまで到達します。そして、肌の弾力を司るコラーゲンやエラスチンを変性させ、切断してしまうのです。
このダメージは長期間蓄積し、年齢を重ねるごとにはっきりとしたシワやたるみとして現れます。
紫外線の種類と皮膚への影響
| 種類 | 到達する深さ | 主な影響 |
|---|---|---|
| UVA (紫外線A波) | 真皮層 | コラーゲン・エラスチンの変性(たるみ・シワ) |
| UVB (紫外線B波) | 表皮層 | 炎症(日焼け)、シミ |
皮膚のバリア機能を低下させる「乾燥」
皮膚の最も外側にある「角質層」は、水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激から肌を守るバリア機能を持っています。
しかし、エアコンによる空気の乾燥や、間違ったスキンケアによって肌が乾燥すると、このバリア機能が低下します。
バリア機能が弱まると外部からの刺激を受けやすくなるだけでなく、肌内部の水分も保持できなくなり、乾燥小ジワが発生します。
この小ジワが、やがて深いたるみへと進行するきっかけになるケースも少なくありません。
急激な体重変動による皮膚の伸縮
短期間での急激なダイエットやリバウンドも、皮膚たるみの原因となります。体重が急に減少すると皮下脂肪は減りますが、伸びていた皮膚はすぐには収縮できません。
その結果、皮膚が余ってしまい、たるみとして残る場合があります。逆に太ると皮膚は伸ばされます。この伸縮が繰り返されると、皮膚の弾力が失われやすくなります。
顔の構造から理解する「たるみの種類」
顔のたるみは原因となる皮膚の層によって、主に3つの種類に分類されます。
皮膚自体の弾力が失われる「皮膚性」、筋肉の衰えによる「筋肉性」、脂肪の下垂による「脂肪性」があり、自分のタイプを知るのがケアの第一歩です。
皮膚の弾力低下による「皮膚性たるみ」
これは、主に真皮層のコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚自体のハリが失われるために生じるたるみです。紫外線ダメージの蓄積や加齢が主な原因です。
特徴としては、顔全体に細かいシワ(ちりめんジワ)が目立ち、皮膚が薄くなったように感じられる点が挙げられます。
筋肉の衰えによる「筋肉性たるみ」
表情筋の衰えにより、その上にある脂肪や皮膚を支えきれなくなるために生じるたるみです。加齢のほか、無表情でいる時間が多い人にも見られます。
頬の位置が下がり、ほうれい線やマリオネットライン(口角からあごにかけての溝)が深くなるのが特徴です。
脂肪の下垂・蓄積による「脂肪性たるみ」
皮下脂肪が重力によって下垂したり、特定の場所に過剰に蓄積したりして生じるたるみです。加齢によるリガメントの緩みや、体重増加が関わっています。
フェイスラインがぼやけ、頬がブルドッグのように垂れ下がる、二重あごが目立つ、といった特徴があります。
たるみの種類別チェックポイント
| たるみの種類 | 主な原因 | 見られる特徴 |
|---|---|---|
| 皮膚性たるみ | 紫外線、加齢、乾燥 | 皮膚が薄い、細かいシワが目立つ |
| 筋肉性たるみ | 加齢、無表情 | ほうれい線、マリオネットラインが深い |
| 脂肪性たるみ | 加齢、体重増加、リガメントの緩み | フェイスラインの崩れ、二重あご |
たるみが示す「心の状態」?ストレスと皮膚の関係性
物理的な要因だけでなく、慢性的な「ストレス」も顔のたるみに関係します。
ストレスによる表情筋の過度な緊張や血行不良が肌の弾力を失わせ、「ストレス顔」としてたるみを定着させる可能性があるため、心のケアも重要です。
慢性的なストレスと表情筋の緊張
ストレスを感じると体は無意識に「闘争・逃走反応」の準備をします。このとき、顔の筋肉、特にあごや眉間、こめかみ周辺の筋肉は強く緊張します。
悩み事があったり、プレッシャーを感じたりしているとき、無意識に歯を食いしばっている方も多いでしょう。
この緊張が慢性化すると、特定の表情筋が過剰に発達(肥大)したり、逆に固まって動きにくくなったりします。
「ストレス顔」が定着する理由
筋肉が常に緊張しているとその部分の血流が悪化します。血行不良は、皮膚細胞に必要な酸素や栄養素が届きにくくなる状態を意味し、老廃物の排出も滞りがちになります。
このため肌のターンオーバーが乱れ、コラーゲンの生成も妨げられます。
結果として肌が弾力を失い、緊張によってできた「不機嫌そうな表情」や「疲れた表情」が、そのままシワやたるみとして顔に刻まれてしまうのです。
ストレスが引き起こす顔への影響
- 表情筋の過度な緊張(食いしばりなど)
- 血行不良による栄養不足とくすみ
- ホルモンバランスの乱れによる肌荒れ
- 睡眠の質の低下による修復機能の阻害
心のセルフケアが皮膚に与える影響
もし、あなたがスキンケアやマッサージを頑張ってもたるみが改善しないと感じているなら、それは心が緊張状態にあるサインかもしれません。
意識的にリラックスする時間を持つ、例えば深呼吸をする、趣味に没頭する、ゆっくりと入浴するなど、自分なりのストレス解消法を見つける工夫が重要です。
心をほぐす時間は結果として表情筋の緊張を解き、血流を改善し、健やかな肌を取り戻す手助けとなります。顔のケアと同時に、心のケアも行う視点が、たるみ改善の近道になるかもしれません。
自宅で実践!たるみ改善・予防のためのセルフケア
たるみの進行を遅らせ、予防するためには、日々のセルフケアが重要です。基本となる「保湿」と「紫外線対策」の徹底、表情筋を鍛えるエクササイズ、そして「正しい姿勢」を意識しましょう。
基本のスキンケア「保湿」と「紫外線対策」
セルフケアの土台は、日々のスキンケアです。最も重要なのは「保湿」と「紫外線対策」です。
乾燥は肌のバリア機能を低下させ、あらゆる肌トラブルの引き金となります。洗顔後はすぐに化粧水で水分を補給し、乳液やクリームで油分を補い、水分が蒸発しないようしっかりと蓋をします。
そして、紫外線対策は一年中行う必要があります。光老化はたるみの最大の原因で、曇りの日でも室内でも、UVAは窓ガラスを透過して届きます。日焼け止めを塗る習慣を徹底しましょう。
スキンケアの基本ステップ
| ステップ | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 洗顔 | 汚れを落とす | 摩擦を避け、泡で優しく洗う |
| 保湿(化粧水・美容液) | 水分と美容成分を補給 | 肌にしっかり浸透させる |
| 保護(乳液・クリーム) | 水分の蒸発を防ぐ | 乾燥しやすい目元・口元は丁寧に |
| 紫外線対策 | 光老化を防ぐ | 毎日、塗りムラなく塗布する |
表情筋を鍛える「フェイシャルエクササイズ」
皮膚の土台となる表情筋は、意識的に動かさないと衰えやすいものです。日常生活で使いにくい筋肉をターゲットにしたエクササイズを取り入れましょう。
ただし、やり過ぎや間違った方法は、かえってシワの原因になる場合もあるため注意が必要です。鏡を見ながら、動かしたい筋肉を意識して行うことが大切です。
口周り・頬のエクササイズ例
口を大きく開けて「あ・い・う・え・お」と、一音ずつゆっくり、大げさに口を動かします。特に「う」の時は唇を強く前に突き出し、「い」の時は口を真横に引くように意識します。
これを数回繰り返すだけでも、口周りや頬の筋肉が刺激されます。
たるみを防ぐ「正しい姿勢」の意識
日中の姿勢の見直しも、たるみ予防につながります。特にデスクワーク中は背筋を伸ばし、あごを軽く引くように意識します。耳と肩が一直線上にくるようなイメージです。
スマートフォンを見る時もできるだけ顔の高さまで持ち上げ、うつむく時間を減らしましょう。
正しい姿勢はフェイスラインをすっきりと保つだけでなく、首や肩の凝り改善にもつながります。
食事で内側からサポート!たるみケアのための栄養素
たるみケアには外側からのスキンケアに加え、内側からの栄養サポートも必要です。
肌の材料となる「タンパク質」、コラーゲン生成を助ける「ビタミンC」、酸化を防ぐ「抗酸化物質」を食事で意識的に摂取しましょう。
肌のハリを支える「タンパク質」
皮膚や筋肉の主成分はタンパク質です。コラーゲンもタンパク質の一種であり、十分なタンパク質がなければ新しい皮膚細胞やコラーゲンを生成できません。
肉や魚、卵や大豆製品など、良質なタンパク質を毎食取り入れるように心がけましょう。
コラーゲン生成を助ける「ビタミンC」
ビタミンCは、コラーゲンの生成をサポートする上で欠かせない栄養素です。また、強力な抗酸化作用を持ち、紫外線のダメージから肌を守る働きも期待できます。
ビタミンCは体内に蓄積できないため、こまめに摂取する習慣が大切です。
たるみケアに役立つ主な栄養素と食材
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚、筋肉、コラーゲンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンC | コラーゲン生成促進、抗酸化作用 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血行促進 | ナッツ類、アボカド、植物油 |
酸化を防ぐ「抗酸化物質」
紫外線やストレスによって体内で発生する「活性酸素」は細胞を傷つけ、コラーゲンを変性させて、たるみをはじめとする老化を促進します。この活性酸素の働きを抑えるのが「抗酸化物質」です。
ビタミンCやビタミンEのほか、ポリフェノール(緑茶、カカオなど)やアスタキサンチン(鮭、エビなど)も強力な抗酸化物質として知られています。
抗酸化作用を持つ成分
- ビタミンA (β-カロテン)
- ビタミンC
- ビタミンE
- ポリフェノール
- アスタキサンチン
それでも改善しない場合に|美容クリニックでの治療
セルフケアはたるみの予防や進行を遅らせるために非常に重要ですが、すでに深く刻まれたたるみや、大きく下垂した脂肪を元に戻すには限界がある場合もあります。
そのような場合、美容皮膚科や美容整形クリニックでの専門的な治療が選択肢となります。
たるみ治療の主な種類と特徴
美容クリニックで行うたるみ治療には、大きく分けて「照射治療」「注入治療」「糸(スレッド)治療」などがあります。
それぞれ特徴やダウンタイム(日常生活に戻るまでの期間)、期待できる効果が異なります。
代表的なクリニックでのたるみ治療
| 治療法 | 主な仕組み | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 照射治療 (HIFUなど) | 超音波や高周波で熱を与え、組織を引き締める | リフトアップ、コラーゲン生成促進 |
| 注入治療 (ヒアルロン酸など) | ボリュームが減った部分に注入し、溝を埋める | ほうれい線や頬のコケの改善 |
| 糸(スレッド)リフト | 特殊な糸を挿入し、皮膚を引き上げる | 物理的なリフトアップ、フェイスラインの改善 |
HIFU(ハイフ)などの照射による引き締め
HIFU(高密度焦点式超音波)は、超音波エネルギーを皮膚の深層部(SMAS筋膜)に集中的に照射し、熱凝固を起こして組織を引き締める治療法です。
皮膚表面を傷つけずに、土台となる筋膜からリフトアップを図ります。コラーゲンの生成も促すため、中長期的なハリ感アップも期待できます。
ヒアルロン酸・ボツリヌス注入による調整
ヒアルロン酸注入は、加齢によって減少したボリュームを補ったり、深いシワの溝を埋めたりするために用います。ほうれい線やマリオネットライン、こけた頬などに注入し、顔全体の印象を若々しく整えます。
一方、ボツリヌス注入は、筋肉の過度な緊張を和らげる治療です。
食いしばりによるエラの張りや、眉間のシワなどに用いられるケースが多いですが、筋肉のバランスを整えるとたるみの改善につながる場合もあります。
クリニック選びで大切なこと
治療を受ける際は、クリニック選びが非常に重要です。価格だけでなく、医師の経験や実績、カウンセリングの丁寧さ、アフターフォロー体制などを総合的に判断する必要があります。
自分の悩みをしっかりと聞き、どのような治療がなぜ必要なのか、リスクも含めて丁寧に説明してくれるクリニックを選びましょう。
クリニック選びの視点
- たるみ治療の実績が豊富か
- カウンセリングで十分な説明があるか
- リスクやダウンタイムの説明が明確か
- アフターケアや緊急時対応が整っているか
顔の皮膚たるみに関するよくある質問 (Q&A)
顔の皮膚のたるみは、肌の構造の変化が複雑に絡み合って起こります。また、生活習慣や姿勢、紫外線対策不足なども大きく関係しています。
まずはご自身でできるケアを行い、さらに積極的に顔の皮膚のたるみを改善したい方は美容医療を検討してみましょう。
- 一度できてしまったたるみは、セルフケアで元に戻りますか?
-
完全に元に戻すのは難しいですが、改善は期待できます。セルフケアは、たるみの進行を予防し、現状を維持・改善するために非常に重要です。
保湿や紫外線対策、表情筋のエクササイズ、生活習慣の見直しを継続すると、肌のハリを取り戻し、たるみを目立ちにくくできます。
ただし、深く進行したたるみに関してはセルフケアだけでは限界があるため、美容医療の併用も選択肢となります。
- セルフケアはどれくらいの期間で効果を感じられますか?
-
効果の感じ方には個人差が大きく、一概には言えません。
肌のターンオーバー(生まれ変わり)の周期が約1ヶ月以上かかることを考えると、まずは最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続して様子を見る必要があります。
紫外線対策や保湿はすぐに肌の調子を整える効果が期待できますが、表情筋の変化やコラーゲンの質的改善には時間がかかります。焦らず、日々の習慣として続けましょう。
- 顔のマッサージは、たるみに逆効果になることもありますか?
-
その可能性があります。強い力でのマッサージや皮膚を過度に摩擦する行為は、肌のバリア機能を壊したり、真皮層のコラーゲン線維にダメージを与えたりして、かえってたるみやシワを助長する場合があります。
マッサージを行う際は必ずクリームやオイルで滑りを良くし、皮膚を引っ張らないよう、優しく圧をかける(指圧)程度にとどめましょう。
- 美容クリニックの治療は痛みを伴いますか?
-
治療法によって痛みの感じ方は異なります。例えば、HIFU(ハイフ)のような照射治療では、皮膚の奥に熱が加わるため、チクチクとした痛みや熱感を感じるときがあります。
注入治療では針を刺す痛みがありますが、多くの場合、麻酔クリームや局所麻酔を使用して痛みを最小限に抑えます。
カウンセリングの際に、痛みに不安があることを医師に伝え、どの程度の痛みなのか、どのような緩和策があるのかを事前に確認しておくと安心です。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
EZURE, T., et al. Sagging of the cheek is related to skin elasticity, fat mass and mimetic muscle function. Skin Research and Technology, 2009, 15.3: 299-305.
TSUKAHARA, Kazue, et al. Comparison of age-related changes in facial wrinkles and sagging in the skin of Japanese, Chinese and Thai women. Journal of dermatological science, 2007, 47.1: 19-28.
OHSHIMA, Hiroshi, et al. Relevance of the directionality of skin elasticity to aging and sagging of the face. Skin Research and Technology, 2011, 17.1: 101-107.
GONZALEZ-ULLOA, Mario; FLORES, Eduardo Stevens. Senility of the face—basic study to understand its causes and effects. Plastic and reconstructive surgery, 1965, 36.2: 239-246.
TROJAHN, Carina, et al. Characterizing facial skin ageing in humans: disentangling extrinsic from intrinsic biological phenomena. BioMed research international, 2015, 2015.1: 318586.
HAMRA, Sam T. Prevention and Correction of the“Face-lifted”Appearance. Facial plastic surgery, 2000, 16.03: 215-230.
PANDA, Arun Kumar; CHOWDHARY, Aarti. Non-surgical modalities of facial rejuvenation and aesthetics. In: Oral and maxillofacial surgery for the clinician. Singapore: Springer Nature Singapore, 2021. p. 661-689.
HANEY, Beth. Facial rejuvenation/non-surgical procedures. In: Image-Guided Aesthetic Treatments. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 51-63.