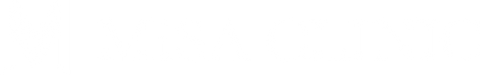50代の顎のたるみ(二重顎)を撃退!原因と効果的な解消エクササイズ

50代になると気になる顎のたるみや二重顎に「もう年齢だから」と諦める必要はありません。
実は、50代の顎のたるみには特有の原因があり、適切なケアとエクササイズで改善が期待できます。
この記事では、なぜ50代で顎のたるみが目立つのか、その原因を詳しく解説し、自宅で簡単にできる効果的な解消エクササイズや生活習慣の見直しポイントを紹介します。
なぜ50代で顎のたるみは深刻化するのか?
40代まではそれほど気にならなかったフェイスラインのもたつきが、50代に入ると急に目立ち始める場合があります。
これは、肌の内部構造や身体全体に訪れる変化が複合的に関与しているためです。
加齢によるコラーゲンとエラスチンの減少
肌のハリや弾力を支えているのは、真皮層に存在するコラーゲンとエラスチンという線維状のタンパク質です。
これらは肌の構造を保つ重要な役割を担っていますが、年齢とともに減少し、質も低下します。
特に50代ではその減少が顕著になり、肌の土台が緩んでしまうため重力に逆らえずに皮膚が下がり、顎のたるみとして現れます。
肌の弾力を支える主要成分の変化
| 成分 | 役割 | 50代における変化 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 肌の構造を支える柱 | 量・質ともに大幅に低下し、硬くなる |
| エラスチン | 肌に弾力を与えるバネ | 変性・減少し、弾力性が失われる |
| ヒアルロン酸 | 水分を保持する | 生成量が減り、肌が乾燥しやすくなる |
筋力の低下がフェイスラインを崩す
顔には多くの表情筋があり、皮膚や脂肪を支えています。しかし、身体の筋肉と同じように、顔の筋肉も使わなければ衰えます。
特に顎周りや首にある広頚筋(こうけいきん)や舌骨筋群(ぜっこつきんぐん)が衰えると、フェイスラインをシャープに保つ力が弱まり、たるみや二重顎に直結します。
日常生活で意識して動かす機会が少ないため、50代になると筋力低下の影響が表面化しやすいです。
女性ホルモンの変化が肌のハリに与える影響
50代は多くの女性が閉経を迎える時期であり、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少します。
エストロゲンは、コラーゲンの生成を促進して肌の潤いやハリを保つ働きを持っています。
そのため、エストロゲンが減少すると肌の乾燥が進み、弾力が失われ、たるみが一気に深刻化する要因となります。
蓄積された紫外線ダメージの顕在化
若い頃から浴び続けてきた紫外線のダメージは、年月をかけて肌の内部に蓄積します。
紫外線はコラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の老化を加速させる最大の外的要因です。
50代になると肌のターンオーバー(新陳代謝)も遅くなるため、ダメージの修復が追いつかなくなり、シミやシワだけでなく深刻なたるみとして肌表面に現れてくるのです。
50代の顎たるみを引き起こす複合的な原因
加齢による変化だけでなく、長年の生活習慣が顎のたるみを助長しているケースも少なくありません。
無表情や姿勢の悪さ、無意識の食いしばりなど、何気なく行っている癖や習慣がフェイスラインの崩れを招いている可能性を考えてみましょう。
表情筋の衰えと無表情の習慣
人と話す機会が減ったり、スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続けたりすると、無表情の時間が長くなりがちです。
表情が乏しいと表情筋が使われず、衰えを早めてしまいます。
特に口角を上げる筋肉や顎周りの筋肉が弱ると、皮膚や脂肪を支えきれなくなり、たるみにつながります。
顎のたるみに関わる主な要因と対策
| 要因 | 主な原因 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 筋肉の衰え | 無表情、加齢 | 表情筋エクササイズ、意識して話す・笑う |
| 姿勢の悪さ | デスクワーク、スマホ操作 | 正しい姿勢の意識、ストレッチ |
| 血行不良 | 食いしばり、冷え、運動不足 | マッサージ、入浴、適度な運動 |
姿勢の悪さが生む首への負担
猫背や、頭を前に突き出すような姿勢(ストレートネック)は、首や肩に大きな負担をかけます。
この姿勢が続くと首の前側にある広頚筋が常に縮こまった状態になり、衰えやすいです。
広頚筋はフェイスラインを引き下げる方向に作用するため、この筋肉が緩むと顎下のたるみが顕著になります。長時間のデスクワークやスマホ操作は特に注意が必要です。
食いしばりや歯ぎしりの隠れたリスク
日中の集中している時や、就寝中に無意識に行っている食いしばりや歯ぎしりは、顎周りの筋肉(咬筋)を過剰に緊張させます。
咬筋が硬くなるとその周辺の血行が悪化し、老廃物が溜まりやすくなります。
その結果、顔全体のむくみやフェイスラインのもたつきが生じ、たるみを悪化させる一因となるのです。
急激な体重変動と皮膚のゆるみ
50代になると代謝が落ちて太りやすくなる一方で、無理なダイエットで急激に体重を落とす方もいます。
体重が増えれば脂肪で二重顎になり、急激に痩せると脂肪が減った分だけ皮膚が余ってしまい、たるみとして残るケースがあります。
肌の弾力が低下している50代では、皮膚が脂肪の減少に追いつけず、一度伸びた皮膚が元に戻りにくくなるため注意が必要です。
見た目だけじゃない!顎のたるみによる身体への影響
顎のたるみは、単に「老けて見える」という美容上の問題だけではありません。
実は、いびきや睡眠時無呼吸症候群、肩こりや頭痛、滑舌の悪化といった健康健康上の不調を引き起こす可能性があります。
老け顔印象を加速させるブルドッグ顔
顎のたるみが進行すると口角が下がり、マリオネットライン(口角から顎にかけての溝)が深くなります。そのため、不機嫌そうな、疲れたような印象を与えがちです。
フェイスラインがぼやけて顔の下半分にボリュームが出るため、いわゆる「ブルドッグ顔」と呼ばれる状態になり、実年齢よりも老けた印象を強くしてしまいます。
いびきや睡眠時無呼吸症候群との関連
顎周りの筋力が低下して脂肪が増えると、就寝時に舌が喉の奥に落ち込みやすくなります(舌根沈下)。これが気道を狭め、いびきの原因となります。
症状が進行すると一時的に呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群(SAS)を引き起こす場合もあり、睡眠の質の低下や、日中の強い眠気、さらには生活習慣病のリスクを高めることにもつながります。
顎のたるみと関連しうる身体の不調
| 不調の種類 | 顎のたるとの関連性 |
|---|---|
| いびき・睡眠時無呼吸 | 顎下の筋力低下による気道の狭窄 |
| 肩こり・頭痛 | 姿勢の悪さや食いしばりによる筋肉の緊張 |
| 滑舌の悪化 | 舌や口周りの筋力低下 |
肩こりや頭痛の一因になるケースも
顎のたるみの原因となる姿勢の悪さや食いしばりは、首や肩、側頭部の筋肉に常に負担をかけ続けます。
これらの筋肉の緊張は血行不良を引き起こし、慢性的な肩こりや緊張型頭痛の原因となります。
フェイスラインのケアと合わせて、姿勢や癖を見直すと、これらの不快な症状の緩和にもつながる可能性があります。
滑舌が悪くなる?話し方への影響
顎や舌周りの筋肉は、言葉をはっきりと発音するためにも重要な役割を果たします。
これらの筋力が低下すると舌の動きが鈍くなり、滑舌が悪くなったり、口が回りにくくなったりする場合があります。
「ら行」や「さ行」が言いにくいと感じるときは、口周りの筋力低下が関係しているかもしれません。
諦めるのはまだ早い!50代だからこそ響く「自分いたわりケア」の新常識
これまで多くの情報に触れ、「これも試した、あれもやった」と、たるみケアに疲れてしまった方もいるかもしれません。
50代のケアはストイックに「戦う」よりも、今の自分を受け入れて心と体を「いたわる」という視点が大切です。心と身体はつながっており、心の状態が肌にも現れます。
「頑張る」から「いたわる」への意識転換
たるみを解消するために、痛みを伴うマッサージを我慢したり、義務感でエクササイズを続けたりしている方も見受けられます。
50代からのケアは、心地よさやリラックスを伴うほうが長続きし、結果的に良い影響を得られます。
例えば、エクササイズは「やらなければ」ではなく「今日も一日頑張った自分へのご褒美」と捉え、気持ちの良い範囲で行うと良いでしょう。
ストレスと顎のたるみの意外な関係性
強いストレスを感じると、体内で活性酸素が過剰に発生します。この活性酸素は肌のコラーゲンやエラスチンを傷つけ、たるみを促進する原因となります。
また、ストレスは無意識の食いしばりを引き起こし、血行を悪化させます。
自分なりのリラックス法を見つけ、心穏やかに過ごす時間を意識的に作ると、実は効果的なたるみケアにもなるのです。
ストレスが肌に与える主な影響
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 活性酸素の増加 | コラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の老化を促進 |
| 血行不良 | 筋肉の緊張(食いしばり等)により、肌の栄養不足やくすみを招く |
| ホルモンバランスの乱れ | 肌のターンオーバーを乱し、バリア機能の低下につながる |
心地よさを感じるスキンケアの選び方
スキンケアは、ただ成分の優劣だけで選ぶのではなく、自分が心地よいと感じるテクスチャーや香りを取り入れるのも大切です。
肌に触れる手の感触を楽しみ、好きな香りで深呼吸する、といった五感に働きかけるスキンケアタイムは心身のリフレッシュにつながり、肌への良い影響も期待できます。
高価な製品でなくても、自分がリラックスできるお気に入りのアイテムを見つけましょう。
リラックスできるスキンケアのポイント
- 好きな香りの製品を選ぶ
- 肌触りの良いテクスチャーを選ぶ
- 肌を温めながら行う
- ゆっくりと時間をかける
自分を好きになるための小さな習慣
鏡を見てため息をつくのではなく、今日の自分の良いところを一つ見つけて褒めてみましょう。
「今日は肌の調子がいいな」「笑顔が素敵」など、どんな小さなことでも構いません。自分自身を肯定的に捉えると自己肯定感を高め、表情を明るくします。
明るい表情は自然と表情筋を使うことにつながり、結果としてフェイスラインにも良い影響を与えるでしょう。
今日から始める!顎のたるみ解消エクササイズ
顎のたるみ解消には、顎から首にかけての筋肉を鍛え、巡りを良くするエクササイズが効果的です。
舌を使ったトレーニングや表情筋を動かす運動、ストレッチやツボ押しなどを組み合わせ、毎日少しずつ継続すると、すっきりとしたフェイスラインを目指せます。
舌を使った広頚筋トレーニング
首の前側から胸元にかけて広がる薄い筋肉「広頚筋」を鍛えるエクササイズです。
- 姿勢を正し、顔をゆっくりと真上に向けます。首の前側が伸びているのを感じましょう。
- その状態で、舌を突き出し、上(天井方向)に向かって5秒間伸ばします。
- ゆっくりと舌を戻し、顔も正面に戻します。この動作を3〜5回繰り返します。
このように、広頚筋を鍛えるとフェイスラインが引き締まります。
舌を使ったトレーニングのポイント
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 姿勢 | 背筋を伸ばし、肩の力は抜く |
| 速度 | すべての動作をゆっくりと行う |
| 意識 | 首の前から顎の下の筋肉が伸びていることを意識する |
「あいうえお」発声で表情筋を動かす
口周りの筋肉(口輪筋)や頬の筋肉を大きく動かすと、顔全体の血行を促進し、たるみを予防できます。声を出せばより効果が高まりますので、実践してみましょう。
- 「あー」口を大きく縦に開く
- 「いー」口を横に大きく広げ、口角を上げる
- 「うー」唇をすぼめて、前に突き出す
- 「えー」口を横に広げ、「い」よりも口角を強く引く
- 「おー」口を大きく縦に丸く開く
一文字ずつ5秒キープしながら、ゆっくりと行いましょう。2〜3セットが目安です。
首のストレッチでリンパの流れを促進
首周りの筋肉が凝り固まっているとリンパの流れが滞り、老廃物が溜まってむくみやたるみの原因になります。ゆっくりとしたストレッチで巡りを良くしましょう。
- 椅子に座り、背筋を伸ばします。
- 右手を頭の左側に置き、ゆっくりと右に倒します。左の首筋が伸びるのを感じながら20秒キープします。
- 反対側も同様に行います。
- 次に、両手を鎖骨の上に置き、皮膚を軽く下に押さえながら、顔をゆっくりと上に向け、20秒キープします。
簡単ツボ押しでフェイスラインをすっきり
顔には多くのツボ(経穴)があり、刺激すると血行を促進し、リフトアップ効果が期待できます。食いしばりで硬くなった筋肉をほぐすのにも有効です。
フェイスラインに効く主なツボ
| ツボの名前 | 場所 | 押し方 |
|---|---|---|
| 頬車(きょうしゃ) | 耳の付け根と顎の角を結んだ線の真ん中あたり。歯を食いしばると盛り上がる所。 | 人差し指か中指の腹で、気持ち良い強さで5秒押して離すを数回繰り返す。 |
| 廉泉(れんせん) | 顎の真下、のどぼとけの上にあるくぼみ。 | 親指で真上に向かってゆっくりと押し上げるように5秒押す。 |
エクササイズ効果を高める!50代からの生活習慣改善ガイド
エクササイズと並行して日々の生活習慣を見直せば、たるみケアの効果は格段に上がります。
肌のハリを作る食事や正しい姿勢の維持、質の良い睡眠や年間を通した紫外線対策を意識しながら、たるみの改善を加速させましょう。
ハリのある肌を作る食事と栄養素
美しい肌は毎日の食事から作られます。特に50代は、肌の材料となるタンパク質や、抗酸化作用のあるビタミン、ミネラルをバランス良く摂取する工夫が大切です。
肌のハリをサポートする栄養素と主な食材
| 栄養素 | 働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 肌や筋肉の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
| ビタミンE | 血行を促進し、抗酸化作用がある | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
正しい姿勢を保つための意識と工夫
常に正しい姿勢を意識することは、最も手軽で効果的なたるみ対策の一つです。
デスクワークやスマホ操作中は定期的に立ち上がって伸びをしたり、モニターの高さを目線に合わせたりする工夫をしましょう。
正しい姿勢のチェックポイント
- 頭のてっぺんが天井から糸で吊られているようなイメージ
- 肩の力を抜き、少し後ろに引く
- 顎を軽く引き、耳と肩が一直線になるように
睡眠の質が美肌を育む
睡眠中には肌の修復や再生を促す成長ホルモンが分泌されます。
眠り始めの深いノンレム睡眠時に多く分泌されるため、睡眠時間を確保するだけでなく、「質」を高める取り組みが重要です。就寝前のスマホ操作を控え、リラックスできる環境を整えましょう。
紫外線対策の重要性を再確認
紫外線対策は夏だけのものではありません。一年中、曇りの日でも紫外線が降り注いでいます。
日焼け止めを毎日塗る習慣をつけ、帽子や日傘なども活用して、これ以上のダメージ蓄積を防ぐ努力が将来の肌を左右します。
セルフケアの限界と美容医療という選択肢
セルフケアはたるみの予防や進行を緩やかにするために非常に重要ですが、すでに深く刻まれたたるみを劇的に改善するには限界があるのも事実です。
より確実な効果を求める場合、HIFU(ハイフ)や糸リフトなどの美容医療も有効な選択肢となります。
ホームケアで改善できる範囲
毎日のエクササイズや生活習慣の改善は、主に筋肉の衰えや血行不良、むくみによる軽度のたるみに効果を発揮します。
フェイスラインがすっきりしたり、肌のハリが改善したりといった変化は期待できますが、加齢によって伸びてしまった皮膚そのものを元に戻すのは困難です。
美容クリニックで受けられるたるみ治療
美容クリニックでは専門的な知識と技術に基づき、たるみ治療を行います。
肌の深層部に熱エネルギーを加えてコラーゲン生成を促す機器治療(HIFUや高周波など)や、たるみを引き上げる糸リフト、ヒアルロン酸注入など、症状や希望に応じて多様な方法があります。
治療法ごとの特徴とダウンタイム
治療法によって、効果の現れ方や持続期間、ダウンタイム(回復期間)が異なります。
メスを使わない治療はダウンタイムが短い傾向にありますが、効果がマイルドな場合もあります。
自分の生活タイルや、どの程度の変化を望むのかを医師と相談し、納得のいく方法を選ぶようにしましょう。
主な美容医療の比較
| 治療法 | 特徴 | ダウンタイムの目安 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | 超音波で筋膜を引き締める | ほとんどなし〜数日 |
| 高周波(RF) | 高周波で真皮層のコラーゲン生成を促す | ほとんどなし |
| 糸リフト | 溶ける糸を挿入し、物理的に皮膚を引き上げる | 数日〜2週間程度 |
信頼できるクリニックの選び方
治療を受ける際は価格だけで選ばず、カウンセリングを丁寧に行い、メリットだけでなくリスクやデメリットについてもきちんと説明してくれるクリニックを選びましょう。
医師の実績や症例写真を確認し、自分が信頼できると感じる医師を見つけると、満足のいく結果につながります。
50代の顎のたるみに関するよくある質問
診察をしていると、顎のたるみを改善したいと来院される50代の方も多いです。
加齢による肌内部の構造やホルモン分泌の変化、筋力低下など「仕方ない」部分も多いですが、普段の習慣を見直したり、エクササイズやストレッチなどのセルフケアでたるみが軽減する場合があります。
ただし、ご自身で行うケアにはどうしても限界がありますので、即効性を求める方やより積極的に改善したいと思う方は、美容医療を検討するのも良いでしょう。
- エクササイズはどのくらいの期間で効果が出ますか?
-
効果の感じ方には個人差がありますが、毎日継続すると1〜2ヶ月後には顔周りがすっきりした、むくみが取れたといった変化を感じ始める方が多いです。
継続が大切ですので、劇的な変化ではなく、少しずつの改善を目指しましょう。
- 体重を減らせば二重顎は解消しますか?
-
脂肪が原因の二重顎であれば、減量によって改善される可能性が高いです。
しかし50代の場合、皮膚のたるみや筋肉の衰えが複合的に関わっているケースが多いため、体重を落としただけでは皮膚が余ってしまい、逆たるみが目立つ方もいます。
減量と並行して、筋力トレーニングやスキンケアを行うと良いでしょう。
- 男性でも同じケアで効果がありますか?
-
男性でも効果が期待できます。たるみの基本的な原因は男女で共通しているため、エクササイズや生活習慣の改善は、男性の顎のたるみにも有効です。
男性は女性に比べて皮下脂肪が少ないですが、筋肉の衰えや姿勢の悪さは同様にたるみの原因となりますので、ぜひ試してみてください。
- 美容医療を受けるのが少し怖いです。
-
初めてのことに不安を感じるのは当然ですので、まずはカウンセリングだけを受けてみるのがおすすめです。
多くのクリニックでは無料カウンセリングを行っており、専門家から直接話を聞くと疑問や不安が解消される場合もあります。
無理に治療を勧めることはありませんので、情報収集の一環として気軽に相談してみると良いでしょう。
50代たるみ・若返りに戻る
参考文献
ARORA, Gulhima; SHIROLIKAR, Manasi. Tackling submental fat–A review of management strategies. Cosmoderma, 2023, 3.
GALANIN, Ivan; NICU, Carina; TOWER, Jacob I. Facial fat fitness: a new paradigm to understand facial aging and aesthetics. Aesthetic Plastic Surgery, 2021, 45.1: 151-163.
HOGAN, Sara, et al. Submental fat contouring: a comparison of deoxycholic acid, cryolipolysis, and liposuction. Advances in Cosmetic Surgery, 2019, 2.1: 75-87.
PERSING, Sarah; STEINBACHER, Derek M. Submental liposuction. Aesthetic Orthognathic Surgery and Rhinoplasty, 2019, 535-546.
ALAM, Murad, et al. Association of facial exercise with the appearance of aging. JAMA dermatology, 2018, 154.3: 365-367.
FURLAN, Andreza Sonego, et al. Facial Exercises: Enhancing Facial Structure and Reducing Signs of Aging-A Comprehensive Review. Current Cosmetic Science, 2024, 3.1: E181223224616.
BROITMAN, Topaz. The Effect of Facial Exercise on Perceived Appearance, Self-Esteem, Face Image, and Well-Being. 2021. Master’s Thesis. Reichman University (Israel).
DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.