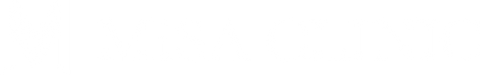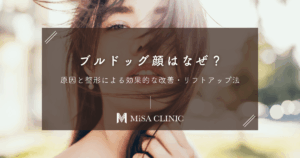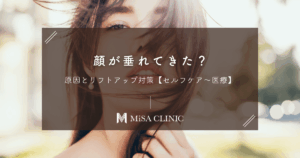たるみの本当の原因とは?年齢だけじゃない意外な要因と今すぐできる対策

顔のたるみは加齢だけで起こるものではありません。紫外線や日々の生活習慣、さらには自分では気づきにくい骨格や筋肉の癖も、たるみを深刻化させる大きな要因です。
この記事では、皮膚の構造からたるみの根本原因を解き明かし、年齢以外の意外な要因を詳しく解説します。
そして、今日から始められる対策から美容クリニックでの本格的な治療まで、たるみと向き合うための具体的な方法を紹介します。
たるみの正体とは?皮膚の構造変化
たるみの原因を探る前に、まずは私たちの皮膚がどのような構造になっているのかを理解することが大切です。
皮膚は外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」という3つの層で構成され、その下にSMAS(スマス)筋膜と筋肉、そして骨が土台となっています。
これらのいずれかの層に変化が起きると、たるみが発生します。
皮膚のハリを支える「真皮」の役割
たるみに最も深く関わるのが、皮膚の本体ともいえる「真皮」です。
真皮は、肌のハリや弾力を保つ「コラーゲン」と、それを束ねる「エラスチン」、そして潤いを保持する「ヒアルロン酸」などで満たされています。
これらの成分がしっかりとした網目構造を作ることで、肌が弾力を保ち、重力に負けないハリを維持します。
しかし、何らかの原因でこれらの成分が減少したり変性したりすると、肌の土台が崩れ、たるみとなって現れます。
肌の各層の役割
| 層の名称 | 主な役割 | たるみとの関連 |
|---|---|---|
| 表皮 | 外部の刺激から肌を守る(バリア機能)、潤いを保つ | 乾燥による小じわの原因になるが、たるみへの直接的な影響は少ない |
| 真皮 | 肌のハリと弾力を保つ | コラーゲン等の減少がたるみの主な原因となる |
| 皮下組織 | 脂肪を蓄え、衝撃を吸収する | 脂肪の増減や下垂がたるみにつながる |
クッションの役割を担う「皮下組織」
真皮の下にある皮下組織は、その大部分が「皮下脂肪」で構成されています。皮下脂肪は、外部からの衝撃を和らげるクッションの役割や、体温を保つ断熱材の役割を果たします。
適度な皮下脂肪は若々しい印象を与えますが、増えすぎるとその重みで皮膚が垂れ下がり、たるみの原因になります。
逆に、急激に減少すると皮膚が余ってしまい、これもまたたるみにつながります。
土台となる「SMAS筋膜」と「表情筋」
皮下組織と筋肉の間には、「SMAS(スマス)筋膜」という薄い膜状の組織があります。SMAS筋膜は皮膚と筋肉をつなぎ、一体となって表情を作り出します。
このSMAS筋膜が加齢などによって緩むと、その上にある皮下脂肪や皮膚を支えきれなくなり、雪崩のようにたるみが生じます。
また、表情を作る「表情筋」の衰えも皮膚を支える力を弱め、たるみを助長する要因です。
加齢だけではない!たるみを引き起こす3つの主要因
たるみの原因として最もよく知られているのは加齢ですが、それだけではありません。
ここでは、たるみを引き起こす主な3つの要因について詳しく見ていきましょう。これらの要因が複雑に絡み合って、たるみが進行していきます。
コラーゲンとエラスチンの減少と変性
肌のハリを支える真皮層のコラーゲンとエラスチンは、20代をピークに徐々に減少し始め、質も変化していきます。
線維芽細胞という細胞がこれらの成分を作り出しますが、加齢とともにその働きが鈍くなるため、産生量が減少します。
さらに、紫外線や糖化などの影響でコラーゲンやエラスチンが硬くなったり、断裂したりする「変性」が起こります。
この産生量の減少と質の低下が、肌の弾力を失わせ、たるみを引き起こす根本的な原因です。
コラーゲンとエラスチンの特徴
| 成分 | 特徴 | 役割 |
|---|---|---|
| コラーゲン | 真皮の約70%を占める線維状のタンパク質 | 肌の構造を支え、ハリを与える |
| エラスチン | ゴムのように伸縮性のあるタンパク質 | コラーゲンを束ね、肌に弾力を与える |
皮下脂肪の増減と移動
顔の皮下脂肪は、加齢とともにその位置を変える性質があります。
若い頃は頬の高い位置にあった脂肪が年齢を重ねるとともに重力に引かれて下方へ移動し、ほうれい線やマリオネットライン、フェイスラインのもたつきの原因となります。
また、急激なダイエットなどで脂肪が減少すると、皮膚が風船の空気が抜けたように余ってしまい、たるみとして現れます。
逆に体重が増加して脂肪が増えると、その重みで皮膚が垂れ下がります。
表情筋の衰えとSMAS筋膜のゆるみ
顔には約30種類もの表情筋がありますが、日常生活で使われるのはその一部にすぎません。特に意識して動かさないと、多くの筋肉は年齢とともに衰えていきます。
筋肉が衰えると、その上にある脂肪や皮膚を支える力が弱まり、たるみにつながります。
さらに、皮膚と筋肉をつなぐSMAS筋膜も、加齢によって緩んできます。
この筋膜の緩みは顔全体のたるみを引き起こす大きな要因であり、フェイスリフト手術などではこの層への働きかけが重要になります。
その「たるみ」、実は骨格や筋肉の癖が原因かもしれません
多くの人がたるみの原因を皮膚や脂肪の問題だと考えがちですが、実はその土台となる「骨」の萎縮や、無意識の「癖」が、たるみを加速させているケースは少なくありません。
ここでは、他のサイトではあまり触れられない、たるみの意外な原因について掘り下げます。ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、確認してみてください。
加齢による「骨の萎縮」という土台の変化
あまり知られていませんが、顔の骨も体の骨と同じように、年齢とともに萎縮していきます。特に、目の周りの眼窩(がんか)や頬骨、あごの骨は萎縮しやすい部位です。
骨という土台が縮むと、その上にある筋肉や脂肪、皮膚が余ってしまい、行き場を失って垂れ下がります。
これが、目元のくぼみやゴルゴライン、フェイスラインの崩れといった、加齢による深刻なたるみの一因です。骨の萎縮は、皮膚表面のケアだけでは対応が難しい問題です。
骨萎縮が影響しやすい部位と現れるたるみ
| 萎縮しやすい骨の部位 | 現れやすい変化・たるみ |
|---|---|
| 眼窩(目の周り) | 目の下のくぼみ、たるみ、クマ |
| 頬骨 | ゴルゴライン、ほうれい線 |
| 顎骨(あご) | フェイスラインのもたつき、マリオネットライン |
片側だけで噛む癖と顔の非対称なたるみ
食事の際に、無意識に左右どちらか片側だけで噛む癖のある方もいるでしょう。
片側だけで噛む習慣があると、よく使う側の筋肉(咬筋)ばかりが発達し、顔の左右差が生まれます。使われない側の筋肉は衰え、たるみやすいです。
この左右非対称なたるみは、ほうれい線の深さや口角の高さに違いとなって現れ、顔全体のバランスを崩す原因になります。
姿勢の悪さが招く首から顔へのたるみ
スマートフォンやパソコンの長時間利用による猫背やストレートネックも、顔のたるみと無関係ではありません。
頭の重さは約5kgもあり、首が前に傾くほど、首や肩の筋肉に大きな負担がかかります。この状態が続くと、首の前側にある広頸筋(こうけいきん)が縮んで硬くなり、フェイスラインを引き下げる力が働きます。
この結果、二重あごやフェイスラインのもたつきが生じやすくなります。良い姿勢を保つ心がけは、顔のたるみ予防にもつながるのです。
無意識の表情の癖と刻まれるたるみ
眉間にしわを寄せる、口を「へ」の字にする、頬杖をつくなど、無意識に行っている表情の癖もたるみの原因になります。
特定の筋肉ばかりを緊張させると、その部分の血行が悪くなり、皮膚のハリが失われます。
また、頬杖は片側の顔に継続的な圧力をかける行為であり、皮膚やSMAS筋膜を歪ませ、たるみを定着させる可能性があります。自分の癖に気づき、意識して直すことが大切です。
紫外線による肌への深刻な影響「光老化」
たるみの最大の外的要因ともいえるのが「紫外線」です。紫外線によって引き起こされる肌の老化現象は「光老化」と呼ばれ、自然な老化とは区別されます。
日光を浴びる機会が多い人は、そうでない人と比べて、たるみやシワが深く刻まれやすいことがわかっています。
そのため紫外線対策は、たるみケアの基本中の基本です。
真皮にまで届くUVAの脅威
紫外線には、波長の長い「UVA」と波長の短い「UVB」があります。
UVBが肌表面の表皮にダメージを与えて日焼けやシミの原因になるのに対し、UVAはより深く、真皮層にまで到達します。
そして、肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンを破壊する酵素(マトリックスメタロプロテアーゼ)を増やす作用があります。
このUVAの作用により真皮の構造がじわじわと破壊され、肌が弾力を失い、たるんでいきます。
紫外線の種類と肌への影響
| 種類 | 特徴 | 主な肌への影響 |
|---|---|---|
| UVA(紫外線A波) | 波長が長く、雲や窓ガラスを通過して真皮に届く | たるみ、シワの原因(光老化) |
| UVB(紫外線B波) | 波長が短く、主に表皮に作用する | 日焼け(炎症)、シミ、そばかすの原因 |
気づかぬうちに浴びている生活紫外線
UVAはUVBと異なり、季節や天候による変動が少なく、一年中降り注いでいます。また、雲や窓ガラスも透過するため、「曇りの日だから」「室内だから」と油断はできません。
日常生活の中で知らず知らずのうちに浴びているこれらの紫外線を「生活紫外線」と呼びます。
毎日の紫外線対策を習慣にすることが、光老化を防いで将来のたるみを予防するために重要です。
紫外線対策の基本と日焼け止めの選び方
紫外線対策の基本は、日焼け止めの正しい使用です。日焼け止めには「SPF」と「PA」という表示があります。
SPFはUVBを防ぐ効果の指標、PAはUVAを防ぐ効果の指標です。日常生活ではSPF20~30、PA++程度のもので十分ですが、屋外でのレジャーなどではより効果の高いものを選びましょう。
また、汗や摩擦で落ちてしまうため、2~3時間おきに塗り直すのが効果を持続させるポイントです。
生活習慣に潜むたるみのリスク
たるみは、毎日の何気ない生活習慣の積み重ねによっても引き起こされます。
食事や睡眠、喫煙などの習慣が、肌のコンディションに大きく影響します。ご自身の生活を見直し、たるみを加速させるリスクがないかチェックしてみましょう。
栄養バランスの偏りと「糖化」
肌は私たちが食べたものから作られます。タンパク質やビタミン、ミネラルなど、バランスの取れた栄養摂取は健康な肌を保つために必要です。
なかでもタンパク質はコラーゲンの材料となり、ビタミンCはその合成を助ける働きがあります。
一方で、糖質の過剰摂取には注意が必要です。体内の余分な糖がタンパク質と結びつくと、「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質が生成されます。
この現象を「糖化」と呼びます。糖化によってコラーゲンが変性すると肌が黄色くくすみ、弾力を失ってたるみの原因になります。
たるみ対策に役立つ栄養素と食品
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 肌や筋肉の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける、抗酸化作用 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康を保つ | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |
睡眠不足と成長ホルモンの関係
睡眠中は肌のダメージを修復し、再生を促す「成長ホルモン」が分泌されます。入眠後の最初の3時間はゴールデンタイムと呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になります。
睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、肌のターンオーバーが乱れたり、コラーゲンの修復が追いつかなくなったりします。この結果、肌のハリが失われ、たるみやすい状態になります。
質の良い睡眠を十分にとる工夫は、高価な美容液にも勝るスキンケアといえるでしょう。
喫煙による血行不良とビタミンCの破壊
喫煙はたるみにとって百害あって一利なしです。タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があるため、皮膚の血行が悪くなります。
血行不良に陥ると、肌細胞に必要な酸素や栄養素が届きにくくなり、老廃物の排出も滞ります。
また、タバコを1本吸うごとに、体内で大量のビタミンCが破壊されます。ビタミンCはコラーゲンの生成に必要であるため、その欠乏は直接的に肌のハリ低下につながります。
喫煙者の肌が、非喫煙者に比べて老化しやすいのはこのためです。
たるみを悪化させるNG習慣
- 急激なダイエット
- 猫背・ストレートネック
- 片側での噛み癖・頬杖
- 睡眠不足
誤ったスキンケアと肌への摩擦
良かれと思って行っているスキンケアが、逆にたるみを招いている可能性もあります。
例えば、クレンジングや洗顔の際に肌をゴシゴシと強くこする行為は肌への摩擦となり、真皮のコラーゲン線維にダメージを与えます。
また、マッサージも方法を間違えると、皮膚を不必要に引っ張ってしまい、SMAS筋膜の緩みを助長しかねません。
スキンケアは常に「優しく触れる」を基本とし、肌に余計な負担をかけないように心がけましょう。
たるみの種類別セルフケアと限界
たるみの原因が多岐にわたるように、その対策も一つではありません。ここでは、ご自身で取り組めるセルフケアの方法をいくつか紹介します。
ただし、セルフケアで改善できる範囲には限界があることも理解しておくことが重要です。
保湿と紫外線対策は全ての基本
どのようなたるみであっても、基本となるのは「保湿」と「紫外線対策」です。
肌が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。セラミドやヒアルロン酸などが配合された化粧品で十分に保湿し、肌の健康状態を保ちましょう。
そして、光老化を防ぐために季節を問わず紫外線対策を徹底することが、将来のたるみを予防する上で最も効果的なセルフケアです。
エイジングケア化粧品の選び方と使い方
たるみ対策を目的としたエイジングケア化粧品には、コラーゲンの生成をサポートする「レチノール」や「ビタミンC誘導体」、抗酸化作用のある「ナイアシンアミド」などの成分が配合されています。
これらの成分は、肌のハリや弾力をサポートする効果が期待できます。
ただし、化粧品が浸透するのは角質層までであり、真皮層のコラーゲンを劇的に増やしたり、緩んだSMAS筋膜を引き締めたりできません。あくまでも、たるみの予防や初期段階のケアと位置づけましょう。
代表的なエイジングケア成分
| 成分名 | 期待される効果 | 使用上の注意点 |
|---|---|---|
| レチノール | ターンオーバー促進、コラーゲン生成サポート | 刺激を感じることがあるため、少量から試す |
| ビタミンC誘導体 | コラーゲン生成サポート、抗酸化作用、メラニン生成抑制 | 様々な種類があり、製品によって特徴が異なる |
| ナイアシンアミド | シワ改善、セラミド生成促進、メラニン生成抑制 | 比較的刺激が少なく、他の成分と併用しやすい |
表情筋トレーニングの正しいやり方
表情筋を鍛えることは、筋肉の衰えによるたるみの予防に役立ちます。ただし、やみくもに行うと、逆にシワを深くする可能性もあるため注意が必要です。
鍛えたい筋肉を意識し、他の部分に余計な力が入らないようにするのがポイントです。鏡を見ながら、ゆっくりと正確に行いましょう。
口の周りの口輪筋や、頬を引き上げる大頬骨筋などを意識して動かすトレーニングが効果的です。
セルフケアの限界と美容医療という選択肢
保湿や紫外線対策、化粧品によるケアはたるみの予防や進行を遅らせる上で非常に大切です。
しかし、すでに進行してしまった真皮の変性やSMAS筋膜の緩み、皮下脂肪の下垂をセルフケアだけで元に戻すのは困難です。
これらの根本的な原因に働きかけ、目に見える改善を望むのであれば、美容クリニックでの治療が有効な選択肢となります。
セルフケアは「守りのケア」、美容医療は「攻めのケア」と考えるとよいでしょう。
美容クリニックでできる本格的たるみ治療
セルフケアでは改善が難しいと感じたら、美容クリニックへの相談をおすすめします。現在の美容医療では、メスを使わずにたるみを改善できる様々な治療法があります。
ご自身のたるみの状態や原因、生活スタイルに合わせて、専門医と相談しながら治療法を選択していきましょう。
HIFU(ハイフ)によるSMAS筋膜への働きかけ
HIFU(高密度焦点式超音波)は、超音波の熱エネルギーを皮膚の深層部、特にSMAS筋膜にピンポイントで照射する治療法です。
熱によってSMAS筋膜が収縮し、即時的なリフトアップ効果が期待できます。さらに、熱ダメージを受けた組織が治癒する過程でコラーゲンの生成が促進されるため、中長期的に肌のハリや弾力が向上します。
ダウンタイムがほとんどなく、メスを使わずに土台から引き上げたい方に適しています。
高周波(RF)による真皮の引き締め
高周波(RF)治療は、ラジオ波という電磁波を皮膚に照射し、その抵抗熱で真皮層を加熱する治療法です。
真皮層のコラーゲン線維が熱によって収縮し、即時的な引き締め効果を得られます。
また、HIFUと同様に、創傷治癒の働きで新たなコラーゲンやエラスチンの生成が促されるため、継続的なハリ感アップにつながります。皮膚表面の引き締めや、小じわの改善にも効果的です。
HIFUと高周波(RF)の比較
| 治療法 | 主な作用部位 | 得意なたるみ・効果 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | SMAS筋膜、皮下組織 | フェイスラインのリフトアップ、土台からの引き上げ |
| 高周波(RF) | 真皮層、皮下組織浅層 | 皮膚表面の引き締め、ハリ感アップ、小じわ改善 |
糸リフト(スレッドリフト)による物理的な引き上げ
糸リフトは、コグ(とげ)の付いた特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ組織を物理的に引き上げる治療法です。
ほうれい線やマリオネットライン、フェイスラインのもたつきなど、脂肪の下垂によるたるみに効果を発揮しやすいです。
使用する糸は時間とともに体内に吸収されますが、その過程で糸の周りにコラーゲンが生成されるため、肌のハリを維持する効果も期待できます。
ダウンタイムは他の照射治療に比べてやや長めですが、その分、見た目の変化を実感しやすい治療です。
ヒアルロン酸注入によるボリューム補充
たるみは皮膚が垂れ下がるだけでなく、加齢によるボリュームロス(くぼみやへこみ)によっても目立ちます。
ヒアルロン酸注入は、こめかみや頬、あごなどにヒアルロン酸を注入し、失われたボリュームを補う治療法です。
骨の萎縮によってできた影やくぼみを改善し、顔全体を立体的に若々しい印象に整えます。適切な部位に注入すると、リフトアップしたように見せることも可能です。
よくある質問(FAQ)
たるみの原因は皮膚の老化だけでなく、光老化や骨の萎縮、生活習慣などさまざまです。とくに、紫外線による光老化は、肌の老化原因の80%を占めると言われています。
たるみの原因が分かれば、新たなたるみを作らないように対策も行えますが、筋膜や骨といったセルフケアだけでは働きかけられないところの変化があるのも事実です。
たるみを本格的に改善したい方は、いちどクリニックの無料カウンセリングに足を運んでみましょう。
- たるみ治療は何歳から始めるべきですか?
-
たるみ治療に「何歳から」という決まりはありません。たるみが気になり始めた時が、治療を検討するタイミングです。
20代後半から30代で予防的にHIFUなどを受け始める方もいれば、40代、50代以上で本格的なたるみ治療を開始する方もいます。
大切なのは、ご自身の肌の状態と向き合い、早めに予防的なケアを始めることです。紫外線対策や保湿などのセルフケアは、年齢にかかわらず今日から始めましょう。
- 治療の効果はどのくらい続きますか?
-
治療法によって効果の持続期間は異なります。例えば、HIFUや高周波の効果は半年から1年程度、糸リフトは1年から2年程度、ヒアルロン酸注入は製剤の種類によりますが半年から2年程度が目安です。
ただし、これらはあくまで目安であり、個人の肌質や生活習慣によっても変わります。また、治療後も老化は続くため、効果を維持するためには定期的なメンテナンスや日々のセルフケアが重要です。
- 治療後のダウンタイムや痛みはありますか?
-
治療法によってダウンタイムや痛みは異なります。HIFUや高周波のような照射治療はダウンタイムがほとんどなく、施術後に赤みや軽い腫れが出る場合がありますが、数時間から数日で治まるケースがほとんどです。
糸リフトや注入治療は、内出血や腫れ、むくみなどが数日から2週間程度続く場合があります。
施術中は麻酔を使用するため、強い痛みを感じる方は少ないですが、治療法による違いや個人差があります。カウンセリングの際に、医師に詳しく確認してみましょう。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
EZURE, T., et al. Sagging of the cheek is related to skin elasticity, fat mass and mimetic muscle function. Skin Research and Technology, 2009, 15.3: 299-305.
IMOKAWA, Genji; NAKAJIMA, Hiroaki; ISHIDA, Koichi. Biological mechanisms underlying the ultraviolet radiation-induced formation of skin wrinkling and sagging II: Over-expression of neprilysin plays an essential role. International Journal of Molecular Sciences, 2015, 16.4: 7776-7795.
TSUKAHARA, Kazue, et al. Comparison of age-related changes in facial wrinkles and sagging in the skin of Japanese, Chinese and Thai women. Journal of dermatological science, 2007, 47.1: 19-28.
SJEROBABSKI-MASNEC, Ines; SITUM, Mirna. Skin aging. Acta Clin Croat, 2010, 49.4: 515-8.
FARAGE, M. A., et al. Intrinsic and extrinsic factors in skin ageing: a review. International journal of cosmetic science, 2008, 30.2: 87-95.
IMOKAWA, Genji; ISHIDA, Koichi. Biological mechanisms underlying the ultraviolet radiation-induced formation of skin wrinkling and sagging I: Reduced skin elasticity, highly associated with enhanced dermal elastase activity, triggers wrinkling and sagging. International journal of molecular sciences, 2015, 16.4: 7753-7775.
DOBOS, G., et al. Evaluation of skin ageing: a systematic review of clinical scales. British Journal of Dermatology, 2015, 172.5: 1249-1261.
MCCULLOUGH, Jerry L.; KELLY, Kristen M. Prevention and treatment of skin aging. Annals of the New York Academy of Sciences, 2006, 1067.1: 323-331.