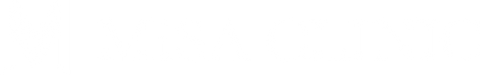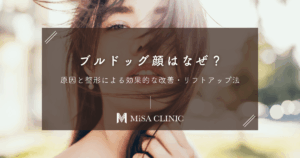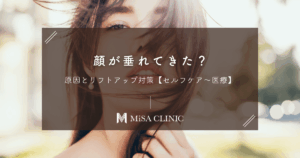口角のたるみを上げて笑顔美人!原因と効果的な改善エクササイズ

口角のたるみは、「不機嫌そう」「疲れている」といった印象を与えがちで、笑顔にも自信が持てなくなってしまいます。
このたるみは、加齢だけでなく、日常のさまざまな習慣が原因で起こります。
この記事では、口角がたるむ原因を詳しく解説し、自宅でできる効果的な改善エクササイズ、さらには美容クリニックでの専門的な治療法まで、幅広く紹介します。
なぜ口角は下がる?たるみの原因
口角が下がる主な原因は、皮膚の弾力低下と、口周りの筋肉(表情筋)の衰えです。これらが複合的に絡み合い、たるみとして現れます。
加齢による皮膚の弾力低下
年齢を重ねると肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンが減少し、質も変化します。その結果、皮膚が弾力を失い、重力の影響を受けて垂れ下がりやすくなります。
特に口周りは皮膚が薄く、動きが多いため、たるみの影響が出やすい部位です。
表情筋(口輪筋など)の衰え
口の周りを囲む「口輪筋(こうりんきん)」や、口角を斜め上に引き上げる「大頬骨筋(だいきょうこつきん)」などの表情筋が衰えると、口角を支える力が弱まります。
表情筋は使わなければ衰えます。日常的に表情をあまり動かさないでいると筋力が徐々に低下し、口角が下がってしまいます。
口角に関連する主な筋肉
| 筋肉名 | 主な働き | 衰えるとどうなるか |
|---|---|---|
| 口輪筋 | 口を閉じたり、すぼめたりする | 口元のハリが失われ、口角が下がる |
| 大頬骨筋 | 口角を斜め上に引き上げる(笑顔) | 笑顔が作りにくく、口角が上がらない |
| 口角下制筋 | 口角を下に引く(「へ」の字口) | この筋肉が緊張しすぎると口角が下がる |
紫外線や乾燥による肌ダメージ
紫外線は、肌の弾力線維であるコラーゲンやエラスチンを破壊する最大の外的要因です。長年にわたる紫外線ダメージの蓄積は肌の土台を脆弱にし、たるみを加速させます。
また、肌が乾燥するとバリア機能が低下し、あらゆる外的刺激の影響を受けやすくなり、ハリの低下につながります。
姿勢や生活習慣の影響
猫背やストレートネックなど、悪い姿勢は顔の筋肉にも影響を与えます。首が前に出る姿勢は、あごの下の筋肉をたるませ、結果として口角を引き下げる力につながる場合があります。
また、頬杖をつく癖、片側だけで食べ物を噛む癖なども顔の筋肉バランスを崩し、たるみの原因となります。
口角のたるみが引き起こす「見た目」の変化
口角がたるむと不機嫌に見えたり、老けた印象を与えたりするなど、顔全体の印象を大きく左右します。単に「口元が下がっている」というだけでなく、さまざまな変化が現れます。
怒っているように見える?「不機嫌顔」の定着
口角が下がっていると、無表情でも「怒っている」「不機嫌そう」という印象を他者に与えがちです。
本人はそんなつもりがなくても、ネガティブな印象を持たれてしまうのは社会生活において大きな悩みとなり得ます。
マリオネットラインとの関係
口角からあごにかけて伸びる線を「マリオネットライン」と呼びます。口角のたるみが進行すると、このマリオネットラインがくっきりと刻まれます。
この線があると口元がさらに強調され、老けた印象が強くなります。
笑顔に自信が持てなくなる
口角が下がっていると笑顔を作ろうとしても上手く上がらない、あるいは笑顔がぎこちなく感じられるときがあります。
それが原因で人前で笑うことに抵抗を感じるようになり、徐々に笑顔が減ってしまうという悪循環に陥るケースも少なくありません。
全体的な「老け顔」印象
口角の下がりは、ほうれい線やマリオネットラインと連動し、顔の下半分の印象を重く見せます。
顔の上半分が若々しくても、口元がたるんでいるだけで、全体として「老けた顔」という印象を与えてしまいます。
たるみの進行と印象の変化
| たるみのレベル | 主な状態 | 与える印象 |
|---|---|---|
| 初期 | 真顔の時に口角が水平より下 | 少し疲れている、元気がない |
| 中期 | 「へ」の字口が目立つ | 不機嫌そう、怒っている |
| 進行期 | マリオネットラインが明確になる | 老けて見える、頑固そう |
口角のたるみは「心の疲れ」のサイン?
口角のたるみは、身体的な老化現象だけでなく、ストレスやスマートフォンの長時間利用などによる「心の疲れ」や「生活の歪み」が反映されたサインでもあります。
あなたの口角は、心と体の状態を正直に映し出しているかもしれません。
ストレスと表情の強張り
強いストレスや持続的な緊張状態は、無意識のうちに顔の筋肉を強張らせます。特に、食いしばりや歯ぎしりは、口周りやこめかみの筋肉(咬筋や側頭筋)を過度に緊張させます。
この緊張が口角を下げる筋肉(口角下制筋)を優位にし、口角が下がりやすくなるのです。
スマートフォンが招く「無表情」の時間
スマートフォンやPCの画面に集中している間、私たちはどのような表情をしているでしょうか。多くの場合、真顔、あるいは無表情で画面を見つめ続けています。
この「無表情の時間」が長ければ長いほど、表情筋、特に口角を引き上げる筋肉を使う機会が激減します。これが「デジタルたるみ」とも呼べる現象です。
スマホ利用時の姿勢と筋肉
| スマホ利用時の特徴 | 影響 | 口角への結果 |
|---|---|---|
| うつむき姿勢 | 首やあご下の筋肉への負担 | 顔全体のたるみを助長 |
| 無表情 | 表情筋(特に口角挙上筋)の不使用 | 筋力低下、たるみ |
| ブルーライト | 睡眠の質低下、目元の疲れ | 間接的に肌のターンオーバーを阻害 |
笑顔の減少が筋力低下を招く悪循環
心が疲れていると、自然と笑顔は減ります。笑顔が減ると笑顔を作るための筋肉(大頬骨筋など)が使われず、衰えていきます。
筋肉が衰えると、さらに口角が上がりにくくなり、たるみが進行します。この悪循環が見た目の印象をさらに暗くし、心の状態にも影響を与える可能性があります。
今すぐチェック!あなたの口角たるみ度
鏡や割り箸を使って、ご自身の口角のたるみ度を簡単にチェックできます。まずはご自身の状態を客観的に把握してみましょう。
鏡で簡単セルフチェック法
まず、鏡の前に立ち、真正面から自分の顔をリラックスした状態(真顔)で観察します。口角の位置を確認してください。
理想的な状態は、口角が口の中心線(唇の閉じた線)よりもわずかに上、または少なくとも水平であることです。
もし、真顔の状態で口角が水平線より下に下がっていたら、たるみが始まっているか、口角を下げる筋肉が強く働いている可能性があります。
「への字口」になっていないか
意識していない時に、口が「へ」の字になっている方も少なくありません。
口角からあごに向かって斜め下に走る線(マリオネットライン)が薄くても、口角自体が下がっていると全体として「への字」の印象を与えます。これが定着すると、たるみが進行しているサインです。
割り箸を使った筋力チェック
清潔な割り箸やストローを1本用意します。それを横にして唇だけでくわえ、「いー」と発音するように口角を限界まで引き上げます。その状態で30秒間キープできるか試してみてください。
もし30秒キープできない、口角がプルプルと震えてしまう、唇ではなく歯で噛んでしまう場合は、口輪筋の筋力が低下している可能性があります。
口角たるみ度チェック
- 真顔の時、口角が下がっている
- 以前より笑顔が作りにくくなったと感じる
- マリオネットラインが目立ってきた
- 割り箸を30秒間キープできない
- 口を閉じている時、無意識に口が開くことがある
自宅でできる!口角挙上エクササイズ
口角のたるみは、表情筋を鍛えるトレーニングによって改善が期待できます。「ウイウイ」トレーニングや舌回しなどを毎日コツコツと続ける努力が重要です。
基本の「ウイウイ」トレーニング
これは口輪筋と口角を引き上げる筋肉を同時に鍛えるエクササイズです。
まず、唇を前に突き出して「ウー」の形を5秒間キープします。次に、口を横に大きく引き、「イー」の形(口角を最大限に引き上げる)を5秒間キープします。
この「ウー」「イー」を1セットとし、10回ほど繰り返します。
舌を使った口輪筋強化
口を閉じた状態で、舌先を使って歯茎の表面をなぞるように、口の中で大きく円を描きます。
まず右回りで10周、次に左回りで10周行います。ほうれい線の内側を舌で押し出すように意識すると、口輪筋全体に働きかけられます。
ペットボトルを使った簡単エクササイズ
空の500mlペットボトルを用意します(最初は水がなくてもOK、慣れたら少量の水を入れる)。
これを唇の力だけでくわえ、歯を使わずに10秒間キープします。これは特に口輪筋の強化に役立ちます。
ただし、あごに力が入りすぎないよう注意してください。
口角エクササイズまとめ
| エクササイズ名 | 鍛えられる筋肉 | 目安 |
|---|---|---|
| ウイウイトレーニング | 口輪筋、大頬骨筋など | 10セット(1日2回) |
| 舌回し | 口輪筋、舌筋 | 右回し10周、左回し10周 |
| ペットボトルくわえ | 口輪筋 | 10秒キープ(3セット) |
エクササイズの適切な頻度と注意点
エクササイズは、毎日の継続が大切です。朝晩のスキンケアのついでになど、習慣化しやすいタイミングで行うと良いでしょう。
ただし、やりすぎは禁物です。筋肉痛がひどい場合や、あごに痛みを感じる場合は、回数を減らすか、一時中断してください。
また、エクササイズ中は鏡を見て、口角が左右均等に上がっているか確認しながら行うとより効果的です。
エクササイズだけじゃない!日常で心がけるたるみ予防
たるみ予防には、エクササイズと並行し、保湿や紫外線対策、正しい姿勢やバランスの取れた食事といった生活習慣の改善が非常に重要です。
保湿と紫外線対策の徹底
肌の弾力を保つため、保湿は欠かせません。化粧水や乳液、クリームなどで肌に水分と油分を補い、潤いを保ちましょう。
また、紫外線の影響は季節や天候に関わらず存在します。日焼け止めを毎日使用し、帽子や日傘も活用して、肌を紫外線ダメージから守る習慣が未来のたるみ予防につながります。
正しい姿勢を意識する
特にPCやスマートフォンを使用する際は背筋を伸ばし、画面が目線の高さに来るよう調整しましょう。
猫背やうつむき姿勢は、顔のたるみを引き起こす原因になります。常に頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで、正しい姿勢を心がけます。
バランスの取れた食事と良質な睡眠
肌は食べたもので作られます。偏った食事は肌の健康を損ないます。
良質なたんぱく質(コラーゲンの材料)、ビタミンC(コラーゲン生成を助ける)、ビタミンA・E(抗酸化作用)などをバランス良く摂取すると良いです。
たるみ予防のための栄養素
- たんぱく質(肉、魚、大豆製品、卵)
- ビタミンC(ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類)
- ビタミンA(レバー、うなぎ、緑黄色野菜)
- ビタミンE(ナッツ類、アボカド、植物油)
また、成長ホルモンが分泌される夜間の睡眠は、肌の修復と再生に重要な時間です。質の良い睡眠を十分にとるよう努めましょう。
よく噛んで食べる習慣
食事の際、あまり噛まずに飲み込んでいる方も見受けられます。「よく噛む」という行為は、口周りの筋肉(表情筋や咀嚼筋)を自然に鍛えるトレーニングになります。
一口入れたら30回噛むことを目安にしたり、少し歯ごたえのある食材(根菜やきのこ類など)をメニューに取り入れたりするのも良い方法です。
日常の「ながら」予防策
| 場面 | 予防行動 | 理由 |
|---|---|---|
| 食事中 | 左右均等に、よく噛む | 咀嚼筋と表情筋のトレーニング |
| PC・スマホ作業中 | 背筋を伸ばし、時々上を向く | うつむき姿勢によるたるみ防止 |
| 屋外 | 日焼け止め、帽子、日傘 | 紫外線によるコラーゲン破壊防止 |
セルフケアの限界?美容クリニックのたるみ治療
エクササイズや生活習慣の改善は、たるみの予防や初期段階の改善には効果が期待できます。
しかし、すでに深く刻まれてしまったマリオネットラインや、表情筋の衰えが著しい場合、セルフケアだけでは満足のいく結果を得るのが難しいのも事実です。
美容医療で期待できること
美容クリニックでは医師の診断のもと、たるみの原因や程度に合わせて、より直接的で効果的な治療を選択できます。
セルフケアが「予防」や「緩やかな改善」であるのに対し、美容医療は「積極的な改善」や「修復」を目指せます。
ヒアルロン酸注入によるアプローチ
ヒアルロン酸は、もともと体内に存在する保湿成分です。これを口角周辺やマリオネットラインに注入すると、皮膚を内側から持ち上げ、溝を目立たなくさせます。
また、口角を下げる筋肉(口角下制筋)の働きを調整するボツリヌス・トキシン注射と組み合わせて、自然に口角が上がりやすい状態を作る治療も人気です。
HIFU(ハイフ)などの照射治療
HIFU(高密度焦点式超音波)は、皮膚の深い層(SMAS筋膜)に熱エネルギーを加え、組織を収縮させてたるみを引き締める治療です。
メスを使わずにリフトアップ効果が期待でき、コラーゲンの生成も促すため、肌のハリ感アップにもつながります。
糸リフト(スレッドリフト)の選択
たるみが中程度以上進行している場合には、医療用の特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚を物理的に引き上げる「糸リフト」も選択肢となります。
糸が組織を支えるため、口角やフェイスラインがシャープになります。糸の素材や形状によって、期待できる効果や持続期間が異なります。
主なクリニック治療法比較
| 治療法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 溝を埋める、ボリュームを補う | 比較的短時間で効果を実感しやすい |
| HIFU(ハイフ) | 皮膚の引き締め、リフトアップ | メス不要、ダウンタイムが少ない傾向 |
| 糸リフト | 物理的な引き上げ | たるみが強い場合に効果的 |
美しい笑顔のために専門家へ相談
口角のたるみの状態や原因は、人それぞれ異なります。ご自身の判断でケアを続けるのも大切ですが、専門家の視点を取り入れると、より安全で効果的な道筋が見つかります。
なぜ専門家の診断が必要か
たるみの原因が「皮膚のゆるみ」なのか、「筋肉の衰え」なのか、あるいは「骨格の変化」も関係しているのかによって、適した方法が全く異なります。
自己流のケアが、かえってシワを深めてしまうケースもゼロではありません。医師が直接お顔の状態を拝見し、たるみの根本原因を診断することが改善への第一歩です。
カウンセリングで話すべきこと
カウンセリングは、医師とご自身の認識を合わせる重要な場です。
「いつから気になっているか」「どのような時に一番気になるか」「どのような状態になりたいか」など、ご自身の悩みや希望を具体的に伝えてください。
また、不安に思っていること、疑問点も遠慮なく質問しましょう。
カウンセリングのポイント
- 現在の悩みを具体的に伝える
- 理想のイメージ(写真など)があれば提示する
- 治療に関して不安な点をリストアップしておく
- 予算や通院可能な頻度を伝える
あなたに合った治療計画
美容クリニックでは、診断結果と患者さんのご希望(ダウンタイムは取れるか、予算はどれくらいか等)を総合的に判断し、一人ひとりに合った治療計画を提案します。
HIFUで土台を引き締め、ヒアルロン酸で細部を整えるなど、複数の治療を組み合わせる場合もあります。
治療後のアフターケア
治療効果を最大限に高め、長持ちさせるためには、治療後のアフターケアも重要です。
クリニックでの定期的な検診に加え、ご自宅でのエクササイズやスキンケアを継続すると、より良い状態を維持しやすくなります。
治療がゴールではなく、美しい笑顔を保ち続けるためのスタートラインと考え、医師と協力してケアを続けていきましょう。
口角のたるみに関するFAQ
口角のたるみは、本人も気づかないうちに進行していることが多いです。
加齢に加え、肌弾力の低下や表情筋の衰え、紫外線や乾燥、姿勢や生活習慣などが原因であり、若い方でも口角のたるみが現れるケースもあります。
まずはご自身でできるエクササイズやケアを行い、それでも効果を実感できないときは、いちどクリニックの無料カウンセリングを受けてみるのがおすすめです。
- エクササイズはどれくらいで効果が出ますか?
-
効果の実感には個人差があります。一般的には、表情筋のトレーニングは最低でも1〜2ヶ月は毎日継続することが必要です。
筋肉の変化はゆっくりと現れるため、焦らずに習慣化していきましょう。
- ほうれい線と口角のたるみは関係ありますか?
-
深く関係しています。頬全体のたるみがほうれい線と口角のたるみの両方を引き起こします。
頬を支える筋肉が衰えたり皮膚の弾力が失われたりすると、その重みでほうれい線が深くなり、同時に口角も下がってきます。
- クリニックでの治療は痛いですか?
-
治療法によって痛みの感じ方は異なります。
HIFUは部位によって熱感や鈍い痛みを感じる場合があります。注入治療や糸リフトは、麻酔クリームや局所麻酔を使用するため、痛みを最小限に抑える工夫をしています。
痛みの感じ方には個人差がありますので、カウンセリング時にご相談ください。
- 治療後もエクササイズは続けても良いですか?
-
継続をおすすめします。ただし、治療直後は控えるべき期間があります。
例えば、ヒアルロン酸注入後や糸リフト後は、安定するまで数週間は顔を強く動かすエクササイズを避けるよう指示するときがあります。
治療効果を維持するためにも、医師の指示に従い、適切な時期からセルフケアを再開してください。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
D’SOUZA, Raina, et al. Enhancing facial aesthetics with muscle retraining exercises-a review. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 2014, 8.8: ZE09.
DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.
VAN DER SLUIS, Nanouk, et al. Lifting the mouth corner: a systematic review of techniques, clinical outcomes, and patient satisfaction. Aesthetic Surgery Journal, 2022, 42.8: 833-841.
HWANG, Ui-jae, et al. Effect of a facial muscle exercise device on facial rejuvenation. Aesthetic surgery journal, 2018, 38.5: 463-476.
SABRI, Roy. The eight components of a balanced smile. J Clin Orthod, 2005, 39.3: 155-67.
SERNA, Eduardo Morera, et al. Anatomy and aging of the perioral region. Facial Plastic Surgery, 2021, 37.02: 176-193.
VAN BORSEL, John, et al. The effectiveness of facial exercises for facial rejuvenation: a systematic review. Aesthetic surgery journal, 2014, 34.1: 22-27.
ABE, Takashi; LOENNEKE, Jeremy P. The influence of facial muscle training on the facial soft tissue profile: a brief review. Cosmetics, 2019, 6.3: 50.