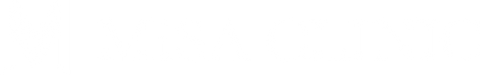顎のたるみ撃退トレーニング|効果的なエクササイズで二重顎も解消!

鏡を見るたびに気になる顎のたるみやシャープさに欠けるフェイスラインを、年齢のせいだと諦めてしまう方もいるようです。
実は、顎のたるみは加齢だけでなく、日常の些細な習慣が原因で進行します。しかし、正しいトレーニングと生活習慣の見直しで、フェイスラインは大きく変わる可能性があります。
この記事では、顎のたるみがなぜ起こるのかという根本的な原因から、ご自宅で今日から始められる効果的なエクササイズ、さらにはトレーニング効果をより高める秘訣まで、専門的な視点から詳しく解説します。
なぜ顎がたるむのか?その原因を徹底解説
顎のたるみは、加齢による筋力低下や悪い姿勢、急激な体重変動など、複数の要因が絡み合って発生します。
まずはご自身の原因を知ることが、効果的な対策の第一歩です。生活習慣を見直すきっかけにしましょう。
加齢による筋力低下と肌の弾力損失
顔には多くの表情筋があり、これらが皮膚や脂肪を支えています。しかし、年齢とともにこれらの筋肉は自然と衰えていきます。
特に、顎から首にかけて広がる広頚筋(こうけいきん)や、舌を支える舌骨筋群(ぜっこつきんぐん)の筋力が低下すると重力に逆らえなくなり、皮膚や脂肪が垂れ下がってたるみとなります。
また、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンも加齢によって減少し、皮膚自体の支持力も弱まってたるみを加速させます。
姿勢の悪さが引き起こす首と顎への負担
長時間スマートフォンを操作したり、デスクワークで猫背になったりする姿勢は、顎のたるみを引き起こす大きな原因です。
頭は体重の約10%もの重さがあり、首が前に傾くほど首や肩への負担が増大します。この状態が続くと首周りの血行が悪化し、老廃物が溜まりやすくなります。
結果としてむくみが生じ、フェイスラインがぼやけて見えるだけでなく、顎周りの筋肉が正しく使われずに衰え、たるみにつながるのです。
姿勢とたるみの関係
| 姿勢のタイプ | 顎への影響 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 猫背・ストレートネック | 首の筋肉が緊張し、顎周りの血流が悪化する。広頚筋が緩む。 | 背筋を伸ばし、耳・肩・腰が一直線になるよう意識する。 |
| 頬杖をつく癖 | 片側の顎に圧力がかかり、顔の歪みとたるみの原因になる。 | 意識的に頬杖をやめ、両手で顔を包むようにする。 |
| うつ伏せ寝 | 長時間、顔に圧力がかかり、シワやたるみを誘発する。 | 仰向けで寝るように心がける。枕の高さを調整する。 |
急激な体重の増減と皮膚の伸縮
体重が増加すると顎の下にも脂肪が蓄積され、二重顎の原因となります。
逆に、短期間で急激にダイエットを行うと脂肪が減少したスペースに皮膚が追いつけず、皮膚が余ってたるんでしまうケースがあります。
風船が一度膨らむとしぼんでも元に戻りにくいのと同じで、皮膚も伸び縮みを繰り返すと弾力を失いやすくなります。体重管理は、たるみ予防の観点からも緩やかに行う工夫が重要です。
顎のたるみによる見た目と印象への影響
顎のたるみは、単にフェイスラインがぼやけるだけでなく、顔全体の印象を大きく左右します。
自分では気づかないうちに、実年齢よりも老けて見えたり、不機嫌そうな印象を与えたりしているかもしれません。
フェイスラインの崩れと二重顎
顎のたるみの最も分かりやすい影響は、フェイスラインが不鮮明になることです。顎と首の境界線が曖昧になり、顔が大きく見えてしまいます。
さらにたるみが進行すると顎の下に脂肪や皮膚が溜まり、二重顎となって現れます。その結果、横顔のシルエットが崩れ、スマートな印象が失われます。
ほうれい線やマリオネットラインの強調
顔の皮膚は一枚でつながっているため、顎周りのたるみは頬のたるみも引き起こします。
頬の位置が下がると、その下にあるほうれい線(鼻の両脇から口角にかけての線)やマリオネットライン(口角から顎にかけての線)がより深く、長く見えるようになります。
これらの線が目立つと、一気に老けた印象や疲れた印象が強まります。
たるみが強調する顔の影
| 線の名称 | 位置 | 与える印象 |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 鼻の両脇から口角 | 老けた印象、疲れた印象 |
| ゴルゴライン | 目頭から頬の中央 | 疲れた印象、厳しい印象 |
| マリオネットライン | 口角から顎 | 不機嫌な印象、老けた印象 |
実年齢より老けて見える「老け顔」
フェイスラインの崩れ、ほうれい線やマリオネットラインの深化は、総合的に「老け顔」の印象を作り出します。
顔の下半分にボリュームが移動するため、若々しい印象の逆三角形の輪郭が加齢を感じさせる四角形やベース型の輪郭に変化します。
このため、実際の年齢よりも上に見られてしまう方が多くなります。
トレーニングを始める前に知っておきたい基礎知識
トレーニングの効果を最大限に引き出すには、鍛えるべき筋肉を理解し、適切な頻度と時間を守ることが大切です。
やみくもに始めるのではなく、まず基本的な知識を身につけて準備を整えましょう。
鍛えるべき筋肉はどこか
顎のたるみ解消には、顔の表面だけでなく、深層にある筋肉を意識することが重要です。
特に重要なのが、口周りの「口輪筋(こうりんきん)」、舌を支え顎のラインを形成する「舌骨筋群」、そして首の前面を覆う薄い「広頚筋」です。
これらの筋肉をターゲットにトレーニングすると、内側からしっかりと皮膚と脂肪を支え、たるみを引き上げます。
ターゲットとなる主要な筋肉
| 筋肉名 | 役割 | 衰えるとどうなるか |
|---|---|---|
| 広頚筋 | 口角を下に引き、首の皮膚を緊張させる | 首の横ジワや顎のたるみにつながる |
| 舌骨筋群 | 舌を支え、飲み込む動作に関わる | 二重顎やフェイスラインの崩れの原因になる |
| 口輪筋 | 口を閉じたり、唇を動かしたりする | 口角が下がり、ほうれい線が目立ちやすくなる |
トレーニングの適切な頻度と時間
顔の筋肉も体の筋肉と同じで、毎日少しずつ継続すると効果的です。一度に長時間行うよりも、1日数分でも毎日続けるようにしましょう。
まずは1日5分程度から始め、慣れてきたら10分程度に延ばすのがおすすめです。朝のスキンケアのついでや、夜のリラックスタイムなど、生活の中に組み込むと習慣化しやすくなります。
効果を実感できるまでの期間の目安
トレーニングの効果はすぐには現れません。個人差はありますが、多くの場合、毎日継続して1〜2ヶ月ほどでフェイスラインに変化を感じ始める方が多いようです。
目に見える変化がなくても、筋肉は着実に鍛えられています。焦らずに、長期的な視点でじっくりと取り組む姿勢が大切です。
自宅で簡単!顎のたるみ撃退エクササイズ
顎のたるみは、特別な道具を使わずに自宅で簡単にできるエクササイズで改善を目指せます。
舌や首、口元の筋肉を鍛えると、すっきりしたフェイスラインに近づきます。無理のない範囲で、正しいフォームを意識して行いましょう。
舌を使ったインナーマッスルトレーニング
顎下のインナーマッスルである舌骨筋群を直接鍛えるエクササイズです。二重顎の解消に特に効果的です。
- 舌回しエクササイズ
- 舌先で鼻を触るエクササイズ
- 「あいうえお」発声トレーニング
まず「舌回しエクササイズ」です。口を閉じたまま、舌先で歯茎の外側をなぞるように、右回りに20回、左回りに20回、ゆっくりと大きく回します。
次に「舌先で鼻を触るエクササイズ」です。真上を向き、舌をできるだけ上(鼻先方向)に伸ばし、10秒間キープします。これを3セット行います。
最後に「あいうえお」と一音ずつ口を大きく動かしながらはっきりと発声するトレーニングも、顔全体の筋肉を動かすのに有効です。
広頚筋を伸ばす首のストレッチ
首の前面にある広頚筋をストレッチすると首のシワを防ぎ、フェイスラインをすっきりと見せられます。
首のストレッチ手順
| 手順 | ポイント | 秒数・回数 |
|---|---|---|
| 1. 姿勢を正す | 椅子に座るか、立った状態で背筋を伸ばす | – |
| 2. ゆっくり上を向く | 顎を天井に突き出すように首の前側を伸ばす | 10秒キープ |
| 3. 口を「いー」の形にする | 首の筋が伸びているのを意識しながら行う | 10秒キープ |
この一連の動作を3〜5セット繰り返します。首を痛めないよう、ゆっくりとした動作を心がけてください。
口輪筋を鍛える口元エクササイズ
口周りの筋肉、口輪筋を鍛えると口角が引き締まり、ほうれい線やマリオネットラインの改善につながります。
ペットボトルを使ったトレーニングが効果的です。500mlの空のペットボトルを用意し、少量の水を入れます。
これを唇だけでくわえ、歯を使わずに10秒間持ち上げます。3セット行いますが、水の量を調整すれば負荷を変えられます。
また、口を大きく開けて「お」の形を作り、そのまま口角をぐっと引き上げるエクササイズもおすすめです。
トレーニング効果を高める日常生活の習慣
トレーニング効果を高めるには、よく噛んで食べる、正しい姿勢を意識する、紫外線対策と保湿を徹底する、といった取り組みが重要です。
エクササイズと並行して日々の習慣を見直すと、たるみの改善効果が格段に高まります。
咀嚼の重要性|よく噛んで食べる
食事の際によく噛むことは、顎周りの筋肉を自然に鍛える最も簡単なトレーニングです。一口につき30回程度噛むように意識しましょう。
左右の歯で均等に噛むのも大切です。ガムを噛む習慣を取り入れるのも良い方法ですが、片側だけで噛む癖がつかないように注意が必要です。
正しい姿勢を常に意識する
前述の通り、姿勢はフェイスラインに大きな影響を与えます。特にデスクワーク中はパソコンのモニターを目線の高さに合わせ、椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばすように心がけましょう。
スマートフォンを見るときは顔の高さまで持ち上げて操作すると、首への負担を軽減できます。
生活習慣チェック
| 項目 | 良い習慣 | 悪い習慣 |
|---|---|---|
| 食事 | 一口30回、左右均等に噛む | 早食い、片側だけで噛む |
| スマホ操作 | 顔の高さで見る | 下を向いて長時間操作する |
| 睡眠 | 仰向けで寝る、自分に合った枕を使う | うつ伏せ寝、高すぎる枕 |
紫外線対策と保湿ケア
肌の弾力を保つためには、スキンケアも重要です。
紫外線はコラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の老化を促進する最大の要因の一つです。季節を問わず日焼け止めを塗り、紫外線対策を徹底しましょう。
また、肌が乾燥するとハリが失われ、たるみが目立ちやすくなります。化粧水や乳液、クリームなどで十分に保湿し、肌のバリア機能を保つケアが大切です。
トレーニングの注意点と効果の限界
セルフケアのトレーニングは有効ですが、やりすぎるとシワの原因になるなど注意が必要です。
また、骨格や脂肪の量が原因のたるみには限界があります。安全かつ効果的に続けるために、注意点と限界を理解しておきましょう。
やりすぎは逆効果?シワの原因にも
早く効果を出したいからと、力を入れすぎたり、長時間やりすぎたりするのは禁物です。
特に、皮膚を強くこすったり引っ張ったりするようなマッサージは、皮膚を支える線維を傷つけ、かえってたるみやシワを悪化させる原因になります。
エクササイズは、筋肉に働きかけるものであり、皮膚を動かすものではないと心得ましょう。
トレーニング時の注意点
- 必ず清潔な手で行う
- 肌の滑りが悪いときはクリームやオイルを使用する
- 痛みを感じたらすぐに中止する
- 鏡を見ながら正しいフォームを確認する
骨格や脂肪の多さが原因の場合
トレーニングで鍛えられるのは筋肉です。そのため、たるみの原因が骨格の形や、蓄積された脂肪の量が大きい場合には、トレーニングだけで理想のフェイスラインを手に入れるのは難しい場合があります。
例えば、もともと顎が小さい方や、脂肪層が厚い方は、筋肉を引き締めても見た目の変化が限定的になる可能性があります。
セルフケアで改善しない場合の選択肢
数ヶ月間トレーニングを継続しても思うような効果が得られない場合や、より確実で早い効果を望む場合は、セルフケアの限界かもしれません。
そのようなときは、一人で悩まずに専門のクリニックに相談するのも一つの有効な選択肢です。専門家の視点から、あなたのたるみの原因を正確に診断し、適した治療法を提案できます。
美容クリニックでできる顎のたるみ専門治療
セルフケアで改善が難しい顎のたるみには、美容クリニックでの専門治療が有効です。
HIFU(ハイフ)などの医療機器や、脂肪溶解注射、糸リフトといった方法で、より根本的な改善を目指します。
高周波(RF)や高密度焦点式超音波(HIFU)
HIFU(ハイフ)は、超音波を皮膚の深層にあるSMAS筋膜という層に集中的に照射し、熱エネルギーで組織を収縮させる治療です。メスを使わずに、内側からたるみを引き上げられます。
一方、高周波(RF)は皮膚の真皮層に熱を加え、コラーゲンの生成を促進して肌のハリを高め、たるみを改善します。
どちらもダウンタイムがほとんどないため、人気の高い治療法です。
HIFUと高周波の比較
| 治療法 | アプローチする層 | 主な効果 |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | SMAS筋膜(深い層) | リフトアップ、引き締め |
| 高周波(RF) | 真皮層(浅い層) | 肌のハリ・弾力アップ、引き締め |
脂肪溶解注射による部分痩せ
顎下の脂肪がたるみの主な原因である場合、脂肪溶解注射が有効です。脂肪を溶かす成分を直接注入して、気になる部分の脂肪細胞を減らします。
手術に抵抗がある方でも受けやすく、二重顎の解消効果を実感しやすいです。
ヒアルロン酸や糸リフトによる形成
たるみによって失われたボリュームを補ったり、物理的に皮膚を引き上げたりする治療法もあります。
ヒアルロン酸を顎のラインに注入すれば、シャープな輪郭を形成できます。糸リフト(スレッドリフト)は医療用の溶ける糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚を直接引き上げる治療法です。
どちらも即時的な効果を実感しやすいのが特徴です。
顎のたるみ撃退トレーニングに関するよくある質問
顎のたるみが気になっている方は意外と多いですが、舌や首、口元の筋肉を鍛えるトレーニングを行うと改善効果が期待できます。
ただし、セルフケアにはどうしても限界がありますので、トレーニングを行っても納得できるほどの効果を得られないときや、より積極的に顎のたるみを解消したいときは、美容医療を検討すると良いでしょう。
- トレーニングはどのくらいの頻度で行えばよいですか?
-
毎日続けるのが理想です。まずは1日5分からでも構いませんので、毎日の習慣にするように目指しましょう。筋肉は継続的な刺激によって強化されます。
ただし、筋肉痛がひどい場合は無理をせず、1日休むなど調整してください。
- 効果はどのくらいで実感できますか?
-
効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には毎日継続して1ヶ月から2ヶ月ほどで、フェイスラインがすっきりしてきた、顎周りが動かしやすくなったなどの変化を感じる方が多いです。
すぐに結果が出なくても諦めず、最低3ヶ月は続けてみましょう。
- トレーニング中に痛みを感じた場合はどうすればよいですか?
-
すぐに中止してください。痛みは、無理な力がかかっているか、フォームが間違っているサインです。
特に顎関節や首に痛みを感じる場合は、顎関節症などの他の問題が隠れている可能性もあります。痛みが続くようであれば、専門の医療機関にご相談ください。
- トレーニングとマッサージはどちらが効果的ですか?
-
目的が異なりますが、たるみの根本改善にはトレーニングがより重要です。
トレーニングは筋肉を内側から鍛えて土台を強化するのに対し、マッサージは主に血行促進やむくみ解消といった外側からの働きかけです。
両方を組み合わせるのが理想ですが、たるみそのものを引き上げるには、筋肉を鍛えるトレーニングを優先しましょう。
参考文献
DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.
HAMMAD, Gamal, et al. Assessment of Double Chin with Exercises and Mesotherapy. Benha Journal of Applied Sciences, 2023, 8.12: 31-37.
LIM, Hyoung Won. Effects of facial exercise for facial muscle strengthening and rejuvenation: systematic review. The Journal of Korean Physical Therapy, 2021, 33.6: 297-303.
VERMA, Kritin K., et al. Facial Contouring Through Jaw Exercises: A Report of Two Cases Examining Efficacy and Consumer Expectations. Cureus, 2024, 16.11.
ARORA, Gulhima; SHIROLIKAR, Manasi. Tackling submental fat–A review of management strategies. Cosmoderma, 2023, 3.
FARRIOR, Edward; EISLER, Lindsay; WRIGHT, Harry V. Techniques for rejuvenation of the neck platysma. Facial Plastic Surgery Clinics, 2014, 22.2: 243-252.
CHARAFEDDINE, Ali H.; COUTO, Rafael A.; ZINS, James E. Neck rejuvenation: anatomy and technique. Clinics in plastic surgery, 2019, 46.4: 573-586.
RUIZ, Robin, et al. Facelifts: Improving the long-term outcomes of lower face and neck rejuvenation surgery: The lower face and neck rejuvenation combined method. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2018, 46.4: 697-704.