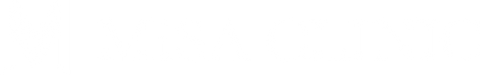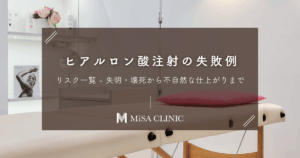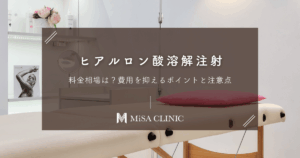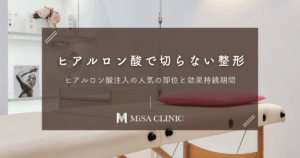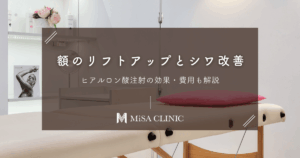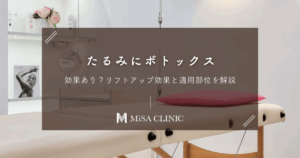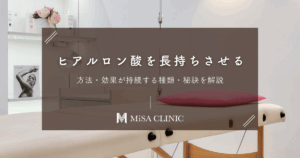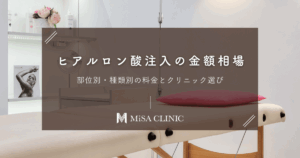ヒアルロン酸の種類と特徴|医師が教える失敗しない選び方のコツ

「ほうれい線が深くなってきた」「顔のたるみで疲れて見える」と相談にいらっしゃる方が多いです。
そのようなお悩みに対し、美容皮膚科ではヒアルロン酸注入という治療法を提案する場合があります。
しかし一言でヒアルロン酸といっても、実は多くの種類が存在し、それぞれに特徴があります。そのため、どの製剤を選べば良いのか分からず、治療をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、医師の視点からヒアルロン酸の種類ごとの特徴や、たるみ治療で失敗しないための選び方のコツを詳しく解説します。
ヒアルロン酸注入とは
たるみ治療を考える上で、ヒアルロン酸注入は広く知られた選択肢の一つです。その人気の背景には、ヒアルロン酸という成分が持つ特性が関係しています。
まずは、なぜヒアルロン酸が美容医療で重宝されるのか、その基本的な理由から見ていきましょう。
ヒアルロン酸がたるみ治療に使われる理由
ヒアルロン酸は、もともと私たちの皮膚や関節、眼球などに存在するゼリー状の物質です。非常に高い保水力を持ち、1グラムで約6リットル(6000倍)もの水分を抱え込むことができると言われています。
皮膚においては真皮層に存在し、コラーゲンやエラスチンといった弾力線維の隙間を埋めて、肌のハリや潤いを保つ役割を担っています。
しかし、このヒアルロン酸は年齢とともに減少し、その結果として肌は水分を失い、シワやたるみといったエイジングサインが現れるのです。
ヒアルロン酸注入治療は失われたボリュームを物理的に補い、内側から肌を持ち上げることで、シワやたるみを目立たなくさせる治療法です。
体内にも存在する安全性の高い成分
美容医療で用いるヒアルロン酸製剤は、アレルギー反応のリスクが低い、安全性の高い成分です。
これは、製剤の主成分がもともと体内に存在するヒアルロン酸と同じ構造を持つためです。
非動物由来の原料をバイオテクノロジーによって生成するため、感染症などのリスクも極めて低いと考えられています。
もちろんどのような医療行為にもリスクは伴いますが、ヒアルロン酸は人体への親和性が高く、広く受け入れられている成分と言えるでしょう。
時間とともに吸収される可逆的な治療
注入されたヒアルロン酸は、永久に残り続けるわけではありません。個人差や製剤の種類にもよりますが、数ヶ月から2年程度かけて体内の酵素によって徐々に分解・吸収されます。
これは一見デメリットに思えるかもしれませんが、「元に戻せる」という大きなメリットでもあります。
万が一、仕上がりが気に入らなかった場合でも、時間とともに元に戻る安心感があります。
さらに、ヒアルロン酸分解酵素(ヒアルロニダーゼ)という薬剤を注入すると、意図的に分解・除去することも可能です。
この可逆性が、初めて美容医療を受ける方にとっても、心理的なハードルを下げる一因となっています。
ヒアルロン酸製剤の「硬さ」と「構造」が効果を左右する
ヒアルロン酸注入で満足のいく結果を得るためには、製剤の特性を理解することが重要です。
特に「硬さ」と「構造」は、仕上がりの自然さや持続期間に大きく影響します。
なぜヒアルロン酸に種類があるのか
顔の皮膚は、部位によって厚みや動きが全く異なります。
例えば、頻繁に動く口元と、あまり動かない額やこめかみでは、皮膚の下の組織構造も違います。もし、すべての部位に同じ種類のヒアルロン酸を注入したらどうなるでしょうか。
柔らかい皮膚の部位に硬い製剤を注入すると、しこりのように感じたり、表情が不自然になったりする可能性があります。
逆に、しっかりと形を作りたい顎や鼻に柔らかい製剤を使っても効果が乏しく、すぐに吸収されてしまうでしょう。
このように、治療する部位や目指す仕上がりに合わせて適した効果を発揮するために、硬さや構造が異なる多様なヒアルロン酸製剤が開発されているのです。
硬さ(G’:ジーダッシュ)の違いと使い分け
ヒアルロン酸製剤の物理的な特性を示す指標の一つに「G’(ジーダッシュ)」があります。これは弾性率を表し、簡単に言えば「製剤の硬さ」を示す数値です。
G’が高いほど硬く変形しにくい性質を持ち、G’が低いほど柔らかくなじみやすい性質を持ちます。
医師はこのG’を参考に、注入部位や皮膚の深さに応じて製剤を使い分けます。
硬い製剤は、骨格を補強するように深く注入してリフトアップの土台を作ったり、鼻筋や顎のラインをシャープに形成したりするのに適しています。
一方、柔らかい製剤は、皮膚の浅い層にある細かなシワや、涙袋のような繊細な部位の形成に使用します。
G’(弾性率)による製剤の使い分け
| G’(硬さ) | 主な特徴 | 適した使用部位 |
|---|---|---|
| 高い(硬い) | 形状を維持する力が強い。リフトアップ力に優れる。 | こめかみ、頬、顎、鼻筋 |
| 中間 | 適度なボリュームと形成力を持つ。 | ほうれい線、ゴルゴライン、マリオネットライン |
| 低い(柔らかい) | 皮膚になじみやすく、自然な仕上がり。 | 目の下のくま、涙袋、唇、額の細かいシワ |
単相と二相|構造の違いを理解する
ヒアルロン酸製剤は、その製造方法によって「単相(たんそう)」と「二相(にそう)」の2つのタイプに大別されます。これは製剤の内部構造の違いであり、仕上がりの質感や注入のしやすさに関わってきます。
単相のヒアルロン酸は、全体が均一なゲル状になっているのが特徴です。
そのため、注入時に滑らかで、組織になじみやすく、凹凸ができにくいという利点があります。自然なボリュームアップや、なめらかな仕上がりを求める場合に適しています。
一方、二相のヒアルロン酸は、ジェル状のヒアルロン酸の中に粒子状のヒアルロン酸が混ざっている構造です。
この粒子が支柱のような役割を果たすため、形をしっかりと作ったり、リフトアップしたりする力に優れています。
どちらが良いというわけではなく、これもまた目的によって使い分けます。
単相・二相ヒアルロン酸の特徴
| タイプ | 構造 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 単相 | 均一なゲル状 | 滑らかで組織になじみやすい。自然な仕上がり。 |
| 二相 | ジェルと粒子の混合 | 形成力・リフトアップ力が高い。持続性に優れる傾向。 |
架橋技術が持続期間と仕上がりを決める
体内に存在するヒアルロン酸は、数日で分解されてしまいます。そのため、美容医療で用いる製剤は、効果を長持ちさせるために「架橋(かきょう)」という化学的な処理を施しています。
これは、ヒアルロン酸の分子同士を結びつけて、分解されにくい構造にする技術です。
架橋に使われる薬剤(架橋剤)の種類や、架橋の仕方によって、製剤の持続期間や硬さ、なじみやすさが決まります。
近年では、少ない架橋剤で効率的に分子を結びつけ、持続性を高めながらも、より体になじみやすい自然な構造を持つ製剤が開発されています。
この架橋技術の進歩がヒアルロン酸注入治療の質を大きく向上させているのです。
【目的別】代表的なヒアルロン酸の種類と特徴
ここでは、患者さんのお悩みやご希望に対して、どのような種類のヒアルロン酸が一般的に用いられるかをご紹介します。
実際の治療では、医師が診察の上で適した製剤を選択しますが、ご自身の希望を伝える際の参考にしてください。
ほうれい線やマリオネットラインを自然に改善したい
多くの方が悩むほうれい線やマリオネットラインには、ある程度の硬さがありながらも、表情の動きに合わせて自然になじむ中程度の硬さのヒアルロン酸が適しています。
これらのシワは単に溝ができただけでなく、頬のたるみが原因となっているケースが多いためです。
溝を直接埋めるだけでなく、頬の高い位置をリフトアップするような注入法と組み合わせると、より自然で効果的な改善が期待できます。
使用する製剤としては、適度なリフト力と柔軟性を両立したものが選ばれます。
額やこめかみのボリュームアップで若々しく
年齢とともに額は平坦になり、こめかみは痩せて凹んできます。この変化は、顔全体に疲れた印象や老けた印象を与えます。
これらの部位には滑らかでなじみやすい、比較的柔らかいヒアルロン酸を用いて、丸みのある自然なボリュームを回復させます。
特に額は皮膚が薄く、注入後に凹凸が目立ちやすい部位でもあるため、均一に広がる性質を持つ製剤が重要です。
こめかみの凹みを補うと顔の輪郭が整い、リフトアップ効果も得られます。
シャープな輪郭・顎を形成したい
フェイスラインをすっきりと見せたい、あるいはシャープな顎のラインを作りたいというご希望には、形成力に優れた硬いヒアルロン酸(高G’の製剤)が用いられます。
これらの製剤は注入した場所でしっかりと形を保つ力が強いため、骨格を補うように注入すると、理想の輪郭をデザインできます。
顎先に注入してEラインを整えたり、フェイスラインのもたつきを改善したりする治療で効果を発揮しやすい硬さです。リフトアップの土台としても重要な役割を果たします。
お悩みと適したヒアルロン酸の硬さ
| お悩み・目的 | 適したヒアルロン酸の硬さ | 期待される効果 |
|---|---|---|
| ほうれい線・マリオネットライン | 中間 | シワの改善、自然なリフトアップ |
| 額・こめかみのボリュームアップ | 柔らかい~中間 | 丸みのある若々しい印象、輪郭の改善 |
| 輪郭・顎の形成 | 硬い | シャープなフェイスライン、Eラインの形成 |
涙袋や唇の繊細なデザイン
涙袋や唇は、非常にデリケートで動きの多い部位です。そのため、粒子感がなく、極めて滑らかで柔らかいヒアルロン酸が選ばれます。
これらの部位に硬い製剤を使用すると、不自然な膨らみやしこりの原因となります。特に唇は、自然な柔らかさと潤いを表現することが重要です。
繊細なデザインが求められるため、医師の技術力とともに、部位に適した製剤選びが仕上がりを大きく左右します。
国内で承認されているヒアルロン酸製剤
日本国内でヒアルロン酸注入を行う際、その製剤が厚生労働省の承認を得ているかどうかは、安全性と品質を判断する上での一つの重要な基準となります。
承認品と未承認品の違いについて理解を深めましょう。
厚生労働省承認品を選ぶメリット
厚生労働省から製造販売承認を得ている医療機器は、有効性と安全性に関する厳しい審査基準をクリアしていることを意味します。
日本人のデータに基づいた臨床試験が行われ、その品質が国によって保証されています。
- 品質、有効性、安全性が国によって審査されている
- 副作用などの健康被害が生じた場合に公的な救済制度の対象となる可能性がある
- 厳格な品質管理のもとで製造・保管・輸送されている
未承認品が必ずしも危険というわけではありませんが、承認品は患者さんが安心して治療を受けるための、一つの明確な指標と言えるでしょう。
ジュビダームビスタ®シリーズ
アラガン・ジャパン社が提供するジュビダームビスタ®シリーズは、国内で初めて厚生労働省の承認を受けたヒアルロン酸製剤です。
独自の「バイクロス技術」により滑らかで体になじみやすく、かつ持続性が高いのが特徴です。
様々な硬さや特性を持つ製品がラインナップされており、顔のあらゆる部位の治療に対応できます。
ジュビダームビスタ®シリーズの主な種類と特徴
| 製品名 | 硬さ・特徴 | 主な使用部位 |
|---|---|---|
| ボリューマ XC | 硬く、形成力・リフト力に優れる | こめかみ、頬、顎など(リフトアップ) |
| ボリフト XC | 柔らかく、なじみやすい | ほうれい線、マリオネットライン、額 |
| ボルベラ XC | 非常に柔らかく、繊細な部位に適する | 涙袋、唇、目の周りの細かいシワ |
レスチレン®シリーズ
ガルデルマ社が提供するレスチレン®シリーズも世界中で長い使用実績を持つ、信頼性の高いヒアルロン酸製剤です。
こちらは「NASHA(ナーシャ)テクノロジー」という技術が特徴で、ヒアルロン酸の粒子をしっかり作り、リフト力や形成力に優れています。
近年では、より柔軟性を持たせた「OBT(オービーティー)テクノロジー」を用いた製品も登場し、治療の選択肢が広がっています。
レスチレン®シリーズの主な種類と特徴
| 製品名 | 技術・特徴 | 主な使用部位 |
|---|---|---|
| レスチレン® リフト™ リド | NASHA技術。高いリフト力。 | 頬、ほうれい線、ゴルゴライン |
| レスチレン® リド | NASHA技術。標準的な硬さ。 | ほうれい線、眉間のシワ |
| レスチレン® ヴォリューム™ リド | OBT技術。柔軟性とボリューム。 | こめかみ、頬 |
その他の承認品と特徴
上記の2大ブランド以外にも、国内で承認されているヒアルロン酸製剤は存在します。それぞれに独自の技術や特徴があり、クリニックによって採用している製剤は異なります。
カウンセリングの際には、どのような製剤を扱っているのか、そしてなぜその製剤を推奨するのか、医師に確認してみると良いでしょう。
複数の選択肢の中から、自分に合ったものを提案してくれるクリニックは信頼できると言えます。
「私の顔に合う」ヒアルロン酸は一つではない?顔全体のバランスを考える重要性
多くの患者さんは、「ほうれい線が気になる」「目の下のくまを消したい」といった、特定の一つの悩みを持ってクリニックを訪れます。
しかし、本当に満足のいく結果を得るためには、その悩みだけに焦点を当てるのではなく、顔全体の構造とバランスを理解することが極めて重要です。
気になる「シワ1本」だけを追いかけてはいけない理由
例えば、ほうれい線が深くなる原因は、単にその部分の皮膚がへこんだからだけではありません。
多くの場合は上にある頬の脂肪が年齢とともに下垂し、ほうれい線の上にかぶさってくるために、影が深く見えるようになります。
この状態でほうれい線の溝だけをヒアルロン酸で埋めようとするとどうなるでしょうか。一時的にシワは浅くなるかもしれませんが、顔の下半分が重たい印象になり、不自然な「パンパンな顔」に見えてしまうケースがあります。
これは、問題の根本原因に対処していないからです。悩みの原因が、実は別の場所にあるというケースは非常に多いです。
顔の土台を支える「リフトアップポイント」への注入
顔には、建物の柱のように骨格を支えている「リガメント(靭帯)」が存在します。
このリガメントが加齢により緩むと、その上にある脂肪や皮膚を支えきれなくなり、顔全体のたるみにつながります。
経験豊富な医師は、この解剖学的な構造を深く理解しています。そして、たるみの根本原因である緩んだリガメントの周辺や、痩せてしまった骨格を補うように、硬めのヒアルロン酸を深く注入します。
この「リフトアップポイント」に注入すると、顔全体の土台が再構築され、自然なリフトアップ効果が生まれます。
その結果として、気になっていたほうれい線やフェイスラインのもたつきが、シワを直接埋めることなく改善されるのです。
複数の製剤を組み合わせるオーダーメイド治療
顔全体のバランスを整えるためには、一種類のヒアルロン酸だけでは不十分なケースがほとんどです。
- 土台を支えるリフトアップポイントには、硬い製剤
- 頬や額のボリュームを補うには、中間的な硬さの製剤
- 皮膚表面の細かいシワや唇には、柔らかい製剤
このように、部位と目的に応じて硬さや構造の異なる複数の製剤を的確に使い分けることで、初めて立体的で自然な、その人本来の美しさを引き出すオーダーメイド治療が可能になります。
これは、画家が様々な種類の絵の具を使い分けて一枚の絵を完成させるのに似ています。
医師とのゴール共有が成功の鍵
だからこそ、カウンセリングが非常に重要になります。
「どのシワが気になるか」だけでなく、「どのような印象に見られたいか」「若々しく元気に見せたいのか、それとも優しく見せたいのか」といった、ご自身のなりたいイメージ(ゴール)を医師としっかり共有してください。
信頼できる医師は悩みの根本原因を突き止め、顔全体のバランスを見ながら、ゴールを達成するための注入計画を複数の選択肢とともに提案してくれるはずです。
単に「ほうれい線に1本打ちましょう」という提案で終わらない医師こそ、パートナーとしてふさわしいと言えるでしょう。
ヒアルロン酸注入の費用相場と持続期間
治療を受ける上で、費用と効果の持続期間は誰もが気になる点です。これらは使用する製剤の種類や注入量によって変動します。ここでは、一般的な目安について解説します。
製剤の種類による価格の違い
ヒアルロン酸の価格は、製剤の種類によって異なります。
一般的に、新しい技術を用いて開発された、持続期間が長い製剤や、特殊な効果を持つ製剤ほど高価になる傾向があります。
また、厚生労働省の承認品は厳格な品質管理や安全性試験にコストがかかるため、未承認品に比べて価格が高めに設定されているものが多いです。
しかし、これは安全性や品質に対する投資と考えられます。
注入量(cc)と部位ごとの費用目安
費用は、使用するヒアルロン酸の量(ccまたはml)によって決まります。必要な量は、治療部位やたるみの程度、目指す仕上がりによって大きく異なります。
以下はあくまで一般的な目安ですが、参考にしてください。
部位別の注入量と費用目安
| 部位 | 注入量の目安(両側) | 費用相場(1ccあたり6万円~10万円の場合) |
|---|---|---|
| ほうれい線 | 1~2cc | 6万円~20万円 |
| 顎の形成 | 1~2cc | 6万円~20万円 |
| 頬・こめかみ | 2~4cc | 12万円~40万円 |
正確な費用は、必ずカウンセリングで確認しましょう。
効果はいつまで?持続期間の目安
ヒアルロン酸の効果の持続期間は、製剤の種類や注入部位、そして個人の体質(代謝の速さなど)によって変わります。
一般的に、硬くて架橋密度が高い製剤ほど長持ちし、柔らかい製剤ほど早く吸収されます。
また、よく動かす口元や唇などは、あまり動かさない部位に比べて持続期間が短くなる傾向があります。
製剤の種類と持続期間の目安
| 製剤の硬さ | 主な使用部位 | 持続期間の目安 |
|---|---|---|
| 硬い製剤 | 顎、頬、こめかみ | 約1年~2年 |
| 中間の製剤 | ほうれい線、ゴルゴライン | 約9ヶ月~1年半 |
| 柔らかい製剤 | 涙袋、唇、目の周り | 約6ヶ月~1年 |
失敗しないためのクリニック・医師選びのコツ
ヒアルロン酸注入は、どの製剤を選ぶかと同じくらい、誰に注入してもらうかが重要です。
満足のいく結果を得るために、クリニックや医師を選ぶ際のポイントを押さえておきましょう。
解剖学を熟知した医師を選ぶ
顔には、重要な血管や神経が複雑に走行しています。
これらの構造を無視して注入を行うと、血管閉塞による皮膚壊死や失明といった、重大な合併症を引き起こすリスクがあります。
顔の解剖学を深く理解し、安全な層に正確に注入できる知識と技術を持った医師を選ぶことが、安全な治療の第一歩です。
医師の経歴や資格(形成外科専門医など)も一つの参考になります。
カウンセリングで丁寧になりたい姿を聞いてくれるか
良いカウンセリングは、一方的な説明で終わるものではありません。
悩みやコンプレックスに真摯に耳を傾け、どのような自分になりたいのかというゴールを一緒に探ってくれるはずです。
その上で、治療のメリットだけでなく、デメリットやリスク、複数の治療選択肢を具体的に提示してくれる医師は信頼できます。
時間をかけて丁寧にコミュニケーションをとってくれるかどうかを見極めましょう。
複数の製剤を取り扱っているか
前述の通り、顔全体のバランスを整えるためには、複数の種類のヒアルロン酸を使い分けるのが理想的です。
取り扱っている製剤の種類が少ないと、そのクリニックにあるもので対応するしかなく、自分にとって最も良い治療が受けられない可能性があります。
様々な硬さや特性を持つ製剤を複数取り揃えているクリニックは、患者さん一人ひとりの状態に合わせて適した提案ができる体制が整っていると言えるでしょう。
医師・クリニック選びのチェックポイント
- 顔の解剖学に関する知識が豊富か
- カウンセリングの時間は十分で、話を聞く姿勢があるか
- メリットだけでなくリスクや代替案の説明があるか
- 複数の種類のヒアルロン酸製剤を取り扱っているか
- 万が一のトラブル(アレルギー、血管閉塞など)への対応策が明示されているか
万が一のトラブルへの対応体制
どんなに熟練した医師が慎重に治療を行っても、医療に絶対はありません。アレルギー反応や感染、血管閉塞などの合併症が起こる可能性もあります。
そのような万が一の事態に備えて、クリニックがどのような対応をしてくれるのかを事前に確認しておくことは非常に重要です。
ヒアルロン酸分解酵素を常備しているか、緊急時の連絡体制は整っているかなど、安全性への配慮がしっかりしているクリニックを選びましょう。
ヒアルロン酸注入に関するよくある質問
ヒアルロン酸注入には様々な種類があり、注入する部位や目指す仕上がりによって使い分けます。
メスを使わず、ヒアルロン酸を注入するだけの簡単な施術のように見えるかもしれません。
しかし、製剤選びから始まり、その人の骨格や顔全体のバランスを考えた深さと場所に、適した量を注入する必要があり、知識や経験、技術力の求められる施術です。
失敗を避けて、満足のいく仕上がりを目指すためには、信頼できるクリニックを選びましょう。
- 痛みはありますか?
-
注入時には、注射針を刺すチクッとした痛みと、製剤が入ってくる感覚があります。痛みの感じ方には個人差がありますが、多くのクリニックでは痛みを軽減するための工夫をしています。
例えば、注入部位を冷やしたり、表面麻酔のクリームを使用したりします。また、最近のヒアルロン酸製剤の多くには、麻酔成分(リドカイン)が含まれており、注入中の痛みを和らげます。
痛みが心配な方は、カウンセリング時に遠慮なく相談してください。
- ダウンタイムはどのくらいですか?
-
ヒアルロン酸注入は、ダウンタイムが比較的短い治療です。
注入直後に針を刺した部分に赤みや腫れ、内出血が出るときがありますが、これらは数日から1週間程度で自然に治まるケースがほとんどです。内出血は、メイクでカバーできる程度の場合が多いです。
大きな腫れが出ることは稀ですが、大切なイベントなどを控えている方は直前の治療は避け、2週間程度の余裕を持っておくと安心です。
- 注入後にしこりができることはありますか?
-
注入したヒアルロン酸が、しこりのように感じられることがあります。
これは、注入直後のむくみによる一時的なものである場合や、製剤がまだ組織になじんでいないために起こるケースが多いです。通常は時間とともになじんできます。
しかし、不適切な部位に硬すぎる製剤を注入したり、一度に大量に注入したりすると、しこりとして残ってしまうリスクがあります。
また、非常に稀ですが、アレルギー反応や感染によってしこりが形成されるケースもあります。気になる症状が続く場合は、すぐに治療を受けたクリニックに相談しましょう。
適切な製剤選びと、医師の正しい注入技術が、しこりのリスクを最小限にします。
- 気に入らない場合、元に戻せますか?
-
ヒアルロン酸注入の大きな利点の一つは、修正が可能であることです。
仕上がりがイメージと違った、膨らみすぎたと感じたなどの場合には、「ヒアルロニダーゼ」というヒアルロン酸を分解する酵素を注入して、元に戻したり、量を減らしたりできます。
この「やり直しができる」という安心感が、ヒアルロン酸治療が広く受け入れられている理由の一つです。
ただし、分解酵素の注射にもアレルギーなどのリスクは伴いますので、まずはそのような事態にならないよう、経験豊富な医師のもとで慎重に治療を受けるのが大前提です。
参考文献
FUNDARÒ, Salvatore Piero, et al. The rheology and physicochemical characteristics of hyaluronic acid fillers: their clinical implications. International journal of molecular sciences, 2022, 23.18: 10518.
EDSMAN, Katarina, et al. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatologic Surgery, 2012, 38.7pt2: 1170-1179.
FALCONE, Samuel J.; BERG, Richard A. Crosslinked hyaluronic acid dermal fillers: a comparison of rheological properties. Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials, 2008, 87.1: 264-271.
SALWOWSKA, Natalia M., et al. Physiochemical properties and application of hyaluronic acid: a systematic review. Journal of cosmetic dermatology, 2016, 15.4: 520-526.
MOLLIARD, S. Gavard, et al. Key rheological properties of hyaluronic acid fillers: from tissue integration to product degradation. Plast Aesthet Res, 2018, 5: 17.
MONHEIT, Gary D.; COLEMAN, Kyle M. Hyaluronic acid fillers. Dermatologic therapy, 2006, 19.3: 141-150.
RZANY, Berthold, et al. Full‐face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatologic surgery, 2012, 38.7pt2: 1153-1161.
CHOI, Won Joon, et al. The efficacy and safety of lidocaine-containing hyaluronic acid dermal filler for treatment of nasolabial folds: a multicenter, randomized clinical study. Aesthetic plastic surgery, 2015, 39: 953-962.