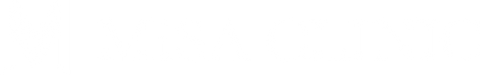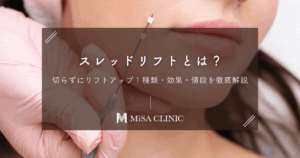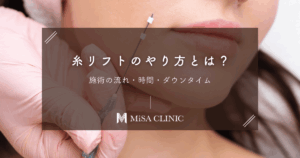糸リフトの効果はいつまで?1年後の状態と持続期間を解説

「糸リフト(スレッドリフト)の引き上げ効果は、一体いつまで続くのか」多くの方がこのような疑問をお持ちのようです。
糸リフトは切開を伴わずにたるみを改善してフェイスラインを整える人気の施術ですが、その効果の持続性について正しく理解しておくと、満足のいく結果につながります。
この記事では、糸リフトの効果持続期間の目安、施術から1年後の肌がどのような状態になるのか、そして効果をできるだけ長く保つための秘訣について、専門的な視点から詳しく解説します。
糸リフトの基本的な仕組みと効果
糸リフトは、医療用の特殊な糸を皮下組織に挿入して、たるんだ皮膚を物理的に引き上げる治療法です。
単に引き上げるだけでなく、肌の内部に働きかけて長期的な美肌効果も期待できます。
挿入する糸の種類と特徴
施術で用いる糸は、時間が経つと体内で自然に吸収される素材で作られています。
糸の種類によって、持続期間や引き上げる力、そしてコラーゲン生成を促す能力に違いがあります。
クリニックでは、一人ひとりのたるみの状態や希望する効果に応じて、これらの糸を使い分けます。
主な糸の種類と特性
| 糸の種類 | 主成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| PDO | ポリジオキサノン | 吸収が比較的早く、引き締め効果に優れる。 |
| PCL | ポリカプロラクトン | 柔軟性が高く、吸収が緩やかで持続期間が長い。 |
| PLLA | ポリ乳酸 | 硬めの素材で、強いリフトアップ力とコラーゲン生成能力を持つ。 |
たるみを引き上げる物理的な作用
糸には「コグ」と呼ばれる小さなトゲのようなものが付いています。
このコグを皮下組織に引っかけることで、たるんだ皮膚や脂肪組織を直接持ち上げ、理想の位置に固定します。
物理的な引き上げ作用により、施術直後からフェイスラインの改善やほうれい線の軽減といった視覚的な変化を感じられます。
コラーゲン生成を促す長期的な効果
挿入された糸は、皮膚の真皮層を刺激します。この刺激が創傷治癒反応を引き起こし、糸の周囲に新たなコラーゲンやエラスチンの生成を促します。
コラーゲンが増えると肌の弾力やハリが向上し、糸が吸収された後も肌質の改善効果が持続します。
この作用こそが、糸リフトが単なるリフトアップ治療にとどまらない理由です。
期待できる具体的な美容効果
糸リフトによって、さまざまな美容効果が期待できます。たるみの改善だけでなく、肌全体の若返りにもつながります。
- フェイスラインの引き締め(Vライン形成)
- ほうれい線やマリオネットラインの改善
- 頬の位置が高くなることによる若々しい印象
- 肌のハリ・ツヤ・弾力の向上
糸リフトの効果持続期間の目安
糸リフトの効果がどのくらい続くかは、多くの方が最も知りたい点の一つでしょう。
持続期間はいくつかの要因によって変動しますが、一般的な目安を確認しておきましょう。
糸の種類による持続期間の違い
効果の持続期間を左右する最も大きな要因は、使用する糸の種類です。
体内で吸収されるまでの時間が長い糸ほど、効果も長く持続する傾向にあります。
糸の吸収期間と効果持続の目安
| 糸の種類 | 吸収までの期間 | 効果持続の目安 |
|---|---|---|
| PDO | 約6ヶ月~1年 | 約1年~1年半 |
| PCL | 約2年~3年 | 約2年~3年 |
| PLLA | 約1年半~2年 | 約1年半~2年 |
これらの期間はあくまで目安です。糸が吸収された後も、生成されたコラーゲンによる引き締め効果は一定期間続きます。
個人の体質や肌の状態が与える影響
肌の質や年齢、皮下脂肪の量や生活習慣なども持続期間に影響を与えます。
例えば、新陳代謝が活発な若い方や、皮膚が薄い方は、糸の吸収が早い場合があります。
反対に、皮下脂肪が多い方は糸にかかる負担が大きくなり、効果の持続が短くなる可能性を考慮する必要があります。
施術部位による効果の感じ方の差
施術する部位によっても効果の感じ方や持続性が異なります。
動きの多い口周りや目周りは、他の部位に比べて効果の減退を早く感じるケースがあります。
一方で、頬やフェイスラインは比較的効果が長持ちしやすい部位です。
部位別の効果の感じやすさ
| 施術部位 | 特徴 | 効果の感じ方 |
|---|---|---|
| 頬・フェイスライン | 面積が広く、たるみを支える重要な部位。 | リフトアップ効果を実感しやすく、持続性も高い傾向。 |
| ほうれい線・口周り | 表情によってよく動く部位。 | 改善効果は高いが、動きが多いため変化を感じやすい。 |
| 目周り・こめかみ | 皮膚が薄く、繊細なリフトアップが求められる。 | 細かいシワの改善や目の開きやすさを実感できる。 |
糸リフトから1年後の肌状態
施術から1年が経過すると、肌はどのような状態になっているのでしょうか。
多くの場合、挿入した糸の一部または全部が吸収され始めていますが、美肌効果は続いています。
糸が完全に吸収された後の肌内部
1年後、PDOのような吸収が早い糸は、ほとんどが体内で分解されています。
しかし、糸が挿入されていた周囲には、自己のコラーゲン線維が新たに構築されています。このコラーゲン線維が肌の土台として残り、たるみを支える役割を果たします。
そのため、施術前の状態に完全に戻るわけではなく、肌のハリや弾力はある程度維持されます。
維持されるリフトアップ効果と肌のハリ
1年後の時点では、物理的な引き上げ効果は施術直後よりは緩やかになりますが、多くのケースで満足のいく状態を維持しています。
特に、コラーゲン生成による肌質の改善効果は安定してきます。
肌に触れた時のハリや弾力、化粧ノリの良さなど、内側からの変化を実感できる時期です。
効果が薄れてきたと感じるサイン
効果の持続には個人差があるため、1年を過ぎたあたりから効果が薄れてきたと感じる方もいます。
そのサインを早期に察知すると、次のメンテナンス計画を立てやすくなるでしょう。
- 以前は気にならなかったフェイスラインのもたつき
- 夕方になるとほうれい線が深く見える
- 肌のハリ感が以前よりなくなった気がする
1年後の状態を左右する要因
1年後の状態が良好かどうかは、いくつかの要因に左右されます。
| 要因 | 内容 | 1年後への影響 |
|---|---|---|
| 施術内容 | 挿入した糸の種類、本数、挿入方法など。 | 適切な施術計画が長期的な効果の土台となる。 |
| アフターケア | 施術後の紫外線対策や保湿などの日常ケア。 | 肌のコンディションを良好に保ち、効果の持続を助ける。 |
| 生活習慣 | 食生活、睡眠、喫煙、ストレスの有無など。 | 体の中から肌の健康を支え、老化の進行を緩やかにする。 |
これらを理解し、適切なケアを続けることが重要です。
施術後のケアや生活習慣が、将来の肌状態に大きく関わってきます。
糸リフトの効果を最大限に長持ちさせる秘訣
せっかく受けた糸リフトの効果は、できるだけ長く維持したいものです。
施術後の過ごし方や日々のケアを少し意識するだけで、効果の持続期間は大きく変わります。
施術後のダウンタイムの過ごし方
施術後、約1ヶ月間は特に重要な時期です。この期間の過ごし方が、糸の定着と効果の安定化に直結します。
大きな口を開けたり、顔を強くマッサージしたりする行為は避けましょう。
歯科治療や激しい運動も、医師の指示に従って一定期間控える必要があります。
日常生活で意識すべきスキンケア
日々のスキンケアも持続性を高める上で大切です。
紫外線はコラーゲンを破壊し、たるみを促進する最大の要因です。季節を問わず、日焼け止めを徹底しましょう。
また、肌の乾燥もハリを失わせる原因になるため、十分な保湿を心がけてください。
効果を持続させるスキンケア成分
| 成分名 | 期待される働き |
|---|---|
| レチノール | ターンオーバーを促し、コラーゲン生成をサポートする。 |
| ビタミンC誘導体 | 抗酸化作用で肌を守り、コラーゲンの生成を助ける。 |
| セラミド | 肌のバリア機能を高め、乾燥から肌を守る。 |
他の美容医療との賢い組み合わせ方
糸リフトの効果を補い、さらに高めるために、他の美容医療を組み合わせるのも有効な手段です。
相乗効果を狙うと、より満足度の高い結果を長く維持できます。
| 施術 | 特徴 |
|---|---|
| HIFU(ハイフ) | 超音波で筋膜を引き締め、たるみの根本原因にアプローチする。 |
| ヒアルロン酸注入 | ボリュームが不足している部分を補い、より自然なリフトアップを助ける。 |
| ボツリヌストキシン注射 | 筋肉の過剰な動きを抑え、表情ジワの悪化を防ぐ。 |
これらの治療を組み合わせるタイミングや順序については自己判断せず、医師に相談しましょう。
定期的なメンテナンスの重要性
糸リフトの効果を継続的に維持するためには、定期的なメンテナンスが鍵となります。
効果が完全になくなる前に次の施術を計画すると、たるみが深刻化するのを防ぎ、より少ない本数の糸で良好な状態を保てます。
1年〜1年半ごとのメンテナンスを検討するのが一般的です。
1年後を変える施術後の生活習慣
糸リフトの持続性は、クリニックでの施術だけで決まるものではありません。
実は、施術後の「生活習慣」そのものが、1年後の肌状態を大きく左右するのです。
食生活がコラーゲン生成に与える影響
私たちの肌は、日々の食事から作られます。
コラーゲンの材料となる栄養素を意識的に摂取すると、糸リフトの効果を内側から支えられます。
コラーゲン生成を支える栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | コラーゲンの主原料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンC | タンパク質からコラーゲンを合成する際に必要。 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |
| 鉄分 | コラーゲン合成を助け、肌に酸素を運ぶ。 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
これらの栄養素をバランス良く摂ると、肌の再生能力を高めてハリのある状態を長く保つ助けになります。
睡眠の質と肌の再生力の関係
質の良い睡眠中には、肌の修復と再生を促す「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。
なかでも入眠後の最初の3時間が「肌のゴールデンタイム」と呼ばれます。
睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げて肌の回復を遅らせる原因となりますので、毎日決まった時間に就寝し、十分な睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
表情の癖がリフトアップ効果に影響する
無意識に行っている表情の癖も、リフトアップ効果の持続性に影響を与えます。
例えば、スマートフォンを見る際に下を向く時間が長いと、首のシワやフェイスラインのたるみを助長します。
また、眉間にシワを寄せる、口角を下げるといった癖は、せっかく引き上げた皮膚に余計な負担をかけてしまいます。
時々鏡で自分の表情をチェックし、リラックスした状態を保つ意識が大切です。
ストレス管理とホルモンバランスの重要性
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、肌のコンディションを悪化させます。
ストレスを感じると活性酸素が増加し、コラーゲンを傷つけます。
また、ホルモンバランスの乱れは、肌のバリア機能の低下や皮脂の過剰分泌につながります。
自分なりのリラックス方法を見つけ、心身ともに健やかな状態を保つ工夫が、美肌を維持する上で欠かせません。
糸リフトの再施術を受ける適切な時期
「次回の施術はいつ頃が良いのか」というのも、多くの方が悩むポイントです。
再施術のタイミングを適切に見極めると効率的に若々しい印象を維持できます。
効果の減退を感じ始めた時が目安
最も分かりやすい目安は、自分自身で「少し効果が落ちてきたかな」と感じ始めたタイミングです。
たるみが完全に元に戻ってしまう前に施術を受けると、前回のリフトアップ効果を土台にしながら、より自然な仕上がりを維持しやすくなります。
鏡を見て「少し前の自分に戻ったような気がする」と感じたら、相談を検討するサインです。
前回の施術からの推奨される期間
一般的には、前回の施術から1年〜2年後が再施術の一つの目安とされています。
ただし、これは使用した糸の種類や本数、個人の状態によって異なります。
医師が肌の状態を確認し、コラーゲンの生成具合やたるみの進行度を評価した上で適したタイミングを提案します。
再施術のタイミング目安
| 前回の糸の種類 | 推奨される再施術の時期 |
|---|---|
| PDO | 1年~1年半後 |
| PCL / PLLA | 1年半~2年半後 |
医師との相談で決めるべき理由
再施術のタイミングは、自己判断で決めるべきではありません。客観的に肌の状態を診断できる経験豊富な医師と相談することが重要です。
現在の肌に必要な糸の種類や本数は、1年前とは異なる可能性があります。
医師が肌の変化を正確に評価し、過剰な治療や不十分な治療を避けるための適した計画を立ててくれます。
糸リフトの持続性に関する注意点とリスク
糸リフトは優れたたるみ治療ですが、効果の持続性に関して理解しておくべき注意点や、それに伴うリスクも存在します。
これらを事前に把握しておくことが、安心して施術を受けるための第一歩です。
効果の持続には個人差がある
効果の持続期間はあくまでも目安であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
年齢や肌質、骨格や生活習慣など、多くの要因が絡み合って結果に影響します。
他人の体験談や平均的な持続期間だけを鵜呑みにせず、自分の場合はどうなのか、カウンセリングで医師にしっかりと確認するようにしましょう。
施術後の感染や引きつれのリスク
非常に稀ですが、施術後に起こりうるリスクとして、感染や引きつれ感などが挙げられます。
感染はクリニックの衛生管理が徹底されていればほとんど起こりませんが、術後のケアを怠ると可能性はゼロではありません。
また、引きつれ感や凹凸は通常時間とともに馴染んでいきますが、長く続く場合は糸の挿入技術に問題がある可能性も考えられます。
経験豊富な医師を選ぶ重要性
糸リフトの持続性や仕上がりの美しさ、そして安全は、施術を行う医師の技術力と経験に大きく依存します。
顔の解剖学を熟知し、一人ひとりのたるみの原因を的確に診断できる医師を選ぶことが、満足のいく結果を得るための最も重要な要素です。
カウンセリングで親身に相談に乗ってくれるか、リスクについても正直に説明してくれるかを見極めましょう。
よくある質問
糸リフトの持続期間は、1~2年が一つの目安です。使用する糸の種類や本数、生活習慣や体質によって異なりますが、再施術を受ける時期も1~2年後が良いタイミングになる方が多いです。
より長く効果を持続させるために、生活習慣の見直しと改善を行っていくと良いでしょう。
- 1年後に糸は完全に無くなりますか?
-
使用する糸の種類によります。PDOのような吸収の早い糸は1年後にはほとんど吸収されていますが、PCLのような長持ちする糸はまだ残っています。
ただし、糸がなくなった後も、生成された自己のコラーゲンによる引き締め効果は持続します。
- 1年経たずに効果がなくなることはありますか?
-
可能性はゼロではありません。
新陳代謝が非常に活発な方、皮下脂肪が極端に多い、または少ない方、あるいは施術後に顔のマッサージを頻繁に行うなどの要因で平均より早く効果が薄れるケースがあります。
気になる場合は、早めに施術を受けたクリニックに相談しましょう。
- 再施術を繰り返すと肌に負担はかかりますか?
-
適切な間隔と方法で施術を行う限り、肌に大きな負担がかかることはありません。むしろ、定期的なメンテナンスはたるみの進行を予防する効果があります。
ただし、短期間に過剰な本数を挿入するなどの不適切な施術は肌への負担となるため、信頼できる医師のもとで計画的に行うことが重要です。
- 1年後の効果に満足できない場合はどうすれば良いですか?
-
まずは施術を受けたクリニックで医師に相談してください。
状態を診察した上で、追加の施術(糸の追加、HIFU、注入治療など)で改善が可能か、あるいはどのような選択肢があるかを提案してくれます。
不満を抱えたままにせず、専門家のアドバイスを求めることが解決への近道となるでしょう。
糸リフト・スレッドリフトに戻る
参考文献
GÜLBITTI, Haydar Aslan, et al. Thread-lift sutures: still in the lift? A systematic review of the literature. Plastic and reconstructive surgery, 2018, 141.3: 341e-347e.
HONG, Gi‐Woong; PARK, Soo Yeon; YI, Kyu‐Ho. Revolutionizing thread lifting: Evolution and techniques in facial rejuvenation. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.8: 2537-2542.
OBOURN, Chelsea A.; WILLIAMS, Edwin F. A decade of thread-lifting—what have we learned over the last 10 years?. JAMA facial plastic surgery, 2018, 20.5: 349-350.
HONG, Gi-Woong, et al. What are the factors that enable thread lifting to last longer?. Cosmetics, 2024, 11.2: 42.
ABRAHAM, Rima F.; DEFATTA, Robert J.; WILLIAMS, Edwin F. Thread-lift for facial rejuvenation: assessment of long-term results. Archives of Facial Plastic Surgery, 2009, 11.3: 178-183.
ATIYEH, Bishara S.; CHAHINE, Fadel; GHANEM, Odette Abou. Percutaneous thread lift facial rejuvenation: literature review and evidence-based analysis. Aesthetic Plastic Surgery, 2021, 1-11.
DIASPRO, Alberto; ROSSINI, Gabriele. Thread lifting of the midface: a pilot study for quantitative evaluation. Dermatologic Therapy, 2021, 34.4: e14958.
BERTOSSI, Dario, et al. Effectiveness, longevity, and complications of facelift by barbed suture insertion. Aesthetic surgery journal, 2019, 39.3: 241-247.