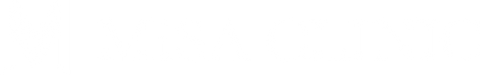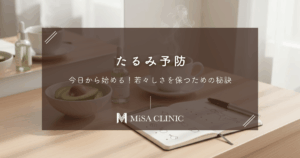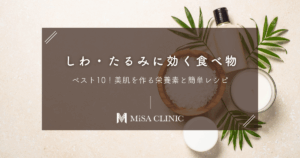【たるみケア】自宅でできる簡単セルフケアから美容医療まで解説

たるみは加齢とともに誰にでも起こりうる肌の変化ですが、その原因は一つではありません。
紫外線や乾燥、生活習慣など、様々な要因が複雑に絡み合って進行します。
この記事では、たるみが起こる原因から、ご自宅で今日から始められるセルフケア、そして美容クリニックで受けられる専門的な治療まで幅広く解説します。
ご自身のたるみの状態を正しく理解し、自分に合ったケアを見つけましょう。
そもそも「たるみ」はなぜ起こるのか?主な3つの原因
顔のたるみは、皮膚やその下の組織が重力に抗しきれなくなり、垂れ下がってしまう状態を指します。
その背景には、肌の内部構造の変化が大きく関わっています。主な原因として、肌の弾力低下、皮下脂肪の変化、そして筋肉の衰えという3つの側面が挙げられます。
肌の弾力低下(コラーゲン・エラスチンの減少)
肌のハリや弾力は、真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンといった線維状のたんぱく質によって支えられています。
コラーゲンは肌の構造をしっかりと保つ骨組みの役割を、エラスチンはそれに弾力を与えるバネのような役割を担います。
しかし、加齢や紫外線の影響でこれらのたんぱく質は減少し、質も低下します。結果として肌の土台が弱くなり、皮膚が重力に負けてたるんでしまうのです。
たるみを引き起こす主な要因
| 要因 | 肌への影響 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 加齢 | 線維芽細胞の働きの低下 | コラーゲンやエラスチンを生成する細胞の機能が衰え、産生量が減少します。 |
| 紫外線 | 光老化による変性 | 特にUVA波は真皮層にまで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊・変性させます。 |
| 乾燥 | 肌表面のバリア機能低下 | 肌の水分が失われると、ターンオーバーが乱れ、真皮層にも影響が及びます。 |
皮下脂肪の増減と移動
顔の皮下脂肪は肌にふっくらとした丸みを与えていますが、加齢とともにその位置が変化します。
若い頃は頬の高い位置にある脂肪が年齢を重ねるとともに下の方へ移動し、フェイスラインのもたつきやほうれい線、マリオネットラインの原因となります。
また、急激なダイエットなどで脂肪が減少すると皮膚が余ってしまい、たるみとして現れるケースもあります。
表情筋の衰えとSMAS筋膜のゆるみ
皮膚や皮下脂肪を土台から支えているのが、表情筋と、その上を覆うSMAS(スマス)筋膜という線維性の膜です。
身体の筋肉と同じように、表情筋も使わなければ衰えていきます。無表情でいる時間が増えると、筋力の低下につながりやすいです。
SMAS筋膜も加齢によってゆるむため、筋肉と脂肪を支えきれなくなり、顔全体のたるみを引き起こします。
たるみが現れやすい部位とそれぞれの特徴
たるみは頬や目の下、フェイスラインにとくに現れやすく、それぞれに特徴的な見た目の変化をもたらします。
ご自身の悩みがどのタイプに当てはまるか確認してみましょう。
頬のたるみ(ほうれい線・マリオネットライン)
頬は顔の中でも面積が大きく、皮下脂肪も多いため、たるみの影響が現れやすい部位です。
頬の位置が全体的に下がることで、鼻の両脇から口角にかけてのシワである「ほうれい線」や、口角から顎にかけて伸びる「マリオネットライン」が深く刻まれます。
これらが目立つと、一気に老けた印象や疲れた印象を与えがちです。
目の下のたるみ・クマ
目の下の皮膚は非常に薄くデリケートなため、たるみのサインが早期に現れやすい場所です。
眼球を支えている脂肪(眼窩脂肪)が前方へ突出してくると、目の下にふくらみ(たるみ)ができます。
このふくらみの下が影になり「黒クマ」と呼ばれるクマが生じて、疲れた印象を強調してしまいます。
フェイスラインのもたつき(二重あご)
フェイスラインのシャープさが失われ、輪郭がぼやけてくるのも、たるみの代表的な症状です。
頬や口元の脂肪が下垂することに加え、首周りの筋力の低下も影響します。
顎下に脂肪が溜まると、いわゆる「二重あご」となり、顔が大きく見えたり首が短く見えたりする原因にもなります。
部位別たるみの主な原因
| 部位 | 主な原因 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| 頬 | 脂肪の下垂、コラーゲンの減少 | ほうれい線、マリオネットラインが目立つ。 |
| 目の下 | 皮膚のゆるみ、眼窩脂肪の突出 | ふくらみと影(黒クマ)ができる。 |
| フェイスライン | 頬全体の脂肪の下垂、筋力の低下 | 輪郭がぼやける、二重あごになる。 |
【自宅でできる】たるみ対策セルフケアの基本
たるみの進行を緩やかにし、予防するためには、紫外線対策や正しい保湿、表情筋エクササイズや頭皮マッサージといった日々のセルフケアが基本となります。
毎日の習慣に取り入れて、未来の肌への投資を始めましょう。
紫外線対策の徹底
紫外線はたるみの最大の原因である「光老化」を引き起こします。
なかでも波長の長いUVAは雲や窓ガラスも透過して肌の奥深く(真皮層)に到達し、コラーゲンやエラスチンにダメージを与えます。
季節や天候を問わず、一年中、日焼け止めを塗る習慣をつけましょう。SPF値だけでなく、UVAを防ぐ指標であるPA値の確認が大切です。
紫外線(UVAとUVB)の違い
| 種類 | 特徴 | 肌への影響 |
|---|---|---|
| UVA(紫外線A波) | 波長が長く、真皮まで到達する | たるみ、シワの原因となる |
| UVB(紫外線B波) | 波長が短く、表皮で吸収される | シミ、そばかす、日焼けの原因となる |
正しい保湿スキンケア
肌が乾燥するとバリア機能が低下し、紫外線などの外部刺激を受けやすくなります。また、乾燥自体が小じわの原因となり、放置すると深いたるみにつながる場合もあります。
化粧水で水分をたっぷり与えた後、乳液やクリームなどの油分でしっかりと蓋をして、水分が蒸発しないようにしましょう。
代表的な保湿成分
- セラミド
- ヒアルロン酸
- コラーゲン
- アミノ酸
表情筋を鍛えるフェイスエクササイズ
顔の筋肉を意識的に動かすと、筋力の低下を防ぎ、リフトアップ効果が期待できます。
ただし、やりすぎや間違った方法はかえってシワの原因になるときもあるため注意が必要です。肌を強くこすったり、無理に引っ張ったりせず、ゆっくりと丁寧に行いましょう。
「あ・い・う・え・お」と口を大きく動かすだけでも、普段使わない筋肉を刺激できます。
頭皮マッサージのすすめ
顔の皮膚と頭皮は一枚でつながっています。頭皮が凝り固まって血行が悪くなると顔の皮膚を支える力が弱まり、たるみを引き起こす一因となります。
シャンプーの際などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐすようにマッサージしましょう。血行が促進され、リフトアップ効果だけでなく、顔色も明るくなります。
たるみケアで意識したい食生活と栄養素
たるみにくい肌を作るには、肌の材料となるたんぱく質や、抗酸化作用のあるビタミン類、肌の調子を整えるミネラルなどを食事からバランス良く摂取する工夫が大切です。
多くの方が外側からのスキンケアに注目しがちですが、美しい肌は内側からの栄養によっても育まれます。
たんぱく質で肌の土台を作る
肌のハリを支えるコラーゲンやエラスチンは、たんぱく質から作られています。
肉や魚、卵や大豆製品など、良質なたんぱく質を毎食きちんと摂る習慣が、肌の土台作りの第一歩です。
たんぱく質が不足すると新しい皮膚細胞の生成が滞り、肌の弾力が失われやすくなります。
ビタミンC・A・Eで抗酸化対策
体内で発生する活性酸素は細胞を傷つけ、老化を促進させる原因となります。
ビタミンC、ビタミンA、ビタミンEは「ビタミンACE(エース)」とも呼ばれ、強い抗酸化作用を持つ栄養素です。これらを積極的に摂ると肌の酸化を防ぎ、たるみを予防できます。
たるみケアに役立つ主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 肌の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンC | コラーゲン生成を助ける、抗酸化作用 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康を保つ | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(人参、ほうれん草) |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、植物油 |
亜鉛や鉄分などのミネラルも重要
ミネラルも健やかな肌を維持するために必要な栄養素です。特に亜鉛は、新しい細胞が作られる際に働き、肌のターンオーバーを正常に保ちます。
鉄分は全身に酸素を運ぶ役割を担っており、不足すると肌細胞に十分な酸素が届かず、くすみや機能低下の原因となります。
ストレスや生活習慣がたるみに与える意外な影響
たるみは加齢や紫外線だけでなく、スマートフォンの長時間利用による姿勢の悪化や睡眠不足、食いしばりやストレスといった日常の生活習慣も大きく影響します。
見落としがちな習慣が、たるみを加速させているかもしれません。
「スマホ首」が引き起こす顔のたるみ
スマートフォンやパソコンを長時間使う際、うつむいた姿勢を続けている方も多いです。この姿勢は首の前側の筋肉を縮ませ、顎から首にかけての筋肉(広頸筋)を衰えさせます。
この広頸筋はフェイスラインの皮膚とつながっているため、その衰えは直接フェイスラインのもたつきや二重あごにつながります。
意識的に画面を目線の高さに合わせ、時々ストレッチをしましょう。
睡眠不足と肌の再生サイクルの乱れ
肌は私たちが眠っている間に日中のダメージを修復し、新しい細胞へと生まれ変わります。この再生を促すのが「成長ホルモン」で、特に深い眠りの間に最も多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり眠りの質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、肌の修復が追いつきません。
結果として、コラーゲンの減少が進み、たるみやすい肌状態になってしまいます。
あなたの生活習慣は大丈夫?たるみリスクチェック
| チェック項目 | 対策のヒント |
|---|---|
| 1日に3時間以上スマホをうつむいて見る | スマホを目線の高さで持つ、休憩を挟む |
| 寝る直前までスマホやPCを見ている | 就寝1時間前には電子機器の使用をやめる |
| 朝起きると顎や歯が疲れているときがある | 日中、上下の歯を接触させないよう意識する |
| 片側の歯ばかりで食べ物を噛む癖がある | 左右均等に噛むように意識する |
食いしばりや歯ぎしりがフェイスラインを崩す
日中に無意識に歯を食いしばったり、夜間に歯ぎしりをしたりする癖は、顎周りの筋肉(咬筋)を過剰に緊張させます。
この咬筋が発達しすぎるとエラが張ったように見え、フェイスラインが横に広がってしまいます。
また、この緊張が顔全体の筋肉のバランスを崩し、たるみやほうれい線を悪化させる一因にもなります。
慢性的なストレスと活性酸素の発生
強いストレスを感じると、体内では対抗するためにコルチゾールというホルモンが分泌されます。
コルチゾールが過剰になると、肌のコラーゲンを破壊する働きがあるため、肌の弾力低下につながります。また、ストレスは活性酸素を大量に発生させ、細胞レベルでの老化を促進します。
自分なりのリラックス方法を見つけ、上手にストレスを発散する工夫が、たるみ予防にもつながるのです。
セルフケアの限界と美容医療を考えるタイミング
セルフケアを続けても改善が見られない、深いシワが定着してしまった、あるいはより早く確実な効果を求めたいときが、美容医療を検討するタイミングです。
セルフケアでは届かない肌の深層部への働きかけが必要なサインかもしれません。
セルフケアで改善が見られない場合
保湿や紫外線対策、マッサージなどを数ヶ月続けても、たるみが改善する兆しが見えないときは、皮膚の深い層や筋膜レベルへの働きかけが必要なサインかもしれません。
セルフケアは主に皮膚の表面(表皮)に対するケアが中心ですが、たるみの根本原因はさらに奥の真皮層やSMAS筋膜にあります。
セルフケアと美容医療の違い
| セルフケア | 美容医療 | |
|---|---|---|
| アプローチ層 | 主に表皮層 | 真皮層、皮下組織、SMAS筋膜など |
| 期待できる効果 | 予防、現状維持、ハリ感の向上 | 根本的な改善、リフトアップ |
| 即時性 | 穏やか(数ヶ月〜) | 比較的早い(施術による) |
深いシワやほうれい線が定着してきた
無表情の時でも、ほうれい線やマリオネットラインがくっきりと見えるようになったら、それは皮膚に「折りジワ」が定着してしまった状態です。
この段階になると、スキンケアで肌のハリを多少取り戻せたとしても、シワそのものを消すのは困難です。
ヒアルロン酸注入などで物理的に溝を埋める治療が有効な選択肢となります。
より早く確実な効果を求めるなら
大切なイベントを控えているなど、「短期間で見た目の印象を変えたい」という明確な目的がある場合も美容医療を検討する良いタイミングです。
美容医療は専門的な知識と技術、医療機器を用いてたるみの原因に直接作用するため、セルフケアに比べて早く確実な変化が期待できます。
美容クリニックで受けられる代表的なたるみ治療
美容クリニックでは、たるみの原因や程度、希望に合わせて様々な治療法を提案します。
広く行われている代表的な治療法は「照射治療」「注入治療」「糸リフト」「外科手術」の4つです。
HIFU(ハイフ)などの照射治療
高密度の超音波エネルギーを皮膚の深層部に照射し、熱エネルギーで組織を収縮させてリフトアップを図る治療法です。
特にSMAS筋膜に直接働きかけられるのが大きな特徴で、「切らないフェイスリフト」とも呼ばれます。
肌表面を傷つけずに治療できるため、ダウンタイムがほとんどない点も魅力です。
ヒアルロン酸やコラーゲンなどの注入治療
ヒアルロン酸などの製剤を、シワや溝が気になる部分に直接注入し、内側から肌を持ち上げて平らにする治療です。
ほうれい線やマリオネットライン、目の下のくぼみなどに効果的です。
また、コラーゲンの生成を促す成分が含まれた製剤もあり、肌全体のハリを取り戻す目的でも使用します。
糸リフト(スレッドリフト)
コグ(とげ)の付いた特殊な医療用の糸を皮下に挿入し、たるんだ組織を物理的に引き上げる治療法です。
フェイスラインのもたつきや頬のたるみを強力にリフトアップする効果が期待できます。
使用する糸は時間とともに体内に吸収されるため安全性が高く、糸が吸収される過程でコラーゲン生成が促進されるという副次的な効果もあります。
代表的な美容治療の比較
| 治療法 | 主な効果 | 向いている方 |
|---|---|---|
| HIFU(照射) | SMAS筋膜からの引き締め、リフトアップ | 顔全体のゆるみが気になる、ダウンタイムを避けたい |
| ヒアルロン酸(注入) | シワや溝を埋める、ボリュームアップ | ほうれい線や目の下のくぼみが気になる |
| 糸リフト | 物理的なリフトアップ、フェイスラインの形成 | 頬や顎下のもたつきを強力に引き上げたい |
外科手術によるリフトアップ
余分な皮膚を切除し、SMAS筋膜からしっかりと引き上げる外科的な手術です。
たるみ治療の中では最も効果を実感しやすく、持続期間も長いですが、その分ダウンタイムも長くなる傾向があります。
たるみの進行が著しい場合や、他の治療では満足な効果が得られなかった場合の最終的な選択肢となります。
たるみ治療を受ける前に知っておきたい注意点
たるみ治療を安心して受けるためには、事前のカウンセリングで十分に相談する、各治療のダウンタイムやリスクを理解する、信頼できるクリニックを選ぶ、といった点が重要です。
満足のいく結果を得るために、これらのポイントを確認しましょう。
カウンセリングの重要性
治療を成功させるためには、医師との事前のカウンセリングが非常に重要です。ご自身の悩みや希望を正確に伝え、医師から治療法の詳しい説明(効果、リスク、費用など)を受けましょう。
疑問や不安な点はすべて質問し、納得した上で治療に進むことが大切です。
信頼できる医師は一方的に治療を勧めるのではなく、あなたの話を丁寧に聞き、複数の選択肢を提示してくれるはずです。
治療ごとのダウンタイムとリスク
どの治療法にも、効果の反面、一定のリスクや副作用、ダウンタイム(回復期間)が存在します。
例えば、注入治療では内出血や腫れ、糸リフトでは一時的なひきつれ感などが起こる可能性があります。
治療を受ける前に、どのようなリスクが考えられるのか、ダウンタイムはどの程度必要なのかを正確に把握し、ご自身の生活スタイルと照らし合わせて計画を立てましょう。
主な治療のダウンタイム目安
| 治療法 | ダウンタイムの主な症状 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| HIFU | 赤み、軽い筋肉痛のような痛み | ほぼ無し〜数日 |
| ヒアルロン酸注入 | 腫れ、赤み、内出血 | 数日〜1週間程度 |
| 糸リフト | 腫れ、痛み、内出血、ひきつれ感 | 1〜2週間程度 |
信頼できるクリニックの選び方
クリニック選びは、たるみ治療の結果を左右する最も重要な要素の一つです。
ウェブサイトの情報だけでなく、実際にカウンセリングに足を運び、院内の清潔さやスタッフの対応、医師との相性などを自分の目で確かめるのがおすすめです。
クリニック選びで確認したいポイント
- 医師にたるみ治療の経験が豊富にあるか
- カウンセリングが丁寧で、質問しやすい雰囲気か
- メリットだけでなく、リスクやデメリットも説明してくれるか
- 料金体系が明確で、追加費用の説明があるか
たるみケアに関するよくある質問
日々のセルフケアは、たるみの予防や進行を遅らせる上で非常に重要です。紫外線対策や保湿といった基本と合わせて、エクササイズやマッサージ、生活習慣の見直しなども行いましょう。
しかし、すでに深く刻まれてしまったシワや、大きく垂れ下がってしまった脂肪に対して、セルフケアだけでは元の状態に戻すのは難しいのが現実です。
そのため、より積極的なたるみケア・改善を行いたい方は、いちどクリニックのカウンセリングで相談してみるのがおすすめです。
- たるみ治療は何歳から始めるべきですか?
-
たるみ治療を始めるのに決まった年齢はありません。「たるみが気になり始めたとき」が治療を検討するタイミングです。
予防的な観点から、20代後半〜30代前半でHIFUなどの照射治療を始める方も増えています。たるみが進行する前にケアを始めると、より良い状態を長く維持しやすくなります。
- 治療の効果はどのくらい続きますか?
-
効果の持続期間は、治療法や個人の肌質、生活習慣によって大きく異なります。
一般的に、HIFUは半年〜1年、ヒアルロン酸は製剤によりますが半年〜2年、糸リフトは1〜2年程度が目安です。
効果を持続させるためには、定期的なメンテナンス治療や、日々のセルフケアを継続することが重要です。
- 痛みやダウンタイムはありますか?
-
治療によって異なります。HIFUはチクチクとした熱感や骨に響くような痛みを感じる場合があります。
注入治療や糸リフトは、麻酔を使用するため施術中の痛みは少ないですが、施術後に腫れや内出血などのダウンタイムが生じることが一般的です。
カウンセリングの際に、痛みの程度やダウンタイムについて詳しく確認しましょう。
- セルフケアと美容医療は併用できますか?
-
併用をおすすめします。美容医療でたるみを改善した後も、紫外線対策や保湿などのセルフケアを続けると、治療効果をより長く持続させられます。
また、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけることも、美しい肌を保つ上で大切です。
たるみ予防・生活習慣に戻る
参考文献
VAN BORSEL, John, et al. The effectiveness of facial exercises for facial rejuvenation: a systematic review. Aesthetic surgery journal, 2014, 34.1: 22-27.
COHEN, Marc, et al. Home-based devices in dermatology: a systematic review of safety and efficacy. Archives of Dermatological Research, 2022, 314.3: 239-246.
BAUMANN, Leslie. Skin ageing and its treatment. The Journal of Pathology: A Journal of the Pathological Society of Great Britain and Ireland, 2007, 211.2: 241-251.
PRALL, J. K., et al. The effectiveness of cosmetic products in alleviating a range of skin dryness conditions as determined by clinical and instrumental techniques. International journal of cosmetic science, 1986, 8.4: 159-174.
AUST, Matthias C., et al. Percutaneous collagen induction therapy: an alternative treatment for scars, wrinkles, and skin laxity. Plastic and reconstructive surgery, 2008, 121.4: 1421-1429.
DE VOS, Marie-Camille, et al. Facial exercises for facial rejuvenation: a control group study. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 65.3: 117-122.
M. SMITH, Abigail, et al. Non-traditional and non-invasive approaches in facial rejuvenation: a brief review. Cosmetics, 2020, 7.1: 10.
KO, E. J., et al. Efficacy and safety of non‐invasive body tightening with high‐intensity focused ultrasound (HIFU). Skin Research and Technology, 2017, 23.4: 558-562.