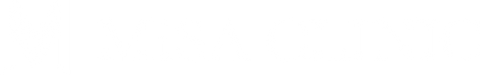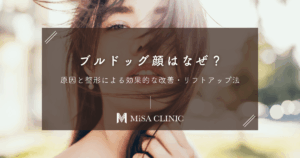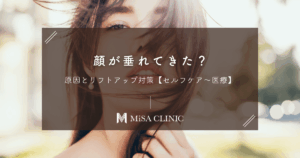ダイエットで顔がたるむ原因と対策|キレイに痩せるための重要ポイント

「痩せたら老けて見られるようになった」「ダイエットに成功したのに、ほうれい線やマリオネットラインが目立つ」と感じる方もいるでしょう。体重が減っても、顔がたるんでしまっては喜びも半減します。
ダイエットによる顔のたるみは、急激な体重減少や栄養不足、加齢などが複雑に関係して起こります。しかし、原因を知り、正しい対策を行えば、たるみを予防しながらキレイに痩せることは可能です。
この記事では、美容皮膚科の視点から、ダイエットで顔がたるむ原因を詳しく解説し、食事やセルフケア、美容医療による対策まで、ハリのある若々しい印象を保つための重要なポイントを紹介します。
なぜダイエットで顔がたるむのか?3つの原因
ダイエットを始めると、多くの方が体重の変化に集中しがちです。しかし、その裏で顔の「たるみ」が進行している場合があります。
ダイエットで顔がたるむのは、主に「急激な体重減少で皮膚が余る」「顔の脂肪と筋肉が減る」「栄養不足で肌の弾力が低下する」という3つの原因が関係しています。
急激な体重減少による皮膚の余り
顔の皮膚は、その下にある脂肪や筋肉の体積に合わせて存在しています。風船をイメージすると分かりやすいですが、急激なダイエットで顔の脂肪が急速に減少すると、皮膚がその体積変化に追いつけません。
行き場を失った皮膚が余ってしまい、重力に従って垂れ下がる、これが「たるみ」の正体の一つです。
特に、短期間で大幅な減量を行うと皮膚の収縮が間に合わず、たるみとして現れやすくなります。
顔の脂肪と筋肉の減少
顔には皮下脂肪だけでなく、表情を作る「表情筋」という筋肉があります。無理なダイエットは、体脂肪だけでなく顔の脂肪や筋肉も減少させます。
顔の脂肪は適度にあれば肌にハリを与え、若々しい印象を保つクッションの役割を果たします。これが減りすぎると、顔がこけたり、くぼんだりして「しぼんだ」印象になります。
さらに、皮膚を内側から支えている表情筋が痩せると皮膚を支える力が弱まり、たるみにつながります。
栄養不足による肌弾力の低下
極端な食事制限を行うと、肌の健康を維持するために必要な栄養素が不足しがちです。肌のハリや弾力は、真皮層にあるコラーゲンやエラスチンといった線維組織によって保たれています。
線維組織の主成分はタンパク質であり、その生成にはビタミンCや亜鉛などの補酵素も関わります。
ダイエット中にこれらの栄養素が不足すると新しいコラーゲンの生成が滞り、肌の弾力が失われます。結果として肌がゆるみ、たるみやすい状態を自ら作ってしまうのです。
顔のたるみを引き起こすNGなダイエット法
痩せたい一心で取り組むダイエットが、かえって顔のたるみを招いてしまうケースは少なくありません。
「極端なカロリー制限」「単品ダイエット」「運動を全くしないダイエット」は、体重が減っても肌のハリを失わせ、たるみを引き起こすため、美容の観点からは推奨できません。
極端な食事制限(カロリーカット)
「早く痩せたい」と、1日の摂取カロリーを基礎代謝以下にまで極端に減らす方法です。
体は生命維持のために、脂肪だけでなく筋肉も分解してエネルギー源にし始めます。これには顔の表情筋も含まれます。
筋肉量が減ると基礎代謝が落ちて痩せにくい体になるだけでなく、顔の土台がゆるみ、皮膚を支えきれずにたるみが発生します。
また、必要な栄養素が絶対的に不足するため、前述の通り肌の弾力も失われます。
特定の食品だけを食べる「単品ダイエット」
リンゴだけ、ゆで卵だけ、といった特定の食品だけを食べ続けるダイエット法です。一時的に体重が落ちるケースはありますが、栄養バランスが極端に偏ります。
例えば、タンパク質が不足すれば筋肉や肌の材料が足りなくなり、脂質をカットしすぎれば肌が乾燥し、ビタミンやミネラルが不足すれば肌のターンオーバー(再生)が正常に行われなくなります。
こうした栄養の偏りは肌の健康を著しく損ね、たるみを促進します。
NGダイエットが招く結果
- 筋肉量の低下と基礎代謝の悪化
- 肌のハリ・弾力の急速な喪失
- リバウンドしやすい体の形成
運動を全くしないダイエット
食事制限だけで痩せようとすると、体重が減る際に脂肪と同時に筋肉も失われやすくなります。運動、特に筋力トレーニングは、ダイエット中に筋肉量を維持・向上させるために重要です。
顔には直接的な筋トレが難しい部分もありますが、全身の筋肉量が維持されて血流が良くなると、顔の肌にも良い影響を与えます。
運動を全くせずに食事だけで痩せると、全体的にハリのない、たるんだ印象の痩せ方になる危険性が高まります。
キレイに痩せるための食事の基本
顔のたるみを防ぎながら健康的に痩せるには、「何を食べるか」が非常に重要です。カロリーを抑えることだけに注目せず、肌と体の材料となる栄養素をしっかり摂取する意識を持ちましょう。
タンパク質の積極的な摂取
タンパク質は、肌や髪、筋肉や内臓など、体を作る主要な材料です。ダイエット中は特に不足しやすいため、意識して摂取する必要があります。
肌のハリを保つコラーゲンやエラスチンもタンパク質の一種です。肉や魚、卵や大豆製品、乳製品などを毎食取り入れ、体重1kgあたり1g〜1.5g程度を目安に摂取しましょう。
特に朝食でタンパク質を摂ると、日中の代謝アップにもつながります。
良質な脂質(オメガ3など)の選び方
「ダイエットの敵」と見なされがちな脂質ですが、良質な脂質は健康と美容に必要です。脂質は細胞膜の材料となり、肌の潤いを保つ皮脂膜の形成にも関わります。
青魚(サバ、イワシなど)に含まれるオメガ3系脂肪酸や、アボカド、ナッツ類、オリーブオイルに含まれる不飽和脂肪酸は積極的に摂りたい脂質です。
逆に、揚げ物やスナック菓子に含まれるトランス脂肪酸や酸化した油は体内の炎症を引き起こし、肌の老化を早める可能性があるため避けましょう。
摂るべき脂質・避けるべき脂質
| 脂質の種類 | 主な食品 | 働き・影響 |
|---|---|---|
| オメガ3系脂肪酸 | 青魚(サバ、イワシ、サンマ)、亜麻仁油、えごま油 | 炎症を抑える、血流改善、細胞膜の材料 |
| オメガ9系脂肪酸 | オリーブオイル、アボカド、ナッツ類 | 悪玉コレステロールを減らす、抗酸化作用 |
| トランス脂肪酸 | マーガリン、ショートニング、スナック菓子、揚げ物 | 悪玉コレステロールを増やす、体内の炎症促進 |
ビタミン・ミネラルで肌の土台作り
ビタミンやミネラルは、タンパク質や脂質が体内で効率よく働くための「潤滑油」のような役割を果たします。
これらが不足すると、いくら良い材料(タンパク質など)を摂っても、うまく肌や筋肉に変換できません。
コラーゲンの生成を助けるビタミンC、肌のターンオーバーを整えるビタミンA、抗酸化作用の高いビタミンEは「美肌ビタミン」とも呼ばれます。
野菜や果物、海藻やキノコ類などをたっぷり摂り、バランスを整えましょう。
水分補給の重要性
体内の水分が不足すると血液の循環が悪くなり、肌細胞に必要な栄養素や酸素が届きにくくなります。また、肌自体も乾燥し、ハリが失われて小じわやたるみが目立ちやすくなります。
ダイエット中は食事量が減るため、食事から得られる水分も少なくなりがちです。
のどが渇いたと感じる前に、こまめに水や白湯、ノンカフェインのお茶などで水分を補給しましょう。1日に1.5リットル〜2リットルが目安です。
肌のハリを保つ栄養素とその働き
肌のハリを保つためには「ビタミンC」「ビタミンA」「ビタミンE」「アミノ酸(タンパク質)」が重要です。
これらの栄養素は、コラーゲンの生成を助けたり肌のターンオーバーを整えたりする働きがあり、不足するとたるみが出やすくなります。
コラーゲン生成を助けるビタミンC
ビタミンCは、肌のハリの元であるコラーゲン線維を合成する際に重要な働きをします。
体内でタンパク質(アミノ酸)からコラーゲンを作る工程でビタミンCが不足していると、正常なコラーゲンが作られません。
また、ビタミンC自体も強力な抗酸化作用を持ち、紫外線などによる肌のダメージを防ぎます。
喫煙やストレスでも大量に消費されるため、意識的に摂取したい栄養素です。ピーマンやブロッコリー、キウイや柑橘類などに多く含まれます。
肌のターンオーバーを整えるビタミンA
ビタミンA(レチノール)は皮膚や粘膜の健康を保ち、肌のターンオーバー(新陳代謝)を正常に整える働きがあります。
ターンオーバーが乱れると古い角質が残り、肌がごわつくだけでなく、真皮層でのコラーゲン生成にも影響が出ます。
ビタミンAはレバー、うなぎ、卵黄などの動物性食品や、ニンジン、かぼちゃ、ほうれん草などの緑黄色野菜(βカロテンとして含まれ、体内でビタミンAに変換)から摂取できます。
肌の土台を作るビタミン・ミネラル
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンC | コラーゲン生成の補助、抗酸化作用 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、イチゴ |
| ビタミンA | 皮膚・粘膜の健康維持、ターンオーバー促進 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(ニンジンなど) |
| ビタミンE | 強力な抗酸化作用、血行促進 | ナッツ類、アボカド、植物油(ひまわり油など) |
抗酸化作用で細胞を守るビタミンE
ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強力な抗酸化作用を持っています。体内で発生する活性酸素は細胞を酸化させて(錆びさせて)老化を促進し、コラーゲンやエラスチンを変性させます。
ビタミンEは活性酸素から細胞膜を守り、肌の老化を防ぎます。また、末梢血管を広げて血行を促進する働きもあり、肌の隅々まで栄養を届けるのを助けます。
アーモンドなどのナッツ類、アボカドや植物油などに豊富です。
筋肉の材料となるアミノ酸
タンパク質が分解されるとアミノ酸になります。コラーゲンも特定のアミノ酸(プロリン、グリシンなど)からできています。
ダイエット中にタンパク質摂取が不足すると、体は筋肉を分解してアミノ酸を取り出し、生命維持に必要なエネルギーや他のタンパク質の合成に使おうとします。当然、肌のコラーゲン生成は後回しにされます。
良質なタンパク質をしっかり摂り、アミノ酸、特に体内で合成できない必須アミノ酸を不足させない工夫がたるみ予防の基本です。
ダイエット中の顔たるみ予防セルフケア
たるませないためには、食事(内側)からのケアと同時に外側からのセルフケアも重要です。
表情筋トレーニングや保湿・紫外線対策といった日常生活で取り入れられる簡単な習慣が、未来のフェイスラインを守ります。
表情筋トレーニング(顔ヨガ)のすすめ
顔には約30種類以上の表情筋がありますが、日常生活ではその一部しか使われていない場合が多いです。特にマスク生活が長引いたことで無表情の時間が長くなり、表情筋が衰えやすくなっています。
筋肉が衰えれば、その上にある皮膚や脂肪を支えきれずにたるみます。
意識的に顔の筋肉を大きく動かす「表情筋トレーニング」や「顔ヨガ」を取り入れ、筋肉の衰えを防ぎましょう。
簡単な表情筋トレーニング例
- 「あー」「いー」「うー」「えー」「おー」と口を大きく開けて発声する
- 目を大きく見開き、その後ゆっくりと固く閉じる(眼輪筋)
- 口を閉じたまま、頬を風船のように大きく膨らませ、ゆっくりとしぼませる(口輪筋)
保湿ケアと紫外線対策の徹底
肌の乾燥はバリア機能の低下を招き、あらゆる肌トラブルの原因となります。乾燥した肌はハリを失い、たるみが目立ちやすくなります。
ダイエット中は特に皮脂の分泌が減る場合もあるため、化粧水で水分を与えた後、乳液やクリーム(セラミドやヒアルロン酸配合など)でしっかり蓋をする「保湿」を徹底してください。
また、紫外線のなかでもUVA(紫外線A波)は肌の奥深く(真皮層)まで到達し、コラーゲンやエラスチンを破壊する最大の外的要因です。
ダイエットを頑張っても、紫外線を浴びていてはたるみが加速します。季節や天候に関わらず、日焼け止めを毎日塗る習慣をつけましょう。
質の良い睡眠で成長ホルモンを促す
睡眠中、特に眠り始めの深いノンレム睡眠時に「成長ホルモン」が分泌されます。成長ホルモンは日中に受けた肌のダメージを修復し、肌のターンオーバーを促進する重要な役割を果たします。
ダイエット中はストレスを感じやすく、睡眠が浅くなる方もいます。質の良い睡眠の確保はたるみ予防だけでなく、ダイエットの効率アップ(食欲抑制ホルモンの分泌など)にもつながります。
睡眠の質を高める工夫
- 就寝1〜2時間前に入浴し、体温を一度上げる
- 就寝前のスマートフォンやPCの使用を避ける
- カフェインの摂取は午後に控える
首や肩のコリをほぐすマッサージ
首や肩が凝り固まっていると、顔への血流やリンパの流れが滞ります。すると、顔に老廃物が溜まってむくんだり栄養が届きにくくなったりして、たるみを助長します。
デスクワークやスマホ操作が多い方は、定期的に首や肩を回したりストレッチをしたりして、コリをほぐすよう心がけましょう。
お風呂上がりの温まった体で、鎖骨周りや首筋を優しくマッサージするのも良い方法です。
本当にダイエットだけが原因?隠れた要因の見極め方
ダイエットによるたるみは、「加齢による肌弾力の低下」や「姿勢の悪さ(スマホ首)」「ストレスによる食いしばり」といった隠れた要因と組み合わさって現れる方が非常に多いです。
ダイエットが引き金となり元々あった要因が表面化するケースを理解すると、正しい対策につながります。
30代からの「たるみ痩せ」と20代の「しぼみ痩せ」の違い
同じダイエットをしても、年代によってたるみの現れ方は異なります。
20代の場合、肌の弾力(コラーゲン量)がまだ十分にあるため、急激なダイエットをしても「たるむ」というより、脂肪が減って「こける」「しぼむ」といったボリュームロスの印象が強くなります。
一方、30代以降は加齢によってすでにコラーゲンやエラスチンが減少し始めています。
肌の弾力が低下しているところにダイエットによる脂肪減少が加わるため、皮膚が余り明確な「たるみ」として現れやすくなるのです。
年代別たるみの特徴
| 年代 | 主な原因 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| 20代 | 急激な脂肪減少(ボリュームロス) | 頬がこける、疲れて見える、しぼむ |
| 30代以降 | 脂肪減少 + 加齢による弾力低下 | ほうれい線、フェイスラインのもたつき、皮膚が余る |
ダイエットが加速させる「加齢たるみ」
年齢を重ねると皮膚(真皮層)の弾力低下だけでなく、さらに深い層でも変化が起こります。
顔の骨は徐々に萎縮し、皮膚を支える「リガメント(支持靭帯)」もゆるみ、SMAS(スマス)という筋膜も伸びてきます。これらは加齢による自然な変化(加齢たるみ)ですが、ゆっくり進行します。
しかし、ダイエットで急に脂肪という「重し」が減ると、ゆるんでいた支持組織が一気に重力に負け、たるみが顕在化する場合があります。
これはダイエットが悪いのではなく、ダイエットによって加齢変化が目立つようになった状態です。この場合、食事や運動だけでの改善には限界があります。
姿勢の悪さ(スマホ首)がフェイスラインに与える影響
日常生活の「姿勢」も、顔のたるみに大きく関係しています。
スマートフォンを見る時のうつむいた姿勢(スマホ首、ストレートネック)は、顎下の筋肉(広頚筋)を常にゆるませ、二重あごやフェイスラインのもたつきを直接的に引き起こします。
また、猫背の姿勢は首や肩の血流を悪化させ、顔のむくみやたるみの間接的な原因となります。
ダイエットで痩せてもフェイスラインがスッキリしない方は、姿勢を見直す必要があります。
ストレスによる食いしばりと顔の緊張
ダイエット中は食事制限などからストレスを感じやすい状態です。ストレスを感じると無意識のうちに歯を食いしばったり、寝ている間に歯ぎしりをしたりする人がいます。
この「食いしばり」は、顎の筋肉(咬筋)を過剰に発達させ、エラが張ったように見せます。
咬筋が常に緊張していると顔全体の筋肉のバランスが崩れ、側頭部や頬の筋肉の動きが悪くなり、結果としてたるみにつながるケースもあります。
ストレスケアと、咬筋の緊張をほぐす工夫も大切です。
ダイエットと並行したい美容皮膚科のたるみケア
セルフケアではなかなか改善が難しい「余った皮膚」や「ゆるんだ支持組織(筋膜や靭帯)」によるたるみには、美容皮膚科や美容整形クリニックでの治療が有効な選択肢となります。
ダイエットで体型を整えながら、顔はプロの手で引き締める、という組み合わせも賢い方法です。
肌の引き締め(HIFU・高周波)
たるみの根本原因である皮膚の奥深く、SMAS(筋膜)層に働きかけられるのが、HIFU(ハイフ:高密度焦点式超音波)です。
超音波の熱エネルギーをピンポイントで加え、筋膜を収縮させて土台から顔を引き上げます。また、真皮層にも熱を加えてコラーゲンの生成を促し、肌のハリも改善します。
高周波(RF)治療(サーマクールなど)は皮膚の広範囲(主に真皮層)に熱を加え、コラーゲン線維全体を収縮させて肌を引き締め、たるみや毛穴の開きを改善します。
美容クリニックの主な引き締め治療
| 治療法 | 特徴 | ダウンタイム |
|---|---|---|
| HIFU(ハイフ) | SMAS筋膜に熱を加え、土台から引き上げる | ほぼ無し(赤みや筋肉痛のような鈍痛が数日) |
| 高周波(RF) | 真皮層に熱を加え、皮膚自体を引き締める | ほぼ無し(赤みが出る場合がある) |
肌の弾力を育てる(注入治療・スレッドリフト)
ダイエットで「こけて」しまった部分や、加齢でボリュームが減った部分には、ヒアルロン酸注入が適しています。
単にくぼみを埋めるだけでなく、リガメント(支持靭帯)の緩んだ部分に注入し、土台を補強することで顔全体をリフトアップする考え方もあります。
また、医療用の溶ける糸を皮下に挿入するスレッドリフト(糸リフト)は、たるんだ皮膚を物理的に引き上げ、シャープなフェイスラインを作ります。
糸の刺激によってコラーゲン生成が促されるため、肌のハリ感アップも期待できます。
たるみを補う治療法
| 治療法 | 特徴 | 適したたるみ |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | ボリュームロスを補い、支持組織を補強する | 頬のこけ、ほうれい線、目の下のくぼみ |
| スレッドリフト(糸リフト) | 糸で物理的に皮膚を引き上げる | フェイスラインのもたつき、マリオネットライン |
医師による栄養・スキンケア指導
多くの美容クリニックでは、治療だけでなく、医学的根拠に基づいた栄養指導やスキンケア指導も行っています。
血液検査で不足している栄養素を特定し、サプリメントを処方したり、日々の食事内容をアドバイスしたりします。
また、肌質を診察した上で、たるみ予防に効果的なスキンケア成分(レチノールやビタミンCなど)を含むドクターズコスメの提案も可能です。ダイエットと肌管理をトータルでサポートします。
たるませないダイエット成功の秘訣
たるませずにダイエットを成功させる秘訣は、「月1〜2kg減のゆるやかなペースを守る」「筋トレと有酸素運動をバランス良く行う」「体重計の数字より見た目を重視する」です。
この3つの心構えが、キレイに痩せるために重要です。
目標設定は「月1〜2kg減」のゆるやかペース
たるみの最大の原因は「急激な体重減少」です。皮膚が収縮する時間を与えながら、ゆっくりと痩せることが最も重要です。
目標設定は1ヶ月に1〜2kg、または現体重の5%以内(例:60kgの人なら月3kgまで)に留めましょう。
時間はかかりますが、このゆるやかなペースがリバウンドを防ぎ、皮膚をたるませないための最大の防御策となります。
適正なダイエットペースの目安
| 現体重 | 1ヶ月の減少目標(体重の5%以内) |
|---|---|
| 70kg | 〜 3.5kg |
| 60kg | 〜 3.0kg |
| 50kg | 〜 2.5kg |
筋トレと有酸素運動のバランス
食事制限だけでなく運動を必ず取り入れましょう。筋トレ(無酸素運動)は筋肉量を維持・増加させ、基礎代謝を高く保ち、引き締まった体を作ります。
有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)は脂肪燃焼に効果的です。どちらか一方に偏るのではなく、両方をバランス良く行うことが、健康的に痩せるための鍵です。
おすすめの運動バランス
- 筋力トレーニング(週2〜3回)
- 有酸素運動(週3〜5回、1回30分以上)
- 日々のストレッチ(血行促進、姿勢改善)
体重計の数字より「見た目」を重視する
ダイエット中は体重計の数字に一喜一憂しがちです。しかし、筋肉は脂肪より重いため、筋トレをしっかり行うと、体重の減りが停滞するときがあります。
ここで「痩せていない」と焦って食事を減らすと、筋肉が落ちてたるみにつながります。
体重計の数字はあくまで目安とし、それ以上に鏡で自分のフェイスラインや体の引き締まり具合、肌のハリといった「見た目」の変化を重視しましょう。
見た目がスッキリしていれば、ダイエットは順調に進んでいます。
ダイエットと顔のたるみに関するよくある質問
美しいスタイルを目指してダイエットを行う方は多いです。ただ、正しい方法でなければ、顔がたるんでしまう可能性があります。
キレイに痩せるために減量するペースを見直して、栄養摂取や肌のケアにも気を配りましょう。すでにたるみが目立っている方は、美容医療を検討するのも良い方法です。
- 一度たるんだ顔はダイエット後でも元に戻りますか?
-
ケースバイケースです。
軽度のたるみや、栄養不足による一時的なしぼみであれば、ダイエット後に栄養バランスの取れた食事に戻し、保湿や表情筋トレーニングなどのセルフケアを続けると、ある程度ハリが戻る可能性はあります。
しかし、急激なダイエットで大きく皮膚が余ってしまった場合や、加齢によるたるみが強く関わっている場合、セルフケアだけで完全に元の状態に戻すのは難しいことが多いです。
その場合は、美容医療(HIFUやスレッドリフトなど)の併用が改善への近道となります。
- 顔だけ痩せないのはなぜですか?
-
特定の部位だけ痩せる「部分痩せ」は、基本的には難しいとされています。脂肪が落ちる順番には個人差があり、顔の脂肪が最後まで残るタイプの方もいます。
また、痩せないと感じる原因が「脂肪」ではなく、「むくみ」や「食いしばりによる筋肉(咬筋)の発達」である可能性も考えられます。
生活習慣を見直し、塩分を控えてむくみを取ったり、食いしばりを意識してやめたりするだけでも、フェイスラインがスッキリする場合があります。
- ダイエット中に顔のマッサージをしすぎると逆効果ですか?
-
やり方によっては逆効果になる可能性が高いです。
強い力で肌をこするマッサージは、肌表面(表皮)を傷つけてバリア機能を低下させるだけでなく、肌の奥にあるコラーゲン線維にダメージを与えたり、皮膚自体を伸ばしてしまったりして、たるみやシワを助長する危険性があります。
マッサージを行う際は、摩擦を避けるために必ずオイルやクリームを使い、リンパを優しく流す程度の圧にとどめましょう。
- プロテインを飲むと顔のたるみ予防になりますか?
-
予防に役立つ可能性があります。プロテインはタンパク質を手軽に補給できる補助食品です。タンパク質は肌のコラーゲンや筋肉の主成分であり、ダイエット中は特に不足しがちです。
食事だけで必要なタンパク質を摂取するのが難しい場合、プロテインを活用して補う工夫は肌のハリを保ち、筋肉量を維持するために有効です。
ただし、プロテインさえ飲んでいれば良いわけではなく、あくまでビタミンやミネラルなど、他の栄養素もバランス良く摂るのが基本です。
顔全体のたるみ対策に戻る
参考文献
GLOBAL, Alma; AMERICA, N. Combating Facial Volume Loss from Weight Loss: Advanced Solutions for Restoring Youthfulness.
LIU, Xuan-jun; SULTAN, Muhammad Tipu; LI, Guang-shuai. Obesity, glycemic traits, lifestyle factors, and risk of facial aging: a Mendelian randomization study in 423,999 participants. Aesthetic Plastic Surgery, 2024, 48.5: 1005-1015.
EZURE, T., et al. Sagging of the cheek is related to skin elasticity, fat mass and mimetic muscle function. Skin Research and Technology, 2009, 15.3: 299-305.
SADICK, Neil S., et al. The facial adipose system: its role in facial aging and approaches to volume restoration. Dermatologic Surgery, 2015, 41: S333-S339.
KAUR, Manavpreet; GARG, Rakesh K.; SINGLA, Sanjeev. Analysis of facial soft tissue changes with aging and their effects on facial morphology: A forensic perspective. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2015, 5.2: 46-56.
WALTZMAN, Joshua T.; ZINS, James E.; COUTO, Rafael A. Face and neck lifting after weight loss. Clinics in Plastic Surgery, 2019, 46.1: 105-114.
RUEDA, Steven; REBANE, Mari; THALLER, Seth. Contour deformities after massive weight loss. In: Body Contouring Following Bariatric Surgery And Massive Weight Loss: Post-Bariatric Body Contouring. Bentham Science Publishers, 2012. p. 39-49.
BELLITY, Philippe, et al. The facial rejuvenation enhancing cheek lift (FRENCH LIFT), a facelift technique that treats sagging of the anterior column of the face: a single surgeon’s 10-year experience with 1100 operated patients. Aesthetic Plastic Surgery, 2025, 49.10: 2685-2694.